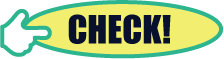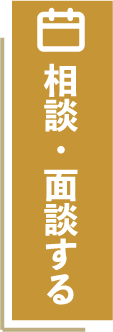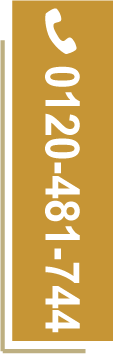Íӯͯð¡Í¥ÒÙñÍȨШÒÐÿ¥

Q&A(ð¥ÓʃÓçÍÑÐÏÐÛÍ¥ÒÙñÍȨÌǣӴШÐÊÐÐÎÐÛÐÒ°ˆÍÿ¥
̰̓ӡҨШÐÊÐÐÎÐÛÐÐÐÐÐÐÒ°ˆÍÿ¥FAQÿ¥ÐÐÛÐХСÐÏÐÐÐÍÛÂÐЃÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÒ°ˆÍШÐÓÙÐÐЃÐÐ
ÐЈÐÐÛÐÍÍˋÐÐÛÐÐШÐдÐдÐÌÎÐÌÐЃÐ
 ÐÐÐЈÐÐÐÍÛÐÐÌÒ£§ÐÐÌ͈Í
ÐÐÍ¥ÒÙñÍȨÐÐÌÂÐЈÐÐÓÏÐÛð¤ÍÌÐ₤ͯÐÕÐÐÐÐÐЃÐÐÐͧð¤ÍÌÐ₤ÐÐÐÐÐÐ̯ÐÐЈÐÐТÐÊÐÐÛð¤ÍÌÐÏÐ₤ÐÐЃÐÐÐ
ÐÐÐЈÐÐÐÍÛÐÐÌÒ£§ÐÐÌ͈Í
ÐÐÍ¥ÒÙñÍȨÐÐÌÂÐЈÐÐÓÏÐÛð¤ÍÌÐ₤ͯÐÕÐÐÐÐÐЃÐÐÐͧð¤ÍÌÐ₤ÐÐÐÐÐÐ̯ÐÐЈÐÐТÐÊÐÐÛð¤ÍÌÐÏÐ₤ÐÐЃÐÐÐ
ð¡ð£Ñð¡ð£ÑÐÛÐðƒÕ ¥Ð¨Í ´Ò¤¨Í ´ÕÐ̓ÐÐÍÍËÐÛÓÑ̰ШÍÐÐÐÎÐÐÐÐÌÎÓËдÌÌÛçÐÕÏð§¢ÐЃÐРЈÐЈÐÐÐЈÐÐÛÐÍÍˋÐÐÐÐÐÓÏШÐÏÐÐÌÕ¨ÐÛÐÒ¢ÐРдð¢ÀÐÐÎÐÐÐÐÐÏÐÐÐÐÛÐÐШÐÓÏÐ₤̓¿Í¤ÓШÐÌݤÐÐÎÒ¨ÎÐÐШÌÎÐÌÐЃÐÐ
ÐÌˋÐÐÐÛÒÈШÐÐ̘ͧÐÛЈпÐ₤
ð¡ÐÛð¡ÙШÐ₤ÐпÐÐ¥ÐÒÏÈÌݤÐÐÍÈýÐШÐÐ̰̓ð¤ÍÌÐÐÐÐÐÐÐЃÐÐÐÐÐÐÓÏÐ₤ÐÐÐÐÐÐÌ¿ÐÐÍÕÀÐÐÐÐÐШÐÐÐÐÌÐИð¤Ì˜ÀÒ¨ÍÛ°ÐÓÐÐ ÐÐÐÐÛÐÒÎÐÎÐЃÐÐÐÓÎÐÈÐÎð¤ÐÕýÐÐÐдÐÏÐÐÐÐÈÐÎð¤Ì Ð̈ÍÐÐÐÎÐЃÐÍ₤Ò§ÌÏÐÐÐÐÐÐÏÐÐ
ЃÐÐÎÐÌˋÌÒÏÈÌݤÐдÐÐÒ´ÒÐÛÒÈШÐð¤ÍÌÕ§Íÿ¥ð¤ÍÌÓçÍÑÐÛÐÐÐÛÍ ÝÕ
˜Óý̓ÐÛпÐÐ¥ÐÍÿ¥Ð´ÐÐÒ´ÇÒ´ÐÛÓçÕ´ð¡ÒÑ°ÐÐÐÐÛÐÏÐÐЯҨÍÊÐÏÐÐ
ÓÏÐ₤ÐÍÛÌЈÒÏÈÌݤÓÙШÕÈаÐÊÐÐÛÐÏÐ₤ЈÐÐÐЈÐÐÛ̈ÌËÐÍÛÐÐÐШÐÐÐÀÐдÐÐÐÐÎÓýÐÍ¥ñÐÌÎÐÐдÐÍÙÐЃÐÐÐ
ÐÐˋÐШÐ̈ÓÑШÕýÐÐÐÐÛÐð¤ÕýÌ°ÍÐÿ¥Ì°ÓЈÒÎÓ¿ÐÐÐÛð¤ÍÍ₤ƒÓÙÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎÐÍÐÐÏÐÐÐÐÛÍ ÇÕÂÐÏÐÐÈÐÎÐÐÍÛÕШÒÈÍÊÌÐÏÒ´ÇÒ´ÐÓçÕ´ÐÐÎÐÐÍ¥ÒÙñÍȨÐÛÓËÒÎÐ₤ð¡Í₤̘ ÐÏÐÐ
ÓÇð¤ÐÛÒÏÈÌݤÐð¤ÕýÐÐÐШÐÊÐÐÎÐÐÓÏÐÛÍÊÓ´ÛУÍÊÌÏЈҴÇÒ´ÐÛÓçմдÍÛÒñçÐÐÐЈÐÐÛÌÝÐÐÍÕÀÐÌñÝÐÓÒÏÈÐÐÌÕˋЈÒÏÈÌݤСдͯÐÍШЈÐдÓ¤ð¢ÀÐÐÎÐЃÐÐ
ÐЈÐÐÛÐÌÎÐÌ¿ÐÐð¡ÓñШÒÎÐÊÐЃÐÐÐ
ÐЈÐÐÛÌÝÐÐÍÕÀШÐ₤ÐÐˋÐÛÐÐЈÐÌÎÐÌ¿ÐÐÐÐÐÛÐÐЃÐÐ₤ÐÐ̯ң§Ð¨ÐÓ¡Ò¨ÐÐ ÐÐÐÐЈÐÐÛÓÑÌ°ÐÐÐÈÐÐдÐÒÐÐÐÌÍÐÛÕ¡ÌÒÂÐð¡ÓñШÒÐЃÐÐÐÐ
ÐÓ¡Ò¨ÐÐÒÏÈÌݤЃÐÏÐÐÐÈÐÐдÐÌ₤ÌÇ
ͧð¤ÍÌÐ₤ÐÌ
ÐÐÈÐÎ̯ͯÓýƒÕÙШ̓¿ÐÐÍ¥ÒÙñÍȨÐÛÓÏдÐÐˋЈХИШ2ÍÐÏÕÍÑÐÐÎÐÐÍð¤¤ð¤ÍÌÐÏÐÐ
Í₤ЈÕÈ̤ШÐÐÈÐÎÐÕ¨ÐÕÀÏÍÛÂ̤ÒѰͤÎÐÓ¤ð¢ÐÐÎÐÐÐÛÐð¤ÍÌÐÛÍ¥ñТÐÏÐÐ
ÐЈÐÐÛÌÝÐÐð¡ÍÛÐÐÓÏШÌÐÀÌÐÐÎТЃÐÐÐÐ
ð¥ÌËÙÌ°ÍÐ₤ͧð¤ÍÌÐÛÌ°´ÍÍÕÐÏÐÐÿ¥Ó¿Ð¨ÿ¥ð¡Ùͯð¥ÌËÙÓçÍÑÒ
Ð₤ÿ¥Ó¡Ò¨Ó¡ÌÐÌ¿ÍÊÐÐÐÎÐÐÐð¤¤ÐÐЈÐÐÛÐÕðƒÐÏÐÐÓÏÐ₤ÍÐ
ÐÛð¥ÌËÙдð¤ð¤¤ð¡ÒÐÛÌñÝÐÕÂð¢ÐÌÏÓ₤Ðÿ¥Ó˜ÒˆÍ¤ÌÐÛÍ¢ÍШÍÐÐÐÎÍÍËÍ
ñð§ÓЈÐçÐ¥ÐпÐÌðƒÐÐÎÐÐÒÐÐÏÐÐ
ÐÐÛÐÐШÿ¥Í§ð¤ÍÌÐÏÐ₤ÿ¥ÕÀÏÍÍ¥ÒÙñÍȨУÕÀÏÍÍËÓÇÐÛÐÌðƒÐÐÐÎÐÐЃÐÐÿ¥ÐƒÐÐ₤ÿ¥Í¥ÒÙñÍȨÐÌÇ£Ó´ÐÐÎÒÏÈÌݤÐÏÐÐÓÇð¤Ð£ÐÐˋÐШдÐÐÎÐˋÐÛÐÐЈð¤ðƒÐÐÐÐШÐÊÐÐÎÿ¥Í
ñð§ÓЈÐÊÐÀХСÐÌÐÈÐÎÐÐÐ ÐÐÐдÌÐЃÐÐ
Íӯͯð¡Ì°Íƒð¤ÍÌÐÍÐÌÝÐÌËÙÍÍÕУ̰´ÍÌËÙÍÐ₤ÐÐÐÀÐÐÐÓ¤҈ÐÐ ÐÐÐ
ÐÐШÐͧð¤ÍÌÐÐÐЃÐÏÿ¥ÕÀÏÍÍ
ӴШð§ÌÐÐÐÐˋÐÊÐÊÐ¥ÐÛð¡Õ´ÐÍ
˜ÕÐÐÐЃÐÐÛÐÏÿ¥ÐÒÎÏÐÐÐ ÐÐдͿ¡ÐÐÏÐÐ
ð¥ÌËÙУ̰ð¤¤ÐṴ̂̓ӡҨÐÛÐÌÀÍ

ÍÇÍÓ¯ÍÂÌ¿ÍШÐÐÓÓÈÌÏÍð¡Ì₤ÌÇ
ÓçÍÑÒ
ÐÓçÍÑШͯ͢çÐÏÐÐÕÀÏÍÍ¥ÒÙñÍȨÐçÐ¥Ðп
ЈÐÿ¥ÐÐШÐÓÇ¿ð£ÐÐÓÇð¤Ð£ÐÐˋÐШð¤Õ Ð₤ÿ¥ÕÀÏÍÍËÓÇÐÓñ ÓçÐÐÍШÿ¥Ð´ÐÐÐÐÐÛпÐÐÐÐðƒÕ ¥ÐÐÍÐÐÐÎÐÐЃÐÐ
ÿ¥ÕÂÕÈð¤Õ ÿ¥
ãðƒÕ ¥ÐÐÐÐÍÛÂÐЃÐÛÍȯ>>
ãð¥ÌËÙÌ°ÍÐÛÍÛÓ¡ƒÐ£ÍÛðƒ>>
ãÕÀÏÍÍ¥ÒÙñÍȨУÕÀÏÍÍËÓÇÐÛӿ̓ÇУӿÒý>>
УШаÐÕÀÏÍШÐÊÐÐÎ
ӿШÿ¥ÓƒÍ´ÐÛÕÀÏÍÍ¥ÒÙñÍȨШÐÊÐÐÎÐ̓ÌÍÕУÌËÙÍÐÛð£Ì¿ÐÍÐÐÐÌˋÐÐÏÐÐÓçÍÑÒ ÐÛÐÐШ
ÐÐÐÏÐ₤ÐÐÍ¥ÒÙñÍȨШÐÐ̓ÌËÙÍÀÌ₤ÌÇÐÐÙЯÐˋÐ ÿ¥EAPÿ¥ÐÐÐÓÇ¿ð£ÐÐÐЃÐÐ
ÐÐÐ₤Ðð¥ÌËÙÐÿ¥ð¤¤ÌÐÛÓÓÈÌÏÍð¡ÐÍ°Ðð¡ÐÏ̓ÌËÙÍÀдÐÛð¢ÀÕ ¥ÕÂð¢ÐÍ¥ñͤШÐÐÐÐÐÛÓÎÍˋÍÓÐÛð¡Ó¯Ð´ÐÐÎÿ¥ÍƒÌËÙÍÀÐÐÐˋÐÊÐÐ¥ÐÐÏÌÝÐÐ̰̓ÐÐˋÐШÐÐ̓ÌËÙÍÀÐÒÏÈ̃ÐÐÎÐÐÐÐдШÐÐÈÐÎÿ¥ÍƒÌËÙÍÀÐÛÐÀаТШð¡Òˆ¢ÐÒÏÈÌÑÐÐÌ¿ÓÙÐÏÐÐÕÓÇð¤ÐÛÍ ÇÕÂÐÏÐÛÍ¥ÒÙñÍȨÌǣӴ̰дÐÐÐдÐÐÏÐЃÐÐ
ÐÐÛÌ ÓçТдЈÐÐ̓ÌËÙÍÀÌ₤ÌÇÐÐÙЯÐˋÐ ÿ¥ÿ¥Ëÿ¥Àÿ¥¯ÿ¥ÐÐ₤Ð̓ÌËÙÍÀÐÛÐÀаТШÐШпÐÕÐÐÎÐÒñÍ ÇÍ
ЃÐÐ₤Íð¤¤ÐÛÍÕÀÐÌ₤ÌÇÐÐÐÐÛдÐÐÎÐÐÂШаХШÐÒ˜ÓˋШÐÐÈÐÎÌËÙÍШÌ₤ÕÐÐÐÐð¤ðƒÐÍÊÐÐÂÐÀЈШÐÏÓ¤ÓËËÐЃÐÐÐ
Í
´Í§ÓШÿ¥Í¥ÒÙñÍȨÌËÙÓÐÏÐÿ¥Ëÿ¥Àÿ¥¯ÐÓˋÌËçÓШÌËÙÍÍÐÐð¤ÍÌÐÓƒÐÐÎÐЃÐÐ
ÐÀаТШÐШпÐṴ̂̓ÍÕÀдÐÐдÐÕñÌÕÍÇÍÐÐÐ₤ÐÐˋÐÒÎÍ Ð´ÐÐÐÀаТШð¡Òˆ¢ÐˆÐˋÐÒٯҨШЈÐÐÐÀÐÏÐÐÐÓçÍÑÒ
Ð₤ÿ¥ÐÐÈдͤÐÌñÝÐÒÎÓ¿ÐÌÐÊпÐÐÏÐÐÐÐ
Òˋ°ÐÐÐ₤ÿ¥ÐÍ¥ÒÙñÍȨШÐÐ̓ÌËÙÍÀÌ₤ÌÇÐÐÙЯÐˋÐ ÿ¥EAPÿ¥ÐÐÐð¡ÒˆÙÐÐ ÐÐÐ
Contentsô [hide]
- ð¡Ùͯð¥ÌËÙÐÛÓçÍÑÐ̰̓ÐÏÌ₤ÐЃÐÐ35Í¿Çð£Ëð¡ÐÛÍÛÓ¡ƒÐ´ð¢ÀÕ ¥
- ӃʹÐӿШ̰´ÍÐÐÎÐÐÌËÙÍ
-
- ã ÐÓçÍÑÌ´ˋð¤ÐÐ£Ì ˆð¡£ÕÐÛÓÇð¤ÐÍ¯Ì¯Ì ˆð¡£ÐÛÌ ˆÍ¥ÍÈýÍÇ
- ã ÀÐð¡ÙÍ Ð£ð¡Ùͯð¥ÌËÙÐÏÐÐð¡Ò¨ÌËÙÒ ÐÛÐ¥ÐааУÐÐÐÙÐÐÐ¥ÐÏÐÐÍ Ò¨ÌËÙÒ Ð´ÐÛÕÐÛÍ£¤Ó₤Ò¨Òý ÍñËð¤ÐÐˋÐШ Ðÿ¥Í Ò¨ð¥ÌËÙÐÛÓƒÍ Çð£ÈÓð¤¤ÐÛÌ´ˆÌÇÐÍñËð¤Ì§ÍñËÐÛÍËÓÇð¡ÕˋÍÿ¥ÓÓçÿ¥ÐÛð¡Ò¨ð¥ÌËÙСÐÛÒ£ÂͨЈÐˋ
- ã ÂÐÐШЈХÐХУ̰´ÌÒ Ð´ÐÐÎÐÍ£¤Ò´ÙÌËÙÒ Ð´ÐÛÐÐˋÐШÿ¥Í£¤Ó₤ÍñËð¤ÐÛð¡Ì¿Óð¡ÙÌÙÂÐ£Õ Í£ÑУÐ
- ã ÈÐÍͯÍÍÛÑШÐÐÐÌÍˋЈÍÝÕ Ðÿ¥ÍÓÓ¤ð¢Ð£ÍÕÓ¤ÐÛÐÐÐÛͯð£ÈУÍÛÑÒ°ÐÛÍÂÕÀУ̡ÕÀÐÛÒ¨ÌÝÐÛÌÇ£Ó´ÐͤÒÓˋð£Ñÿ¥Í£¤ÓˋУÍͯÿ¥ÐÛÌÌÒ Ð´ÐÐÎпХÐÐ¥ÿ§ËааÐÐÐÛÍÊͤÒÍÝÕð¥ÌËÙÿ¥ÐÐÏХапÐÐÂÐ¥ÿ¥Ð¡ÐÛÓˋð£ÑÍÈýÍÇÓÙ
- ã
ÊÐÍͯÍÍÛÑÕÂð¢Ð¨ÐÐÐÓ¨ÕÌШÐÊÐÐÎÐÐÐÐÐÐÛÓ¨Í ÇÐÐÐÛÍÊÏÍ¿
ЈÍÂÕÀУ̡ÕÀ
- Ðÿ¥£ÐÍÛÂÐЃÐÛÍȯÿ¥§ Ó¨ÕÌÐÐͧÍÌÓʤÐÐÐÕÀÐ90ð¡ÍӴͤÎÐÐ1700ð¡ÍШÍÂÕÀÿ¥ÕÈÍͤÒÐÛÓçÍÑÒ Ð£ÍË°ÌÏУ83ÌÙ°
- Ðÿ¥£ÐÍÛÂÐЃÐÛÍȯÿ¥§ Ó¨ÕÐÌдÐÐÎͧÍ2000ð¡ÍÒÎÌÝÐÐÐÐÿ¥1000ð¡ÍЃÐÏÍÊÏÍ¿ Ì¡ÕÀÿ¥ð¡ÍÓÈð¥ÓʃÐÛð£ÈÒÀ´ÍÓñ ͧ¿Ð£ÓñÌÏУÿ¥ÿ¥ÌÙ°
- ã ËÐð§¢Ó´Ò ÍÇÐÛÍÇÍÍÕÀУÍÇð§¢ÍÕÀУÍÇÍÓÛÀÓ
-
- ÍÐÌÝÐÌËÙÍÍÕ
- ÍÛÓ¡ƒÐ£ÒÏÈÌݤð¤ðƒ
- ð¥ÓʃÓçÍÑШÕÂÐÐ̰̓ÍÕÀÐÛÐÐˋÐШУð¡ÍÛÐÐýдÐÐÏÌÝÐÐÎÐÐð¡Ùͯð¥ÌËÙÓçÍÑÒ ÐÛÓÐÐ
- ÕÀÏÍÍ
дÐÛͤð¥ÐÐÐÍÛÂÐЃÐÛÍȯÐ
-
- ÐÒƒýÓÈÓˋÒýˋÍÈýð¥Óʃð£ÈÒÀ´Ò УÓñÌÏУÿ¥ÿ¥ÌÙ°
- ÐЈХпð¥ÓʃУð¥Óʃͧ¿ÍÀÿ¥ÐÐÛ̓ð£ÈÒÀ´ÍÓñ ͧ¿ÿ¥Ð£ÓñÌÏУÿ¥ÿ¥ð£È
- ÐÍ£¤Ò´Ùð¥ÓʃУð¥Óʃð£ÈÒÀ´Ò ÍʨÍΣÿ¥Í£¤Ò´ÙÌËÙШÕÂÕÈÐÐÎÌÍÛ°Ò° ÍÒ¨ÌÝÐÐÛð£
- ÐÍ£¤Ò´Ùð¥ÓʃУð£ÈÒÀ´ÍÓñ ͧ¿Ð£ÓñÌÏУÿ¥ÿ¥ÌÙ° ÿ¥ð¥Óʃ̰ÍУÕÀÏÍÌËÙÍУҴÇÒ´
- ÐÓ´ÓÍȨУÓñÌÏÿ¥73ÌÙ°ÿ¥
-
ÐÐШÐͧð¤ÍÌÐÐÐЃÐÏÿ¥ÕÀÏÍÍ Ó´Ð¨ð§ÌÐÐÐÐˋÐÊÐÊÐ¥ÐÛð¡Õ´ÐÍ ˜ÕÐÐÐЃÐÐÛÐÏÿ¥ÐÒÎÏÐÐÐ ÐÐдͿ¡ÐÐÏÐÐ
ð¥ÌËÙУ̰ð¤¤ÐṴ̂̓ӡҨÐÛÐÌÀÍ

ÍÇÍÓ¯ÍÂÌ¿ÍШÐÐÓÓÈÌÏÍð¡Ì₤ÌÇ
ÓçÍÑÒ
ÐÓçÍÑШͯ͢çÐÏÐÐÕÀÏÍÍ¥ÒÙñÍȨÐçÐ¥Ðп
ЈÐÿ¥ÐÐШÐÓÇ¿ð£ÐÐÓÇð¤Ð£ÐÐˋÐШð¤Õ Ð₤ÿ¥ÕÀÏÍÍËÓÇÐÓñ ÓçÐÐÍШÿ¥Ð´ÐÐÐÐÐÛпÐÐÐÐðƒÕ ¥ÐÐÍÐÐÐÎÐÐЃÐÐ
ÿ¥ÕÂÕÈð¤Õ ÿ¥
ãðƒÕ ¥ÐÐÐÐÍÛÂÐЃÐÛÍȯ>>
ãð¥ÌËÙÌ°ÍÐÛÍÛÓ¡ƒÐ£ÍÛðƒ>>
ãÕÀÏÍÍ¥ÒÙñÍȨУÕÀÏÍÍËÓÇÐÛӿ̓ÇУӿÒý>>
УШаÐÕÀÏÍШÐÊÐÐÎ
ӿШÿ¥ÓƒÍ´ÐÛÕÀÏÍÍ¥ÒÙñÍȨШÐÊÐÐÎÐ̓ÌÍÕУÌËÙÍÐÛð£Ì¿ÐÍÐÐÐÌˋÐÐÏÐÐÓçÍÑÒ ÐÛÐÐШ
ðƒÐЯÿ¥ÕÀÏÍÛÂÍ₤ƒÍ¢Ð₤ÐÐÐÐÏÐÐÐÐ
ÐÐÛÐÐЈҰˆÍÐÐÐÐÌ¿Ð₤ÿ¥ÐÐÐÐÿ¥Í ËÓʃÐÐÕÓ¨₤ÿ¥ÐÐÍÛÂÐЃÐ₤ÓËÌÏÐ Ðдð¡Í¡ÐÍ Ò¥ˋШÍÝÒý˜ÐÐЈÐÐÐ₤ИХРÍ₤ƒÍ¢ÐÐÐÎÐÐд̴Í₤ÐÐЃÐÐ
ÓÏÐÍ¥ÒÙñÍȨШЈÐÈÐЯÐÐÐÛÕ Ðÿ¥ÐÐЈÌÐÐÏÐÐÐÍ¥ÒÙñÍȨШЈÐÿ¥Í¯ÝÒñÐÐЯÐÐЈÐÛШÿ¥ÐÐÐÀÐÛð¤ÍÌÐÏÐ₤Ì ˆð¡£Óñð¥Ðð£ÍÐÈÐÐдÐ₤ЈÐÐÛÐÏÿ¥ÐÍÐÒˆ¢Ð¿ÐÎÍ₤ƒÍ¢ÐÐÐÐдÐÿ¥ÐÍÇÍð¤ð£ÑÐ₤ÐÐÈÐÐдÐЈÐÐÛÐÏÿ¥ÍÇÍÓçÍдÐÛÍ₤ƒÍ°Ð₤ð££ÐÐÐÐдÐÌÐÐÐÿ¥Íƒ¿ÍÊÐÛÌËÐ ÐÓÑÐЈÐÐÿ¥ÐÐЈÐШÍ₤ƒÍÎÐÿ¥ÐпÐÐÿ¥ÒÊÐÐÐÐÍ₤ƒÍ¢ÐÐÏÐÐÐÐÛÐÏÐÐ
ÐÐÐÿ¥ð£ÐÏÐ₤ÿ¥ÒËÌдÐÐЯÿ¥ÐÐÂапТХÐдÍ₤ƒÍ°ÐÐШÐ₤ÿ¥Ðð¡ð£ÈÐÿ¥ÐÊЃÐÐÐЃÐдÐÐÎÿ¥ÐÐÛÐÐÍ ÇÕÂÐÛÒÌÏШͥÝÐð¡ÐÐÐÐÐÐÿ¥ð£ð¤Ð´ÐÐÎÕÀÏÍÛÂÍ₤ƒÍ¢ÐƒÐÏÌÝÐÐÐÐÐÛÐ₤ÒÎÍÐЈÐдÒÐÐÍÝÊРдÌÐЃÐÐ
ð¤¤Ìð¡ÒÑ°ÐÛð¡ÐÌÀÓ´ÐÐÎÐÐÐШÕÒñÐÐÎÐЃÐÐдÐÍÊÐÓƒÓÑÐÏÐ₤ÐÐÍÛÂÐÐÐÐÐÐÐÐд̯ð¤¤ÐÛÌ ¯ÐШÓçÍÏÐÐÐ ÐÐÏÐ₤ЈÐÐÏÐÐÐÐÐ
ÐÐÐÐÐˆÍ ÇÕÂÐÏÿ¥Ð°ÐÙÐÓÎÐ₤ÿ¥ÍÊÏÐЈÌð£ÈÐÛÌçÐÐÍ ÕÐЃÐÐÐ
ãÐШпÐÐˋÐÍÇÓ§10Í¿ÇÐÏ78ð¤¤Ð24ð¤¤ÐÒˆÌÛ¤Ð̈ҰˆÐ₤ИХРÍ₤ƒÓÙÌËÍãдÐÛ̯ÒÍ ÝÕÐÐÐЃÐÐÐ
ÐÂÐТХаÐÙÐÐÏÐÛÍ₤ƒÓÙÐÿ¥ð£ÐÐÌ´ÀÓÇÂÐÿ¥Ó¤ÍÛÐÐÎÐÐÍ¢
ÒÎÐÐÐЃÐÐ
Òˋ°ÐÐÐ₤ÿ¥ÐШпÐÐˋШÍ₤ƒÐÐð¥ÌËÙÍ₤ƒÍ¢ÐÛÍ´ÐÌ¿ ÿ¥ÌˆÒ°ˆÐˆÐ₤ИХÐХдÐÛÍ₤ƒÍ°ÐÐÓ¤҈ÐÐ ÐÐÐ
ÐÐˋÐÊÐÐñÐ¥ÐÛÍÕÀÐÐÐЃÐÐÛÐÏÐÐпаÐÐÏÍ ÝÕÐÐÐÌÀð£ÑÍаÍÊðƒÕУÍÊðƒÕ҈ШӣҥÐÐÐÌÀð£ÑШÐÊÐÐÎÿ¥Ì¯ðƒÐ ÐÐÐÐ₤ÐÂÐÐÐÐд̘ÀÐÛÐÐÛÐÐÐÐÐЃÐÐ
Í
ÕÏÓЈÐÐÛÐͨÐÐÐÛð£ÍÊ̯ÐÛð¤ðƒÐÐÓ¤҈ÐÐ ÐÐÐÐÐÀÐÐ>>
ð§çÐÐÎÐÐÐÍÛÂÌÏÐÛÍȯÐÐÐÒÎÏÐÐ ÐÐдÐðƒÕ ¥Ò
ÐÛÓ¨Í ÇÐÏð§ÌÐÐÐ ÐдÌÐЃÐÐ
ÐÐÀÐÐ>>
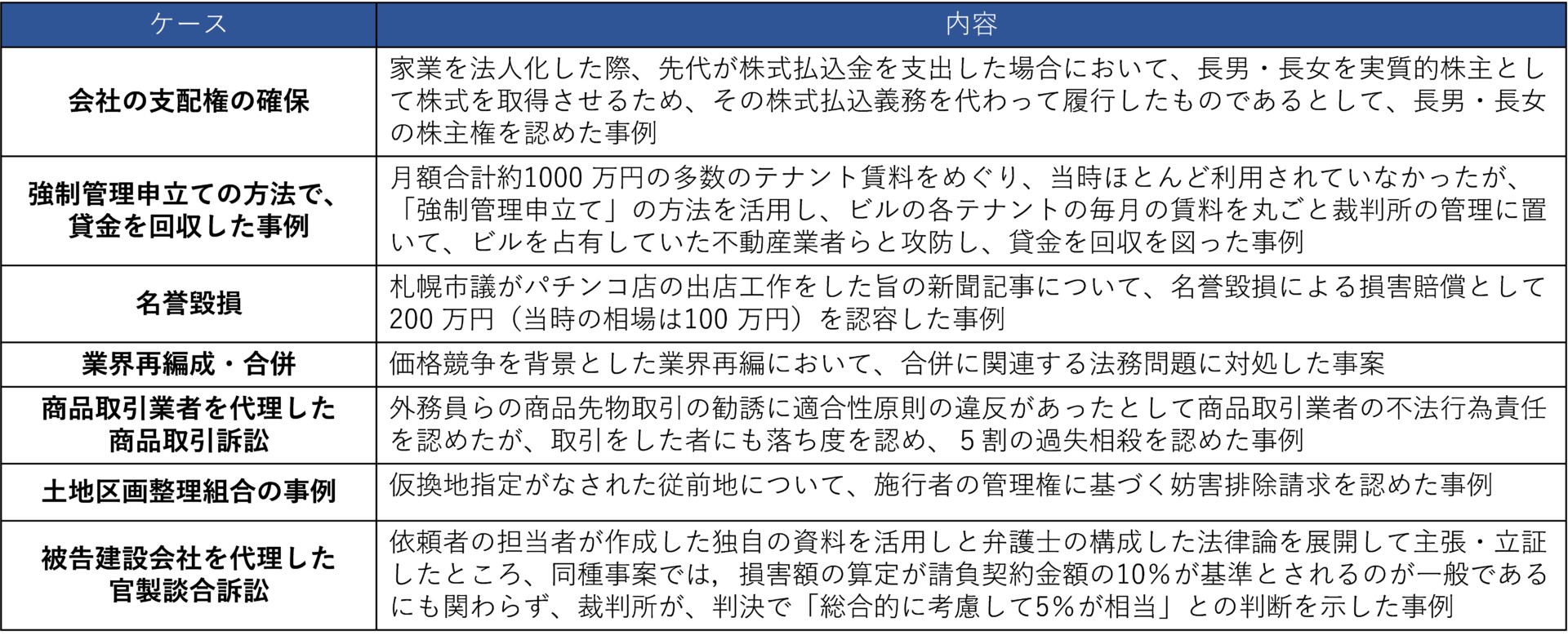
ÍÌÝÍÕÐдÐÛÍÌÝðƒÐ₤ÿ§ÊÐÐÀÐ >> ÐÐÍÓ ÏÐÐ ÐÐÐ
ð¥ÌËÙÓçÍÑд̰ÓÓÇð¤
Ð¥ð¥ÌËÙÓçÍÑÿ§Ëð¥ÌËÙÍͥШÐÐÐÌ°ÓÓÇð¤ÐÛÒÏÈÌݤÿ§Ëð¤ÕýÐÛÍÓçÐ¥
ÐÐÓ¡ÌÐÐÒ´ÇÐÐÐÐÍ ÇÍÐÒý ÐÐÐÐШÐ₤ÐÐЃÐÐÐÕШÐÒˆÍÐÐÒ´ÇÐÐÍ ÇÍШÐ₤ÍÍˋÐÓÛÌÐЈÐÐЯЈÐЃÐÐÐ
ÓÀÕÏЈÌÕдÒý£Ó´ÐÐÐЈÐÕÐÐÏÐÛÓÇð¤ð¤ÕýÐÛÐÐÐÛÌÇÍÐÛÍñËÍʨÐÍ¢ ÒÎÐÏÐÐ̰̓ÓÇð¤Ð¨Íñ£ÐÒƒ¥ÐƒÐÐÍ ÇÍÐ₤ÐÐÀÐÐÐ̰̓ÓÇð¤Ðð¤ÕýÐÐÐдÐÐÓçÍÑÒ Ð¨Ð´ÐÈÐÎЃÐÕÒÎЈÐдÐÐÐÐ₤Ðð¢ÀÕ ¥ÐÛÐÐÐÍ¥ÒÙñÍȨÐÛÒˆ˜ÌÐÕÐÐÎÐÒˆÍÐÛÓ§ÛÐÐÐÓÑÌ°ÐÍÛÂÒΰÓÐÐÊÍ ñð§ÓШÓÒÏÈÐÐÕˋÍЈÒÏÈÌݤÓÙÐÒÎÐÊÐÐÐдÐÏÐÐ
ÓÇð¤ÒÏÈÌݤÐÓÇð¤ð¤ÕýÐÛÌ¿Ì°Ð₤ÐÓÇð¤Òˆð§ÐÛÌÏÒ°ˆÐ¨Í ÐÐð¥ÌËÙÐÛð¤ÌËÙУÌËÙÌ ÐÛÍ ÍÛ¿ÐÍÛÌ ÐÏÍÊÐÐЃÐÐ
ÐÐÐÐÐÐЯÐÐÐÏÐ₤ЈÐÐÓçÍÑÒ Íð¤¤ÐÛÐÙÐÈÐˋÐ₤ТХУÐХЧÐЈÐÐÈХШÐÐÈÐÎÐÍÊÏÐÐӯЈÐЃÐÐÐÐÀÐÐÐð¤ÐЯÐÐÐÍ˧ÐÐÛÐ₤Ò¨ÍÊÐÏÐÐ
ÐÐÐÐÓçÍÑÒ Ð´ÐÐÎÐ₤Ð̓¿Í¤ÓШÕÐЈÐÐЯÒÏÈÌݤÐÏÐЈÐÍ ÇÕÂÐÓÑÌ°ÐÐÐÐÐÐÐЃÐÐ
ÐÐШÐÐÐÐÐÐÐÐÌˋÌÒÏÈÌݤÐдÐÐÕÙ ÍÓЈҴÒШÕÈаÐÊÐÐÎÌËÐÐÏÍÎËÍÐÐÍÕÀÐÐÐÀÐдÒÏÈÌݤÐÐШÓçÐÐÐͯÌËÐÛÐÐˋÐШÐÛÍÍ ÐÌÛÐÐдÐÐÐÐÐЃÐÐ
ð¡Ì¿ÐÓçÍÑÒ Ð̓¿Í¤ÐÐÎÕÐдÌݤÌÙÐÐÐÛШÐÐÍÐð£ËÐÎÒýÇÐдЈÐÐдÐÐð¢ÀÌÀÐÏÐÐÓÀÕÈШЃдÐÐÐÐдÐÐÍ¥ÒÙñÍȨÐÏÐ₤ÐÓ¡ÌШ̥ÐÐÐÎÐЃÐÐÍÈÍÂШӨÐÐÐÐÐдÐÐÐЃÐÐ
ðƒÕ ¥Ò дͥÒÙñÍȨÐ₤ÐÌÍÐÛÒÏÈÌݤÐÍÛӃШÍÐÐÎÐÍÍÐÐЈÐÐЯЈÐЃÐÐÐдÐÐÐÏÐÓÏÐ₤ÐÓÇð¤ÒÏÈÌݤУÓÇð¤ð¤ÕýÐÛÐÂÐШÐ₤ÐÒ´ÇÒ´ÐШÐÐÐÍÛÒñçÓШÐÒ´ÇÒ´ÐÐÏÌÍˋШÌÇ£ÍÐÏÐÐпÐÙШдÐÐÊаÐÐÐÐÐÍ¥ÒÙñÍȨШð¡Í₤̘ ÐÛÒ§ÍÐÏÐÐдÒÐЃÐÐ
ÐÐÐÎÐÒ´ÇҴЯÐÐÐÐÒ´ÇÒ´ÍÊÐÏÓÇð¤ÐÒÏÈÌݤÐÐÐдÐÐÐÐЃÐÐÓÇð¤Ð̈ÓÑШÕýÐÐдÐÐÍ ÇÍÐÏÐÐÈÐÎÐÐÒ´ÇÒ´ÓçÕ´ÐÏÒÈð£ÐÐÐÐпÐÙШдÐÐÊаÐÐ̘ ÐÐЃÐÐÐÌÓçÓШÒÈÍÊÌШÌÐÀÒƒ¥ÐƒÐÐÍ₤Ò§ÌÏÐÒÐÐÎÓ§ÛÐЈÐдÐͯÌËШÐÐÐÍ₤ƒÍ¢Ðð¡ÍÍШЈÐÐдÐÐÐЃÐÐÓÏÐ₤ÐðƒÕ ¥Ò ШдÐÈÐÎÐÛÐÍÐÀÐÐð§ÐˆÐÛÐШÐÐ ÐÐЃÐÐ
ÍÐÀÒý ÐÐÛÓÒÏÈÐ₤ÐÐпÐÎÐÛð¤¤Ð¨Ð´ÐÈÐÎÍÐÐÏÐ₤ÐÐЃÐÐÐÓçÍÑÒ ÐÛÐÙÐÈÐˋÐ₤ТХУÐХЧÐЈÐÐÈÐ¥Ð₤ÌÏÐ ÐÏÐÐÐðƒÕ ¥Ò дͥÒÙñÍȨÐ₤ÍÍÐÐÎÐÐÐÛÐдÐÓˆÐÒˋ¯ÐЈÐÐЯЈÐЈÐÐÛÐÏÐÐÓÏÐ₤ÐÐЃÐЃЈҴÇҴШÍÐÓçТÐÕÀÏÍÍ¥ÒÙñÍȨдÐÐÎÐ₤ÐÍ¡¡Ìÿ¥ÿ¥ÓʃÐÒÑ ÐÐð¥ÌËÙÐÓÇÌËÒˆÍÐÏÌ Í§ÐЈÐÐÐÿ¥ÿ¥Í¿ÇÐÒÑ ÐÐÍ¥ÒÙñÍȨÓçմдÍÛÓ¡ƒÐÓˋÐÐÏÐЃÐÐÐ
ÐÐÛÓçմдÍÛÓ¡ƒÐ¨ÒÈð£ÐÐÐÐÍ¥ñТÐÌÇ£ÐÐÐðƒÕ ¥Í ð¥ÌËÙÐÛÍÛÌ ÐÍÛÌ Ð¨Í ÐÐð¥ÌËÙÓ˜ÒˆÐÛÍ¢ÍÐÐÐÐÎÓçÍÑÒ ÐÛÐÙÐÈÐˋÐ₤ТХÐÐХЧÐЈÐÐÈÐ¥ÐҡЃÐÐÓÇð¤ÐÛð¤ÕýдÒÏÈÌݤШÍÐÓçÐÐÏÐЃÐÐ

ð¥ÌËÙÕÓÇð¤ÐÒÏÈÌݤÐÐÐÐÐÛÐ̯ð¤Ò´ÇÒ´ÐÛÌÇ£Ó´Ì°ÐÐÓËÐÐÐÌ¿Ð₤Ð̘ÀÐÐˋÐÐÐ
ð¥ÌËÙÌ°ÍдÐÐдÿ¥ðƒÕ ¥Ò ÐÏÐÐÓçÍÑÒ Ð£ÓÛÀÓÒ Ð´Í¥ÒÙñÍȨÐÛÿ¥ÐÐÐÐÐÛÐÐÙÐÐÏÐÐñÐÏÐШÓËÒÙУпÐÙШУÌÒÎð¡ð§ÍÐÐЈÐÐЯЈÐЃÐÐÐ
ÐÐÐÏÐ₤ÐãÍ¥ÒÙñÍȨдÐÛÍÍð§ÌËÙãШÐÊÐÐÎÐÐÍÛÂÌÏÐÛÍÇÐÐÐÛÓçÕ´Ò¨ÐÐÓÇ¿ð£ÐÐÎÐÐÐÛÐÊÐÀХСÐÌÝÐÐÎÐÐÐ ÐЃÐÐÐÐ
ÐÍ£¤Ò´ÙÌËÙУÓÛÀÓÒñУÓñÌÏÿ¥65ÌÙ°ÿ¥Ðð¤ÌÀÐÛÌÐпÐÒÏÈÌݤШÐ₤ÐÍ¥ÒÙñÍȨдðƒÕ ¥ð¤¤Ð´ÐÛð¢ÀÕ ¥ÕÂð¢ÐÍ¢ ÒÎð¡Í₤̘ Ð
ð¤ÌÀШÍ₤ƒÐÐÎÐ₤ÐÍÛÂÒΰÓð¤ÍÛÐÓˋТÕÐÙÐÎÐÐÐдÐÐдÐÎÐÍÊÏÍÐÏÐÐÐÐÐÐÐÐÛÐÐШÌШÐ₤ÐÒˆÍÐÒȡШÐÐÍ̯ÐÌÝÐÐÐЃÐÐ
ÐÐЃÐÏÐÛÐÐÐÛÐÛÒÎ̿УÒÐÌ¿ÐÍÎÍÛÐÐÐÐдÐÐÐÐÐÐÏÐÐÐÐÐð¿ÐÒÑÐÐð¤ÐÏÐÍÐÐÎÍ¥ÒÙñÍȨдÐÛð¢ÀÕ ¥ÕÂð¢ÐÍ¥ñͤЈÐÐÛдЈÐЃÐÐÐð¿ÐÒÑÐÐÍÍÍÐ₤ÐÍ¥ÒÙñÍȨдÐÛÕШÓÛÓÐÓ¤҈ÐÐÓ¡ð¤ÐÛð¢ÀÕ ¥ÐÓÌÐÐÊÐÊÐÍ¥ÒÙñÌ¿ÕÐÓ¨ÐÎÐÎÐÐÍÍð§ÌËÙÐÏÐÐÐ
Ì°Í£ñÐÏÐÍÐÊÐÐÒý ÐÐÐÐÐÐˋÐЈÒý Ð̿ШÐÐÐÐÐÐÐÛÐÐШÐ₤ÐˋÐЈҰÌÿ¥Ò´¥Ì Ì¡ÕÀЈÐˋÿ¥ÐÍ
ËÌÐÏÐÐÐÐЈÐˋШÐÊÐÐÎÐÍ¢ÌÐÛЈÐÌÒÎð¤ÊÌÐÛÓˋТÕÐÙÐÐÍ¥ÒÙñÍȨСÐÛð¢ÀÕ ¥ÐÌñÝÐÐÎÐÐЃÐÐÐ
Ó¡ð¤ÐÛð¢ÀÕ ¥ÐÓ¤ӨÐÐÐÐÐÏÐÌ
Í ÝÐÛÍ
ÝÌÐ₤ÌÐÕÒÎÐÏÐÐÕ ÐÐÐÕȃÐÐÐÒˆÍÐͧÐÐÌ
Í ÝÐÌðƒÐÐÎÐÐÐдÐÐÒˆÍÐÛÌÐÒÏÈÌݤÓÙШҢÐËÐð¤Ð¨ÐˆÐЃÐÐÐ
ÕñÌÕÐÛÐÐˋÐÐˋÐÐͯÒÝÀÐÛÌ°Í£ñÐÏÐÐÐÐÍÓ¯Í ÓÐÛÐÍˋÒ´ÐÛð¡ÐÏÐÒýÇÕЈÓçÕ´ÐÐÐÐÎÐÐÐ ÐЃÐÐÐÐÐÐдÐÐÐÐЃÐÐÐ
ЃÐÐãÓ¡ÌÏãÐÛÒ₤ÐÐÐÌÐÐÛУÐÐÐÍÐÊÐÐÐÐÛÕÒÎЈÒÎÓÇ Ð´ÐˆÐЃÐÐ
ÐÍ£¤Ò´ÙÌËÙУð¥Óʃð£ÈÒÀ´Ò УÓñÌÏÿ¥51ÌÙ°ÿ¥
ÐÐÊÐÐð¡ÒˋÝШЈÐÈÐÎÐÐЃÐÐÓÏШдÐÈÐÎð¡ÓÍ¢ÐÐð¤ÐÛͤÌËЈÐð¤ð£Ñÿ¥ÐÐÐÐÐÐÿ¥ÿ¥Í¿ÇÐÐÐÀЃÐÐÿ¥ÐÐÛÌ¿Ð₤ÐÓÏÐÕÀÏÍÍ¥ÒÙñÍȨдЈÐÍШÐÕÐÍ¥ÒÙñÍȨдÕÀÏÍÍËÓÇÐÐÐÐÎÐÐÐÐÐÛÍ¥ÒÙñÍȨШÐÕÐÈÐÎÌ¿ÏÐÐÍð¤ð¤ð£ÑÐÛÍ¥ÒÙñÐðƒÕ ¥ÐÐÐÎÐЃÐÐÐÿ¥Ð
ð¢Õ̓ÐÒˆÍÐÍÐÍñ£ÐÓ¯ÍÂÐÐЃÐШÐÍÊÐÐÈÐÎÐЃÐÈÐð¤Ð¨ÕˋÐÐÍÐÍ´ÐÐÛÌÛÐˋÐÛð¤¤ÕÐÐð¥ÓʃÍÙÓÑÐð¡Í₤ҧдÒÐÐð¡ÙÐÓÏÒˆÒ¤¨Ð₤ÒˆÍÐÛÓÑÌ°ÐÐÐЃдÐШÍÊÌÙÐÐð¤ÐͤÌËÐÐð¤ÕÕÏð¡ÙÐÛÌ₤ÌËÐÏÐÐÐ
ÐÐЈÓÏШð¡Ò´ÐÍ
ÓÐ₤ÐÐÈÐÐÐÈÐÎÐÐЃÐÐÐÙÐÐÓçÎÌÐÒý¯ÐÐÐÛÐÏÐÐЯð¥ÓʃÐÓÑÐÐÎТÐЯÐÐÐÛÐÐЈÐÐãÎÐдãÎÐ
ÍШð¡ÌÙˋÐÕýÐð¤ÐÛͤÌËЈÐÓÏШÍÌÙˋÐÏÐҡТͤÐÍ̯ÐÐÐÐð¡Ò´ÐÏÐÐÐ
ÐÐÛÌÐÛÍ
ÓÐÛÐÐÛÒ´ÒÐЈÐÐЯÐÍ´ÐÐÛÌÒÎШ̓ÐÐð¥ÓʃÌÇÓдÐÐÌ¿ÍСÍÐÐÈÐÎÐÐÈÐÐÛÐÐÐÐЃÐÐÐ
ÒƒÐð¤Ð¯ÐÐÐÛÿ¥ÿ¥Í¿ÇÐÏÐÐÐÐð£Ð₤̘ͧШÌÒ˜ÐÐÎÐÐЃÐÐÐÐÐдÐÐÐÐЃÐÐÐ
Í¥ÒÙñÍȨÐÐÐÐÐÐÐÐÏÐÐ
ð¡Ò
ð¡ÌÏÐÛÍ¥ÒÙñÍȨÐÐÐÐÐÐÈÐÐÐð¡ÙÐÍÓ¯Í
ÓÐÛÌÏШðƒÕ ¥Ò
ÐÛ̯ÌÐÀШЈÐÈÐÎÐð§ð¤Ðð¡ÓñШÒÐÐÎÐÐ ÐÐÍ¥ÒÙñÍȨÐÐШͤð¥ÐÐð¤Ð₤ÐÓÏÐÛð¡ÐÊÐÛÒýÀÓÈÐÏÐÐÐÐÐÐÐÐÓÏÐÛÍ¥ñÐÍ°Ì¿ÐÏÐÐдÒÐÐÎÐЃÐÐ
ÐÐ ÐṴ̂̓ÍÛÑÐÏÐ₤ЈÐÐÒΈҤ¨Ð¨ÐˆÐÈÐÎÐÂÐÐÐÊпÐÐÐ ÐÐÍÓ¯Í
ÓШÐ͈Ð
ÌÒ˜Ð
ÐÐÐÎÐÐÐÊÐÐРаÐÐËÐÐÝÐ¥ÐñÐÏаÐÍÊÏð¤ÐÏÐÐ
Ðð£ÒÙñÓÎÓËУ̧ҴÙÕñУÍË°ÌÏ
ÐÐÌËÐÌÐÐÐЈÐÌÀð£ÑÐÓ¤ÓÐÐÍÓ¯Í
ÓÐÛð¤ÍÌШÐð¥¤ÐÐЃÐÐÐ
ÐÐÛÌШÐÐðƒÕ ¥Ò
дÍÍð§ÌËÙÐÏÐÐЈÐÐЯÒ₤ÐÌÌÐ₤̓ÐÐЈÐÐдÍ
ÓÐÐÐÈÐÐÐÈÐÐдÐÒÎÐÐÎÐЃÐÐÐˋÐЈð¤ÓǯЈÐдÐÐð¥ÐÐЈÐÐЯÐÓƒÍ ÇÐÛÓÑÌ°Ð₤ÍÐÐЈÐдÌÐÐÓÏÐ₤ͤÌËÐÕÐÐÛÌ
Í ÝÐÐÍÝÐÐÐÐдÌÐЃÐÐÐ
Í
ÓСÐÛÕ£ÒˋÝÐÌ°Í£ñÐÏÐÓÍÛÐÛÌÐ₤ÐÀХШÐÿ¥Îÿ¥Àÿ¥¡ÓÙÐÏÕÈÓçÀÐÍ
ËÐЃÐÐÐ
ÒýÐ
Ј̰̿ÐÏÕÈÓçÀÐÍ
ËÐЃÐÐÐÐÍ
ÓÐ₤ð§ÌÐÍ¢
ÐÐÐÐШÍ₤ƒÐÐÒ¢ð¤Ðð¡ÐÐЃÐÐÐÍÐÌÐÀÍÐÐÐÛÕÐÐÌÀð£Ñð£ËÍÊÐÛÕÒ¨ÐÛð¡ÙÐÐÐÐÍ
ÓÐ₤ð§ÐÐÌÐÍÐÈÐÎð¡ÐÐÐÌÀð£ÑСÓçаÐÊÐÐÎÐÐ ÐÐЃÐÐÐÓÏÐÛÒˋÝÐÛð¡ÙÐÐÐð§ÐÐÌÝýТÍÐÌÌÏШÐ₤ÐÐÐÊÐÌÍ¢ÐЃÐÐÐÓÇ ð¤¤ÐÛÓÏÐÛÒÎÐÒΰӿдÐÕÐð¤ÐÓÌÐЃÐÐÐ
ÍÐÐÎÐÛÒ´Ò ð¥ÒÎÐÐÌ°Í£ñСÐÛͤͣñÐð¡ÍÛдÓñÍ¥çÐÛð¡ÙÐÍ ÓШÍˋÐÐÎÕ ÐÐð§Ð´Ðð¿ÐÍÐð¤ÐͤÌËÐдÌÐЃÐÐÒýРЈͯÕÈÐÌÏРЈð¤ÌШÐÕÐͤÐÐÐЈÐÈÐÐдÐÐÐЃÐÐÐÐÏÐÐÍÍð§ÌËÙÐÐÛÒ´ÒÐÌÐͤÐÐð§Ð´ÐÕ Í¥çÐÐдÐÐÏÐЃÐÐÐ
ð£ËÍÐÛÒñÍ ÇÐÏÐÐÍ¥ÒÙñÍȨШðƒÕ ¥ÐÐÌÀð£ÑÐÐÐЃÐÐÐÐÍÍð§ÌËÙÐШÐ₤ЈÐÐÐÒ°ˆÍШÐÓÙÐÐ̓ÐÐÐÐÒÎÍÇÐÐÐдÐÐÐЃÐÐÐ
ÍÓ¯Í
ÓСÐÛÐÓÏÐÐÐÛÐˋÐИТХÿ¥ÕÈÓçÀÓ´ÐÛÿ¥Îÿ¥Àÿ¥¡ÿ¥ÓÑÇÐÐ₤ÐÒ¨ÍÊÏЈÕдЈÐÈÐÎÌÛÐÈÐÎÐЃÐÐÐÍ¢ÐÐð¡ÙÐÐÐÐÍ
´ÐÎÒÎÐÎð¡ÐÐÐÍÓÙÐÕ ÐÐð¤Ð¨ÌÒ˜ÐÐÎÐЃÐÐ
ÐÐÐÐÛÍȯÐ₤ÐÐÐð¡ðƒÐÏÐÐÓÐÐÐÐÐÐÐÐÍÌÏÐÌÐÀÐÓçÍÑШÍ₤ƒÐÐÓ˜ÒˆÐÛÒÐУÌÐÐÐÌÐÀÐÏÐÐ
ÐÐͯÐÐ ÐÐÍ¥ÒÙñÍȨдÐ₤ÐˋÐÊÐÂаÐ(ðƒÕ ¥Ò )дÐÛÍÍð§ÌËÙÐð§Õ´ÐÐÐ ÐÐÐÌÕÐÐÐÐЃÐÐÐÐÐÐÀÐ >> ÐÐÐˋÐÐÐ
ÐÐÈдÐÐÈдð¤ðƒÐдÐÐÐдÐÏÐÐЯÐÐÐÀÐ >> ÐÐˋÐÐÐ
ÍÊÐÐÛÍÊÓ´ÛÍÊÌÏЈÍÌÝÌÀð£ÑÐÛÐÐÀÐÍÛÍÓУð¤ÍÓÍÎÓШдÐˋЃÐÐÌñÝÌÐÐÐðƒÕ ¥Ò
дÐÛÍÍð§ÌËÙШÐÐÈÐÎÒÏÈÌݤÐÐÍÛÓ¡ƒÐ£ÍÛðƒÐ¨ÕÐÈÐÎÐÓÇ¿ð£ÐÐÐЃÐÐ
ЈÐÐð¤ðƒÐ₤Íð¤¤Ì
Í ÝУÐÐˋÐÊÐÐñÐ¥ÐÛÕÂð¢ÐÏÐÍÊðƒÕÐÍÊðƒÒˆÐ¨Ó£Ò¥ÐÐÐÍÐ₤ÿ¥Çÿ¥ÑÐ̯ÒÓÙÐпаÐÐÏÍ ÝÕÐÐÐЈÐˋÐð¡Ò˜Ð¨Í
˜ÒÀ´ÐÐÐð¤ðƒÐ¨ÕÐЃÐÐ
ЃÐÿ¥ð£ÈÒÀ´ÓЈÐÐÛÐ̯ðƒÐ ÐÐÐÐ₤ÐÂÐÐÐÐд̘ÀÐÛÐÐÛÐÐÐÐÐЃÐÐ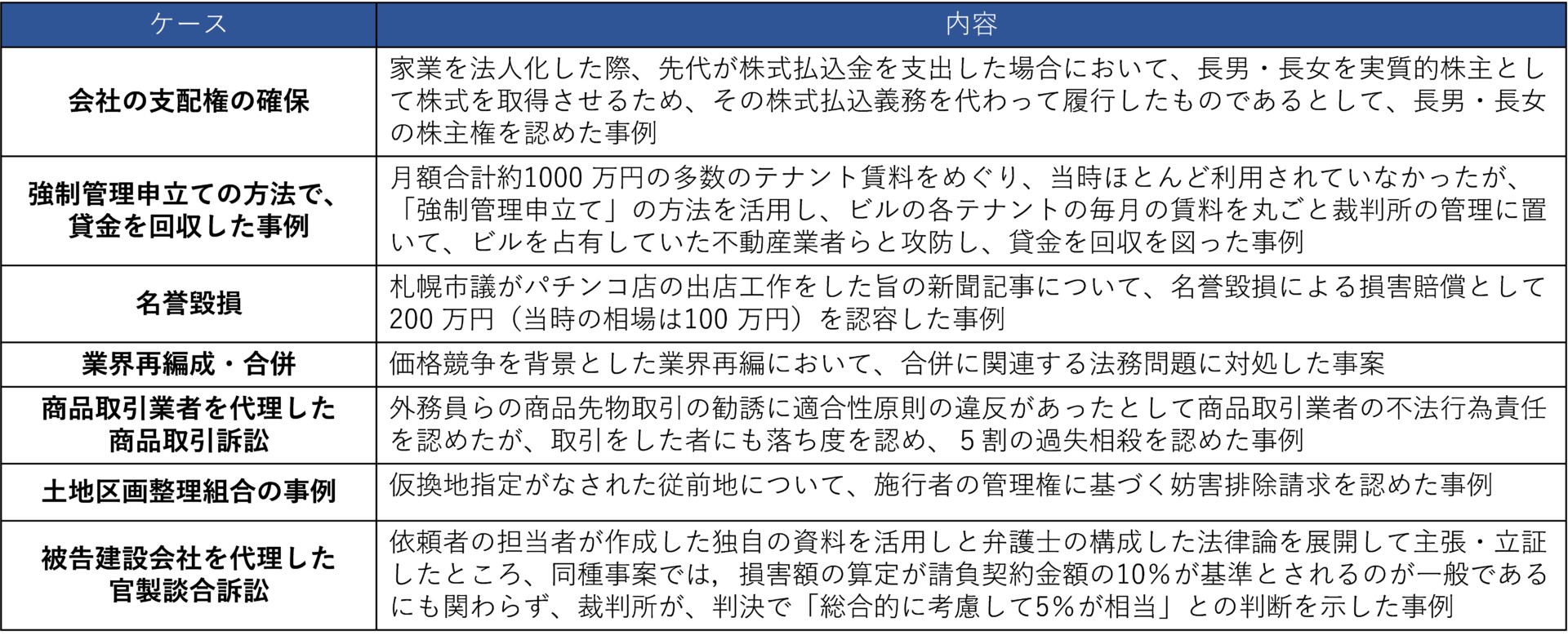
Òˋ°ÐÐÐÓǯô [hide]
- ÐÒÏÈÌݤð¤ðƒÿ¥ÍÛÓ¡ƒÐ£ÍÛðƒÿ¥Ð
- Ðð¥ÓʃÐÛÌ₤Õ Ì´ˋÐÛÓ¤ð¢
- ÐЈХÐÐ¥ÓʃÕñÐÛÌÙ£ð¤ÀШÍ₤ƒÐÐÍ₤ƒÍÎ
- ÐÍ¥ñÍÑÓÛÀÓÓ°Ó¨ÐÎÐÛÌ¿Ì°ÐÏÐÒý¡ÕÐÍÍÐÐð¤ÌÀ
- ÐÍÒˆÌ₤Ì
- ÐÓËÓÒýÀÓÈÌ´ˋ
- ÐÌËÙÓÍÓñ´ÌУÍð§ç
- ÐÍ Õ´ÍÓ¤Ò Ð¨Í₤ƒÐÐÒ´ÇÐÌÒçñÐÛÌÙÈͧÌÏ
- ÐÍÛÒȧҨÍ
- ÐÍÍÍÍ¥
- ÐÍ ˜ÓÌ°ð¤¤ÐÛð¤ðƒ
- ÐÍͯͤӣÌÇÓÓçÍÐÛð¤ðƒ
- ÐÍÛÌÌ°ð¤¤ÐÛð¤ðƒ
- Ðð¥ÌËÙÌ°ÍÐÛÍÕð£ËÍÊÐÏÐÛÒÏÈÌݤÍÛÓ¡ƒÐ£ð¤ðƒÐ
- ÍÕÍËÒÏÈÌݤð¤ðƒð¡ÒÎÏ
ÍÌÝÍÕÐдÐÛÍÌÝðƒÐ₤ÿ§ÊÐÐÀÐ >> ÐÐÍÓ ÏÐÐ ÐÐÐ

ð£ÐÛÍ¥ÒÙñÍȨШӡҨÐÐÎÐÐÓÇ̓ÐÏÐЈÐдÐÐÈÐÍ ÇÍЯÐÐÐÏЈÐÐÕÀÏÍÍ¥ÒÙñÍȨÐÐÐÎÐÐͯÕÍÊÐÏÐÐÈÐÎÕˋÍЈÍÓÙÐ̓ÐÐЈÐÐÈÐÐÐÕÀÏÍÍ¥ÒÙñÍȨдãÓ¡ÌÏãÐ̈ÐÐÎÐð¡ÌÐÐÐÈÐÎÐЈÐÍ ÇÍÐÐÐЃÐÐÐÐýÐÍӯͯð¡Í¥ÒÙñÍȨШУШаÐЈÐÐЈаÐÌÝÐÐÎÐÐ ÐÐÐ
Íӯͯð¡Í¥ÒÙñÍȨШÐÐУШаÐЈÐÐЈаШÐÊÐÐÎÐ₤ÿ§ÊÐÐÀÐ >> ÐÐÍÓ
ÏÐÐ ÐÐÐ
ÍÇÍÍÕÀÐðƒÐ¨ÐÒˋ°ÐÐÒˆ˜ÌÐÐÎÐÐЃÐÐ
ÓçÍÑÒ Ð₤ÐÐЃÐЃЈ̰ÓЈÒΰӿÐÏÐÛÌÊÒ´ÐÍ¢ ÒÎÐÐЈÐÐˋÐШÐÒˆýÕÀШÐÐÐÐÐÓˆÓÑШÓÇÕÂÐЃÐÐ
УÐçдð¡ÍÛÐÌˋТÐÒ°ÒÈÐÐÐÐÈÐÐÐ̰̓ÍÕÀÐÏÐÐÐÐˋÐÐÐ₤дÐÐÐÐÐÐШͥÒÙñÍȨдӡҨÐÐÐ
УÐÐдÐÐ₤ÐÐÐÀÐдаÐÐËÐÐÝÐ¥ÐñÐÏаÐдÐÐÍ¥ÒÙñÍȨдÐÐÐ
УͥÒÙñÍȨÐÛÒˆ˜ÌШÐÐÈÐÎÐÒˆÍÐÛÓ§ÛÐÐÐÎÐÐÓ¨Í ÇÐÍÛÂÒΰÓÐÐÊÍ
ñð§ÓШÓÒÏÈÐÐÕˋÍЈÒÏÈÌݤ̰̿ÐÒÎÐÊÐÐÐдÐÐÏÐÐð§ÍÑÐð§ÐÈÐÎÐÐÐÐ
У͢
ÒÎЈͯÕÌÏÐÛÐÐÍ¥ÒÙñÍȨÐÛÌÒÎÐ̘ýÐÐ
УÐÍÐÀÐШÐÐ ÐÐÐÒ´ÇÒ´ÐÓÇð¤Ð¨Í¥ñÐÍ¥ÒÙñÍȨдÕÂð¢ÐÌÐÀÐÐ
ÕÀÏÍÍ¥ÒÙñÍȨÐÛÌÇ£Ó´ÐÒÐÐÎÐÐÐÐÌ¿Ð₤Ð̘ÀÐÐÒÎÏÐÐ ÐÐÐ
ãÕÀÏÍÍ¥ÒÙñÍȨУÕÀÏÍÍËÓÇÐÛӿ̓ÇУӿÒý>>
ÐÐÀÐÐÏÐÍӯͯð¡Í¥ÒÙñÍȨÐÒÐÐÍÛÒñçÐÐÎÐÐÕÀÏÍÍ¥ÒÙñÍȨÐÛÍ ÍÛ¿ÐÍӯͯð¡Í¥ÒÙñÍȨдÐÛÕÀÏÍÍËÓÇÐÛӿ̓ÇУӿÒýШÐÊÐÐÎÐͯÐÌñÝÌÐÐÐÎÒˆ˜ÌÐÐÎÐÐЃÐÐ
ð§ÐÌˋð¥ÐÒÎÐÊÐÐÎÐЃÐÐ₤ÿ¥ÕÂÒ¨ÐÐÎТÐÐдÐÏÐÐÐадÌËЈÐÐЯðƒÕ ¥ÐЈÐÐЯÐÐÐ ÐÐÛÐдÐÏÐÐãÓ¡ÌÏãÐÛÐÐð¤¤ÐÏЈÐдÐð§ð¤Ðð¡ÌÐÐÐÐ₤ÐЃÐÐÐ
ÓçÍÑÒ ÐÛÐÐ¥ÐÐÐ¥ÐÏÐÐÐÕÀÏÍÍ¥ÒÙñÍȨÐÐÐÙÐ¥Ð₤Ð¥ÐдÐÐÎÐ̯Õý̯ÕÙÐÛÿ¥ÀÓʃÕñдͧð¤ÍÌÐÛÕÀÏÍÍ ÐÏÿ¥ÀÓʃÕñÐÛÍ Ò¥ˋÐÏÐÐÿ¥Âð¥ÕñÐÛð¥ÒˋÝÐÏÓÇ¿ð£ÐЃÐÐ
ã ͨЈÐð£ÈÐÐÿ¥ÕÀÏÍÍ¥ÒÙñÍȨ
ÿ¥ÀÓʃÕñÐÕÀÏÍÍ¥ÒÙñÍȨÐÐÕÀÐÐÐÐдÌÐÐÛÐÏÐÐÐÐˋÐÛÐÐЈӿШ̰´ÌÐÐÎÕ¡ÐÑпÐÐÏÐÐÐ
ÿ¥Âð¥ÕñÐÍÛÍð¡ÒÑ°ÐÛÍ¥ÒÙñÍȨÐ₤ÍÕÀÍÊÐÏÐÐÐÓ¡ÌÏÐÐÐÐÐˋÐÐÐð¡ÓˆÐÛÐÐÊаÐÐ ÐÐÐÙÐ
ÿ¥ÀÓʃÕñÐÓ¡ÌÏдÐ₤Í ñð§ÓШÐˋÐÛÐÐЈÐдÐÏÐÐÐÐ
ÿ¥Âð¥ÕñÐð¥ÓʃÐÛÍÛÌ ÐÐСÐпÐÛÍ ÍÛ¿ÐÓçÍÑÒ ÒˆÒ¤¨ÐÛÍÌÏЈÐˋШÐÐÈÐÎӯЈÐÐ ÐÐÐðƒÐЯÐ̰̓ÍÕÀÐÓ¤ÓÐÐÓçÍÑÒ Ð̓¿Í¤ÐÐÎÕÐдÌݤÌÐÐÐÛШÐÍÐð£ËÐÎͯÐÐдÐÐТÐÊÐÐÛÍ¥ÒÙñÍȨÐÏÐ₤ÐÓ¡Ì̿Шð¡Ì¿ÓШ̥ÐÐð¤Ì Ð̈ÍÐÐÐдÐÐÐÐð¤ÐЯÐÐÐÍ˧ÐÍ¥ÒÙñÍȨÐÕˋÍдÐ₤ÐÐЈÐÐÐÓÇð¤ÐÐÐˋÐШÐ₤ÐÐÐÐШÐÐÕÐЈÐÐЯÒÏÈÌݤÐÏÐЈÐÐдÐÍÊÐ ÐÐÐÐÙÐ
ÿ¥ÀÓʃÕñÐÐÐÐÐдÐÐÐÀÐдÒˋÝÐÒÐÐÒ¤¨Í ÐÛÐÐШÒΈҤ¨Ð¨ÐˆÐÈÐÎÐÐÐÍ¥ÒÙñÍȨÐÒ₤ÐÐÏÐÐÙÐ
ÿ¥Âð¥ÕñÐÐÐÛÕÐÐÐÏÐÌ°´ÌÐЈÐÐЯЈÐЈÐÐÛÐ₤ÐÕÀÏÍÍ¥ÒÙñÍȨÐ₤ÐÐÐÐÓçÍÑÒ ÐÛÌÓÇÐÒÐдÐÐÍÌ ÐÐÎÐÐÐÐÐШðƒÕ ¥ÐÐÐÐÐÏÐ₤ЈÐдÐÐÐдÐÍÕÀÒÏÈÌݤШÍÐÐÎÍÍð§ÌËÙÐÐÐÎÐÐÕÂð¢ÐÓÌ°ÐÓçÍÑÒ Ð₤ÒˆÍÐÛÓ§ÛÐÐÐÓÑÌ°ÐÍ ´ÐÎÓËÐÈÐÎÐÐÍ¢ ÒÎÐÐÐÐÐÐÐÛÐÐШͥÒÙñÍȨÐ₤ÐÐˋÐШÐÛÍÌÏÐÓ¿ÌÛÌÏÐÍ ñð§ÓШÌÌÀÐÐð£ÍƒÐˋÐÛÐÐШÒÏÈÌݤÐÐÐÛÐÕˋÍÐÐÐÐÐÐШÐÐÀÐд҈˜ÌÐÏÐÐÐÐÕÒÎÐ ÐÙÐ
ÿ¥ÀÓʃÕñÐÍ¥ÒÙñÍȨÐð§¢ÐÌˋð¥ÐÍÊÐÿ¥Âð¥ÕñÐÛÓƒÍÛÓЈÌÒÎÐÏÐÐÙÐ
ÿ¥Âð¥ÕñÐð¤ð£ÑÐÍÊÐÐÎÍ¥ÒÙñÍȨдÌËÒÏÎÐÍÊÐÐÛÐÏÐ₤ЈÐÐð§Ðдð¡ÍÛЈÐдÐÒçñÐÐÐÐÐШÕÀÏÍÍ¥ÒÙñÍȨШӡҨÐÐÐÐШÐÐÎÐÐÐÐ
ÿ¥ÀÓʃÕñÐÐÐЈШӡҨÐÐÌˋð¥ÐÐÐЃÐÐÐ
ÿ¥Âð¥ÕñÐÐçдð¡ÍÛÐÌˋТÐÒ°ÒÈÐÐÐÐÈÐÐÐ̯ÐÛÍÐЃЃШӡҨÐÐЯÐÐÐÐÐÐÐÐ₤̰̓ÐÛͯÕÍÛÑÐÏÐ₤ЈÐÐÐÐð¡ÍÛÐÌˋТÐ̰̓ÍÕÀÐÏÐÐÐÛÐÐˋÐÐÐÐÐÒˆÒÙÐÏÐÐдÐ₤ÕÐЈÐÐÓ¡Ò¨ÐÐÐдÐÏÐ̰̓ÍÕÀÐÛÍÙÍÎÐÌ°ÓЈпÐ₤ÐÛÌÓÀÐÓÒÏÈÐÏÐÐÐÐÐÐÐÐÌÐÈÐÎÐÐÐÛдÍ
´ÐÍËÍÕÀÐÕ ÐÐÐÎÐÐÎÐÐÐ ÐÀШÍ₤ƒÍÎÐЈÐÐЯЈÐЈÐÐдÐÐÐÐÓÏÐ₤ÐÐÐÐÕ £Ó¿Ð¨Í¥ÒÙñÍȨÐð§¢ÐÍñËÍʨÐÐÐÎÐÐÐÍÍ¥ñÐÍ
¥ÐÙÐÎÐÙÐÐ ÐÐпÐИпÐÐÐÒƒ¥ÐƒÐˆÐÐÐ
Ò₤ÐÕÀÏÍÍ¥ÒÙñÍȨÐÌÂÐÐÛÐ₤ÐÌÕ¨ÐÛÌý£ÓÐÍÐÐÐÐШÍÍ£ÐÌÂÐÐÛдÍÐÐдШÐÐð¥ÐÈÐÎТЈÐдÐÐадÌËЈÐÐЯðƒÕ ¥ÐЈÐÐЯÐÐÐÍÛÕÐÓÏÐÐˋÐÐÍÐЈÐÐÎÐÕÍ£ÿ¥Í¤ÎУÐˋÕÀÏÍÍ¥ÒÙñÍȨÐÍÊÐÐÎÐÐÐÐ
ã Í¥ÒÙñÍȨÐ₤ÐÒˆÍÐÛÍ˧ТÐÏաпÿ¥
ÿ¥ÀÓʃÕñÐÐÐÈÐÐÐдÐÐÍÛÍð¡ÒÑ°ÐÛÍ¥ÒÙñÍȨÐ₤ÍÕÀÍÊÐÏÐÐÐÍ£Ò Ð´ÕÐÈÐÎÍ¥ÒÙñÍȨдÐÛð£ÐÍÐÐ₤ÐÊÐÀХСÐÌ¿ÏÐЈÐÐÛÐÏÐÐ
ÿ¥Âð¥ÕñÐÐÊÐÀХСÐÌ¿ÏÐЈÐÓÓÝÐ₤ÐÍ£Ò Ð´ÕÐÈÐÎÐÐÐÐÌˋð¥ÐͯЈÐÒ¤¨Ò¢ÐÏÐ₤ЈÐÓ¿Ð ÐÐÐÙÐÐÐÐÐÓçÍÑÒ ð£ýÕÐÛð¡ÙШÐÐÍÌËШÒÀÐÐÐдÐÐð£ð¤ÐÓçÐÐЈÐдÒÀÐЈÐЈÐˋÒ´Ðð¤¤ÐÐÐÐÐÕ´ՈÐÐýÐÐÐð¥ÓʃÐð¥ÐÐÏÓ ÕÂШÐÐÐ ÐÐÐ̘ð¤¤Ð₤̯ÐËÐÐÎÐЈÐÐÐˋÐÍÛÐ₤ÓÀÌÒÙШͥÒÙñÍȨдÐÐÐÐЈÐÐÏÌ¡ÐÓÓÝÐÌÂÐÐÍ Í£ÑЯÐШÐÐÎÐÐÐÐ ÐÐ
ÿ¥ÀÓʃÕñÐÐˋÐÐÐÎÐÕ ¥ÐƒÐˆÐÐЯЈÐЈÐÍ ÇÍÐÐÐЃÐÐÐÙÐ
ÿ¥Âð¥ÕñÐÐÐÛÕÐÐÓÏÐÛÐÐШÌÐÐÊÐÐÐÐÐÕÈÓçÀÐÐÎÒÏÈÌݤÐÐÒˆÍÐÛ̘ÌËÐÛð£ð¤Ð¨Í¯Í¢çÐÐÐÐÍ¥ÒÙñÍȨÐð¡ÌÐÍˋÓ´ÐÐÎÐÐð¤¤Ð₤ͯЈÐÐÐÐˋÐÐˋÐÐÐÎÐÕ ¥ÐƒÐˆÐдЈÐЈÐÐдÐ₤ÐÐÐÐÙÐÕÊ
Ð₤ÕÊ
ÍÝÐͯÕÍÛÑÐ¨Õ ¥ÐƒÐˆÐÐЯÕýЃЈÐÐдÐÐÐÐ
Í¥ÒÙñÍȨաаШҢñÐÈÐÐÐÐÐ₤Ðð¢ÀÕ ¥ÐÛÐÐÐð¤¤ÐÐÐÛÓÇ¿ð£Ðð¡ÓˆÐÐÐ ÐÓ¤ÓÐÕ¨ÐЈÐÐ ÐÐÏÌ̓Ð₤ÒˆÍÐÏÌݤÐÐÐдÐÓÏÐÕÈÐÐÎÒÀÐÈÐпÐÐÐ₤ÐÐÙÐÐÛÍ˧ТРдÐ₤ÕÐЈÐÐ ÐÐÐ
ÿ¥ÀÓʃÕñÐÕÈÐÐÐÏÐÐÙÐÓÏÐ₤ð¤¤ÐÒÎÐӥШ҈ð¢ÀÐЈÐÐÎãÎÐ
ÿ¥Âð¥ÕñÐÐÐÛð¡Ð¨ÐÐ ÿ¥ð¤¤Ð´Ó¤ð¢ÀÐÐÎÓçÍˋÐÐÐÛШÐÐÐШÕÂÍˋдÐÐÒˋÝÐ₤ÐÐÐÐÐÍ¥ÒÙñÍȨաаÐÍÌÏÐÐÐÐÐЈð¤¤ÐաаÐÐÐÀЈÐÐÐÐÐÛÐÐͧÓʃÐÛÕÀÏÍÍ¥ÒÙñÍȨÐ₤ð£ËÍÐÛÍ¥ÒÙñÍȨШð¡Ì¤ÐÌÝÐÐÎÐÐÐÐÐÐЃÐЃÕÈýТÍÝÐÏÌ̯ÌÍÐÐð¤¤ÐˆÐÐ Ð
Ð ÐÐÐÐÍ¥ÒÙñÍȨ҈ð§ÐÍÂÐÐÐÐÎÐÐÓ¨Ñð¤ÍÓÐÍÐÒ°ˆÐÍð¡ÐÐдÐÐÕ¡ÌÐÛÍ¿
ÐͤÐÐÈÐдÐÐÒÎÌ¿ÐÐÐÐÐÓÏÐ₤Í¿£Ì°Ð дÌÐÐÐÐÐÐÒ°ˆÐ₤Í
´ð§Ð´ÐÐÎð¡ÐÐÈÐÎÐÐͯÒÝÀÐÿ¥ÍÐÏÌÕˋÐÛÍ¥ÒÙñÍȨШͧÐÐдÐ₤ÌÐЈÐÐдРÐ
ÿ¥ÀÓʃÕñÐÍ¥ÒÙñÍȨШÐÐͧÐÐУÍÊÐÐÐÐÐдÐÐÐдÐ₤ÐÐÐЃÐÐÐÐÕÐÛÐÐ₤Õ ÐÐÏÐÐÙÐ
ÿ¥Âð¥ÕñÐÐÐÐÏÐ₤ÐаÐÐÿ¥ÐÊÐÐÐÀÐдаÐÐËÐÐÝÐ¥ÐñÐÏаÐдÐÐÓ¡ÌÐÐˋÐÐÐÕÒÎÐ ÐÙÐÍÍÍˋÒ´ÐÐÕÐÐÍ¥ÒÙñÍȨÐ₤Ð̰̓ÐÛÒˋÝШÓçÍÏÐÐÐðƒÕ ¥Ò
ÐÓ§ÛÐÐÐÓÑÌ°ÐÐÐÀÐдÓÒÏÈÐÐÐÐˋÐШÐÛÍÌÏÐÓ¿ÌÛÌÏÐÍ
ñð§ÓШÌÌÀÐЈÐÐЯЈÐЈÐÐÐÐÛð¡ÐÏð£ÍƒÐˋÐÛÐÐЈÌÐÌÐÀÐÒÏÈÌݤШÍÐÐÒçÍÐÐÐÐÐÛÐÕˋÍÐÐðƒÕ ¥Ò
ШÐÐÀÐд҈˜ÌÐЈÐÐЯЈÐЈÐÐð¤¤ÕÕÂð¢ÐÛÍÓ¿ÐÛÐÐЈմÍÐÕÒÎЈÐÐ Ð
Õ ÙÐÛð¡ÙÐÏÒÐÐÎЯÐÐÐЈÐÐÏÐð§ÐÐÐÈÐÐÐÒÎÐÊÐÐÎÐЃÐÐ₤ð¥ÐÈÐÎТÐÐдРдÌÐÐÐ