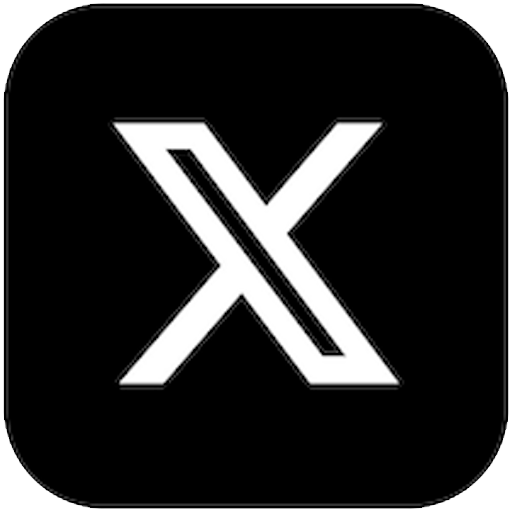ÿ¥˜ÿ¥ˋÿ¥Ûÿ¥ËÌð£ÈÐÛаÐÐËÐÐÝÐ¥ÐñÐÏадÐÌÌÒÀ´ÓʤÐУÐð¢ÀÓ´ÌÏÿ¥Ò´¥Ì ðƒÀÍÊÿ¥ÐÐÛÍÝÐÐ
ÿ¥˜ÿ¥ˋÿ¥Ûÿ¥ËÐ₤ÐÐдÐдÍÛÑÌÐÍð¤¤Ð´ÐÛ̯ң§ÐˆÕÈÓçÀÐ̯ÌÐÀÐÛÍ
ÝÌÐÓÛÓдÐÐÎÓ¤ÍÝÐÐÎÐÐÐХШÐÏÐÐ
ÐÐÛÐÐÐÍ°ÌÌÏУÕÍ
˜Í¥ÌÏУÌÌÏЈҢÓÙÐÒ´ÝÍÛ¿ÐÐÌÏÒ°ˆÐÍ¥ñÐÐÐÍ
ÍÛ¿ÐÍÍШÌÊÒ´ÐÐÐÐÐÏÓ¤ÍÛÓЈÌÌÐÒÀ´ÌÐÐÌÌÛçÐдÐÐÎÐ₤ÐÐÐÐÐÒ´ÙÒ´ÐÐÐÎÐЃÐÐÐÏÐÐÐ
дÐÐÐÐÍˋÓ´Ò
ÐÛÌËÍÂддÐШÐӃʹÐÏÐ₤ÌËÙÍÕÈÓçÀÐÒñÍ ÇÐÛÌÓʤÐÍÍ¥ÕÂð¢ÐÛÕÈÓçÀдÐÐÈÐÐÍ
˜ÓУ̤Í
˜ÓÐˆÍ ÇÕÂÐÏÐͤÐð§¢ÐÐÐÐÐШЈÐÈÐÎÐЃÐÐ
ÐÐÐÐÐÐÐÐÛÍ ÇÕÂШÕˋÐÐÐÍˋӴШХШÐÐÐÒý˜ð££ÐÛÓ₤ÍýÐÐ₤ÍÍШÌÇÓÐÐÐÎÐÐÐÐÓçÌдÐÐÎÐÓÏÓЈð§¢ÐÌ¿ÐÛÐ₤УÐÐÐÛЃЃÍ
˜ÓÕ ÍСÌÐÀÒƒ¥ÐƒÐÐÎÐÐÐÛÐÍÛÌ
ÐÏÐÐ
ãÍÛÌ Ð̘ÌÐÍ¢ ÐÐÐÍÌ ÐЈÐãÐÀÐУХСÐÓЃÐÐÓÓÝ
ÌËÍ¡¡ð¥ÒˋÝÐÏÐÐͧÂÍ¥ÓШÐÐÐÐдÐÐÐÐЃÐÐÐÐТЃÐÐÐÐð§Í¤ÎÐÓ¿¯ÐÒ¢ÐÍ ÇÕÂÐÐÐЃÐÐ
ÓÒÙñÍ¡¨Ðð£ÒÙñÍȨÐð§Í¤ÎÐÐÐÐÐЈÐÐÐÙÐдÍȯÐÐÐÐÐÛÐÐÌݤÐÐÎãÒ˜Ó§ˆãÐÓÛÓÐÏÐ₤ЈÐÐÕÂð¢ÐÓˋÐÐШð¢ÐÊÐÐÐÛ̧ÊÌ£Ìý¿Ð´ÐÐÎÐÛÍÇÕÂÐÍ¥ñÐдҴÐÐЃÐÐ
ÐÐÐÐÐÒ´ÒÐÛÌÍ°ÐÐÐÐÐÕÂð¢ÐÛÓÑÙÌÐÐÍˆÍ ÐÐаÐÐËÐÐÝÐ¥ÐñÐÏаÐ₤Ðÿ¥˜ÿ¥ˋÿ¥Ûÿ¥ËÐÛÍ ÇÕÂÐÏÐ₤ÐÐШÕÀÒШӃÐЃÐÐ
-
-
-
ð¡Í¡ÐÍÍ¥Í ÐÐÐÛÐÀÐУХСШÐдÐÐÐÐÍ°Ò¢ð¢ÀÐÐ
-
ÌñÝÐÒÐÐð§ÒÈÐЈÐЃЃÐð¤ÒÏÈÐÏÐÐдҢÐÐÎÐЃÐ
-
дШÐÐÐð£Ð₤ÒÏÐÓ¨ÐÎЈÐÒ¢ð¤ÐÐաаÐÐÀ
-
-
ÐÐÛÐÐШÐÐÐÛÍ ÇÐÐÛÐÐŲ̂ÍÛÓЈ͢ÓÙÐÍÂÐÐÐÐЈÐÈÐÎÐЃÐÐ
ÐÍÕÊУÓñ´ÕÐÍÛ¿ÌÐдÐÐÓ¿ÌÏÐÓ¤ÍÛÓÌÌÐÌÌÏШÐÐ
Ì¡Ó¯ÀÐÐÀХШдӯЈÐÐLINEÐÏÐ₤
-
-
-
Õð¢À̓ÐÛÍÕÊ
-
Óñ´Õÿ¥ð¢ÛÌÙÈÿ¥
ÐÍÛ¿ÌШÐÏÐЃÐÐ
-
-
ÐÐÛÐÐÐÊÐÏÐÓÇÐÐÐдÐÐÌÒÎÐÐ
ãð£ÐÐÛÐÀÐУХСШÓ¤ÍÛÓЈÌÌÐÒƒ¥ÐÐÍ¢
ÒÎÐ₤ЈÐãдÐÐÍ¢ÓÐÓТÐÐÐÐÌÌÒÀ´ÓʤÐÛÓ¤ÍÛÌÏÐÍ¥ÝÐÐÍÍ Ð¨ÐЈÐÈÐÎÐЃÐÐ
Í ˜ÓЈÐÐˋÐШШӤÍÝÐÐÐÐÓÓÝ
ÐÐÐÐLINEÓ¿ÌÐÛÌÏÒ°ˆÐҡЃÐÐдÐLINEð¡ÐÛÐÀÐУХСÐ
-
-
-
̘ͧÐÛÌÌ
-
Ì°ÓЈÌÌÒÀ´Óʤ
-
ÍËÓÇð¡ÐÛÍÌ
-
-
дÐÐÎÌÝÐÐÐÛÐÐˋÐÐÐÌ
ÕЈÍÊÌÙÐÍ¢
ÒÎÐÏÐÐ
ÐÒ´ÐÈÐÿ¥Ò´ÐЈÐÐÐð¤ÒÏÈÐÐÿ¥ÐÐÎÐЈÐÐЈÐˋÐÛÓÇð¤ÐÛÓ´ÛШЈÐÐÐÐÐÛÐÐÐÐÛÌÏÕ ÓÓÓÝШÐÐÐÐÛÐÏÐÐ
ЃдÐ
ÿ¥˜ÿ¥ˋÿ¥Ûÿ¥ËÐÛÓ¿ÌÏдÐÐÛÍ ˜ÓÍˋӴШÐÐÐÍÕÀÓ¿ÐҡЃÐÐÿ¥˜ÿ¥ˋÿ¥Ûÿ¥ËÐÛÐÐдÐÐÏÐÛÐÀÐУХСШÐÊÐÐÎÐÛÐͧð¤ÍÌÐÛÌ Í§ÌÀð£ÑÐÏÐÛÓçմдÍÛÒñçÐͤШÐ
ÌÌÒÀ´ÓʤÐÛÓ¤ÍÛÌÏÐÒ´¥ÌÍÿ¥ãÒ´¥Ì ðƒÀÍÊÿ¥Ð´ÐÐÈÐÒÎÓ¿ÐÐÐð¥ÐÐÐÐЃÐÐÐ
ÕÂÕÈÒ´ð¤
ÐÐÛÐÐ¥ÐÐÒÈÍÊÐÛð¤Ó¿Ð´ÐˆÐÈÐð¤ðƒÐ₤ÐÐÐÀÐÐ