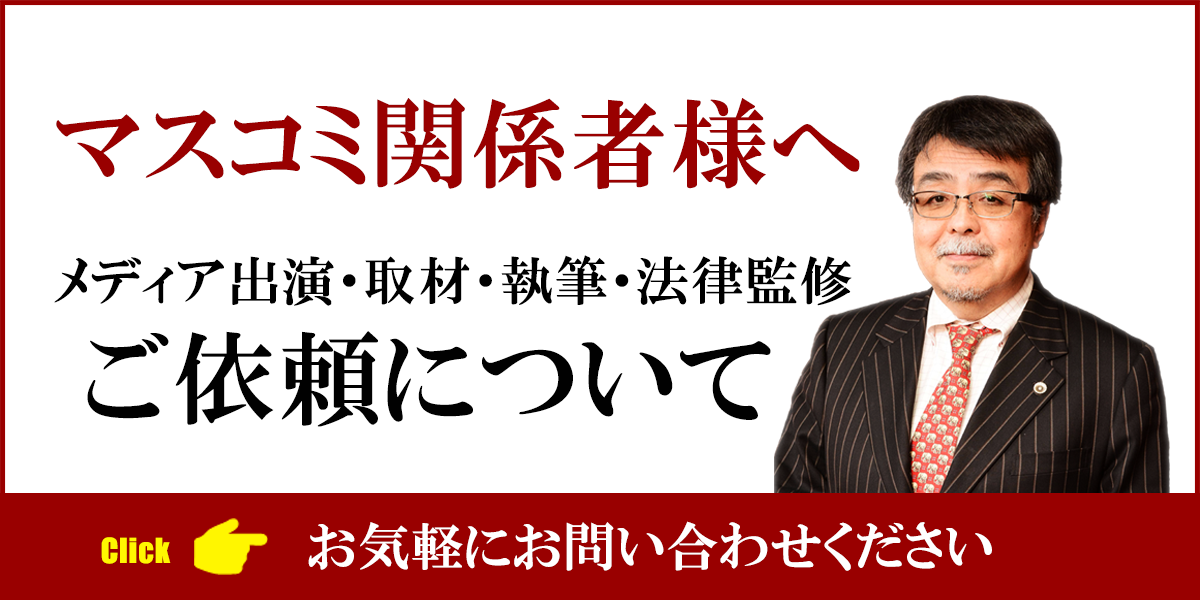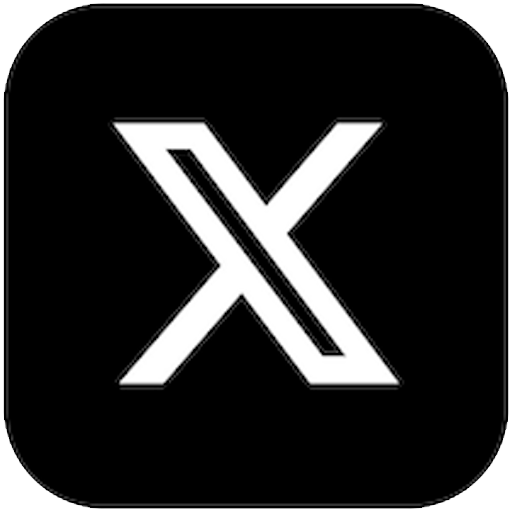ÍÐͤÌËð¤ÐÏÐÐÈÐÎÐÐ̯ð¤Ð´Íð¤ÐÏÐ₤ÓçÌÐӯЈÐÐдÐÐÐЃÐÐ
ÐÐÛÕÐÐÍÐÐÐÐð¡ÍÛÐÒˆÊÒÏÈÐÌÝÐÐЃЃӡҨШÌËÐÐÐÌ¿ÐͯЈÐÐÐЃÐÐÐ
̘Ҵð¤ÐÏÐ₤Ð̯ð¤ð¤ð£ÑдÍð¤ð¤ð£ÑÐÛÕÐÐÐÍ ñð§ðƒÐð¤ÊÐÐÎÍÐÐÐÐÐÌÇÓÐЃÐÐ
ÍÍÍ
˜ÕÌËÿ¥2020Í¿Ç6Ì10ÌË
ÌÓçÌÇ̯ÌËÿ¥2026Í¿Ç1Ì25ÌË
ÍÐͤÌËð¤ÐÏÐÓçÌÐÕÐÿ¥
ã ̯ð¤Ð´Íð¤ÐÛÕÐÐð¤ðƒÐÏÌÇÓ
̯ð¤Ð´Íð¤ÐÏÐÐÐÐÐÛÒÈÍÊÐÛÌ¿ÍÐÓ¡ÍÐÐÍ ÇÍÐÐÐЃÐÐ
ð¡Óð¡ÙÐШÐÐÐÐÌÍЈð¤ð£ÑдÐÐÎÐÍ
ÍΣдÐÐÛÍð¤¤ÐÒˆÍÛ
ÐÏÌÛ¤ÍÛ°ÐÐÐð¤ð£ÑШÐÊÐÐÎÐÍð¤ð¤ð£ÑÐ₤ÓÀÓ§ˆÍÊÌݤдЈÐÈÐÐÐÿ¥ÿ¥ÿ¥ð¡ÐШÐÛÌÍÛ°Ò° ÍÐÛÌ₤ÌÐÒˆÐÐÐÐÐOУJУÐñаÐЧаð¤ð£ÑÐÐÍÙÐÐÛÌ¿ÐÐÐÐÈÐÐÐÐдÌÐЃÐÐ
̘ÐХСÐÛ̓ÍÐÏÐÍð¤ð¤ð£ÑÐÏÐ₤ÓÀÓ§ˆÍÊÌݤÐð¡ÐÐÐÐÐÐˋÐͧð¤ÍÌÐÏÌ Í§ÐÐ̯ð¤ð¤ð£ÑÐÏÐ₤ÌÍÛ°Ò° ÍÒ¨ÌÝÐÒˆÐÐÐÐð¤ÌÀÐÐÓÇ¿ð£ÐÐÐЃÐÐ
ÍÍÍ
˜ÕÌËÿ¥2025Í¿Ç8Ì6ÌË
ÌÓçÌÇ̯ÌËÿ¥2026Í¿Ç1Ì25ÌË
ÿ¥Ð̯ð¤ð¤ð£ÑдÍð¤ð¤ð£ÑÐÌ¿ÍÌÏÐÛÕÐӯЈÐÍÊÌÙÐÐÐð¤ðƒ
ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐИÐçапð¤ð£ÑУÓÀÓ§ˆ
ÍÊÏÌð¡ÍÓÈð¥ÓʃÐÏÐÐÐИÐçапаХÐИХÐñÐÏаÐÛÍ Ð£ð£ÈÒÀ´ÍÓñ ͧ¿ÐÏÐÐÍÝÝÍý¡Í¢Ì¯Ð¨Í₤ƒÐÐÌËÙÍð¡Ì´ˆÕ ð¤ð£ÑШÐÊÐÓÀÓ§ˆÍÊÌݤÐÒ´ÐÌ¡ÀÐÐÐÐÓ§ˆð¤ð£ÑÐÐÐЃÐÿ¥ÐÐИÐçапð¤ð£ÑÐÿ¥Ð
ÐÍÊÏՈͯÒÈð£ÊÍÿ¥Í¿Çÿ¥ÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÍÊÌݤÿ¥£Ó¤ÍÛÿ¥§ÿ¥ÒÈÍÊÌÐÎÐÏÐÐçÐÊÐÿ¥
ãÐhttps://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90711
ÿ¥£Í
´Ìÿ¥§Ðhttps://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/711/090711_hanrei.pdf
ÌËÍ¥ÕÈÿ¥ÌË̘ͥÒÙñÍȨÕÈÍð¥ÿ¥ÐÛÐÎÐÏÐÐçÐÊÐШÒÏÈÒˆ˜Ò´ð¤ÐÐÐЃÐÐ
ãÐps://www.nichibenren.or.jp/activity/criminal/visualisation/falseaccusation/case5.html
ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐИÐçапÓÀÓ§ˆÍ§Ò° Ò¨ÌÝÒ´ÇÒ´Ð£Í Ò¨Íð¤¤ÐÛÒ¨ÌÝÌÈÍÇ
дÐÐÐÐÓÀÓ§ˆÐ´ÐˆÐÈÐÍÝÝÍý¡Ì¯ÐÛÌÒçñÐÐͧҰ Ò¨ÌÝÒ´ÇÒ´ÿ¥ÐÐИÐçапÓÀÓ§ˆÍ§Ò° Ò¨ÌÝÒ´ÇÒ´Ðÿ¥ÐÛÓ˜˜ð¡Í₤ˋÐ₤ÐÐÐÛÒ¨ÌÝÐÌÈÍÇÐЃÐÐÐ
ÐÍÊÏՈͯÒÈð£ÊÍÿ¥Í¿Çÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÿ¥ÒÈÍÊÌÐÎÐÏÐÐçÐÊÐÿ¥
ãÐhttps://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=94098
ÿ¥£ÍÊÓʤð¤Õ
ÐÛÒÎÌ´ÿ¥§
ÌËÙÍð¡Ì´ˆÕ ð¤ð£ÑÐÛÒ¨ÓÒ
дÐÐÎÕÛÌÐ̓ÓÍаÍ
˜Ò´ÇÌÒçñÐÐÐÐÐÛÐÛÐÓ˜˜ð¡Í₤ˋÐÏÓÀÓ§ˆÍÊÌݤÐÓ¤ÍÛÐÐÍÍÐÐÌÊÍ₤ÍÛÐÛÕ̰ЈÕÛÌÐ̓ÓÐÍ
˜Ò´ÇÌÒçñÍаÍÒˆ¢Ð¿Ð¨ÐÐÌÍÛ°ÐÒ¨ÐÈÐдÐÐÎÐÒ¨ÍШÍ₤ƒÐÐͧÍÛÑÒ° ÍÌ°ÿ¥ÌÀÿ¥Õ
ШͤÐËÐÍÍШÓÐÐÌÍÛ°ÿ¥ÿ¥ÿ¥Íÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ð¡Íð§ÐÐÛÐÐÀÿ¥Íÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ð¡Íÿ¥ÍаÕ
Í£ÑÌÍÛ°ÕÐÛÌ₤ÌÐÌÝÐÐð¤ÌÀШÐÊÐÐÌÊÍ₤ÍÛШÐÐÐÎÐÕÂð¢Ò
ÐÛðƒÒ¢¯ÓÙÐÍÌШÐÍÍШÌËÙÍð¡Ì´ˆÕ ÐÛÌ
ÌÍаÍ
ÝÒ˜ÐÒˆÐÐÐÐдÍÊÌÙÐÐÕÛÌÐ̓ÓÍаÍ
˜Ò´ÇÌÒçñШҰÐÈÐÐдШÐÊÐÐÎÐÐÐÛÍÓÌÏÐÒ₤ÍÛÐÐÐдÐÐÏÐЈÐӴͤÎШÕÐÐÎÐÐдÐ₤ÐÐЈÐÐÐÐͧÍÛÑÒ° ÍÌ°ð¡Õ̰дÐ₤ÐÐЈÐдÐÐЃÐÐÌÊÍ₤ÍÛÐÛÍÍШÍ₤ƒÐÐÍÒˆ¢Ð¿ÐÐͧÍÛÑÒ° ÍÌ°ð¡Õ̰дÐ₤ÐÐЈÐдÐÐÎÐÍÍÐÛÒ¨ÌÝÐÌÈÍÇÐÐð¤ðƒ
ÿ¥£Í
´Ìÿ¥§Ðhttps://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/098/094098_hanrei.pdf
ЈÐÐÐÐÛ̘ͤð¤ð£ÑÐÐÌǃÓÐÐÌÌ¡Ìͤͧð£ÊШÍ₤ƒÐÐÒ´ÝÍ₤ÌÍð¤ð£ÑÐÏÐÐÌÕ¨ÒÈð£ÊÍÿ¥Í¿Çÿ¥ÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÓ˜˜ð¤Í¯Ì°Í£ñÌݤÍÛУÒÈÍÊÌÐÎÐÏÐÐçÐÊÐÐ₤Ð̘ÀÐÛдÐÐ
ÐÌÕ¨ÒÈð£ÊÍÿ¥Í¿Çÿ¥ÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÿ¥ÒÈÍÊÌÐÎÐÏÐÐçÐÊÐÿ¥
ãÐhttps://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=93424
ÿ¥£ÍÊÓʤð¤Õ
ÿ¥§
ÌÊÍ₤ÍÛÐÒ¨ÓÒ
дÐÐÎÍÐÒˆ¢Ð¿ÐÒ
ÐÛðƒÒ¢¯ÍаÐÐÛÓÑÌ°ÐÕýÕ°ÍаÕýÓ£ÐÍÌШÒÀÐ̰̿ШÐÐÒ´ÕýÐÐÒ´Õý͈ð§ÐÐ̯ҴÇÌ°ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÌÀÿ¥ÍñÌÍÛÐÛÐÐÐÐ̰̓ÕÂð¢Ì̡ШÒˋýͧÐÐдÐÐÎÌÌ¡Ìͤͧð£ÊÐÛÓ°Ó¨ÐÎÐÐÐÐÍ ÇÍШÐÍÒ´ÇÌ°ÿ¥ÿ¥ÌÀШͤÐËÐÐÐÛÌͤÐÌÍÎÐÐð¡Ò´Ò´Õý͈ð§ÐÛÌÌÒ
ÐÏÐÐͧÐÛÍÊÌÙÐÐÒÈÕÌ´ˋÐÛÓ₤ÍýÐÕ¡ÒÝÐÍÐ₤ÐÐÐÌ¢¨Ó´ÐÐÐÐÛдÐÐÐð¤ðƒ
ÿ¥£Í
´Ìÿ¥§Ðhttps://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/424/093424_hanrei.pdf
ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÍÛÍÍÛÑÐÛÌ¿Òˋ
ÒÍЈÍ
ÒÈÍÊÍÛÐÛÒÏÈÒˆ˜ÐÐÐЃÐÿ¥Í ÒÊ̯ÍʈÕÐÐИÐçапͧҰ Ò¨ÌÝð¤ð£ÑШÐÐÐÒçñÒ´ÇÐÕÛÌУ̓ÓШÐÊÐÐÎÐÛÕÌ°ÌÏÐNBLÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥Íñÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥Ð
ð¡Ò˜Ò¨ÐÛð¡ÙÐÏÐ₤ÐÐÍð¡ð¤ÒÝÀÐÍ₤ƒÒÝÀдÐÐ̯ð¤ÍÊÌݤдÍð¤ÍÊÌݤдÐÏÒˆÍÛУÍÊÌÙÐð¿ÕÂÐÐÓçÒ¨ÐӯШÐÐÐдÐÐÐÐÐдҢ¯Ð¿ÐÎÐÐÐÐÐÌÍÊÏÐÛÍÕÀÓ¿Ð₤ÐӃʹÐÛÍÊðƒÌ°ÓÐÌÙÈÒÏÈÐÐÐдЈÐð¤ÍÛÒˆÍÛÐÒÎÓ₤ÓÒˋðƒÀШÕýÐÐÏÐЃÐÈÐÐдШÐÐÐÍÒ¨ÓШÐÐãÎãÎÐÒ¨ÓÍÕÍУÓçÕ´ÍШÍÐÐÐÛÐÏÐ₤ЈÐÐÐÐÐÌÐÐÎÌÏÒ´ÇÍ₤ˋÐÛÍÊÌÙÐ̓
ÐÊÐдШÐÐÐÐÐдÓçÒ¨ÐÐÎÐЃÐÐ
ÿ¥Ðͧð¤ÍÌÐÛÌ Í§ÌÀð£Ñ
Íð¤ð¤ð£ÑÐÏÐ₤ÓÀÓ§ˆÍÊÌݤÐð¡ÐÐÐÐÛÐÏÐÐÐͧð¤ÍÌÐÏÌ Í§ÐÐ̯ð¤ð¤ð£ÑÐÏÐ₤ÌÍÛ°Ò° ÍÒ¨ÌÝÐÒˆÐÐÐÐð¤ÌÀÐÐÐЃÐÿ¥Í ÍÛ°Ò ÐÛð£ÈÓð¤¤Ð₤ÐÍð¤ð¤ð£ÑÐ̯ð¤ð¤ð£ÑÐÍÐÍ¥ÒÙñÍȨÐÏÐÐÿ¥ÐÒ¨ÍÐ₤ÐÍ ÍÛ°Ò Ð¨Í ÐÐð¢Õ¤ð¥ÓʃдÍÌÏÐÛÌËÙÍÐÍÑÐÒˆÍÒ£Í ÝÌ¡ÐÏÐÐÐÐÐÀÐÐÛð£ÈÓð¤¤ÐÍÐÍ¥ÒÙñÍȨÐÏÐÿ¥ÐÀЈТШÐͧð¤ÍÌÐÏÌÝÐÈÐÒˆÍÒ£Í ÝÌ¡ÐÕÂÐÐð¤ÌÀдÐÐÎÐÐÐÀÐÐÐÐЃÐÐÿ¥Ð
Ð2019Í¿ÇÐÛҨͯÓÏÌÙ£ð¤Àð¤Ì ÍÈð§ÒñÍÀÐÛÓñÌÏÿ¥63ÿ¥Ð¨ÕÒ£ÂÓÀÓ§ˆ …Ðÿ¥HBCÐÐËХп(ÍÌçñÕ̃Õ)ÿ¥ÿ¥£ÒÈÍÊÕñÐÕÌý¥Ì§ÿ¥§
ÐÌÙÍ¿Õ¨ÒÈð£ÊÍÿ¥Í¿Çÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÍÊÌݤ
ãÐhttps://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=93981
ÿ¥£ÍÊÓʤð¤Õ
ÐÛÒÎÌ´ÿ¥§
ÕÍÊÝÕÒ£ÂÒÇÌÙ£ÐÛð¤ÌÀШÐÐÐÎÐÓ˜˜ð¡Í₤ˋÐ₤ÐÌÊÍ₤ÍÛÒ¨ÌÝÐÛÕÍÛШͤÐËÐÐÎÒÀӈͯӿÐÒˆÍÛÐÐÓçÌÍÕ¢Í₤Ò§ÌÏÐÒˆÐÐÎÍÍÊÓʤÕÍÊÝÐÒˆÍÛÐÐÐÌÏÒ´ÇÍ₤ˋÐ₤ÐÍÍÊÌݤÐÛÍÊÌÙÐ₤Ò¨ÓÍÓçÕ´ÍÓÙШÍÐð¡ÍÓÐÏÐÐÐÍÊÌݤШͧÝÕ¢ÐÍÐ¥ÐÐдÐÌÐÐЈð¤ÍÛÐÛÒˆÊÒˆÐÐÐдÐÐÎÓ ÇÌÈÐÐð¡ÐÏÐÌÏÒ´ÇÍ₤ˋШÐÐÐÒ´ÇÍ ÍÊÌÇ̓ÐÛÒ´ÇÍ Ð¨ÐÐÐÌÊÍ₤ÍÛð¡£Í¥çÐÛÓçÌÍÕ¢Í₤Ò§ÌÏÐÕÍÊÝÐ₤ÒˆÐÐÐЈÐдÐÐÎÐÓÀÓ§ˆÐÛÒ´Ì¡ÀÐÐÐÐÐ
ÿ¥£Í
´Ìÿ¥§Ðhttps://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/981/093981_hanrei.pdf
Ó˜˜ÿ¥Í₤ˋÐÛÌÙͿͯÒÈÐÛÍÊÌݤÐ₤ÐÍñÒÀÓÑð¤ð£ÐÐÛÌÓ§ˆÐÏÐÐÿ¥ÌÙͿͯÒÈð£ÊÍÿ¥Í¿Çÿ¥Ìÿ¥ÌËÍÊÌݤÿ¥Ð
ð¤ÊÕð¤Ì
ШͤÐËÐÌÍÛ°Ò° ÍÒ¨ÌÝÐÛð¤ÌÀÐÏÐÍð¤ð¤ð£ÑÐÛÍÎÓÐÛÕýÌÐ̓
ÐÀЃÐÐÐÐ̯ð¤ð¤ð£ÑÐÛÌÑÌ£
ÌÍ¿ÐÍÛÌÐÐÐÐÐÐЃÐÏÒçñÒ´ÇÐÐÐÐ̯ð¤ð¤ð£ÑÐÌÒçñÐЃÐÐÐÐÍð¤ð¤ð£ÑÐÛͧÝÕ¢ÐÏÐ̯ð¤ð¤ð£ÑÐÛÍÊÌݤЃÐÏÐÿ¥Í¿ÇÐÒÑ
ÐÐÍ¿ÇÌÐÒÎÐÐÐддЈÐЃÐÐÿ¥ÌÙͿͯÒÈð£ÊÍÿ¥Í¿Çÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÿ¥£Ó¤ÍÛÿ¥§ÿ¥Ð
ÐÐÛÕÐÍð¤ð¤ð£ÑÐÛÓ¡ÍÐÐÓ˜˜ÿ¥Í₤ˋÐÌÏÒ´ÇÍ₤ˋÐÛÍÍÊÌݤÐÌЃÐÈÐÐÐÐÏÐÐ
̯ð¤ð¤ð£ÑШÐÊÐÐÎÐ₤ÐÌÏÒ´ÇÍ₤ˋÍÊÌݤÍШÐÍÌ¿ð¡£Í¥çÓ¨Ò´¥ÐÓçÐЃÐÐÐÐÌÏÒ´ÇÍ₤ˋÍÊÌݤ̓ШÓçÍ₤ˋдÐÐÐддЈÐÈÐÎÐЃÐÐÐ
̘հÐÌ´Í₤ÐÐШÐÓ˜˜ÿ¥Í₤ˋÐÛÒÈÍÊÍÛÐÐÐÐÈдÕˋÐÐÐдÐÏÐÐÐÐ
ÍÍÐÒ´ÇÒ´ð£ÈÓð¤¤ÐÛÓÏÐ₤ÐÐÐÛӿШÕÂÐÐÎÐ₤Ð̘ÀÐÛдÐÐÐÛð¡£Í¥çÐÒ¢§Í ÐЃÐÐÿ¥Ó˜˜ÿ¥Ì¤ÍÌ¡ÕÂÿ¥Ð
ÐÐ̘ð£ÑÍð¤ð¤ð£ÑÐÛÌÏÒ´ÇÍ₤ˋШÐÐÐÎÐÌÙÍ¿Õ¨ÓÙÒÈÍÊÌÐ₤Ðð£ÊÍÿ¥Í¿Çÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÐÍÍÊÌÝ¤Ó ÇÌÈÿ¥ÓÀÓ§ˆÿ¥ÐÛÍÊÌݤÐÐÐдÐÛÐдÐÏÐÐÐ
ÒÈÍÊÌÐ₤ÐÐÒ¨Íð¤¤ÐÐÒ¨ÍÛ°Ò
дÐÛÒÀÓˆÍ ÇÌÐÏÐÐÿ¥ÀͯӿÐÐÐÐÓçÌÍÕ¢ÐÍ₤ҧЈÌÍÐÛͯӿÐÏÐÒ¨ÍÛ°Ò
ÐÒÎÒˆÍ₤Ò§ÐÏÐÐÈÐдÐÐШÐ₤ÍÓÓЈÓÐÐÌÛÐÐдÐÐÎÐÐͧÍ₤ˋ̯ҴÇÍ Ð¨ÐÐÐÌÊÍ₤ÍÛð¡£Í¥çÐÛÓçÌÍÕ¢Í₤Ò§ÌÏÐÕÍÊÝÐ₤ÒˆÐÐÐÐÐͧÍ₤ˋ̯ҴÇÍ Ð¨ÐÐÐÕÍÊÝÕÒ£ÂÒÇÌÙ£ÐÛð¤ÍÛÐÒˆÍÛÐÐÐдÐ₤ÐÏÐЈÐÐд҈˜ÓʤÐÐдÐÐÿ¥ð¿ÿ¥ÿ¥ÐÛÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥Ð̯ð¤Ò´ÇÒ´ÌÓÑШÐÐÐÓ¨Ò´¥Ð₤ÐÍ¢
ÐÐÐÍð¤Ò´ÇÒ´ÌÓÑШÐÐÐÓ¨Ò´¥ÐÛÐÐШÐÍÓÓЈÓÐÐÍñÛÐÌЃЈÐӴͤÎЃÐÏÒÎÌÝÐÐÐÎÐÐÐÐÐÏÐ₤ЈÐÐдÐÐÐÐдÐ̘ð£ÑШÐÐÐÎÐ₤ÐÒ´¥Ì ÍаͥҨÐÛÍ
´ÒÑÈ̴ШÐÐЯÐÒ¨ÍÐÛÓçÌÍÕ¢Í₤Ò§ÌÏÐÕÍÊÝÐÒˆÐÐÐдÐÐÏÐÐдÐÐпÐÐÏÐÐÐ
ЈÐÐð¡Ò´Õ¨ÒÈÍÊÌݤÐ₤ÐÐÐЃÐÏÍÍÐÒ´ÇÒ´ð£ÈÓð¤¤ÕÐÐÛÐдÐÏÐÐÐÐÍÝð¤¤ÓЈͯÒÝÀÐÌÌÙÐÏÐЈÐÿ¥ÌÙÍ¿Õ¨ÒÈð£ÊÍÿ¥Í¿Çÿ¥Ðÿ¥Ó˜˜ÿ¥ÿ¥ÍñÍÿ¥Í¿Çÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÍÊÌݤУÌÕ¨ÒÈÿ¥´ÿ¥¯ÿ¥Ð
̓ÀÒÈÍÊÌШÐÐÐÎÐ₤Ð̯ð¤Ò´ÇÒ´ÐÛÍÑͤÎÒÑÈÌ´ÐҡЃÐÐ̓Ш̘ð£ÑÍð¤ð¤ð£ÑÐÛÌÏÒ´ÇÍ₤ˋШÐÐÐÍÊÌݤÓçÌШͥÐÐÐÐÐÐдЈÐÐÓ˜ÒˆÐÛÓ¨Í ÇÐÏÌÙÈͧЈÍÊÌݤÐÐÐÐÐдÐÌ̓
ÐÐÐÐ
̯ð¤Ð´Íð¤ÐÏÐÐÐÐÐÛÒÈÍÊÌÐÛÓçÒ¨ÐÓ¡ÍÐÐÍ ÇÍШÐÊÐÐÎÐ₤Ðÿ¥ÐÏÓÇ¿ð£ÐÐÍÛÍÍÛÑÐÛÌ¿ÒˋÐˋÐÐÐð¡Ò˜Ò¨Ð₤ÐÐÛдÐÐÐÏÐÐÐÐÍÊÌݤ̡РÐÐÒÎÐÎÒˋðƒÀÐÐдÐÐÕÐÐð¤ð£ÑШͰÐÐÌ¿ÒˋÐÒ¢¯Ð¿ÐÐÐÐдÐð¡ÒÎÒÏÈдÐÐÐдШЈÐÐÏÐÐÐÐÐÐ ÐÍÛÕÐÛÍ₤ˋÓÐÛð¡ÙÐÏÍÐÐÎÐÐдÐÌ̓ШÒÈÐÿ¥ÐЯÐÿ¥Ì ͧÒÈÍÊÍÛШÐÐÈÐÎÐÐ¥ÐÐ¥ÍÐÐÐÍÊÌݤ̡ШÐ₤ÓƒÐЈÐð¤ÐÍÝÝÐÛÐÐШÐÐÐÐÛÐÏÐÐÐÐЃÐÏÐÛÍ₤ˋÓÐÛð¡ÙÐÏÕÂÐÐð£ÈÓð¤¤ÐÓÓ ÛÐÐÛÓÑÌ°ÐÐˋÐÌÐÿ¥ÐЯÐÿ¥ÐÐÓƒÍÛÐÛÓçҨШͧÝÕ¢Ðð¡ÐÐÐÐÐÏÐÐÐÐÐÐÛð£ÈÓð¤¤ÐÛÌÌÐÐÛÍñÏÌШÐÐÈÐÎÐͯЈÐÐÐÍÊÐÐÈÐÎÐÐÐÏÐÐÐÐ
Ó¡ÌÌ¿ÿ¥Ì¯ð¤ð¤ð£ÑÐÛÒ¨ÍÐÍð¤ð¤ð£ÑÐÛÒ¨Íð¤¤ÿ¥Ð₤Ð̯ð¤ð¤ð£ÑÐÏÐÐÍð¤ð¤ð£ÑÐÏÐÐÒ¨ÍÛ°Ò
ÐÒˆÌÛ¤ÐÍ°ÐÈÐÐÐÛÐÏÐÐдð¡£Í¥çÐÐÎÐÐÐÌçӰШ̯ð¤ð¤ð£ÑÐÏÐ₤ÐдÐÐÓÀÓ§ˆÍÊÌݤдЈÐÈÐÍð¤ÌÏÒ´ÇÍ₤ˋÐÐÒˆÌÛ¤ð¥Í°ÐÛð¡£Í¥çÐ₤ÌÌËÐÐÐÐ̯ð¤ð¤ð£ÑÐÐÍð¤ð¤ð£ÑÐÛͧÝÕ¢ÐÏÕñÍ¥ÐÐÐдÐ₤ÍÎÍÛÐÏÐЈÐдÐÐÐÓýÕдÐÐÐÐÐÐÐÛЈÐÌÊÍ₤ͤÐÛÌÌ£ÐÛÕӴШÍÊÏÐЈÍÕÀÐÐÐÈÐдÐÐÐÐÐ̓ЈÐÐÐÛÐÏÐÒ¨ÍÛ°Ò
ÍÇдÐÐÎÐ₤ÐÓ
§ÐÐÐÐÐÈÐдÐÛÌÐÍÎÐЈÐдÐÐÐÏÐÐÐÐÐÐÏÐÐ̯ð¤ð¤ð£ÑÐÏÐ₤ÐÐÐЯÌÓ§ˆÍÊÌݤдЈÐЃÐÐÐ
̘ð£ÑÐÛÍÌШÐÊÐÐÎÐ₤ÐÒ¨ÍÛ°Ò
ÍÇÐÛð£ÈÓð¤¤ÐÛÓ¨Í ÇÐÏÓÌ₤ШÌÕдÍÇÍÐÌÍ
ËÐÐÍÛÕÐͤШÐÌ¿ÒˋÐÒÑ
ÐÐÎÐÐÐÐÒ¢¯Ð¿ÐÐÐдÐ₤ÐÐЃÐÐÐÓ¤ÍÛÐÐÓÀÓ§ˆÍÊÌݤÐÐÐÐдÐÒÐÐÓƒÌÓ¿ÐÏÐ₤Ðð£Ëð¡ÐÛÕÐÐÛÒˆ˜ÌдÐÐÎÐÐЃÐÐ

Ðð§ÐÐÐÐÐÐдÌÐÐÐÐÓ¿
ÐÐÐÐÀÐÐÏÐÍËÐÛÒÏͤÎÐÐÌÇÓÐÐÎÐЃÐÐ