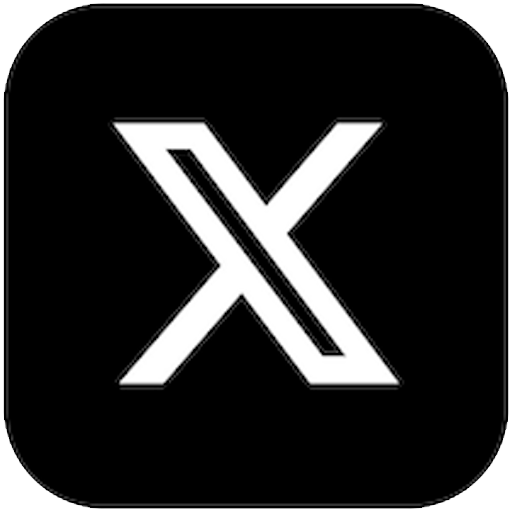Õð¡Í Çð¥ÓʃÐÛÌ ˆÍ¥Ð̓ÓÑÒ
ÍÕÀÐ₤ÐÍЈÐ̰̓ÐÓ´ÍÐÛÍÎÓШдÐˋЃÐЃÐÐÐ
ÐÐШÐ₤ÐÌÌ
ÐдÐÍÛÍˋÐÐÒÊÕШð¤ÊÕ₤ÐÐÍÛÑÌÐð¥ÓʃÐÛ̈ÌËÐÍñÎÍ°ÐÐÒˆ¢ÌÇÐÍ¢
ÒÎШЈÐЃÐÐ
ÍÊÏÌð¤ÍÌÐÛÍÌËÙð§ÍÑÐÏÐ₤ÌÝÐШÐÐÍÝÕÂÐÐÐÐÐ̯ͯÓýƒÕÙЈÐÐÏÐ₤ÐÛÐÒˆ¢ÌÇÍÐдÐÌÎÓËÍÐдÐÐÈÐÍ¥ñТÐÌÝÐÐÐÐÐдÐͯЈÐÐÐЃÐÐÐ
ãÀ̯ͯÓýƒÕÙÐ ÐÐÐÐÓ¤ÌÛÐÏÐÐÿ¥ÐÊÐÛÍ
ÿ¥ÐãÌÌ ãдãÍÛÍˋãÐÛÒˆ¢ÌÇÍ
Õð¡Í Çð¥ÓʃÐÛÌ ˆÍ¥Ó¡ÓÑÐð¤ÌËÙÌ¢ÓÑÐÏÐ₤ÐÍЈÐ̰̓ҨÐÓ´ÍÍÎÓÐ ÐÐÏЈÐÐ
ãÀÐÕñÓñШÓÑÐÐÐÐÐÐð£ÐÛÓ¡ÓÑð¤¤ÐÛÓÒÏÈÐ̓ÐÐÐ
ãÀÐÕ¤ÓÍÐÐˋÐÓƒÍÛÓШ҈¢ÌÇÐÐÐÐ
ãÀÐÓ¡ÓÑÓ´ÒˋðƒÀÐð¡ÐÐÐÐ
ãÀÐÕð¡Í Çð¥ÓʃÐÛÍ¯Ì¯Ì ˆð¡£ÐÛÍÕÀÿ¥ÐÍÓçÐÐÐÍ¯Ì¯Ì ˆð¡£Ðÿ¥
дÐÐÈÐÐÌÌ ÓУð¤¤ÕÕÂð¢ÓÒÎÓÇ Ð´ÐÍÛÍˋÐÛð¡ÀÕÂÐÒˆ¢ÌÇÐÐÍÐÌÝÐÐÐЃÐÐ
ÐÐШÐ₤ÐðƒÕ ¥Ò
ШÌñÝÐÍ
ËÐÒƒ¥Ð¢ÐÓýÐÍ¥ñÐÕÂð¢Ò
дð¤Ê̡У҈¢ÌÇÐÓÑÐÐÍ¢
ÒÎÐÐÐЃÐÐ
ÍÊÏÒÎÌ´Àð¤ÍÌÐÏÐ₤ÐÍÌËÙУͿÓÍÐÐÕÒÎÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÌ°ËÒÙÐÒÊÕЈÌÀð£ÑÐ₤ð¡ÍƒÌЈÐдÐÐÐЃÐÐ
ÿ¥ÐÒ¢ ÕУÌңЈÍ₤ƒÍ¢
Íð¤¤ð¤ÍÌÍÐÛÍ¥ÒÙñÍȨÐ₤Ð̘ÀÐÛÐÐЈÍˋÓ¿ÐÐÐЃÐÿ¥
ãÀÍ¥ÒÙñÍȨ҈Ҥ¨ÐÌÎÓËÒ´ÙÒ´ÐÐð¤Ê̡ЃÐÏð¡Òý¨ÐÐÎÌ Í§
ãÀÐÌ°ÍÐÐ ÐÐÏЈÐÐÓçÍÑÒÎÓ¿ÐÐͨÐÐÎÍ ´ð§Í₤ƒÍ¢
ãÀÓÑÌ°ÐÛÍÊÍШͰ͢ÐÏÐÐÌˋÍÍ
ÍÊÏÌð¤ÍÌÐÏÐ₤ÐÍÍÍ₤ƒÍ¢Ð₤ÒËÌãð¡ÙÍ ãÐÐ¥ÐÐХͥÒÙñÍȨдÐÐÕÍÝÊÓÌÏÕ ÐÐÐÐÐÐÌˋÍÌÏШ̘ ÐÐÐÐÌÎÓËÐÛð¡Òý¨ÌÏÐÍ¥ÝÐЈÐÐдÐÐÐЃÐÐ
ÿ¥ÐÒÀ´Ð¨Í¤ÐˆÐÐÓ¡ÓÑÐÛҧдÐÓˋÇÐÐÒÎÌÐÓçÕ´ÍÊ
Ò°ÓÈÍÛÑÐÓçÍÑÒ ÐÛÓ¡ÓÑÐÏÐ₤ÐðƒÐЯÿ¥
ãÀÍÓƒˋÌ ˆÐÕÍ£ÐÛÒÇð¡ÐÍÕÀÍ
ãÀÒˆÓÊƒÌ ˆÐÛÒˋðƒÀÕÀÐÌ°ÍÛÍÊШըմ¯ÐÐÎÓ¡ÓÑÓ´ÐÒ´Í¥ç
ãÀÕñÍ¿Çð¥ÓʃÐÌ₤ÐÐÎÐÐÒΈÌÐÕÊÍÊÐÐÐÎÐÐˋÐШ
ãÀÓ¡ÓÑÒýÀÓÈÐÛÍÕ Ðð¤ÌËÙÓÑÓÑдӡÍÐÐÎÐЃÐ
дÐÐÈÐ ÒÊÕÐÐÊð¤ÍÍ₤ƒÓÙÐð¡Í₤̘ ЈÍÕÀÐÍÊÓ¤ÐЃÐÐ
Íð¤¤ð¤ÍÌÍÐÛÍ¥ÒÙñÍȨÐ₤ÐðƒÕ ¥Ò дÐÌÕÐÐÐÐÍ₤ƒÒˋÝÐШÐÐÐÐÐÐÐÛЈпÐ₤ÐÌçÛÐͧ¨ÐШÐÐÌ°ÍУӴÍУð¤¤ÕÕÂð¢ÐÛð¡ð§ð¡ð§ÐÏÐÐˋаÐÓñÇÐЃÐÐ
ÿ¥ÐÍÊմͯÕÍÛÑдÐÛã̘ͧÐÛÕÈ̤ãÐÍ₤Ò§
ÍÊÏḬ̀̓ð¤ÍÌÐÏÐ₤ÐÐÓʃÍ
ÐХРÍ
ÕÈ̤ÐÐ₤ÐÐÈÐÎÐÐÓ´ÓÍȨЈÐˋдÐÛÕÈ̤Ð₤ͧÂÍ¥ÓЈÐдÐͯЈÐÐÐЃÐÐÐ
ð¡Ì¿ÐÍð¤¤ð¤ÍÌÍÐÛÍ¥ÒÙñÍȨÐ₤ÐÓ´ÓÍȨУð¥Ò´ÍȨУð¡ÍÓÈÕÍÛÍȨЈÐˋдÌÀð£ÑÐдШÌңШÐХРÐÓçТÐÓƒÍ ÇИÐШÐÏÓñ£Í₤Ш҈¢ÌÇУÍÛÒÀÐÏÐЃÐÐ
дÐÐ¨Ì ˆÍ¥ÒˋðƒÀÐÓÇÓ´Ò°ÕÍ₤ƒÓÙЈÐˋÐ₤ÐÍ¥ÒÙñÍȨûÓ´ÓÍȨûÕÒÌˋÕÂÐÛÕÈ̤ÐÌÍÎÐÍÐÐÍ ÇÕÂÐÍÊÐÐÐÐÍÊմд̘ͧШð¢ÀÕ ¥ÕÂð¢ÐÓ₤ÐÐÎÐÐÍ¥ÒÙñÍȨÐÌЃÐÐÐÛÐÏÐÐ
ÿ¥ÐÍÛÑÌШãÓÇ̓ÒÏÈãÐÐÐÐÐÒˆ¢ÍÍ
Õ¨Ò°ÓÈУð¡Ùͯð¥ÌËÙЈХÐÐ¥ÐÛÓ¡ÓÑÐ₤̓РШÐÐÎÐ̘ÀÐÛÐÐЈӃÍÛШÓÇÕÂÐЃÐÿ¥
ãÀÓ¡ÓÑð¤¤ÍÍȨÐÛÓ¤Íñÿ¥Í Í¥ÍÏÍοÕÐÛð¡Í ˜Í¿°Ìÿ¥
ãÀÒˆÓËÓÐÛÒΈÐÐÐÐÒýÀÓÈÓÛÀÓÐÕ¤Ò´ÐÛÍÕÀ
ãÀÒñÀÓÑÐдÐÐð£ËÍÊÐÛÓ¡ÓÑð¤¤ÐÛÍˋÍÛ°Í₤ƒÓ¨
Í Í¥ÍÏÍοÕÐÛð¡Í ˜Í¿°ÌÐÍˋÍÛ°Í₤ƒÓ¨ÐˆÐˋÐ̤ð¡ÐÛÌ°ÓÐ ÐÐÏÐ₤ÒÏÈÌݤÐÏÐЈÐÍÕÀШÐÌÕÐÐÐÐÎÍ₤ÐÌñ£ÐÐÍÌͧÂÌÐͯÐЃÐÐÐÐÐ₤Íð¤¤ÍÐÛÍ¥ÒÙñÍȨÐÛÌ¿ÐÍÏÍÓШͥñÐÍÕÐÏÐÐ
ãÀÕˋÌÕˋÌÐÛÒˆ ÍÛЈÍÊÌÙ
Õð¡Í ÇÌ ˆÍ¥Ð̓ÓÑÒ
ÍÕÀÐ₤ÐͧÂÍ¥ÓЈÍÎÓÐ ÐÐÏÐ₤ÒÏÈÌݤÐÏÐЃÐÐÐ
ÐÐШÌÝÐÐÐÐÐÛÐ₤Ðð¤¤Ð´ð¤¤ÐÒˆ¢ÌÇÐÐÍдÐ̈ÌËÐÒÎÌÛÐÐÌÎÓËÐÏÐÐ
̯ͯÓýƒÕÙÐ ÐÐÐÐÐð¡Òý¨ÐÐÒý˜ð££ÐÐÐÈÐÎÐðƒÕ ¥Ò ÐÛÍÊÏÍЈÍÝÕÂÐÌ₤ÐÐÎÐÐÐдÐÐÏÐÐÍ ÇÍÐͯЈÐÐÐЃÐÐÐ
ÐÐÀÐÐÐÐпÐÎÐÛÌÀð£ÑШ̯ͯÓýƒÕÙÐÛð§ÍÑÐÌÕˋдÐÐÐÐÐÏÐ₤ÐÐЃÐÐÐ
ͧÕÍÍ¥ÐÍñ´ÍÊÏM&AÐÍÊÏÒÎÌ´ÀÒ´ÇҴЈÐˋÍÊð¤¤Ì¯Ð¨ÐÐÍÌËÙð§ÍÑÐð¡Í₤̘ ЈÌÀð£ÑÐ₤ÐÍÊÏḬ̀̓ð¤ÍÌШÐÐÕˋÐÐÎÐЃÐÿ¥ÐÐÈдÐÐðƒÕ ¥Ò
дÍ₤ÌËЈÕÂð¢ÐÓ₤ÐÐð¡ÐðƒÕ ¥Ò
ÐÛÍÇÐÏÐÍÊÏÌУÍÊÏÒÎÌ´À̰̓ð¤ÍÌÐð£ÍÐͧ¿ÍýÐ̓ÌдÐÐÍð¤¤ð¤ÍÌÍÐÛÍ¥ÒÙñÍȨÐ₤ÍÙÍ´ÐЃÐÐÿ¥Ð
ͧð¤ÍÌÐ₤ÐÐÓÏÐÐÀÐÛÍ¥ñТÐÓШÌÇ£ÐÐÐÐÐˋÐÐÐÐÍ¡¡Ð¨ÒÎÌËçÐÐÍ¢ ÒÎШ͢ÐÐÎð£ÐÛͯÕð¤ÍÌÐÐÓÇ¿ð£ÐÐÐдÐÐÐЃÐÐ
ÐÐÛÐÐÐÏÐÿ¥ÿ¥Ì¯Í¿ÇÐÒÑ
ÐÐÓçմдÍÛÒñçÐÓÐÐÐ̯ͯÓýƒÕÙЈÐÐÏÐ₤ÐÛÌˋÍÍдð¡Òý¨ÌÏÐÍ¥ñТдÐÐÎÐÓ¡ÓÑУð¤ÌËÙÌ¢ÓÑÐÛÍÕÐÏðƒÕ ¥Ò
ШÍ₤ÐÌñ£ÐÐÐЈÐШдÐÈÐÎÌÍÐÛÓçÌÐÓÛÌÐЃÐÐ
ЃÐÐ₤ÐÓ¡Ò¨ÐÐÐ ÐÐÌÀð£ÑÐÛÌÏÒ°ˆÐ£ÒÎÌ´ÀУͯÕÌÏУÓñÌËÌÏЈÐˋÐÌ
ÕШÌÊÒ´ÐÐÐͧð¤ÍÌÐÛÍ¥ñТÐÓШÌÇ£ÐÐÐÐÐˋÐÐÐÐÒÎÌËçÐÐÐÐÐÏÐÐÍ¥ÐÍÐÐÐÎÐЃÐÐ
ÐÐÍÍˋÐÛÐÐÐÛÌÎÓËÐÿ¥COMMITMENTÿ¥
Ð₤ÐÐÀÐÐÐÐ
ÐÐÓÏÐÐÀÐͯð¤¤Ì¯ÐÏÐÐÓÓÝÿ¥ÐЈÐдÐÐÈÐÐð¥ÇÒç¯ÐÐÐÐШÐ
ÿ¥£ÓçÓ¿ÿ¥§Ð₤ÐÐÀÐÐÐÐ
ÐÐÐЈÐÐÛÌˋТÐÍÐÌÙÂÐÐÍÛÍ¿ÓЈÒÏÈÌݤСͯÐЃÐÐ
ÿ¥£Ì°ÍƒÓ¡Ò¨ÿ¥§Ð₤ÐÐÀÐÐÐÐ
ÐÐÐЈÐдð¥ÇÒç¯ÐЈÐÐÐÌÒ₤ÐÛÒÏÈÌݤСͯÐÐÐÐÛÐÐ ÐÐÐ
ÿ¥£Í¥ÒÙñÍÈ¨Í ÝÕ
˜ÿ¥Í¥ÒÙñÍȨÒý£Ó´ÿ¥ÿ¥§Ð₤ÐÐÀÐÐÐÐ
Íӯͯð¡Ì°Íƒð¤ÍÌÌÇ£Ó´ÐÛÐÐÐÛÿ¥Ýÿ¥ÿ¥ÀÐ₤ÐÐÀÐÐÐÐˋÐÐÐ
ÐQ&Aÿ¥Ì°ÍƒÓ¡Ò¨Ð£ÐðƒÕ ¥ÐÛÌçÐÿ¥Ð
ÐQ&A(ð¥ÓʃÓçÍÑдͥÒÙñÍȨÌÇ£Ó´Ì°ÿ¥Ð
ÐÕð¡Í ÇÍÌð¥ÓʃÐÛÍ¯Ì¯Ì ˆð¡£ÐÛÌ ˆÍ¥ÒÙýÌ¡À
ШÕÂÐÐÍÕÀдÒÏÈÌݤÐÛÐÐÊаÐÐ
Ð₤ÐÐÀÐÐ