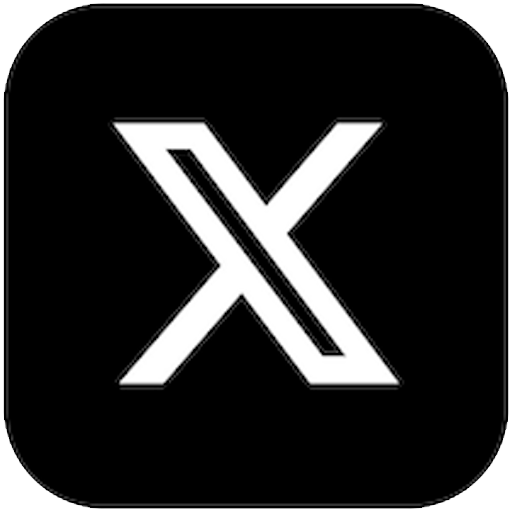ЈÐÓÏÐÐÀÐ₤ãð¡Í´Ó´ÐˆÌÙÈÓƒˋãÐÛÐÐˋÐÐÒÎÓÑÐÐÐÛÐ
Íð¤ÐÌÍÛÐð¡£ð¤¤Í ˜ÐÛÐÐˋÐÐÒÎÐÎÐÐдÐÐÐÐЈÐÐÌ¿Ð₤ÓƒÍÛÐÏÐ₤ÕÐЈÐÐдÌÐÐÍ ÇÕÂÐͯЈÐÐÐЃÐÐÐÍÛÍШ̤ÐÐÓ¨Í ÇÐÐÒÎÐЯÐЈÐÐÐÐÏÐÐÓçÓ¿ÐÛÒÎ̓ÐÌÓÑÐÐЈпÐ₤ÓÛÀÓããÐˋÐÐÓÀÒÎÐÏÐÐÐÐÛÐÏÐ₤ÐÐЃÐÐÐ
ÐÐÐÏÐÐÓÏÐÐÀÐ₤ÐÐÛð¡£ð¤¤Í ˜Ð¨ÕÍÌÐ ÐÐÏЈÐÐÐˋÐÐÍÛÍ çШÐð¥¥ÐÌÌ ÐÒÎÐЃÐÐЈÐÐÏÐÐÐÐÐ
ÓÙÐÐ₤ÍÓÇÐÏÐÓÏÐÐÀÒˆÒ¤¨ÐÌËÍ¡¡ÐÏÐÕÐЈÐÐдÐÐÍÍШ̢ÓËÐÐÎÐÐÐÐÐÏÐÐÌ¢ÓËÐÐÎÐÐÐÐÐШÐÌÌ ÐÌÐÐÌÐÍÐÐÐÊÐÐÍÓÓШÌ₤ÐÒÐÈÐÎÐÐÐÐÐÛÓˋТÕÐÙÐÛð¡ÙÐÏÐÐÐÐÒ´ÝÐÐÐЈÐÐÐÐÐÐÐÐÐÈÐÐдÐÐÒˆÍñÝÍÐÐÍ¢ÐÛÐˋÐÐШÌÛÐЃÐÐ
ÐÐˋÐÐÛð¡£ð¤¤Í ˜Ð₤ÐÐÐÛÒˆÍñÝÍÐÍÛÍ ´Ð¨Í¥ÐÍÐÐÎÐÐЃÐÐÐÐÐͧ¥ÐÐ₤ÐÌݤÐÐÎÓÌ°Ò¨ÐÌ₤ÐÐÐÐЃÐÐÐÓÀÍÈÐÏÐÌÌ°ÐЈÐÐÌШÐ₤Ìð£ÈÕ ÐШÒÎÐÐÐÐÐÐÏÐÒÎÌÐÏð¤¤ÐÒÎÌ´ÐÎЈÐÐÐÐÛÍÏ¢Ð₤ÐÌÙÈÓƒˋÐÛÍÍˋдÐÐÐÐÐÐÐÐÐÏÐð¤¤Ð´ÐÐÎÓñÐÒÑÐЈÐÐÈÐÐдÐÐÓ¤҈ШҢÐÐ
ÒÍ°ÌñÝÐÐÛÐ₤ÐÐÐÐÐͧ¿ÐÌ¥ÐÐð¢°ÍˆÐÐÒËÐÐÍÂÐÐÛÒÝÀ̓ÇÐÏÐ₤ЈÐÐÕͣШÌÍÐÓçÕ´ÐÐ̓ÐÛð¤¤ÓˋÐÏÐÐÐдÐÏÐÐͧ¥ÐÐ₤ÐÐÐÐÐÍÐÀð¡ÐÐð¤¤ÐÐÏÐ₤ЈÐÐÐÍÐÈÐ̓Шð§ÐÌÛÐÐÐÓËÐÈÐÎÐÐð¤¤ÐдÐÐÎÓ£ÕÂШӨÐÀЃÐÐÐÐÛð§ÐƒÐÐÐÒÎÒÇÒ Ð¨ÕͯЈÌ₤Ò¥ÐÍÈÓÙÌÐÌÝÐÐЈÐÐ
ÐÐÛТÐÊÐÐÛÐÐˋÐÐ₤ÐÓƒÍÛÕÕ¢ÐÏÐ₤ÐÐЃÐÐÐÐÐÐÐÓƒÍÛÐÓËÐͯ§ÐÐÐð¤¤ÕÐÐÌÌ ÐÌÇÓÐÐÐÐÐÛÒÈ Ó§ÛÐÏÐÐÌ°ÐШХШÐÍÎÍÛÐÐÐÛÐÏÐ₤ЈÐÐÐÐÛÍÊÍÇШӧÛÐÐÐð¤¤Ì ÐÐÐÐð¡Í¤ÎÓ¤ÐÐÐÍ ÇдҴÐÐÐÏÐÐÐÐ
Óʃð¥ÐÌÓÐÐЯÐÐУÐˋÐÍȯըЈÌÙÈÓƒˋÐ₤ÍÝ Í ÇÌÐÍÊÝÐЃÐÐÐÐÛð£ÈÐÐШÐÕÐÐÏð¡Í´Ó´ÐˆÌÙÈÓƒˋÐÐÐÐÈÐ₤ÐñÐÏаÐÛð¡ÙÐÏÌ₤ÐÐÐÐÐÐÛÐд҈ð§ÐÐð£ÐÛÓʃð¥ÐÛÍËÍ ´ÐдÌ₤ÒÎÐÐÐÛÐð¡ÀÌ¿ÐÓˋÒˆÐÈÐÎÐÐÐÛÐÐÐÐЃÐÐÐ
ãÑÐЈÐÐÐ
Ðð§ÐÐÐÐÐÐдÌÐÐÐÐÓ¿
ÐÐÐÐÀÐÐÏÐÍËÐÛÒÏͤÎÐÐÌÇÓÐÐÎÐЃÐÐ
ã£Ì˜ÌÐÏÒÏÎÐÐÐШХШдð¤¤Ì
ÿ¥ÌÌ
ÐÛÒÀÌ¿ÐдÐÐÐÐ¥ÐÐ₤Ð
ͧð¤ÍÌÐÛ̘ͤÓЈÒÐ̿УÍÊÌÙÐÛÒ£¡Ð¨ÐÐÊЈÐÐÈÐÎÐЃÐÐ
ãÑ conceptÐХС