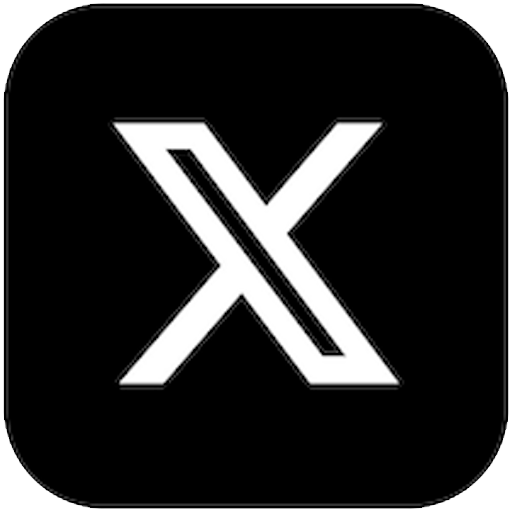ÐÐÐÊÐÛÕШÐÍ₤ÒÈÍÝÊÐдÐÐÒ´ÒÐÛÕÍÌ
ããÌÛÕÐÛð¥ÓʃÍÀÐÓÇÕÂÐÐÐÓ¡ÓÑдÓÇð¤ÐÛÓƒÍÛãã
ã£Ì˜ÐХСÐ₤Ðͧð¤ÍÌÐÛÐÍÊÌÙÌ₤ÌÇÍÐÍÛÍÐÛÒÌ₤ШÐÐÌÒÕÓ´ÐÓʤÐÒÈÒÑ°Ò°ÌÐÏÐÐ
ÒˆÍÐ₤Ò°ÓÈÍÛÑÐÏÐ₤ЈÐÐ
ÐÐÒÐÐÎÐÐÌ¿ÐÐÐÐÌËÓˆÓÑÐÓ¡ÓÑÐÒΈÌÕÐÐˋÐШÐÛͧð¤Ò
ШЈÐÐÝХпÐ₤ÓÐÐÐÐЃÐÐÐ
ð¡ÍÓÈÐÌ ˆÍ¥Ðð¤ÌËÙÓ´Ò°ÓÈЈÐˋÐÒÌ₤ШÐ**ÐÌÛÕÐÛÓÌÇ£ÐдÐÌ°ÓШÐ₤ÍÊÏÐЈҰÓÈÐÌÐÊÓ¨Í ÇÐ**ÐÛФИÐÐð¡Ì¯Ð¨ÍÕÀдÐÐÎÒÀ´ÕÂÍÐЃÐÐ
̘Ҵð¤ÐÏÐ₤ÐÐÐÐÊÐÛÕШÐÍ₤ÒÈÍÝÊÐдЈÐÈÐÌ¿ÐÓÇÕÂÐÐÐÐÌ°ÓЈпÐ₤дÐÍÕÀÐÌñÝÍ£ÍÐÐÍШÒÐÐÎÐÐпÐÒÎÓ¿ÐÌÇÓÐЃÐÐ
ÍÍÍ
˜ÕÌËÿ¥2026Í¿Ç1Ì16ÌË
ÌÓçÌÇ̯ÌËÿ¥2026Í¿Ç1Ì25ÌË
Ð₤ÐÐШ
ÐÒˆÍÐ₤Ò°ÓÈÍÛÑÐÏÐ₤ЈÐÐдÒÐÐÎÓÌÇ£ÐÐÎÐÐð¤¤ÐÐÐÐÓ¡ÓÑÐÒΈÌÕÐÛÍÕÀШÓÇÕÂÐÐдÐÐÍÐÐÎÒˆÍÐÛãÌ°ÓÓ¨Í ÇãÐÍÊÐÐÈÐÎÐÐÐдШ̯ð£ÐÐдÐÐÐЃÐÐ
̘Ҵð¤ÐÏÐ₤ÐÒˆÒÎÐÛЈÐÒ°ÓÈÍÛÑÐÓÇÕÂÐÐЈпÐ₤дÐÐÐÛÍШÒÐÐпÐÒΰӿÐÌÇÓÐЃÐÐ
ãÌÛÕãдãÌ°ÓÒˋðƒÀãÐÛФИ
-
ÌÐÀÍÛÑÐÒÊ̯ÐÐ
-
Ì ˆÍ¥ÐͯÐÌÐÈÐÎÐÐ
-
ÒΈÌÐÍÊÐ
ÐÐÐÐÓÑÌ°Ð₤ÐÌ°ÓШÐ₤ÍÊÏÐЈÒý˜ð££Ð£ÐˆÐ¿Ð₤ÐÛÍ¥ÐÕШЈÐЃÐÐ
ӿШӡÓÑÐÓçÀÐдÐÒΈÌÕÂð¢ÐÛÒˆ¢ÌÇапÐÐð¡Ì¯Ð¨ð¡ÐÐЃÐÐ
Ó¡ÓÑЈпÐ₤ÐÛð¡£ÒÎÍ
-
Ò°ÓÈÐÛÌʹУÍÍ¡ÐÌÌÏ
-
ÌÌÒÀ´ÓʤÐÕ ÐÐ
-
ÒˋÝÐÍÐÐÌÌ Ò¨Ð¨ÕËÐ
ÌñÝÍ£ÍÐÕ¢ÐÐÒÎÓ¿
-
ÌˋÌÐÛаÐÐËÐÐÝÐ¥ÐñÐÏа
-
Ò°ÓÈÐÛÌÓ¤ЈÌÌÀ
-
դҴУð¢ÀҴЈÐˋÐÛÌ°ÓÌ ÓçТÐÛÓÒÏÈ
ЃдÐ
ÒˆÒÎÐЈÐЃЃҰÓÈÍÛÑШЈÐÐдÐ₤ÐÌ°Íð£Ëð¡Ð¨ÐˆÐ¿Ð₤Ðð¥ÇÐЃÐÐ
ÌÇÓдð¤ÍÐÛÌÌÒÀ´ÓʤÐÐÌÍÊÏÐÛÓÇð¤ð¤ÕýÓÙÐÏÐÐ

ÐÐÐÐÀÐÐÏÐÌÏÕ ÐÐÌÇÓÐÐÎÐЃÐÐ