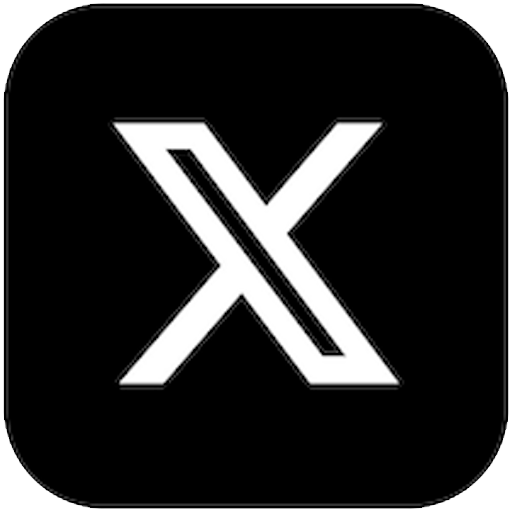ÐÂÐÎÐÐçÐÊÐÐ¥Íð¡£ð¤¤Í
˜ÐÌ ÐÐÌÓÓʃð¥ÐÛÌ°ÌÒÙ
ãЈÐÐð¡Í´Ó´ÐˆÍ¯ÕÍÛÑÐÐÌ₤ÌÐÐÐÐÛÐ
ҢͿÇÐÛÐÐˋÐÐÓˋÒˆÐÏÐ₤ÐÓçӿШÕÎÇÌЃЈÐÐÐÂÐÎÐÐçÐÊÐÐ¥Íð¡£ð¤¤Í
˜ÐÐÓ¿¯ÐÒ¢ÐÌÐÐÐÎÐЃÐÐ
ÐÐÛ̓ÍÐ₤ÐÌÓÐÐÓʃð¥Ð¨ÐÐÐÌ°ÌÒÙдÐÓÀÕÂð¢ÐÏÐ₤ÐÐЃÐÐÐ
̘Ҵð¤ÐÏÐ₤ÐÐÐÐÐÓˋÒˆÌÏÕ ÐÌÐÐÐШÐÓƒð£ÈÓʃð¥Ð¨ÐÐÐ̰̓дͯÕÍÛÑÐÛͧ¿ÍýÐÒÍ₤ÐЃÐÐ
ÍÍÍ
˜ÕÌËÿ¥2026Í¿Ç1Ì17ÌË
ÌÓçÌÇ̯ÌËÿ¥2026Í¿Ç1Ì25ÌË
Íð¤ÐÌÍÛÐð¡£ð¤¤Í ˜ÐÛÐÐˋÐÐÒÎÐÎÐÐдÐÍÛÍÍÛÑÐÛÌÒÎÐÐÐÐЯÕÎÐÐÐÐÐÐЈÐÍ ÇÕÂÐͯЈÐÐÐЃÐÐÐÓçÓ¿ÐÛШХШÐÌÓÑÐÐЈпÐ₤ÓÛÀÓÐÓÀÒÎÐÐЯÐÓƒÍÛÐÏÐ₤Ó¯ÀÍÐ¨Ó¨Í ÇÐÍÊÝÐÐÐÐÐÐÐдÐ₤ÐÍÊÐÐÛÒÎÒÇÒ ÐÍÍШÍÐÐÈÐÎÐЃÐÐ
ÐÐÐÏÐÓÏÐÐÀÐ₤ÐÓÀÌÌ°ÐÏð¡Í´Ó´Ðˆð¡£ð¤¤Í ˜ÐÐÌ̓Шð¤¤ÐÒÎÌ´ÐÎЈÐÍ ÇÕÂШÐÍÎЈÍÛÍ çÐÒÎÐЃÐÐÐÐÐ₤ÐÐÐÛÒÀÍÐÓƒÍÛÓÐ ÐÐÐÏÐ₤ÐÐЃÐÐÐÓƒÍÛÐÏÐ₤ÕÐЈÐдÍÐÐÈÐÎÐÐÐÐÐÐÐ͢ШͥÐÈÐÐÐÐÛÐÏÐÐ
ÌËÍ¡¡ÓÌÇ£ÐÏÐ₤ÐÐÌÙÈÐÐÐÒ´ÐЈÐÐÐÓÒÏÈÐÐÎÐÐÐ̓ÐÐдÐÐÕ¡ÌÐÐÓÏÐÐÀÐ₤Ó¿¯ÐÒ¢ÐÐÎÐЃÐÐÍÓÓÐÏÐÐÐдÐÌ°ÂÕ´ÐÓ¨ÐÎЈÐÐдÐ₤ÐÓʃð¥ÐÏÓÐÐÐÐШ͢ ÒÎÐˆÌ Í¤ÎÐÏÐÐÐÐÐÍÌШÐÐÐÐÒ´ÝÐÐÐЈÐÐÐÐÐÐÐÐÐÈÐÐдÐÐÒˆÍñÝÍÐÐÍÛÍ ´Ð¨ÌÑÐÐÐÐÐÏÐÐÐЃÐÐÐ
ÐÐˋÐÐÛð¡£ð¤¤Í ˜Ð₤ÐÐÐÛÒˆÍñÝÍÐð£ÈÓÓШͥÐÍÐЃÐÐÐÐÐͧ¥ÐÐ₤ÐÌÙÈÓƒˋÐÍȯըШð¡£Í¥çÐЃÐÐÐÓÀÍÈÐÏÐÌШ҈ÊÒÏÈÐÐÐÐˋÐÐÌð£ÈÕ ÐШÐÒÎÐÐÐÐÐÐÏÐÒÎÌÐÏÐ₤ð¤¤ÐÍÐÌ´ÐÎЈÐÐÐÐÛÍÏ¢Ð₤ÐÍÍˋÐÛÓˋ҈дÐÐÐÐÐÐÐÐÐÏÐÓñÐÒÑÐЈÐÐÈÐÐдÐÐÓ¤҈ШҢÐÐÐÛÐÏÐÐ
ÒÍ°ÌñÝÐÐÛÐ₤ÐÐÐÐÐͧ¿ÐÌ¥ÐÐð¢°ÍˆÐÐð£ÐƒÐШð¡ÐÒˆ¢ÍÙÐÛÍÙÍ´ÐÏÐ₤ЈÐÐÐÐÊÐÎÕ Ó¿ÐÓçÕ´ÐÐ̓ÐÛð¤¤ÓˋÐÏÐÐÓ¿ÐÏÐÐͧ¥ÐÐ₤ÐÐÐÐÐÍÐÀð¡ÐÐð¤¤ÐÐÏÐ₤ЈÐÐÐÍÐÈÐ̓Шð§ÐÌÛÐÐÐÓËÐÈÐÎÐÐð¤¤ÐдÐÐÎÓ£ÕÂШӨÐÀЃÐÐÐÐÛð§ÐƒÐÐÐÒÎÒÇÒ Ð¨ÕͤÎЈÌ₤Ò¥ÐÍÈÓÙÌÐÌÝÐÐЈÐÐ
ÐÐÛÓ´ÛÐÛÐÐˋÐÐ₤ÐÓƒÍÛÕÕ¢ÐÏÐ₤ÐÐЃÐÐÐÐÐÐÐÓƒÍÛÐÐÐÓËÐð¤¤ÕÐÐÒˆÍÐÛð¡ÙШÌÛÐÈÐÌÌ ÐÌÇÓÐÐÐÐÐÛÒÈ Ó§ÛÐÏÐÐÌ°ÐШХШÐÍÎÍÛÐÐÐÛÐÏÐ₤ЈÐÐÐÐÛÍÊÍÇШӧÛÐÐÐð¤¤Ì ÐÐÕÐШÓ¤ÐÐÐÍ ÇдҴÐÐÐÏÐÐÐÐ
Óʃð¥ÐÌÓÐÐУÐˋÐÍȯըЈÌÙÈÓƒˋÐ₤ÍÝ Í ÇÌÐÍÊÝÐЃÐÐÐÐÛð£ÈÐÐШÐÕÐÐÏð¡Í´Ó´ÐˆÌÙÈÓƒˋÐÐÐÐÈÐ₤ÐñÐÏаÐÛð¡ÙÐÏÌ₤ÐÐÐÐÐÐÛÐд҈ð§ÐÐð£ÐÛÓʃð¥ÐÛÍÏ¢ÐÐÐÐÌ ÐÐÎÐÐÐÛРдÌÐЃÐÐ
ãÑÐЈÐÐÐ
Ðð§ÐÐÐÐÐÐдÌÐÐÐÐÓ¿
ÐÐÐÐÀÐÐÏÐÍËÐÛÒÏͤÎÐÐÌÇÓÐÐÎÐЃÐÐ
ã£Ì˜ÌÐÏÒÏÎÐÐÐШХШдð¤¤Ì
ÿ¥ÌÌ
ÐÛÒÀÌ¿ÐдÐÐÐÐ¥ÐÐ₤Ð
ͧð¤ÍÌÐÛ̘ͤÓЈÒÐ̿УÍÊÌÙÐÛÒ£¡Ð¨ÐÐÊЈÐÐÈÐÎÐЃÐÐ
ãÑ conceptÐХС