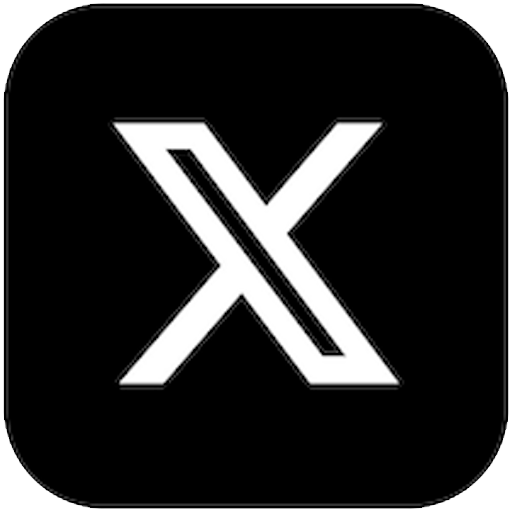ÒÈÍÊÍÛÐÛÍ Í ËÌÐÍÒÎÐÓ˜ÌÙдÐÛÕÐ
Íͤÿ¥ÐThe Lawyers(ÐÑУÐÙÐ¥ÐÊХФ)Ðÿ¥ÐÂÐÊÿ§ËдШÿ§ËдпͤÓÿ¥2016Í¿Ç6ÌÍñ
ÕÈÒ¥ÐÍ¥ÒÙñÍȨУÐˋÓÇ ÌçЈð£ð¤Ð₤ЈÐÿ¥ ÐÓ˜˜ÿ¥Íÿ¥ÍƒÓñ´ÿ¥
ÌýÒ¥ÓÐ₤ÐÐÀÐ
ÒÈÍÊÍÛÐÛÒÐÐÓÍÛÐͧð¤Ò Í̿ШдÐÈÐÎÍÎËͧЈÒÏÈÌݤÐ
ÍÓ₤ÐÏÐ₤ÐӘӨ̓ÕÐЈÐÐÛÌÐÐÏÌñÝÐð¤ð£ÑдÐÐÎÐÒ´ÇÒ´ÍÊð¤ð£ÑÐÓÇ¿ð£ÐЃÐÐÐÐͯ̿է͡ÐÛӤͥÐÏÐÐÓÏÐÛÍ ÇÍÐÒ´ÇÒ´ð¤ð£ÑÐð¤ÍÌÓçÍÑÐÌ₤ÐÐÌËÙÍÐÛÐЈÐÐÛÕ´ÍÐÍ ÐÐÎÐЃÐÐ
Ò´ÇÒ´ð¤ð£ÑдЈÐдÐÒˆ˜ÍƒÐÛÍ₤ƒÒÝÀÐ₤ÐЃÐÐ₤Ì
ͧÒÈÍÊÍÛдÐÐÐдШЈÐЃÐÐ
ÒÈÍÊÍÛÐÛÒð§ÐÒÈÍÊÍÛШÍ₤ƒÐÐÐÂаÐÝÐ¥ÐÐÛÕÒ´ÐÏÐÐЯÐЯÐÒÈÍÊÍÛÐÐÛÒÐÐÍ¥ÒÙñÍȨÐÛÒ´ÇÒ´ÌÇ£ÍÐÛÍ´ÐÌ¿ÐÌÐÐШÐÐÐÎÐЃÐÐÐÐÐÐͧð¤Ò
Ðð§Ð´Ò´ÐÐдÐÓÍÛÐÌÐÐШÐÐÐÛÐ₤ÐÐЃÐÏÒˆÍÐÐÀÐÏÐÐдÐÛð§¢Í§ÌÐ̘ͤдÐÐÐÐШÒÈÍÊÌÐÌÕÌÐÐÐÐШÒÀÐÓÐÐÐШͥÒÙñÍȨÐÛÕˋÍЈҴÇÒ´ÌÇ£ÍÐÌÝÐÐдÐÐÈÐÒÐÐÐͯЈÐЈÐÐÐШÌÐÐЃÐÐ
ÐÐÐÐÐÒÈÍÊÍÛÐÍ´ÐÌ¿ÐÌÓʤÐÐÍÌдÐÐÎÐÒÈÍÊÍÛÐÐÐÐÒˆÒ¤¨ÐÛÍÊÌÙÌÏÕ Ð£ÍÊÌÙÕÓ´ÐÓÓ¤ШÌÌÀÐÐÐÎÐÐÐШÐÊÐÐÎÐ₤ÓÍÐÛÐÐдÐÐÐÏÐÐÍÊÌÙÐ₤ÐÌÒÙÓЈÒÎÍ Ð¯ÐÐÐÏÐ₤ЈÐÐͧÐÛ̘ð¤¤ÐÐÐШ̯Ðð£ÐЈÐЃЃÐÓÀÌÒÙÓЈÒÎÍ Ð¨Í§ÝÕ¢ÐÐÐÐÐÛÐÏÐÐÐÒˆÍÐÛÍÊÌÙÕÓ´ÐÐͧÐÛ̘ð¤¤ÐÍÛÂÒΰÓШÍÌÐÐÐдÐ₤ÕÈÐÐÐдÐÏÐÐ
ÐÐÐÐÍ¥ÒÙñÍȨШÐ₤ÐðƒÕ ¥Ò
ÐÐÐÐÐÐÏÐÐÐð¡ÍÛÐÛÕÂð¢ÌÏÐÏÐÛÐÐпÐÒÏÈÌݤÍÐÐÐÐÒÈÍÊÍÛÐÛÒÐÐÓÍÛÐÓ¤ÍÛÐÐЯÐͧð¤Ò
Í̿ШдÐÈÐÎÍÎËͧЈÒÏÈÌݤдЈÐдÐÐÐÐÐÏÐ₤ÐÐЃÐÐÐ
ÐÐÐÎÐÒÈÍÊÍÛÐÌ°ÍÛÐÐð¤ð£ÑÐÛпСдпÐ₤ЈШÐÐÎÐÐÐÐÐÐÍ
Í
ËÌÐÍÒÎÐÓ˜ÌÙÐÌÕÊÐÐÐð¢Ò´¥Ð₤ÐÒÈÍÊÍÛÒˆÒ¤¨ÐÛÌÕУ͢ÌÏÐШÌ̓
ÐÐУÐЈÐдÐÐÐÛÐÓƒÍÛÐÏÐÐ
ÓÍÛÐ₤ð¡ÐÊÐÏÐÐдҴÐÈÐÎÐÐÐпÐÎÐÛð¤ÍÛШÐÊÐÐÎÐÛÒ´¥Ì ÐÌÛÐÈÐÎÐÐÐÐÐÏÐÐÐЃÐÐÐÐÐÒ´¥Ì ÐÏÓçТӨÐÎÐÐÐÓÍÛÐ₤ÐÐÐЃÐÏÓ¡Í₤ƒÓЈÐÐÛÐÏÐÓÍÛÐ₤ð¡ÍÛÐÛÍ¿
ÐÛÐÐÌÎÍ¢çÐÏÐÐдÐÐÐÐÐ̓ЃÐÐÐÍ¥ÒÙñÍȨдÐÐÎÐ₤ÐðƒÕ ¥Ò
дÐÛÕÂð¢ÌÏÐÛð¡ÙÐÏÐÍ
ñð§ÓÍÎËͧÌÏÐҡЃÐÐÒ´ÝÍÛ¿ÐÐÐÓ₤ÍýÐÛÓÍÛÐÒ¢§ÌÝÐпÐÐÒÈÍÊÍÛÐÛÍÊÌÙÕӴШÌͿШÍÐÌÐÐÎÐÐÐдÐð£ð¤Ð´ÐÐÐдШЈÐÐÏÐÐÐÐ
ÒÈÍÊÍÛÐÛÒÐÐÍÊÐÐÐÛШͧ¿Ó¨ÐÈÐͯÕÍ ñдÐ₤
ÐÐÛÕÓ´ÐÓˋÒˆÐÍ¿ƒÐÊÐÐÛÒÈÍÊðƒÐÌÐÐÎТÐÐдÌÐЃÐÐ
ð¥ÓʃÐÛð£ÈÒÀ´Ò
ÐÛÌÙ£ð¤Àð¤Ì
ШÐÊÐÐÎÐð¢Õ¤ð¥ÓʃÐÛÒ´ÇÒ´ÍÊÐÏÐÛÓʤҨÌÓʤÕÀÐ5927ð¡8720ÍÐÏÐÐÐÐÕ¤ÌÐÛðƒÕ ¥ÐÏÒ´ÇÒ´ÐÌÒçñÐÐдÐÐÐÒÈÍÊÌÐÛÒˆÍÛ¿ÕÀÐ₤8158ð¡5280Íÿ¥Õ
Í£ÑÌÍÛ°ÕÐÍ ÐÐð¢Õ¤ð¥ÓʃÐÛÌÓçÌ₤ÌÕÀÐ₤Ð9202ð¡9710Íÿ¥Ð´ÐˆÐÈÐð¤ð£ÑÐÌ
ͧÐÐÐдÐÐÐЃÐÿ¥ÌÙͿͯÍÊÍ¿°Ìÿ¥Í¿Çÿ¥Ì10ÌËУÐÍÊðƒÐ¢ÐÊРФÐ990Íñ228Õ ÿ¥Ðð¥ÓʃÐÛð£ÈÒÀ´Ò
ÐÛÌÙ£ð¤ÀШÐÐÕ¡ÍÊÝÍˋÓШÐÊÐÐÎÓƒÍÛÐÛÍ ÝÕ
˜ÐͤÓÊдÐÐÎÓÛÍÛÐÐÐð¤ðƒÐÐаÐÙаÐÛ̓ÐÛÕÊ̘ͥÏÍ
ÐÛÒ´Ò¥Ð₤ÐÍÊÌݤÐÓ£Ò¥ÐÐÐÍÊðƒÕÒˆÓÙШÌýÒ¥ÐÐÐÍÊÓʤð¤Õ
ÐÛÒÎÌ´ÐÐÐÛЃЃͥӴÐÐÐÐÛÐÏÐÐð£Ëð¡ÍÐÐÿ¥Ð
ð¤ÊÕÌÍÛ°Ò° ÍÒ´ÇҴШÐÊÐÐÎÐÒÈÍÊÌÐÐÐ₤ÐÍÊÏÕÐÛÍÓ´Ûð¤ÌÀÐÍ
˜Í¿°Ð£Ò¢
ÕШÍÎÓÐÐÐÐÐÍÊÐÐÐÒ° ÍÕÀÐÕÍÊÝÓ¡ÌÛ¤ÓШÕÂÐÐ̤ͤÍÐÍ°ÐÐÐÎÐÐÐдÐÐÐð¤Ó¿Ð¨ÕÂÐÐÒÈÍÊÌÍаͧð¤Ò
ÐÛÒˆÒÙÐ₤ÐӡͧӴͤÎÍ
ÝÕÍÐÐÐÎÐÐÐÐÐÐÐÙÿ¥Í¿Çð£ËÍ
ÐÏÐÛÓÇð¤ÐÛÒÏÈÌݤÐÍ°ÐÐÐÎÐÐдÐÐÐð¤ÌÀÐÛÒÏÈÌÐÍ₤ˋÓÐÐÐÕˋÌÙÈÐÐÊÍ¿ÓÓШÒÀÐÐÐÐдÐÌ̓
ÐÐдÐÐÐÎÐЃÐÿ¥Ì°´ÿ¥ÿ¥Ð
ÐÐÐÎÐÍÊÏÕÐÛÍÓ´Ûð¤ÌÀÐÌÝÐð¤ÊÕÌÍÛ°Ò° ÍÒ´ÇҴШÐÐÐÎÐ₤ÐÒˆÐдÕÀÍÓÍÎÓÐÛШХШÐͧÂÌÐÐÐÐдШЈÐÐÍð¤ÌÀÐÛð¤Ó¿Ð¨ÐÊÐÐÎÐ₤Ðð¥Óʃͧ¿ÍÀÐӿШͯÒÎÌ´Àð¥ÓʃÐÛͧ¿ÍÀÐÛÍ ÝÕ
˜ÐÛð¡ÙШÐ₤ÐÍÇÍÍ₤ƒðƒÀÕ´ÍÐ¨Í ÐÍÛÒ°ˆÓШÐ₤ÍˋÓÕ
ͧմÍÐÐÐдÐÐÎÐÕ¡ÍÊÝÍˋÓÐÛͤÓÊÍÍ
ËÐÐÐÐÛÍÐÌÏÕÊÐпÐÐÏÐÐдÐÐÍÛÍÓÍÌÝÐÐÐÌÂШͧÌУХÓ¤ӨÐÐÐÎÐÐÐÐÐÏÐÿ¥Ì°´ÿ¥ÿ¥Ð
ÐÐÐÐÍÛÕð¡ÐÍÇÍÍ₤ƒðƒÀÕ´ÍÐÓ¤ÍÛÐÐÐÛÐ₤ÒÐÐͯÕÈÐÏÐÐÈÐÎÐÌˋ̯ÓШð¡ÍÛÕÀÐÌÏÕÊÐÐÐдÐÐÐдШЈÐÐÐÙЃÐÐÐÐÐÛð¤ÌÀÐÏÐÐÌ
ͧÒÈÍÊÍÛÐ₤Ðð¡ÍÛÍýÍÌÏÕÊÐÐÐÛÐͧÓÑдÐÐпТапÐÏÐÐÐÍÒÏÈÌÀдÐÐÎÌÓʤÐÐÐÕÕÀÐ₤ÐÍ¿ÇÍÐÛ10ÿ¥
ÐÌÏÕÊÐÐÎÓÛÍÛÐÐ6653ð¡0848ÍÐÏÐÐÐ
ÐÐÐÐÐÐÛÍÛÍÓÍÌÝÐÐÓЃÐÐÐÛÐ₤ÐÓ₤Ó´Í₤ƒÓÙÐÛÐÐШÐͧ¿ÍÀÍ ÝÕ ˜ÐÍÊÐÐÐÐдШÐÐÈÐÎÓçÒý£ÐÛÓ₤ÍýÐͤÐÐÐдÐÐÍÌð¥ÓʃÓÙÐÛÍÛÕШÓÓÛÐÐͯÌËÐÛÕ¡ÍÊÝÍˋÓÐÛÕÀÐÕÍÊÏдЈÐÈÐÎÐЃÐð¡Õ§ÍÐÍÕ¢ÐÐÍ¢ ÒÎÐÐÐÈÐÐÐÐÏÐÐдÒÐÐÐÐÐÐÐ₤ÌËçÐÐÎÓƒÍÛÓЈÍñËÍʨÐÏÐÐÈÐÐ₤ÐÐÏÐÐÐÐÐÐÐÐÛÐÐЈÒÙ¯Ò¨ÐÍÝÕÐÐÎТÐÎÐÐÌ Í§ÒÈÍÊÍÛШÐ₤ÐЈÐЈÐÓÇ̓ÐÐÎÐ₤ÐÐÐЃÐÐÐÏÐÐÐ
ÐˋÐÐÐÐÐÛÐдÒÐÐÐÐÙÐÎÐÐдÐÐÐÓͧð¢Õ¤ÐÛУХШпИÐÐÈÐ¥Ð¨Õ ÌÇÐÐÒýˋð¢ÍÐÛð¡ÙШÐÐð¡Ùͯð¥ÌËÙÓʃÕñÐÛÍÍ
ËдҰÓÈÿ¥ÐÐÐШÓ₤Ó´ÐÐÐÐÐÐÐÐÐШÓÇÓ´ÐÐÐÐСÐÿ¥1994Í¿ÇÐÌË̘ÍÛÌËÙͤÓÓʃÿ¥Ð´ÐÐÍÍÙÐÐÐÐÐÐШð¡Ùͯð¥ÌËÙÓʃÕñÐÛÍ¿ÇÍÓñÕÀÐÛÍ¿°ÍÐ2169ð¡ÍÐÏÐÐдÐÐÍÛÌ
Òˆ¢Ì£ÐÌýÒ¥ÐÐÐÎÐÐÐÛÐÒÎð£ÐÐÐÛÐÏÐÐ
̘ð£ÑÐÛÒ¨ÍÛ°Ò
Ð̓ÐÎÐÐÍ¿ÇÍÐ₤960ð¡ÍÐÏÐÐÐÐÛÍÍÙÐÓýÓ˜˜33ÍñÒ´¥Ð´ÐÒ´¥Ì дÐÐÎÌͤÐÐдÐÐÐÍÊÌݤÐ₤ÐÒ¨ÍÛ°Ò
ÐÛÓƒÍÛÐÛÍÍ
ËÍ
´ÐÎÐÕ¡ÍÊÝÍˋÓÓÛÍÛÐÛͤÓÊдÍÊÌÙÐÐÐÐÛдЈÐЃÐÐÐ
ÐÐÐÐÓýÓ˜˜33ÍñÒ´¥Ð₤ÐÍÊÌÐÛÐˋÐШÐÍ¥Ó´ÐÐÐÎÐÐЃÐÐÐÏÐÐÿ¥ÐÐÈдÐÐð¤ÍÛÒˆÍÛШ͢
ÒÎЈÐÐÛÐÏÐ₤ÐÐЃÐÐÐÐÐÓÍÝð¡Ð₤ÐͥӴШЈÐÐЯЈÐЈÐÐÐÛÐÏÐ₤ЈÐÐÛÐÏÐÐãÎÿ¥Ð
ÐÐÐÎÐÍÊÌð¡ÙÐÛÒˆ˜ÓʤÐÏÐ₤ÐÐÐЃÐÏÐÛÒٯҨШÐ₤ð¡ÍÒÏÎÐÐÐÐÎÐЃÐÐÐÒ¨ÍÛ°Ò
ÐÛÓçÌÙÇÐÓ´¥ÍÓÑÌ°Ðð£ÈÒÀ´Ò
ÐÍÊÐÐÎÐÐÍð¥ÓʃÐÛÌÐдÐÛ̯ÍÙÐ̃ÐÐÐÐÐÐÛÌËÙÓ¡ƒÐÐ̯ÐХСШ̡ÀÐÈÐÎÌÇÓÐÐЯÐÐÐÏÐÐÐÐÐÐÐÐЈÐÓÓÝÐÒˆ˜ÌÐÐÐдÐЈÐЃЃÐÌÙ£ð¤ÀͧÌ̓ÐÎÐÐÍÍ
ËÐ₤Í
´ÐÎÒ¨ÍÛ°Ò
ÐÛÍÇÍÐÛÍ₤ƒðƒÀÐÏÐÐдÒˋðƒÀÐÐÐÛÐӡͧÐÏÐÐдÐÐÐÐÛÐÏÐÐÐ
ÐÐÐÐÐÐÛÍÍÙÐÌͤÐÐð£ËÕÐÛÌçÐÐÒÈÍÊÍÛдÐÛÐÐÍÐÐÐÌ´Í₤ÐÐдÐÐÐÛÍÍÙÐÏð¡Ùͯð¥ÌËÙÓʃÕñÐÛÍ¿ÇÍÓñÕÀÐÛÍÛÌ
ÐÓÒÏÈÐÐÎÐÐÐÈÐÐдÐÐÌ
ͧÒÈÍÊÍÛÐÛÍÊÌÙШÐÊÐÐÎÌݤÍÛÓЈÒÎÍ Ð´ÐˆÐÈÐÐÐÛÐÏÐÐÒÐÐÐÐ̓ЈÐÐÛÐÏÐÐ
ÐÐÐÐ10Í¿ÇӴ̓ШÐÐÐдÍÓ´Ûð¤ÌÀÐÌ
ͧÐÐÍÌÏÐÛÒ´ÇÒ´ÌÇ£ÍÐÐÐð¤ð£Ñÿ¥ÐÐÈдÐÐÒ¨ÍÒ´ÇÒ´ð£ÈÓð¤¤ÐÐÌÍ¥ñÐÍñÌШÍÒ¨ÐÐÎÐÐÐÛÐÏÐÐÕ ÐÐͯð§ÕÐÛÍÎÍÐШÐÒ´ÍÐÐÿ¥Ì°´ÿ¥ÿ¥ÐˆÐˋÌÕÌÐÍÊÐÐ₤ЈÐЃÐÐÐãÎÿ¥ÐÐÐЃÐÿ¥ÌÙͿͯÒÈÍ¿°Ì21Í¿Çÿ¥Ì26ÌËУÐÍÊðƒÌÍ ÝÐ2045Íñ130Õ ÿ¥Ðð¤ÊÕð¤Ì
ÐÏÌÙ£ð¤ÀÐÐ57ÌÙ°ÐÛͯÒÎÌ´ÀЈð¥Óʃð£ÈÒÀ´Ò
ÐÛÕ¡ÍÊÝÍˋÓШÐÊÐÐÎÐͧ¿ÍÀÍ ÝÕ
˜Í¿ÇÕÀ840ð¡ÍÍ
´ÕÀÐÍÇÍÍ₤ƒðƒÀÕ´ÍдÐÐ70ÌٰЃÐÏÓ´¥ÍÍ₤ҧдÐÐÎÓÛͤÐÐÐð¤ðƒÐÿ¥Ð
ÐÐÛÍÊÌݤÐÓ£Ò¥ÐÐÍÌýÍÊðƒÕÒˆÐÛÍýТÒÏÈÒˆ˜ÐÏÐÐÒÈÍÊðƒÐÏÐ₤ÐãÎͧ¿ÍÀÍ ÝÕ
˜ÐÛ50ÿ¥
ЈÐÐ90ÿ¥
дÐÐЈÐˋð¡ÍÛÐÛÍýÍдÐÐÐÐÛÐÌ₤Ò¥ÓÍÊÐÐãÎãÎÐÿ¥ð¡ÙÓËÿ¥Ð̘ÍÊÌݤÐ₤ÐãÎãÎд҈ÐÐÎÕ¡ÍÊÝÍˋÓÐÓÛÍÛÐÐÐÐÛÐÏÐÐÐÍÛÍÐÛð¡Ò˜Ó̓ÍÐÐÍÊÐÐÛÍˋÓÐÒˆÐÐӿШӿÒýÐÐÐÐÛÐÏÐÍÛÍð¡ÐÛÍÒдÐÐÎÓÇ¿ð£ÐÐÐÐдҢ¯Ð¿ÐÐÐÎÐÐÐдÐÒÐÍÐÐÐдÐÐÐÐÐÛð¤ÌÀÐ₤ÐÐÐÐÐÍÊÌð¡ÙШӃÐÐÎÐЈÐÒ´ÇÒ´ÌÇ£ÍÐÐÓçÌШͧÝÕ¢Ðð¡ÐÐÎÐÐдÌÙÍÛÐÐÎÐÐдÒÐÐÎÐЃÐÐ
дÐÐÐÏÐÍÕ ÙШÌÐÐð¤ÌÀдÍÌÌШÌ
ͧÐÐ̓դÕÍÛ°ð¤ÌÀÐÏÐÒˆÍÒ£Í
ÝÌ¡ÐÐÐÐÐ54ð¡ÍÐÛÌÛÕÀÌ₤ÌÌÓʤÐÍÐÓÇ̓ÐЈÐÐÈÐÒ¨ÍÛ°Ò
дҢÒΈÒ
ÐÛðƒÕ ¥ÐÍð££ÐÒ´ÇÒ´ÌÒçñÐÐдÐÐÐ2300ð¡ÍÐÒÑ
ÐÐÌ₤ÌÐÍÐÐÐдÐÐÏÐÐð¤ð£ÑÐÐÐЃÐÿ¥ÌÙͿͯÒÈÍ¿°Ìÿ¥Í¿Çÿ¥Ì27ÌËÍÊÌݤУÐÒˆÍÒ£ð¢Õ¤Ð¡ÐÈÐ¥ÐШÐ1219Íñÿ¥ÐÒ¢ÐÐÛÌ´ˆÌÙÌÙˋÕÌ¡ÀÐЈÐÐÈÐÒˆÒ£ÂÒ£ÐÕÍÊÏЈÕÍÊÝÐÏÐ₤ЈРÕÍÊÝÍýÍÿ¥ÍýÐͥ͡ÓÛÀÓÐÛÿ¥ÓÇÿ¥ÍñÒ
Ó
ÕÂÍ
ËÕÂÐÛð£ÒÙñÌ ÌËÕÀ5000ÍÐÿ¥Ð
ÐÐÐÐ₤Ð₤ͯЈÐдÐð¤ÊÕÌÍÛ°Ò° Íð¤ð£ÑÐÛÌÙ£ð¤Àð¤ÌÀÐ̓դÕÍÛ°ð¤ÌÀШÐÊÐÐÎÐ₤ÐÒ´ÇÒ´ÐÌÒçñÐÐЯÐÒ° ÍÕÀÐ₤ӡͧÍÂÕÀÐÐÐÐддЈÐÐÛÐÕðƒÐÏÐÐÐð¢Õ¤ð¥ÓʃУ҈ÍÒ£Í
Ý̡дÍÛÌШÍÎËÍÐÐпÐÐÏÐ₤ЈÐÐдÐÐÐдÐÍÛÌÐÐÐÐÐð¤ðƒÐÏÐÐÐÐÐÐÐð£ËÕÐð¤ÊÕð¤Ì
ð¤ÌÀÐÛÍÓçШÐÊÐÐÎÐÛÓÏÐÛпТапдЈÐЃÐÐÐ
ÒÈÍÊÍÛÐÛÍÐÏÐ₤ͧ¿Ð¨Ó¨ÐЈÐÍ¥ÒÙñÍȨÐÛЈХИШÐÐÊаÐ
дÐÐÐÏÐÕÀÏÍÍ ÐÏÐÐÍͯͤӣÌÇÓÓçÍÐÐÐÛðƒÕ ¥ÐÏÌ Í§ÐÐð¤ð£ÑÐÏÐð£ÛÌͯÌÍÛÐЈÐÐÐ̓ÍͯШÐÊÐÐÎÐÐÛÍ ÌÒ Ð¨Í₤ƒÐÐÌÌ¡ÀÐÒˆÐÐÐÐð¤ðƒÐÐÐЃÐÿ¥ÌÙͿͯÒÈÍ¿°Ìÿ¥Í¿Çÿ¥Ð₤ÿ¥Ó˜˜1672ÍñÍ10Í¿Çÿ¥Ì28ÌËÍÊÌÝ¤Ð£Í ˜ÍÓˋ̈ӣҥÿ¥Ð
̓ÍͯШÐÊÐÐÎð£ÛÌͯÌÍÛÐÒÀЈÐÐÐШÐÐÐÐÐÐÐÍ£¤ÓˋÓÙÐÛÌÌÒ
ÐÐÓÏ£Ò£ÂЃÐÐ₤ÕÊÍÇШÐÊÐÐÎÍÍÐ̓ÐÐЈÐÍ ÇÍÐÓ¤ÓÐÐÐдÐÐÐЃÐÐÍͯͤӣÌÇÓð¤ÌËÙÐÛ̧ÒÀШͧÐÐÈÐÎÐ₤ÐÍ£¤ÓˋÓÙÐÛÓÏ£Ò£ÂЃÐÐ₤ÕÊÍÇÐỊ́ШÕýЃЈÐÐЯÐͧÓÑð¤ÌËÙÍñËð¤ÐÛÕýÌШÍÊÏÐЈͧÝÕ¢Ðð¡ÐÐð¤ÌËÙÍ
´ð§ÐÕ
Í£ÑÐÐÕÍÊÏЈÍÍ Ð´ÐˆÐЃÐÐ
̧ÒÀÒ
Ð₤ÐÍ£¤Ó₤ÓˋÓÙÐÛÓÏ£Ò£ÂÕÊÍÇÐÐÐÌ´ˋÕÐÐÐÐÐÐˋÐÍ¡Ó¤ÌÕñÐÛÒˆÍ₤ÐÍÐЈÐÐЯЈÐЈÐÐддÐÐÐÎÐÐÿ¥ÍͯͤӣÌÇÓÌ°77ÌÀÿ¥Õ
Ðÿ¥Õ
ÿ¥Ðð§Ì¯ÐÏÐÐÌÏÌÌÒ
дÐÛÐÐˋÐШÐͨÐÍ¡Ó¤ÌÕñÐÒˆÍ₤ÐÐЈÐˋдÐÐÈÐÐдÐ₤Ì̓
ÐÏÐЈÐÐÛÐÍÛÌ
ÐÏÐÐ
ÐÐÐÏÐÍ ÌÒ
ÐÒˆ˜ÍƒÐ£ð¤Ê̡Ш͢ÐЈÐÐЯÐ̧ÒÀÒ
дÐÐÎÐ₤Ð̯ð¤Ò´ÇÒ´ÐÌÒçñÐÐÐÐ̓ЈÐдÐÐÐдШЈÐЃÐÐ
ÐÐÛÐÐÐˆÍ ÇÕÂШÐÊÐÐÎÐÐÍͯͤӣÌÇÓÌ°100ÌÀÐÛÿ¥ÐÛÒÎÍÛШÐÐ̧ÒÀÒ
ÐÓÛÀÓÐÐÍͯШÐÊÐÐÎÐ₤Ð̧ÒÀÒ
Ð₤ÐÌÌÌ´ˋШ̤ÐÐð¡Ó´ÛÐÛÓˋÌ´ˋÓÌ₤Õ
Ì´ˋÐÍ̓ÐÐÍ°ÍͯͤӣÌÇÓð¤ÌËÙÐÛÓÛÓШÐÐÈÐÎÓÑÙÌÓÛÀÓÐÐÍÐ₤ð¤ÌËÙ̧ÒÀÐÛÐÐШ͢
ÒÎЈÓ₤ÍýÍ
ШÐÐÐÎÓ˜˜ð¡Ò
Шð§¢Ó´ÍÓÐÐÐÐÐÐдÐÐÏÐÐÐÐÛдÒÏÈÐпÐÐÐÛÐÏÐÐÐÐÐÓ˜˜ð¡Ò
ÐÌ´ˋÍЈÐÐÐÎÍ°ÍͯÐð¡Ì°Ð¨Í ÌÐÐÍ ÇÍШÐ₤ÐÐÐШÍ₤ƒÐÍ°ÓˋÌ´ˋÓÌ₤Õ
Ì´ˋШͤÐËÐÍ°ÍͯÐÛÌÌ¡ÀÐÌÝÐÐÐдÐÐÏÐÐÐÐÛдÒÏÈÐÐÐÛÐӡͧÐÏÐÐÐÐдÐÐÌÕ¨ÒÈÍÊÌݤÐÐÐЃÐÿ¥ÿ¥£Í
˜Í
Ý̧ҴÙð¤ÍÛͯÿ¥§ÐÛð¤ðƒÿ¥ÿ¥Ì°´ÿ¥ÿ¥Ð
ÐÐÐÎÐÍͯͤӣÌÇÓÓçÍÐÐÕÀÏÍÐðƒÕ ¥ÐÐÐÐÐÈÐÐдЈÐÈÐð¤ð£ÑдÐÐÎÐð£ÛÌͯÌÍÛÐÛÍ₤ƒÒÝÀдЈÐÈÐ̓Íͯÿ¥ð¢Óͯð¤ÍÛͯÿ¥ÐÛÍ ÌÒ
ШÍ₤ƒÐÐÌÌ¡ÀÒ¨ÌÝШÐÊÐÐÎÐÐÐÛÌÕ¨ÒÈÍÊÌݤШÐÛÐÈдÐÈÐÍÊÌÙШÐÐÒˆÐÐÐÐð¤ð£ÑÐÐÐЃÐÿ¥ÌÙͿͯÒÈÍ¿°Ìÿ¥Í¿Çÿ¥Ì26ÌËÍÊÌݤÐÌÙÍ¿Õ¨ÒÈÍ¿°Ìÿ¥Í¿Ç10Ì31ÌËÍÊÌݤУ̓ÌýÐÓçÍͤӣÌÇÓÐ59Íñ32Õ ÿ¥Ð
дÐÐÐÐÓÑÐÐÎðƒÕ ¥ÐÐÐÐÐдÍÓ´ÛÐÛð¤ÌÀÐ₤Ðð£ÛÌͯÐÛÌÍÛÐÍÐÐ̓ÍͯÐÏÐÐð¢ð¤Í¯ÐÛÐÐÀÐð¡Õ´Ð₤ÕÒñ₤ð¤ÍÛͯдÐÐÐÎÐЃÐÐÐÐÐÐð£ËÍÊÐÛÕ´ÍÐ₤ÐÍËÐÛ̓ÍͯÐÛð£ÛÌͯдÐÐÎÌÍÛÐÍÐÐÎÐÐдÐÐÿ¥ÐÐÐÐÐÒÈÌÍÛÐÿ¥Ðð§¢Ó´ÍÓÕÍÏÌËÐÍÛÐÐÐÐÎÐЈÐдÐÐÐÐÛÐÏÐÐÿ¥ÐÐÐÐÐÒ¢§ÒÌÍÛÐÿ¥Ð
Ì
ͧÒÈÍÊÍÛÐ₤ÐÍͯͤӣÌÇÓÌ°100ÌÀÐÛÿ¥ÐÛÒÎͤÐÐÐÐÿ¥ð£ÛÌͯШÌÍÛÐÐÐÎÐЈÐÍͯÐÛÓÛÀÓÿ¥Ð´ÐÐÐÎÐÐÐдШÐÐ ÐÐÐð¢ð¤Í¯ÐÛÐÐÀ̓Ò
ÐÛÕ´ÍШÐÊÐÐÎÐð§¢Ó´ÍÓÕÍÏÌËÐÍÛÐÐÐÐÎÐЈÐдÐÐÎÐÐð£ÛÌͯШÌÍÛÐÐÐÎÐÐÍͯÐÏÐÐÐдÐÐÐÍÌÀÌÍÛÐÛÍͯдÌÝÐÐдÐÒ¤Ò¤ÐÐÐÛÐÏÐÐ
ÍͯͤӣÌÇÓЈÐˋÐÛÍÕÐÏÒÍЈͥÒÙñÍȨÐÛÒ¨Ó´¢ÐÒÎð£ÐЃÐÐÐÐÒÎÐÐШÐÐÒ¢§ÒÌÍÛÐЈÐˋÐЈÐÐÏÐÍ¿ÍÓ¤ÓÌËÐÍ°ð§¢Ó´ÍÓÕÍÏÌËдÐÐð£ÛÌͯÌÍÛÐÍÐÐÒ
ШÍÍдЈÐÈÐÎÐÐÐЯÐÐдҨÐÐ̧ÒÀÒ
ÒˆÒ¤¨Ð¨ÐÐÌÌ¡ÀÒ¨ÌÝÐÐÏÐЈÐÐдÐÍÌдÐÐÍ₤ƒÍÎÌ°ÐÓʤÐÐÐÛÐÏÐÐÈÐÎÿ¥Ì°´ÿ¥ÿ¥ÐÐÐÐÈÐÎͧ̿Шð¡ÍˋЈÐÐÛÐÏÐÐÐ
ÐÐÐÐð¤ÌËÙÐÛÕýÌÓÑÌ°ÐТЈÐÐÐÐð§¢Ó´ÍÓÕÍÏÌËÐÐÐÒ¢§ÐÈÐÎÕÓËÐÐÐдÐÐÎÐÐÐдÐ₤ÐÍÛÍð¡ÐÛÍ¢
ÒÎÐÕ¨ÐÐÐÛÐÏÐÐЃÐÐð£ÛÌͯÐÛÌÍÛÐÍÐÐð¤¤Ð¨ÍÍШЈÐÈÐÎÐÐÐÈÐÎÒÈÍÊÐÒçñÐÐдÐÐÐÛÐ₤ÕÂÍÐÏÐÐЯÐÐÐÐÍÍÐ̓ÐÐЈÐÍ ÇÍШÐ₤ÐÒÏÈÌݤ҈ð§ÐÐÏÐЈÐÐдШЈÐÈÐÎÐЃÐЃÐÐÐÐÐÐÈÐÍÛÌ
Ð̰̓ҨдÐÐÎÌÏÌÐÐÒˆ˜ÍƒÐÒˋÎТЃÐÐÐÐÌ
ͧÒÈÍÊÍÛÐ₤ÌçÌÐÐЯÐÐÐÏÐÐ
дÐÐÐÐ̘ÀÐÛдÐÐÐÓʃÍÈÌ°ð¤¤Í ´Í§ÍͯͤӣÌÇÓÓçÍÕÈÍð¥ÿ¥ÓƒÐ£Í ˜ÓÓʃÍÈÌ°ð¤¤ÒÀÐËÐÐͤӣÌÇÓÍð¥ÿ¥ÐÓ¤ÒÀÐÐÕÒˆÐÓçÍͤӣÌÇÓÐÐÛð¡ÙШÐÐð£ÛÌͯÌÍÛÍаð§¢Ó´ÍÓÐÛÍÌÙÂÐÛÍ¿ÌШÐÊÐÐÎÐдÐÐÒ°ˆÓ̘ÐÐÐÐÐÐÐÏÐÍ£¤Ò´ÙÓէ͡ÍÝͤӣÌÇÓÒˆýÐÐͧ̿дÍð¡ÐÛÓçÒ¨ÐÒÏÈÒˆ˜ÐÐÎÐÐÐÛÐÒÎð£ÐÐÈÐÐÛÐÏÐÿ¥14Íñ43Õ ð£Ëð¡ÿ¥£45Õ ÿ¥§ÿ¥Ð
Ðð£ÛÌͯÌÍÛÍÐ₤ð§¢Ó´ÍÓÐÛÍÌÙÂШÐÐð§¢Ó´ÍÓÐÐÐдÐÛÐÏÐÐÒ ÐÛЈÐЈÐÈÐÍÛ Í¯Ð¨ÐÊÐÐÎÐ₤ÐÌͯÍÎÍÐÛÍ ˜ÍÌËЃÐÏÐ₤Ð̧ÒÀÒ ÐÓÛÀÓÐÐÐддÐÐÐÎÐЃÐÿ¥Ì°Ó˜˜100ÌÀÐÛ2ÐÐÐÛÐÐЈÍͯÐ₤̧ÒÀÒ ÓÛÀÓͯдͥЯÐÐÎÐЃÐÐÿ¥Ð̧ÒÀÒ ÓÛÀÓͯÐÛÍ ñð§ðƒÐ´ÐÐÎÐ₤ÐÍ ˜Í Ý̧ҴÙð¤ÍÛͯÐð¢Óͯð¤ÍÛͯÐÓ¨ð§Ìͯͣ¤ÓˋÐÛÌñͯÐÛð¤ÍÛͯдÐÐÈÐÐÐÛÐÌÐÐÐÐУÐÐð£ÛÌͯдÐÐÎÌÍÛÐÐÐÍÛ Í¯ÐÏÐÐÐð§¢Ó´ÍÓÕÍÏÌËÐÍËШÍÛÐÐÐÐÎÐÐÐÐ̓ÍͯÐÛÍÛ Í¯ÐÛÌÌÒ ÓÙШÐÐð§¢Ó´ÍÓÐÕÍÏÐÐÐÎÐÐÐÐÐÐÊÐÐÐÛð£ÛÌͯдÐÐÎÌÍÛÐÐÐÍÛ Í¯Ð¨ÐÊÐÐÎÐÍËÕð£ÛÌͯÐÌÍÛÐÐÐÎÐÐÍ ÇÍШÐÐÐͧÒˋýð£ÛÌͯдÐÐÎÌÍÛÐÐÐÍÛ Í¯ÐÐ̧ÒÀÒ ÓÛÀÓͯдЈÐЃÐÐÐÿ¥ÍÓ¿ÐÍÓñÐ₤ÓÙÒ ÿ¥
ÐÐÛÕÒˆÐÛÒˋýͧÓÛÌÐÐÌˋÕÐÓýÓ˜˜77ÍñÒ´¥Ð´ÐÐÎÌͤÐÐдÐÐÐÌ
ͧÒÈÍÊÍÛÐÛÌçÌÐ₤ð¡Ó˜Ð¨ÐÐÎÍЃÐÈÐÐÛÐÏÐÐÐÐÐÈдÐÐÐÒÎÏÐÛдÐÐÐÐÐÛÒÏÈÒˆ˜Ð₤ÓçÒ¨ÐÓʤÐÐ ÐÐÏÐÒÈÍÊÍÛÐÌÝÐÐÎÐÐÍÒ´ÓÍШð§ÐÐÛÍÓÙÐÓʤÐÐÐÛÐÏÐ₤ÐÐЃÐÐÐÐÐ ÐÍ£¤Ò´ÙÓէ͡ÍÝͤӣÌÇÓÒˆýÐÒÏÈÒˆ˜ÐÐÐÐÛÐÏÐÐÐ
ÐçдÐÍ¡Ì°ð¢ÛÓ¢ð¡ÙШҴÍÌÊð¤ÓçÕ´ÐÛÐÐÒÈÍÊÍÛÐÐÐÒÀÌ¢Ò´ÇÒ´ÐÒçñÐÐÐÛÐÏÐÐЯÐÓÍÝЯÐÐÐÌ₤ÐÍÐÐÐÒ´ð£ÊÐÏÐÐÐдÕÕÐÏÐÐÐдð§ÐÒÈð£ÐдЈÐͧÍÛÑÌˋÕÂÐÛÌ°ð£ÊÒÏÈÕШÕÂÐÐÐÐÛÐÌÂÐÐдШ̰´ÍÐÐÐÐÐÐÌÓʤÐÐЯÐдÐÈÐÐÐШЈÐÍ ÇÍÐÐÐÐдÌÐÐÐÐÐдÐÌÐͤÐЃÐÐÐ
ÐÐÐÐÎÐÍ
´ÕÂÍÒ´ÇÐÛÍÊÌݤÐÓý̓ÐÐÐдÐÐÏÐЃÐÐÐÐÍÊÌÐÛÒˆ˜ÓʤÐ₤ÐÐÐЃÐÏÐÛÒٯҨШÐ₤Í
´ÐÒÏÎÐÐÐдЈÐÐÐ̘ð£Ñð¢ð¤Í¯Ð̓ÍÐÛÍÛ
ͯдÐÐÎÌÌÐÐÎÐÐÒ¨ÍÍаÿ¥ÀÐ₤Ðð£ÛÌͯÌÍÛÍÎÍÐÍÐÐÐдШÐÐÐ̘ð£Ñð¢ð¤Í¯Ð¨ÐÊÐÐÎð§¢Ó´ÍÓÌ´ˋÕÐ͈ÍÊÝÐÐÎÐÐдÐÐÐ̘ð£Ñð¢ð¤Í¯ÐÛÐÐÀÿ¥ÀÐð£ÛÌͯдÐÐÎÌÍÛÐÍÐÐÕ´ÍÐ₤ÐͧÒˋýÕ´ÍШÐÊÐÐÎÍð¤¤Ðð§¢Ó´ÍÐ₤ÍÓÐÕÍÏÐÐÐдÐÐÏÐÐÌËÐ̈РÍÛÐÐÐÐÎÐЈÐÐÐÐÍð¤¤Ð₤ð§¢Ó´ÐÐÐдÐÐÏÐÐÐЃÐÐ̘ð£Ñð¢ð¤Í¯ÐÛÐÐÛð§ÐÛÕ´ÍÐ₤ÐÕÒñ₤ð¤ÍÛͯдÐÐÐÎÐÐÐÐÐ̘ð£Ñð¢ð¤Í¯Ð₤ÐÓçÍÝÐð£ÛÌͯÐÛÌÍÛÍÎÍШÐÐð§¢Ó´ÍÓÐÐÐÐдÐÐÏÐÐÒ
ÐÛЈÐЈÐÈÐ̓ÍÐÛÍÛ
ͯШÒˋýͧÐÐÐддЈÐÐÐÐÐÐÈÐÎÐÍͯͤӣÌÇÓÌ°100ÌÀÐÛÿ¥Ð¨ÐÐÐÌͯÍÎÍÐЈÐÐÐЃÐÏÐÛÕÐ̧ÒÀÒ
ÐÐÍÍÐÓÛÀÓÐÐÐÐÛдЈÐдÒÏÈÐÐÐÐÐÿ¥ÍÓñÓÙÒ
ÿ¥Ð´ÐÐ̘ð£Ñð¢ð¤Í¯ÐÛÍ
´ÐÎÐͧÓÑÐÛÐдÐÍͯͤӣÌÇÓÌ°100ÌÀÐÛÿ¥ÌÍÛÐÛÍͯШͧÐÐÐÐÛдÐÐð¡ÐÐÐÛ̓ШÓÑÐÕ´ÍÐ₤ÐÍÒ´ÌÕ¨ÒÈÍÊÌݤÐÛÍÊÓʤÐУХÐÐÛЃЃͥӴÐÐÎÐÐÐÐÎÐÍÌÀÐÛÒÎÍÛШÐÐ̧ÒÀÒ
ÐÓÛÀÓÐÐÍͯШÐÊÐÐÎÐ₤Ðÿ¥ð¡ÙÓËÿ¥ãÎãÎÐÏÐÐÐÐÐÌ´ˋÍЈÐÐÐÎÍͯÐÍ ÌÐÐÒ
ШÍ₤ƒÐÐÎÐ₤ÐÍ°ÓˋÌ´ˋÓÌ₤Õ
Ì´ˋШͤÐËÐÌÌ¡ÀÐÐÌÝÐÐддÐШÐÌÌ¡ÀÐÐð¤ÐÒ
ШÍ₤ƒÐÐÎÐ₤Ðð§¢Ó´ÍÓÐÐÌ´ˋÍˋÐЈÐÐдÐÛÓ¤҈ÐÌÝÐÐÐдÐÐÏÐÐдÐÐпÐÐÏÐÐÐÐдÐÐÐÐÛÐÏÐÐÐ
ЃÐÐÍÒ´ð¤ðƒÐÛÍ ÇÍдÍÌÏÐÍÊÌÐÛð¡ÙÐÏÐ₤ÐÐÐÛÕÒˆÐÒ´¥Ì дÐÐÎÍ¥Ó´ÐÐÐÎÐÐЃÐÐÿ¥ÐÐÀÐÐÐð¤ÍÛÒˆÍÛШ͢
ÒÎЈÐÐÛÐÏÐ₤ÐÐЃÐÐÐÐÐÓÍÝð¡Ð₤ÐͥӴШЈÐÐЯЈÐЈÐÐÐÛÐÏÐ₤ЈÐÐÛÐÏÐÐãÎÐÐÐ ÐÐð¡ð£ÑÒ´ÕýÐÛð¡ÙШÐÒÙ¯Ò¨ÐÍÝÕÐÐ̤ÍÌ¡ÕÂдÓýÓ˜˜77ÍñÒ´¥Ð₤ÓÑÇÐÐÐÎÐÐÐð¡Ò´ÇÍ₤ˋÐÛÓÛШÐ₤Í
ËÐÐдШЈÐЃÐÐÿ¥Ð
ÒÀÌ¢ÌˋÕÂÐÛÒÏÈÕÿ¥Í
˜ÍÛÒÏÈÕÿ¥Ð₤ÒÈÍÊÌÐÌÌÐÐÐÐÛÐÏÐ₤ЈÐдÐÐÐдÐ₤ÐÐÐЃÐÏÐЈÐÐдÐÛÐ₤ÐÐÏÐÐÐð¡ÍÛÐÛÌ´ˋÍ´ÓÒÈð£ÐÐÍÙÍ´ÐÐÐд҈ð§ÐÐÍÐ
ÐÛÒÈÍÊÍÛШÐÐÛð¡ÐˆÐÍÛÍ¢ÌÐð¡ÐÐÐÐÛЈÐÛÐÏÐÐÐÐ
ð¤ÊÕÌÍÛ°Ò° ÍÒ´ÇÒ´ÐÏÐÐãÎÐÒÈÍÊÌÓÑÐÏÐÛ̓դÕÍÛ°ÐÛÒˆÍÛÐ₤ÒˆÒ° Òý˜ð¢Õ¤ÐÛ̓դÕÍÛ°ÓÙÓÇÒˆÍÛШÌÌÐÐÐÐÐÛÐÏÐ₤ЈÐÐÒÈÍÊÌÐÐÒ´ÇҴШӃÐÐÍ
´Ò´¥Ì ÐÐÒˆÓÝЈ͢Ҵ¥Ð¨Í¤ÐËÐÐÎÒˆÍÛУÍÊÌÙÐÐÐÐÛÐÏÐÐÐÐÐÐÐãÎãÎÐÒÈÍÊÌÐ₤ÐÒ¨ÍÐÐÐÛÍÍЈÍÒ´¥ÐÛЈÐÕÐÐÍÌÏÐÛÓÙÓÇÐÒˆÍÛÐÐÐдÐÍÊÐÐÍ¿ÓÓЈÍ₤ˋÓÐÒÀÐÐдÐÍ₤ҧдЈÐÐÐдÐÐЃÐÐÿ¥Ì°´ÿ¥ÿ¥Ðð¤ÍÛÒˆÍÛÐÛÍ ÇÕÂÐÏÐ̘ð£ÑдÐ₤̘ÀÍ
ÐÛÕÐÍ ÇÕÂÐÏÐÐÐÒÌ₤ШÐÐÐÎÐ₤Í
´ÐÍÌÏÐÛÌÒÙÌÏÕ Ð´ÐÐÐдÐÐÏÐÐÐÏÐÐÐÐ
ÒÎÐÐШÐÓÒ¤¨ÐÛÒÈÍÊÍÛÐÒˆ˜ÍƒÐÐð¡ÐÏÐð¡Óˆð¢ÀÓ´ÐÐЈÐÐÛÐ₤ÐÍ¥ÒÙñÍȨÐÛÒˆÓϯЈХИШÐÐÊаÐШͤÐËÐ̰̓ÐÛÒٯҨдÐÐУÐÐÐЃÐÐÐÐÐÛÐдÐ₤ÐÍ¡Ì°ð¢ÛÓ¢ÌÕÐÛÓÙÓ¡ÛÐÛÐÐÐÐÒÎð£Ñð¤ÍÛÌÒýÐЈÐЈÐÈÐдÐÐдÐÍ ÝÕÒ´ÒˆÐЈÐЈÐÐÓÐ ÐÐÛ̓ÍÐ₤Í¥ñÐЈÐдð¤Ì°ÐÐÐдÐÐÐÏÐÐ
Ó¡Í Çð£Ëð¡ÐÛÒ° ÍÕÐÓý̓ÐÐÌ¢Ìý£ÍÛÑÐÛÍÒˆÌ₤ÌÒ´ÇÒ´
Ì¢Ìý£ÍÛÑÐÛÍÒˆÌ₤Ìð¤ð£ÑÐÌÝÐÈÐÐдÐÐÐЃÐÿ¥ÌÙͿͯÒÈÍ¿°Ì11Í¿Çÿ¥Ìÿ¥ÌËÍÊÌݤУÐÍÊðƒÐ¢ÐÊРФÐ1047Íñ215Õ ÿ¥ÐÌÙÍ¿Í¡ÒÙ¯ÐÐÐааͤÐÛͤͤÍñËð§ÐÐÐÌ´ÐÛ̯ÒÒ´ð¤Ð¨ÐÊÐÐÎÐÍÒˆÌ₤ÌШÐÐÌÍÛ°Ò° ÍдÐÐÎ200ð¡ÍÐÒˆÍÛ¿ÐÐð¤ðƒÐÿ¥Ð
ͧÌÐÐÍÛÍð¡Ð₤Ð̯ÒÐÕÝÍÒˆÓÙÐÛÐпаÐШÐÐÍÒˆÌ₤ÌÐÛÍ ÇÍÐÐ ÐÐÐÌ ¯Ò˜ÌдÐÐÎ100ð¡ÍÐÒˆÐÐÐÐÐÛÐÓ¡Í ÇдÐÐÈÐÌÒÎÐÐÐÐÐШÌÐÐÐÐÐЈÐˋдÒÈÍÊÍÛÓçÕ´Ò ÐÐÌÌÐÐÐÎÐÐÿ¥Ð100ð¡ÍШХШÐÿ¥ÿ¥Ì°´ÿ¥ÿ¥ÐÐÐÛð¤ÌÀÐ₤ÐÓ¡Í ÇÐÐÍÊÐÐÛÒ° ÍÕÀÐÓý̓ÐÏÐÐð¤ðƒÐÏÐÐÐÐÈдÐÐ̓¿Í¤ÐÐÒ´ÇÒ´ÌÇ£ÍÐÐÐÐдÐ₤ÐÐÀÐÐÐÏÐÐÐð¡ÌÎÓçÍ₤ˋдЈÐÐÐÐÐÐÒ´ð¤ÐÍñÓÙÐÐÒ´Ò ÐÓÙÒ¨ÍӰͤÐÛÒ´¥ð¤¤ÐÐÛͯÍÐÓ¿¯ÐͤÐÐÐддЈÐÈÐð¤Ì ÓÙÐÍÌ ÐÐÎÐÐÐÐШÌÐÐЃÐÐ
ЈÐÐÐÐÛ̓ÐÒÈÍÊÍÛЈÐˋÐÐÒÌ
ÛÒÎÓÇ ÐÛÍÛÍÍÐÌÍÝÐÐÒ¨Ó´¢ÿ¥Ì°´ÿ¥ÿ¥ÐÓ¤ÒÀ´ÐÐÐ̓ÐÍ¿°Ì13Í¿ÇШÐ₤Í ÝÕÌˋÕÂЈÐˋÐÒ¨ÍдÐÐÍÒˆÌ₤ÌÒ´ÇҴШÐÐÐÎÐ500ð¡ÍÐÒÑ
ÐÐÕ¨ÕÀЈÌ
¯Ò˜ÌÐÒˆÐÐÒÈÍÊðƒÐÓƒÐÐÐÐШЈÐÐÍ¿°ÍÕÀÐ424ð¡ÍдЈÐÈÐÐÐÛÐÛÐÍ¿°Ì14Í¿Çð£ËÕÐÛÌ
¯Ò˜ÌÐÛÍ¿°ÍÕÀÐ₤ÐÐÐÐÐ150ð¡ÍÍ¥ÝÐÍ¿°Ì22Í¿Çð£ËÕÐ₤100ð¡ÍÍ¥ñдЈÐÐÍаð§ÕÀШÌÐÐÐÐ̓ÍШÐÐдÐÛÐдÐÏÐÿ¥Ì°´ÿ¥ÿ¥Ð
ÐÐÐ ÐШÐÍÒˆÌ₤ÌШÐÐÌÍÛ°Ò° ÍÐÛð¡Ò˜Ó̓ÍШдÐÐÐÐÐÒ´ÇÒ´ÐдШÐÍÍËЈÍ₤ƒÍ¢ÐÍñËÍʨÐÐÍ¢
ÒÎÐÐÐÐÐШÌÐÐЃÐÐ
ÐÐÈдÐÐÐÐÛÐÐÐˆÍ ÇÕÂÐÛÍÒˆÌ₤ÌÒ´ÇÒ´ÐÏÐ₤ÐÌÍÛ°ÕÀÐÛÍÊÍ₤ÀÐ₤ÍÕÀÐÏÐ₤ЈÐÐÛÐÕðƒÐÏÐÐ̘҈2014Í¿Çÿ¥ÌÍñÐÛÓ¿ÕÐÐÐÎЧÐÐÐÊÐЈÐÓçÍÑÐÛÐÐШÐÐÏÐÒ´ÍÐЃÐÐÐÐ̯ÒÒ´ð¤ÐÌýÒ¥ÐÐÐͧÌÐðƒÕ ¥Ò
Ð₤̯͡ÐÐÐãã̯ÒÐÐÎЧÐÌ¡ÐÐ₤ÐÐЈÐÐÐÎЧÐÏÐÐЈÐÒ´¥ÌÐÐÎТÐÐÐдÒˋ¯ÐÍ₤ÐÐÐÐÛÐÏÐÐÐ
ÍÛÕШÐÐÐÐЈÐÐÈÐÐдÐÒ´¥ÌÐÐÐдЈÐˋÐÐÓ¯ÀÍШÐÏÐÐÐ₤ÐÐЈÐÐÛÐÏÐÐÿ¥ÐÐÐÐ̈ÕÙÐÛÒ´¥ÌÐдÐÐЃÐÿ¥Ðð¡ÕÐÐÒͧÐÕçÍТШÐÐÎð¢ÀÐÒƒ¥Ð¢ÐÍÙÍ´ÐЈÐð¤ÍÛÐð¡ð¤¤ÌÙˋÐÐÍÏÐÐдÐÐÐÊÐÛЃШÐÐÐÐÓÍÛÐÏÐÐÐÐÛÐÐЈͯð§ÐÓ¤ӨÐÐÎÐЃÐÐÛÐÍÛÌ
ÐÏÐÐ
ðƒÕ ¥Ò
Ð₤Ðÿ¥Ðÿ¥ÐÛÍ¥ÒÙñÍȨШӡҨÐÐÐÌÙÐÐÐдÐÛÐдÐÏÐÒˋÐҧдÐÐÎÌËÌÐÐÐÐÐÐÌ°ÈÐÍ₤Í
ËÐÐÐÐÛЃЃ̃ӧÛÐÐÎÐÐЈÐÐÐÐÛÌ¢Ìý£ÓͧШÍÈÌ£
ÓЈÌÌÐð¡ÐÐЃЃдЈÐÈÐШÕÐÐÐЃÐÐÐ
ÍÒ´ÇÐÍÊðƒÕÒˆÌýÒ¥ð£ËÍШÕÒ£ÂÍÊÌݤÐͤÐÎÓ¥Ó§ÐÐÐдÐ
ÐÐЃÐÏÒˆÌ ÂÐШð¤ð£ÑÐÓÇ¿ð£ÐÐÎÐЃÐÐÐÐÌ Í§ÐÐð¤ð£ÑÐÐÐÊÐÍÒ´ÇЯÐÐдÐÐÐÐÐÏÐ₤ÐÐЃÐÐÐ
ÐÇШÐð¥ÍÀÍËÓÇð¡ÐÛÍçÍð¡ÍÝËÒÀШͤÐËÐÒÏÈÕÊÐÓÓÝдÐÐÕ Ò´ÕÐÛÒ¢ÕÒ¨ÌÝÐÌÝÐÒ´ÇÐÐÌÒçñÐÐдÐÐÐÓ˜˜ÿ¥Í₤ˋÐÏÍ
´ÕÂÍÒ´ÇдЈÐЃÐÐÿ¥ÌÙͿͯÒÈÍ¿°Ì10Í¿Çÿ¥Ì29ÌËÍÊÌݤУÐÍÊðƒÌÍ ÝÐ1668Íñ123Õ ÐÐÍÊðƒÐ¢ÐÊРФÐ1014Íñ217Õ ÿ¥ÐÐÇШÐÍ Çð§¢Ó´Ð¨ÐÊÐÐÎÐÓ¿ÍËÐýпÐÌ ÐÛÍ£ÌÙÂÍаð¤ÓÇÍÑͤÎÐÛͯÍ
ËÐЈÐÐÐÐдÐÓÓÝдÐÐð¥ÍÀÐÐÐÛÐÇШÐð¥ÍÀÍËÓÇÒÏÈÕÊШͤÐËÐð¢Ò´¥ÕÓÙÐÛÒ¢ÕÒ¨ÌÝÐÒˆÍÛ¿ÐÐÐð¤ðƒÐÐÐð¤ÓÇð¡ÒÎÐÛÐИХÐñпÐÐ ÍаӿÍËÐýпÐÌ ÐÛÍÑÕÐÍ
ÍۿдÐÐÎÐÐÐÇШÐð¥ÍÀÍËÓÇШÐÐÐÎÐÐÐÐÍÐÌÙÂÐÐÐдÐ₤ÐИХÐÛð£ÓçТÐ̘ͤÓШÍÊÌÇÐÐÐÐÛÐÏÍçÍð¡ÍÝËÒÀШͧÐÐдÐÐÐð¤ðƒÐÿ¥Ð
дÐÐÐÐð§Ð´ÐÐÐÛÓ˜˜ÿ¥Í₤ˋÍÊÌݤÐÍÌýÍÊðƒÕÒˆÐÏÓÇ¿ð£ÐÐÐÕ Ð¨Ð₤ÐÐÐÌÂШÐÓ˜˜ÿ¥Í₤ˋÐÏÕÒ£ÂÌÒ´ÇÐÛÍÊÌݤÐÒ´ÐÌ¡ÀÐÐÐÎÐÐÐÛÐÏÐÿ¥ÌÙÍ¿Õ¨ÒÈÍ¿°Ì11Í¿Çÿ¥Ìÿ¥ÌËÍÊÌݤУÐÍÊðƒÌÍ ÝÐ1693Íñ82Õ ÐÐÍÊðƒÐ¢ÐÊРФÐ1087Íñ203Õ ÿ¥ÐÐÇШÐÍ Çð§¢Ó´Ð¨ÐÊÐÐÎÐÓ¿ÍËÐýпÐÌ ÐÛÍ£ÌÙÂÍаð¤ÓÇÍÑͤÎÐÛͯÍ
ËÐ₤ÐÇШÐð¥ÍÀÍËÓÇШÐÐÐÎð¢Ò´¥ÐÐÐпÐ̘ҰˆÓð¡ÙÌ ¡ÓЈðƒÀÍÊÐÌÐÐÐÐÛдÐ₤ÐÐЈÐдÐÐÎÐÓ¿ÍËÐýпÐÌ ÐÛÍ£ÌÙÂÍаð¤ÓÇÍÑͤÎÐÛͯÍ
ËÐÐÐÐÐдÐÓÓÝдÐÐÎÐÇШÐð¥ÍÀÍËÓÇÐÛÒÏÈÕÊÐÐÐÐдÐ₤Ò´ÝÐÐЈÐдÐÐÐð¤ðƒÐÐÐÐÇШÐÍ ÇÓçÍÑð¥ÓʃÐÐÓ¿ÍËÐýпÐÌ ÐñпÐÐ ÐÍаÐð¤ÓÇЈÐÐÛÐИХÐñпÐÐ ÐÐÍ£ÌÙÂÐÐÎÐÐð¥ÍÀÐÐÇШÐð¥ÍÀÍËÓÇÐÒÏÈÕÊÐÐÎð¢Ò´¥ÕÐÛÒ¢ÕÐÒ¨ÌÝÐÐÐдÐ₤ÐÏÐЈÐдÐÐÐð¤ðƒÐÿ¥Ð
дÐÐÐÏÐÓ˜˜ÿ¥Í₤ˋÍÊÌݤШÐ₤ð£ÛÍñÒÀÍÛÈÒ´ÐÐÐÐÎÐÐÐÍ¿Çð¥Òý£Ì₤Òƒ¥Ð¢ÐÛÕ ÕÍÈͤÏШÐÊÐÐÎÍçÌ´ˋÍñÛÌ¥ÐÐÒˋÎТÐÐÐÛÐÛÐÐÐШÌÐÌ£ÐÐÎÐÐÐÐÐÓˋ¤Ì₤ÐÐÐЃÐЃÐÍÊÐÍ˰̢дÒÀÐÈÐÌ Ó£ÕÊ´ÐÏÐÌÐÐШÐÐÇШÐÍ ÇÕÍÑð¥ÓʃдÐÐÐ₤Ì
ÒÀÐÓçÐРдÐÛÐаÐИÐÐÐÒÎð£ÐÐÐÐÛÐÐШÕÍÑð¥ÓʃÐÓ˜˜ð¡ÍçÍÒ
дÐÐÎÍçÌ´ˋÍñÛÌ¥ÐÐÐÍÒ´250ð¡ÍУÐˋÐÛÍÓ¨ÐÎШÌÍÐÐÎÐÐÐÛÐÏÐÐ
ÐÐÛÐÐÐÓ˜˜ÿ¥Í₤ˋÐÏÐ₤ÐÕÒ£ÂÌÒ´ÇÍÊÌݤÐÐÐÐ ÐÐÐˋÐÐÐÐð£ÛÍñÒÀÐÛÍÓÑÍ̓ˋÍаÌÍÛ°Ò° ÍÐÛÓ°Ó¨ÐÎÐÒˆÐÐÐÐðƒÕ ¥Ò
дÍ
ÝШÐÕШͥñÍÑÍñÒÀÐÐЈÐÐÐШÌ
ÐÎÐçÐÐÐÐÐÛÐÏÐÐÐ
ЈÐÐÐÐÛÍÊÌݤÐÓ£Ò¥ÐÐÍÌýÍÊðƒÐ¢ÐÊРФÐÛÍýТÒÏÈÒˆ˜ÐÏÐ₤ÐÐ̘ÍÊÌݤÐ₤ÐÐÇШÐð¥ÍÀÍËÓÇШÐÐÐÎÐÓ¿ÍËÐýпÐÌ ÐñпÐÐ ÓÙÐÛÍ£ÌÙÂÐÍËÓÇÒÏÈÕÊÐЈÐ̓ÐӴͤÎÐÛÍçÍð¡ÍÝËÒÀШÒˋýͧÐÐдÐ₤ÒˆÐÐÐЈÐдÐÐÐÐÛÐÏÐÐÐÐÿ¥Ðÿ¥Í₤ˋÐÏÍÊÌÙÐÍÐÐÐð¤ðƒÐÏÐÐÐÛÐÏÐð£ÍƒÐÛÍÓ´Ûð¤ÌÀÐÛÍÎÓð¡ÍÒдЈÐÐÐÛдÐÐÎÓÇ¿ð£ÐÐÐдÐдÐÎÐÌñÀ̰ШҢ¯Ð¿ÐÐÐÎÐЃÐÐ
ÐÐÐÐÓÏÐ₤Ðð£ÐÏÐÐÓ˜˜ÿ¥Í₤ˋÐÛÒËÌÒÈÍÊÍÛÐ₤ÐÇШÐÐÒÑÈͰШÐÐÎÐÐÐÐÓ˜˜ÿ¥Í₤ˋÐÛÒÈÍÊÕñÐ₤ÐÇШÐШÐ₤Í
´ÐÕÂÍ¢ÐЈÐÐÈÐÐÛÐÏÐ₤ЈÐÐдՈ̴ÐÐÎÐÐЃÐÐ
дÐÐÐÐÓçÕ´ÍдÐÐÐÐÐÐÛÐ₤Ð̧ÒÝÀÓШ҈ÐÍ ÇÍÐ₤дÐÐÐÐÒÎÐÐÓ₤Íýÿ¥ÒÙÒÎÿ¥ÐÓçմШÐÐÈÐÎÐÐÛÍ
ñð§ÓÍ
ÍÛ¿Ð₤ÌÏÐ
ÐÏÐÐÐÐÐÛИÐÊÐÊÐ¥ÐÏÐ₤ÒÈÍÊÍÛÐÛ̯РÐÐÐÐд̰ÍÛÐÐÌ¿ÐÒ₤ÐÐÐÐÏÐÐ
ÿ¥ÐÌÝð¤˜Í¯ÒÈ̯ð¤ÒÎÓÒ´ÇÒ´Ó ÓˋÑð¥Óñ´Ð̯ð¤ð¤ÊÕÒ´ÇҴШÐÐÐÕÍÊÝÓ¡ÌÛ¤ÓШÐÐÐÕÍÊÝÓ¡ÌÛ¤ÓÐÛÒˆÍṲ̂ͤÿ¥Í
´Ò´ÿ¥Óÿ¥Ðÿ¥ÍËÍÍÊðƒÐ¢ÐÊРФ38Íñÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥£Í¿°Ì26Í¿ÇÐÍÊðƒÐ¢ÐÊРФÓʃÿ¥§
ÿ¥ÐͧÌÍÒШÐÐÌÓÛдÐÐÎÐÍÊÏÍñËÍ¥ñÐͧ¿ÍÀÐÛð¥ÌËÙÌÍÛ°ÍаաÍÊÝÍˋÓÓÛÍÛÿ¥ÐÍ¿°Ìÿ¥Í¿ÇͤÎШÐÐÐÌÝð¤˜Í¯Ì¿ÒÈÍÊÌ̯ð¤27Õ´ÐÛÒÈÍÊðƒÐÛÍÍÿ¥Ì°ð¤¤Í§¿ÍÀÐÛÕ¡ÍÊÝÍˋÓдð¥ÌËÙÌÍÛ°Ðÿ¥ÐÌË̘ð¤ÊÕÌ°ÍÙÎð¥Óñ´Ðð¤¤Ò¤¨Ò° ÍУÒÈÍÓ ÓˋÑÐÓ˜˜ÿ¥Íñ£Ðÿ¥£1995Í¿ÇÐÍÊðƒÐ¢ÐÊРФÓʃÿ¥§
ÿ¥ÐÌÝÕ ÙÌýÌý£ÕÐÌ ˆÍ¥ð¥Óʃ̰ÐÓ˜˜ÿ¥ÓÐ410Õ ÿ¥2008Í¿ÇÐÌÌÕÈÿ¥
ÿ¥ÐÌÕ¨ÒÈÌÙÍ58Í¿Ç10Ì28ÌËÓ˜˜ð¤Í¯Ì°Í£ñÍÊÌݤУÍÊÌ1095Íñ93Õ ÐÕ̯140Íñ249Õ
ÿ¥ÐÍÊÏÍ Ç̯ÕÐÍͯͤӣÌÇÓÐ¥ÐÐÛÓҨдÍÛÕÐ¥Ð210Õ ÿ¥Ì¯ÌË̘̰ÒÎÐ1995Í¿Çÿ¥ÐÍÐÓÑÍͯͤӣÌÇÓÐ¥ÐÐÛÓҨдÍÛÕÐ¥Ð29Õ ÿ¥Ì¯ÌË̘̰ÒÎÐ1997Í¿Çÿ¥ÐÍÐ̯ÓÓ¡ÎÌ´ˆÍͯͤӣÌÇÓÌ°ð¡Ð424Õ Ò´£ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥Ì¯ÌË̘̰ÒÎÐ1995Í¿Çÿ¥
ÿ¥ÐÍÌýÍËÍÍÊðƒÐ¢ÐÊРФ11Õ
ÿ¥ÐÍÓ¯ÓÇÐÍ҈дð¢ÀÓ´ÐÛÍÊÌÛçШÕÂÐÐð¡ÒÍ₤Ðÿ¥Ûÿ¥Âÿ¥˜627Íñÿ¥1997Í¿Ç10Ì15ÌËÍñÿ¥42Õ ð£Ëð¡ÿ¥
ÿ¥ÐÍÀˋÍÇÍÊÐÍÒˆÌ₤ÌШÐÐÌÍÛ°ÕÀÐÛÓÛÍÛШÐÊÐÐÎÐÍÊðƒÐ¢ÐÊРФ1055Íñÿ¥2001Í¿Çÿ¥Ì15ÌËÍñÿ¥ÿ¥Õ ÐÍ¡Ì°Ó ð¢ÛÌÐÌÍÛ°Ò° ÍÒ¨ÌÝÒ´ÇҴШÐÐÐÌÍÛ°ÕÀÐÛÓÛÍÛÐÿ¥Í¿°Ì13Í¿ÇͤÎÌÍÛ°Ò° ÍÍÛÍÓ ÓˋÑð¥ÓçÌÒÎÌ´ÐÍÊðƒÐ¢ÐÊРФ1070Íñÿ¥2001Í¿Ç11Ì15ÌËÍñÿ¥ÿ¥Õ
ÿ¥ÐÍÒÓÍ¥ÒÙñÍȨð¥Óñ´ÐÌ
¯Ò˜ÌÓÛÍÛÐÛÍÛÍÐÓ˜˜ÿ¥ÓÐ71Õ ð£Ëð¡ÿ¥£Í¿°Ì25Í¿ÇÐÐÐÐÐÐÿ¥§
ͧð¤ÍÌÐÛÍÛÓ¡ƒÐ£ÍÛðƒÿ¥£ÒÏÈÌݤð¤ðƒÿ¥§Ð₤ÐÐÀÐÐÐÐˋÐÐÐ
ÒÈÍÊÐÏÐÛÕð¤ÿ¥Ì£ÌÕý̓Àÿ¥ÐÐÑÐÐ₤ЈдÐÐÐÊÐÀХСдÐÐÒΰӿÐÐÐ₤ÿ¥
ÐÐ̈ÕÙÐÛÒ´¥ÌÐдÐ₤ÿ¥ÿ§ÒÈÍÊÐÛÍÌдÌÍÊЈÒÈÍÊÌÐÛШХШÐ
ÒÈÍÊÐÏÐÛð¡£Í¥çУӨҴ¥Ð´ÐÐÒΰӿÐÐÐ₤ÿ¥
Ð̯ð¤ÒÈÍÊÐÛð£ÓçТÐÌ´ˋÍˋÐÛÐÐÐÛÕð¤ÐШÍÐÊÌ¿Ì°Ð
ÐÒ´¥Ì ÐдÐÐÒΰӿÐÐÐ₤ÿ¥
ÐЈШÿ¥Ò´¥Ì ÐЈÐÐÈÐÎÿ¥ÿ¥ ЈÐÐЯÿ¥ð§ÐЯÐÐÐÐЈÐÐÿ¥ÿ¥Ð
ÍÛÕÐÛÒÈÍÊÍÛÐÛÍÊÌÙÐÐÙУпШÕÂÍ¢ÐÐÐÌ¿Ð₤ÿ¥
ÐÒÈÍÊÍÛÐÛÍ
Í
ËÌÐÍÒÎÐÓ˜ÌÙдÐÛÕÐÐ
ÒÈÍÊШÒý ÐÐТÐÊÐдÐÐÒÎÓ¿ÐÐÐ₤ÿ¥
ÐÒÈÍÊШÐÒý ÐÐÐÌ¿Ì°Ð
ÐÐð¡ÒˆÙÐÐ ÐÐÐ
ÒÈÍÊÐ̰̓ШÐ₤ШХШÐÐÐЃÐÐÛÐÏÐпÐÙХРÐÓçТӨÐÎÐÂÐÐÙÐ¥ÐÐÛÌ¿ÍÐÕˋÍШÒÎÌËçÐЈÐдÌÐÐ ÓçÌÐͯÐð¤ÐÐÏÐЈÐÐÛÐÏÐÐ
Í¥ÒÙñÍȨÐÛð£ð¤Ð¨ÐÊÐÐÎÐЃÐÍ¥ÒÙñÍȨШӡҨÐÐÐдÌÐÈÐÌÐÐˋÐÐÐÐ̰̓ÐͰ̿ШÐÊÐÐÐÐÐÛÐÐдÐÐ̯ÐËÐÐÐаÐШЈÐЯͿ¡ÐÐÏÐÐ