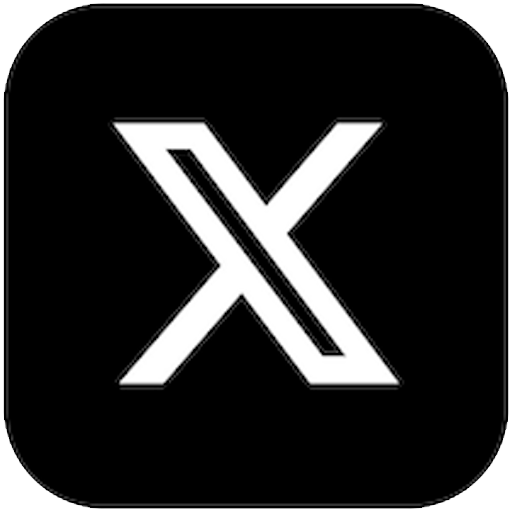̰̓ÍÕÀШÐ₤ÐÐÐÐÌÌ°Ðð§ÐÒ´ÐÈÐÎÐÐÐÛÐÐÐÐÐÐÐÐÓÇ̓ÐÏÐЈÐÐУУУУУУÐÍð¡¡Íð¤ð£ÑÐ
̰̓ÍÕÀШÐ₤ÐÐÐÐÌÌ°Ð ÐÍÊÕÍ¡ÙШÐÐÍ ÇÍÐ₤ÐÐÀÐÐÐͧð¤Ò ÐÐÐÛÐÐЈÌÒÎÐÌÐÊÐдÐͯЈÐЈÐÐ
ͧÌͯÿ¥ÐÛÍð¡¡ÓÏ̓°ÍÐÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥Í¿ÇШÍÊÝÒ¡ˆÐÐð¤ð£ÑÐÏÐÌÛ¤ð¤¤Ó§ˆÐ¨ÍÐÐÐxxÒ¨Íð¤¤Ð¨Í₤ƒÐÐÌÏÒ´ÇÍ₤ˋÐÛÍÍ ˜ÍÊÐÐÿ¥ÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËШÌÙÍ¿Õ¨ÒÈÐ
xxÒ¨Íð¤¤ÐÛð£ËÍð§ÐÐÏÐÐÒƒýÍÛÑÐÛÓÇÍÝÐÐÓ¤ÒÎÐÐÐÕˆ´ÓÐÐÿ¥Êÿ¥Ûÿ¥ÀÕÍÛÐÏÍð¡¡ÍÐÛÐÐÛÐÏÐÐÐдÐÌÐÐШЈÐÈÐдÐÐÎÐxxÒ¨Íð¤¤Ð₤ÐÌÛ¤ð¤¤Ó§ˆÐÛÌÍ¿ÍÛÌÿ¥ÐÌÍШÕÛÌÐÐÐÐÌÛ¤ð¤¤Ó§ˆÐÏÌÙͿͯÒÈШÒçñÒ´ÇÐÐÐÐÐÒ¨Íð¤¤Ðð¡Òý¨ÐÐÎÕ£ÓÏÐÓÑÐÐÎÐÐдÐÐÐÐÐЈÐÌËçÐÐÎÓ¯ðƒÐˆð¤ð£ÑÐ ÐЈÐÐxxÒ¨Íð¤¤Ð₤Ðð£ËÍШÐð££ÌÐÏÍÐÒˆ¢Ð¿ÐÐÐÎÐÐÐÐͧÌÐ₤ÐÌÒÀ̯Ç̤ÐÛÐÐÐÏÕˆ´ÓÐÛÒ¤¨Í ÐÍð¡¡ÍдÐ₤ÌÙÍÛÐÏÐЈÐÐÈÐдÐÐÐÎÐÐÐ
ÌÙͿͯÒÈÐ₤Ðÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÐÓÀÓ§ˆÐÛÍÊÌݤÐÒ´ÐÌ¡ÀÐÐÐÐÐͧÌÐÐð§ÐÒ´ÐÈÐÎÐÐÐÛÐÐÐÐÐÐÐÐÓÇ̓ÐÏÐЈÐÐдÐÐÍȯÐÐͯЈÐÐÐÒÐÐÐÐÐÛÐ ÐÈÐÐ
ÓÀÓ§ˆÍÊÌݤÐÛÒ´Ì¡ÀÐÐÐÐÌÙͿͯÒÈÐÓʤÐÐÎÐÐÓÓÝÐ₤ÐÐÐ Ð
ÐÒ¨Íð¤¤Ðð§ÐÐÐÛÒÀӤШÐÐÍð¡¡ÍÐÌÙ£ð¤ÀÐÐÐÐÐÛ̓ÐÕñÌÕШÐÐÐÍð¡¡ÍÐÛÕ¤ð§Ðð¢ÓÛÀÐÐÐÐÓ¥ÌÐÐÕ¤Õˆ´ÐÕ Í¢ÐÐÎÐÐÐдÐÒ¨Íð¤¤Ðð££ÌÐÛÍÐÒˆ¢Ð¿ÌШ̘ð£ÑдÐÛÐÐÐÐÐУÐÛÐÐÐÒ´ÍÐÓʤÐÐÎÐÐÐдЈÐˋÐÐÐÒ¨Íð¤¤ÐÕÍÊÏЈÓ₤Ó§ˆÐ¨ÐÐÐÍð¡¡ÍÐÌÙ£ð¤ÀÐÐÐÓÐÐÍ¥ñÐдÐÐÐдÐÐÏÐÐÐÐÒ¨Íð¤¤ÐÌÛ¤ÌÐÐÐÈÐÎÍð¡¡ÍÐÌÙ£ð¤ÀÐÐÐд҈ÍÛÐÐШÐ₤ÐЈÐÍÓÓЈÓÐÐÌÛÐдÐÐпÐÐÏÐÐÐ
̘Ӵ¢Ð₤ÐxxÒ¨Íð¤¤ÐÓÀÓ§ˆÐÏÐÐÐÛÐÐÐÐдÐÌÓ§ˆÐÏÐÐÐÛÐÐдÐÐÐдÐÌÊÒ´¥ÐÐÓÏЈÐÐÛÌÒÎÐÒ´ÐÐдÐÐÐÐÛÐÏÐЈÐÐ
ð§Ì ÐÐÓÓÝÐ₤Ó¯ÀÍãÎãÎÐ
ÓÏÐ₤ÐÒ¨Íð¤¤ÐÍð¡¡ÍÐÌÛ¤ÐÓƒÍ ÇÐÒÎÐÎÐЈÐÐÐÐÏÐÐÐÐÐÐЈÐÛͧÐÐÍÿ¥ÐÐЃÐÏÒˆÙÐÐÏÌÐÐÐÐдÌÐÐÐÒˆÙÒ ÐÐÐÐÈÐÐÐÐÐÐÐЈÐÐ
ÐÐÐÐÍÕÀÐÛÓ¤ÓÍ Ð₤ÐÐШÐÐÐÍð¤ÒÈÍÊÐ₤ÐÐÓƒÍ ÇÐÒÎÐÎÐЈÐÐÒÈÍÊÍÛдͥЯÐÐð¤¤Ð ÐÐÒÈÍÊÌдÐÐÍÍÐÏÐÌÊÍ₤ÍÛÐÌÓʤÐÐÓ₤Ó§ˆð¤ÍÛÐÐÐÈÐÐÐˋÐÐÐÐͧÍÛÑÐÛÌݤÍÛдÐÐÎÍÊÌÙÐÐÍÓ§¯ÐÓÏÐÐÐˋÐÐÐÐˋÐÛÐÐЈÍÓ§¯ÐÓÏÐÐÐÓ¤ÍÛÐÐÌÓÑÐ ÿ¥ÐÐÐÐÓƒÍ ÇÐÒÎÐÎÐЈÐÐÐÒÈÍÊÍÛдÐÐÎÒÈÍÊÐÏÐÐÐ̘Ӵ¢ÐÏÐ₤ÐÐð£Ëð¡ÒÏÎÐЈÐÐÐÕаð¤¤ÐÛÕÐÐдÐÐÎÓƒÍ ÇÐÒÎÐãÕ ÍÝÝÐÛÕÐÐãÐ₤ÐÍð¤Ò´ÇÒ´Ì°ÐÏÐ₤ÐÒÈÍÊÍÛдÐÐÎÒÈÍÊÐÐÏÐЈÐÐдШЈÐÈÐÎÐÐÿ¥Ð
ÌË̘ÐÏÐ₤ÍÊð£ÈШÐãÓÓËÌÂÌ¿₤ãÿ¥ÐÐÐÐÀÿ¥Ð´ÐÐÈÐÎÐÐÌ¿₤ШÌÐÍ ËÐÐÎð¡ÙÐÛͯӰЈÐˋÐÍÐͤÐÐÐÓ¨Íñÿ¥ÐÐÐˋÿ¥ÐÛÌÓÀÐӴͤÎÐÏÌÓ§ˆÐÓÀÓ§ˆÐÌݤÐÐÌ¿Ì°ÐдÐÈÐÎÐÐÐдÐÐÐÐÐÐÐÐÌÌͧÐÏÐ₤ÐÒ´¥Ì ШÐÐÒ´¥ÌÐÍ¢ ÒÎШЈÐÈÐÎÐÐÐ
Ò´¥Ì ШÐÐÒ´¥ÌÐÍ¢ ÒÎдЈÐÐÛÐ₤ÐãÓÓËÌÂÌ¿₤ãÐÕÓÏÍÙÎÓРдÐÐÐ ÐÐÏÐ₤ЈÐÐÌÌͧÐÏÐ₤Ð̘ͤÓð¤¤Ì´ˋÐÍÛÐЈÐÐЯЈÐЈÐÐÐд҈˜ÌÐÐÐÐ
ÐÐÐÏÐÐÓÐÐÐÐ₤Ò¨Íð¤¤ÐÛÍˋÓШÐдÐÐÍð¤ÒÈÍÊÐÛÍÍÐÌÓ¨ÐÐÐÐÐÐÐÎÐÐÐÛÍÍШÐÐÈÐÎÐÒ´¥Ì ШÐÐÈÐÎÓ₤Ó§ˆÐÒ´¥ÌÐÐͧ¿ÍýÐÌ ÐÐÛÐ₤ÐͧÍÛÑÌ´ˋÍÐÌ ÐÌÊÍ₤ÍÛÐÛͧ¿ÍýдÐÐÐÎÐÐÐÒ¨Íð¤¤Ð₤ÓÀÓ§ˆÐÒ´¥ÌÐÐÍ¢ ÒÎÐ₤ЈÐÐÐÊЃÐÿ¥ÌÍˋЈҴ¥Ì ÐÌͤÐÐÓƒˋÍÐ₤ЈÐÐxxÒ¨Íð¤¤ÐÛÐÐШð§ÐÒˆÐÐÿ¥ð§ÐÍÒ¨ÐЈÐдÐÐÐдÐÐÐÓÐÐÐÐ₤Ò¨Íð¤¤ÐÛÍˋÓШÐдÐÐÍð¤ÒÈÍÊÐÛÍÍÐÛÐдÐÏÐ₤ÐЃÐШÌÙÈͧЈÒÀӤдÐÐÐдШЈÐÐ
ÐÐÐÒçñÒ´ÇÐÐÐÓ₤Ó§ˆÐÐÌÓ§ˆÐˆÐÛÐÐÓÀÓ§ˆÐˆÐÛÐÐÐˋÐÈÐÀдÐÐÐЈÐдÐÐÍ ÇÍШÐ₤ÐÓÀÓ§ˆÐ¨ÐˆÐÐÓÀÓ§ˆÐ¨ÐˆÐÐÛÐ₤ÿ¥ÐˋÐÒÐÐÎÐãÓÐÈÓ§ãРдÐÐÍ ÇÍÐ ÐÐÏÐ₤ЈÐÐÐÌÊÍ₤ÍÛÐИаÐÐÐÓçÌÏÐÐдÐЃÐÏÒÀÐÈÐÐÐ ÐÐˋÐÙÐÐдÐÐãÓ¯ÒýãÐÛÍ ÇÍÐͨЃÐÐÐ
Í¥ÒÙñð¤¤Ð´ÐÐÎÌÇ£ÍÐÍ ÇÍÐãÓÐÈÓ§ãÐÏÐÐÐдЃÐÏÕ Í¥çÐЈÐдÐÐãÓ¯ÒýãШЃÐÏÌÐÈÐÎÐÐЯÐÓÀÓ§ˆÐ´ÐˆÐÐÐÐ ÐÓÀÓ§ˆÐÏÐÐð£Ëð¡ÐÍð¤ÒÈÍÊÌÓÑШÐÐÐÎÐãÓÐÈÓ§ãÐÏÐÐÐдÐãÓ¯ÒýãÐÏÐÐÐдÐÒ¨Íð¤¤ÐÛÓ¨Í ÇШÕÐÐ₤ЈÐÐ
Íð¡¡Íð¤ð£ÑÐÛÍ ÇÍÐÌÊÍ₤ÍÛÐ₤ÐxxÒ¨Íð¤¤ÐÌÛ¤ð¤¤Ó§ˆÐÏÒçñÒ´ÇÐÐÐÛÐ ÐÐÐÌÛ¤ð¤¤Ó§ˆÐÓ₤ÐÐдÐÐÐÐÐÛÍ¢ ÒÎЈÒÎð£ÑÐÐпÐÎÒ´¥ÌÐЈÐÐЯЈÐЈÐÐÌÛ¤ð¤¤Ó§ˆÐ´ÐÐÐÐШÐ₤Ðð¤¤ÐÌ٣ШҰÐÐÐÒÀÓ¤ÐÌÙ£ÐÛÓçÌÐÛУÐÐÐÌÛ¤ÌÐÐÐÊЃÐÒˆÍÐÛÒÀÍШÐÐÈÐÎð£ð¤¤Ð¨ÌÙ£ÐÛÓçÌÐÒçñÐÐд҈ÒÙÐÐÎÐÐÐдÐÍ¢ ÒÎдÐÐÐÐ
ð¤¤ÐÌÙ£ÐÌÐÒÀÓ¤ÐÒˆÐÐÐÐÐÐÛÒÀӤШÐÐÈÐÎÌÙ£ÐÛÓçÌÐÒçñÐÐÎÐÐÐдÐÒˆÍÛÐÐÐÎÐÐÐÌÛ¤ÌÐÐÒˆÍÛÐÐЈÐÐЯÐÌÛ¤ð¤¤Ó§ˆÐ´ÐÐÐдÐ₤ÐÏÐЈÐÐÌÇÍÐÌ₤ÐÐÈÐÎÌ٣ЈÐÐÎÐЃÐÈÐÍ ÇÍÐÏÐÐÐÍñÍÛ°ÒÇÌÙ£Ó§ˆÐ´ÐˆÐÐÐÐÎÐШЈÐÐÎÐÐÎð¤¤ÐÌ٣ШҰÐÐÐÎÐЃÐÈÐÍ ÇÍÐ₤ÐÕÍÊÝÒÇÌÙ£Ó§ˆÐÐÎÐШЈÐÛӴͤÎÐÕ¨ÐÐЯÐÕÕÍÊÝÒÇÌÙ£Ó§ˆÐÏÐÐÐЃÐÐðƒÐЯÐð¤ÊÕð¤Ì ÐÏð¤¤ÐÌ٣ЈÐÐÎÐЃÐÈÐÐÐÌËÙÍð¡ÕÍÊÝÒÇÌÙ£Ó§ˆÐ´ÐÐÐÐ
ÐÐÐÐÐÐÐÐÛÍ ÇÍÐÐÐÌÛ¤ÌÐÐÒˆÐÐÐЈÐð£Ëð¡ÐÍð¤ÒÈÍÊШÐÐÐÎÌÛ¤ð¤¤Ó§ˆÐ´Ð₤ÐÐЈÐÐ
ÌÛ¤ð¤¤Ó§ˆÐ´ÐÐÐдÐ₤ÐÏÐÐЈÐдÐÐÕÍÊÝÒÇÌÙ£Ó§ˆÐÍñÍÛ°ÒÇÌÙ£Ó§ˆÓÙÐ ÐÍËÐÛÓ₤Ó§ˆÐ´ÐÐÎÍÓ§¯ÐÓÏÐÐÐÍ ÇÍÐÐÐÐ
ÐÐÐÐÍð¡¡Íð¤ð£ÑÐÛÍ ÇÍÐÌÊÍ₤ÍÛÐ₤ÐÌÛ¤ð¤¤Ó§ˆÐ´ÐÐÎÒçñÒ´ÇÐЈÐÐЯÐÐÐÐÐÒ£§ÐÕÍÊÝÒÇÌÙ£Ó§ˆÐ´ÐÐÍñÍÛ°ÒÇÌÙ£Ó§ˆÓÙÐ ÐÏÒçñÒ´ÇÐÐÐдÐ₤ÐÏÐЈÐÐÈÐÐÐÐÐÐÛÓ₤Ó§ˆÐÏÒçñÒ´ÇÐÐÎÐÐÐÐÐÐÌÍ¿ÐÍÛÌÐÐÎÐÐÐдШЈÐÐÍÓ§¯ÐÓÏÐÐÐдÐ₤ÐÏÐЈÐÐÐÐ ÿ¥ÐÐÛÍ ÇÍÐ₤ÐÐÍ Ò´ÇÐдÐÐÍÊÌݤÐÒ´ÐÌ¡ÀÐÐÐÿ¥Ð
ÌÙͿͯÒÈÐ₤ÐÐÌÛ¤ÌÐÐÌÊÍ₤ÍÛÐÒ´¥Ì ÐÏÒ´¥ÌÐÐÎÐЈÐдÍÊÌÙÐÐÐÐÐÐÎÐÌÊÍ₤ÍÛÐxxÒ¨Íð¤¤ÐÌÛ¤ð¤¤Ó§ˆÐ´ÐÐÎÒçñÒ´ÇÐÐÎÐÐШÐÐÐÐÐÐÐÐÐÛÒÎð£ÑÐÿ¥ÐÊÒÑ°ÐЈÐÐÐÓÀÓ§ˆÐ´ÐÐÐÍð¤ÒÈÍÊÐÓÍÝÐÏÒÎÐÕÐÐÍð¡¡Íð¤ð£ÑÐÛÍ ÇÍÐÐÐÐ ÐÐÐ ÐÐÛÐдÐÏÐÐÐ
дÐÐÐÏÐͯÒÈÍÊÌݤШÐÊÐÐÎÐÍ¥ÒÙñÍÇÐ₤ÐÐÓÐÐÐÐ₤Ò¨Íð¤¤ÐÛÍˋÓШÐдÐÐÍð¤ÒÈÍÊÐÛÕÍШ͢ ÍÛЈÍÊÌÙÐÏÐÐдÒˋðƒÀÐÐð¡Ì¿Ðð¤ÍÛÒˆÍÛШÐÊÐÐÎÓÍÐÌÛÐдÐÐÎÐÐÐÐÕÍÊÏЈÓ₤Ó§ˆÐдЈÐÒ´ÍÐÐÐÛÐÐЃÐÐÏÌÓ§ˆÍÊÌݤÐÛÐÐÐ ÐдÒˋÐÐÒÙÒ ÐÐÐÐ
дÐÐÐÛÐ₤ÐãÓÐÈÓ§ãÐÏÐÐÈÐÎÐãÓ¯ÒýãÐÏÐÐÈÐÎÐÐãÕ£ãÐÏÐ₤ЈÐдÍÊÌÙÐÐÐÐÛÐ ÐÐÐÍð¤ð¤ð£ÑÐÛÓçҨдÐÐÎÐÓÀÓ§ˆÐ´ÐÐÎÍÐÌÝÐÐÍÐÐÐÐ ÐÐÐÌÂÐÐÎÐÐÌÛ¤ÌÐð£ËÍÊÐÛÒÎð£ÑÐÒˆÍÛÐÏÐÐÐдÐÐÌÙÍÛÐÐÍ¢ ÒÎÐ₤ЈÐÐдÒÐÐÐÐÐÏÐÐÐ
ãÓ¯ÒýãдÍÊÌÙÐÐÐÛÐ₤Ðð§Ò´ÐˆÐð¡ÒˋÝÐÏÐÐЯÐÐÐÐÒÈÍÊÌÐ₤Ðð¤¤ÌÏÿ¥ÐýдÐЃÿ¥ÐÛð¤¤ÓШÕÂÐÐÐдÐͧÍÛÑÌ´ˋÍÐӃШӘ҈ШÌݤÍÛÐÐÒ´°ÐÏÐÐÐÛÐÐШð¡ÐÐÐÐÎÐÐÐÛÐ₤ÐãÕ£ãÐãÕ£ÐÏЈÐÐãÐÌݤÐÐÌ´ˋÕÐ ÐÐÏÐÐÐÐÐð£Ëð¡Ð¨ÐãÓ§ãÐãÓ§ÐÏЈÐÐãÐÍÊÌÙÐÐð¤¤ÌÏÐÛð¤¤ÓÐÍñÎÍ°ÐÐÍÊÌÙÐÐÐÌ´ˋÕЃÐÏÐ₤ð¡ÐÐÐÐÎÐЈÐÐдÐÐÐдШЈÐÐÐ
ÐÊЃÐÐÒÈÍÊÍÛÐÛÍЈÐãÒ¢¯ÌÐÐÐÌÌ°ãШÐÐÈÐÎÐÍ ÇÍШÐÐÈÐÎÐ₤ÍÓ§¯ÐÓÏÐÐÐÐÛШͿÌçÐÐÐÐЈð¡ÍˋÓÐÒý ÐÐдÐÐÐÐÐдÐÐÒÐÌ¿ÐͤÓÊдÐÐÐÐÛÐÏÐÐÐÐ
ÐÏÐ₤ÐÒÈÍÊÍÛÐ₤ÐÌÊÍ₤ÍÇÐÐˋÐЃÐÏÒ´¥ÌÐÐдÐãÕ£ãÐÏÐÐдÍÊÌÙÐÐÎÐÐÐÛÐÐÏÐÐÐÐÐÍÓÓЈÓÐÐÒÑ ÐÐÐӴͤÎÐÛÒ´¥ÌÐÍ¢ ÒÎÐÏÐÐÐдÐÐÐÎÐÐÐÐÐÐÎÐÌÕ¨ÒÈÍÊÌÐ₤ÐÐÕÍ¡¡ð¤¤ÐˆÐÒˆ¯ÐÏÐÓÐÐÐ₤ÐЃЈÐӴͤÎÐÛÓÍÛÐÐÐдÐÛÓ¤ð¢ÀÐдÒÀ´ÓƒÐÐÎÐÐÐ
ÌÊÍ₤ÍÇÐ₤ÐÌÙͿͯÒÈÐÐ£Ð¥Í ´ÕÂÓШÌÊÍ₤ÍÇÐÛð¡£Í¥çÐÒˆÐÐð¤ÍÛÒˆÍÛÐÐЈÐÐÐÒ´¥Ì ÐÐÐÈÐÐÛШÌÛ¤ÌÐÒˆÍÛÐЈÐÐÈÐÐдÐ₤Ì¢ÌÐÏÐЈÐÐд̿ÍÊÐÐÎÐÐÐÒÎÐÐШÐÌÊÍ₤ÍÇÐ₤ÐÐÌÛ¤ÌÐШÐÊÐÐÎÐÐãÕ£ãÐÏÐÐдÐÐÐÒ´¥ÌÐÐÏÐÐÎÐÐÐдҴÐÐÛÐ ÐÐÐÐÐÈÐÎÐͧÓÑÐÌÏÒ´ÇÐÐÐÌÏÒ´ÇÍ₤ˋÐÏÐ₤ÐÐÐÛӿШÐÊÐÐÎÌ£ÕýÐЈÐÐÐÐдШЈÐÐ
дÐÐÐÏÐÌÙͿͯÒÈÐ₤Ð̘ð£ÑÐÏÐ₤ÐÌÙ£Í ÐÓ¿ÍÛÐÏÐЈÐÐдÐÓ₤ÒÀÌ ÌÏÐÍÛÂÒΰÓШÓ¤ÍÛÐÏÐЈÐÐдЈÐˋÐÐÐÐÒ¨Íð¤¤Ð¨ÌÛ¤ÌÐÐÐÈÐдÐÐÐÐШÐ₤ÐÒ¨Íð¤¤ÐÍð¡¡ÍÐͥаͤÐÐÓÛÓÐÍð¡¡ÍÌÛ¤Í۰ШÓçаÐÊÐÒÓÑÿ¥ÐÐÐÐÿ¥ÌÏÐÕ¨ÐÐдÐÐÒ¨Íð¤¤Ð¨Íð¡¡ÍÌÛ¤ÍÛ°ÐÛÌÓ¤ЈÍÌˋÐÒˆÐÐÐÐÐдÐÍ¢ ÒÎдÐÐпÐÐÏÐÐÐдÐÐÒ´¥Ì ШÐÐÈÐÎÐÐÐÐÐÒˆÐÐÐдÐ₤ÐÏÐЈÐдÐÐÐ
ÐÐÐÐÛÍÊÌÙÐ₤ÐÌÙ£Í ÐÓ¿ÍÛÐÏÐÐÐÓ₤ÒÀÌ ÌÏÐÓ¤ÍÛÐÏÐЈÐÍ ÇÍÐÏÐÐÈÐÎÐÐÒ¨Íð¤¤ÐÍð¡¡ÍÐͥаͤÐÐÓÛÓÐÍÌˋÐÛÒ´¥ÌÍÎð§Ð¨ÐÐÈÐÎÐ₤ÐÐÌÛ¤ÌÐÐÒˆÐÐÐдÐÐÏÐÐÍ ÇÍÐÐÐдҴÐÈÐÎÐÐÐдШЈÐÐ
Íð¡¡Íð¤ð£ÑÐ ÐÐÏÐ₤ЈÐÐÓÇÌËÓЈÍÛÂÒΰÓÒ´¥Ì ÐÛð¿ÐÐÐð£ÐÛ̯РÐÛÍð¤ð¤ð£ÑÐÍ¢çÕ ÙШÐÐдÐͯÒÈÍÊÌݤÐÐÐÌÛ¤ÌÐÐÒˆÍÛÐÐð¡ÐÏÐÛÐÐ¥ÐШÐð¡ÐÐÎÐÐдÐÐÌÌÐÐÐÐÛÐ₤ÐÐÐÛÐÐÐ Ð