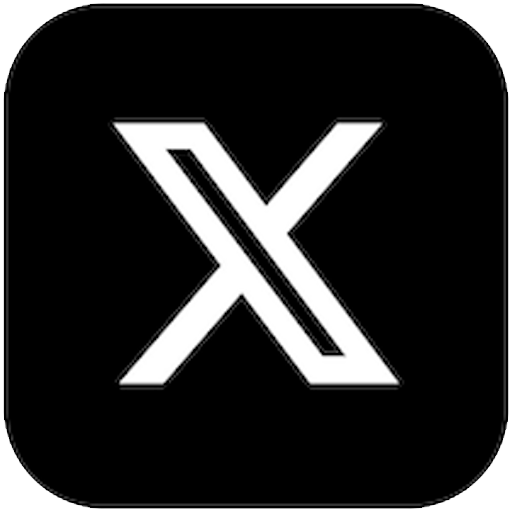Ó¿ÍËÕÊÒÙñÒð¤¤ÐХРÐÛÍ ËÌÒ Ð¨Í₤ƒÐÐÎÒ̓ ÒÀÓ¤ÐÒÀÐÐÐÎÐÐÌ´ÐÛ̯ÒÒ´ð¤ÐÍ̧ҴÙÐÛÒñÍÀÐÐÐÛÌ Í ÝÌðƒÓÙÐÓ¨₤ÓñдÐÐÎÌýÒ¥ÐÐÐÐдШÐÊÐÿ¥Í̧ҴÙÐÒ´ÙÓ§ÛÓçÍÑÐÐÌ°ð¤¤Ðÿ¥ÒÊ̯ÐÛÓÛÌðƒÒ¢¯ÓÙÐÍÙÍ´ÐÐÎÐÐШÐÐÐÐÐÐÿ¥Ò̓ ÒÀÓ¤Ð₤ЈÐð¡Ò´ÐÛÌ Í ÝÐ₤ÒͧÐÏÐÐдÐÐÎÍÒñÍÀШÍ₤ƒÐÐÎÐÐÌÍÛ°Ò° ÍÒ¨ÌÝÒ´ÇÒ´ÐÛÌÒçñÐÿ¥Õ̰ЈÒÀӤдÐ₤ÐÐЈÐдÐÐÐð¤ðƒÐÛð¡ÍÍÓÓ°Ó¨ÓÓÝÌ¡ÐÏÐÐ
Ðð¡ÍÍÓÓ°Ó¨ÓÓÝÐÐÛÐÐÀÿ¥
ÌÕ¨ÒÈШÕÒÎдÐÐÐÕ´ÍÐÛÌÓýÐ₤ÐÐÀÐ
ÐÓ¿ÕÊÐХРÍ
Õ´ÍÓ¤Ò´ÇÒ´ÐÕ¨ÒÈÍÊÌݤÐÓ ÇÌÈÐ
Í
Õ´ÍÓ¤Ò
ШÍ₤ƒÐÐÒ´ÇÐÌÒçñÐÛÌÙÈͧÌÏ
ÍÊÌݤÌÐ₤ÐÐÀÐÿ¥Í§ð¤ÍÌÍÌÝÌÀð£Ñÿ¥ÌÕ¨ÒÈÍÊÌÐÏÍÒ´Çÿ¥
ÌýÒ¥ÐÐÐÍÊðƒÕÒˆÐ₤ÐÐÀÐ
ÒÏÈÒˆ˜ÿ¥ÐÓ¿ÕÊÐХРÍ
Õ´ÍÓ¤Ò´ÇÒ´ÐÕ¨ÒÈÍÊÌݤÐÓ ÇÌÈÐ
Í
Õ´ÍÓ¤Ò
ШÍ₤ƒÐÐÒ´ÇÐÌÒçñÐÛÌÙÈͧÌÏÐ
Ð₤ÐÐÀÐ
ÐÌÕ¨ÒÈШÍˋÐÐÌÝÐÐÐÐ₤ÐÐÀÐ
ð¡ÍÍÓÓ°Ó¨ÐÎÓÓÝÌ¡
Í¿°Ìÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌË
ÌÐÕ¨ÐÒÈÐÍÊÐÌÐ̓Àð¡Ù
ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô Ó°Ó¨ð£ÈÓð¤¤Í¥ÒÙñÍȨÐÐÍ ÐÐÓ¯ ÐÐͯ ÐÐð¡
Ó°ÐÓ¨Ðð¤¤ÐÐÐÿ¥¡
Ó¡ÐÌÐÌ¿ÐÐÿ¥¿1ÍÊÿ¥Í
Ðð¡Ò´Í§ð¤Ò ÕÐÛÌÙÍ¿Õ¨ÓÙÒÈÍÊÌÍ¿°Ìÿ¥ÿ¥Í¿Ç(ÐÍ)Ó˜˜ÿ¥ÍñÌÍÛ°Ò° ÍÒ¨ÌÝð¡ÍÍÓÓ°Ó¨ð¤ð£ÑШÐÊÐÐÎÿ¥Ó°Ó¨ð¤¤Ð₤ÿ¥Ì˜ÀÐÛдÐÐÿ¥ð¡ÍÍÓÓ°Ó¨ÐÎÐÛÓÓÝÐÌͤÐÐÐЈÐÿ¥ÓËÒˆÓÙÐ₤ÿ¥Ì˜ÓÓÝÌ¡ÐÏ̯ÐШӴÐÐÐÐÛÐÛУÐÿ¥ÍÍÊÌݤÿ¥ÍаӘ˜ð¡Í₤ˋÍÊÌݤÿ¥ÐÛðƒÐ¨ÐÐÐ
ÓÐÓÝÐÒÎÐÌ´
ÿ¥Ð̘ҴÇÒ¨ÌÝШÐÊÐÐÎ
ÌÇÒÀÒÀÓ¤ÐÛÍÙÍ´Ðð¡£Í¥çÐÐÎð¡Ì°ÒÀӤШͤÐËÐÌÍÛ°Ò° ÍÐÌÝÐÐð¤ÌÀШÐÐÐÎÿ¥ÌÇÒÀÒÀÓ¤ÐÓÛÌÐÐдÐÛðƒÒ¢¯ÐÐÐÐÐÛÐÛÿ¥ÒÀÓ¤Ò
дÐÐÐÒ
Ð₤ÌÇÒÀÒÀÓ¤ÐÒÀÐÈÐÐдÐÌÓ¤ШÍÎÍÛÐÐÎÐÐдÐÐÿ¥ÓÛÌÒ´¥Ò´ÐÒÈð£ÐÐÍÛÂÒΰÓЈҴ¥Ì ÐÍÙÍ´ÐÐÿ¥Ó¡ÓÓƒÐÐÒ´¥Ì ÐÛЈÐÐÐÐÐÐÐÌÀÓ´Ðÿ¥ÐÐÐÐÌ´ÒÝÀÐÐÐдÐÐÍÊÌÙШÐÐÐÎÿ¥Ó¿Ð¨Ì
ÕЈÍÍ°ÐÐЈÐÐЯЈÐЈÐÐÛШÿ¥ÓÛÌðƒÒ¢¯ÐÛð¢ÀÓ´ÌÏÐÛÓ¤ÍÛÌÏÐÒˆÐÐÐдÐÐÏÐЈÐШÐÐÐÐÐÐÿ¥ÐÐÛð¢ÀÓ´ÌÏÐÒˆÐÿ¥Í§ÒˋýðƒÒ¢¯Ð ÐÐÏÌÇÒÀÒÀÓ¤ÐÛÍÙÍ´ÐÒˆÐÐУÐÿ¥Ì§ÒÝÀÓÍ
ÍÛ¿ÐÏð¥ÒðƒÒ¢¯Ð¨ÕÍÊÏЈðƒÀÍÊÐÒˆÐÐЈÐˋÐÐÎÿ¥Í§ÒˋýðƒÒ¢¯Ð ÐÐÏÌÇÒÀÒÀÓ¤ÐÛÍÙÍ´ÐÒˆÐÿ¥ÍÐ₤ÒÈÍ¥ñÐÐÐÐÐÛÒ´¥Ì дÐÐÎÌÀÓ´ÐÐÎÍÊÌÙÐÐÍÍÊÌݤШÐ₤ÿ¥ÌÕ¨ÒÈÍÊÌÍÊðƒÿ¥ÌÕ¨ÒÈÍÊÌÓ˜˜ð¤Í¯Ì°Í£ñÌÙÍÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥ÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËУ̯Õÿ¥ÿ¥Íñ£ÿ¥Íñÿ¥ÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÍÓ˜˜ð¡Í¯Ì°Í£ñÍ¿°Ìÿ¥Í¿Çÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌË̯Õÿ¥ÿ¥Íñ£ÿ¥Íñÿ¥ÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÍÓ˜˜ð¡Í¯Ì°Í£ñÍ¿°Ìÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÍÊÌݤУÍÊÌÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥Íñÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥Ð¨ÕÍÐÿ¥ÌÀÒ´¥Ì°ÍШÍÐÐÕÌ°ÐÐÐÿ¥ÐˆÐÿ¥ÌÕ¨ÒÈÍÊÌÓ˜˜ð¡Í¯Ì°Í£ñÍ¿°Ìÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥ÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÍÊÌݤУÍÊðƒÐ¢ÐÊРФÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥Íñÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥Ð
Í ÐÐÎÿ¥ÍÍ₤ˋÐ₤ÿ¥ÌÏÒ´ÇÍ₤ˋÐÏÍÐÐÎÌͤÐÐÒ´¥Ì ÐÌÌˋШ̓ÐÐÌ£ÌÕý̓À̰̿дÐÐÎÓÇÐÀШÍÇð¡ÐÐÐдÐ₤ÿ¥ÌÕ¨ÒÈÍÊÌÍÊðƒÿ¥ÌÕ¨ÒÈÍÊÌÓ˜˜ð¡Í¯Ì°Í£ñÌÙÍÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥Ìÿ¥ÌËУ̯Õÿ¥Íñ£ÿ¥Íñÿ¥ÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥Ð¨ÕÍÐÐÕÌ°ÐÐÐÐ
ÿ¥ÐÍÒ´ÇÒ¨ÌÝШÐÊÐÐÎ
ÍÒ´ÇÒ¨ÌÝШÐÊÐÐÎÐÿ¥ÍÍ₤ˋÐÛÍÊÌÙШÐ₤ÿ¥ð¡Ì°ÒÀӤШͧÐÐÒÀÓ¤ÐÛÒˆÍÛШÐÊÐÐÎÿ¥ð¡Ò´ÿ¥Ð´ÍÌÏÐÛÌÀÒ´¥Ì°ÍШÍÐÐÕÌ°ÐÐÐЯÐÐÐÿ¥ÍÒˆÍÛÒÀÓ¤ÐÕÌ°ÒÀÓ¤ÐÏÐÐдÍÊÌÙÐÐШÐÊÐÐÎÿ¥ÌˆÐ ̧ÒÀÐÐÐÎÐЈÐÐÈÐÐÐÐÐÕ¨Õ§ÂÒ
Ò̓
ÕýÌÙÂÌ°ÐÛӨ̰ÒÑÈÌ´ÐÌÇÓ´Ðÿ¥Í
Õ´ÕÍ ÝÒ
Ðð¢ÒÙñÐÿ¥Í
Õ´ÕÍ ÝШÐÐð¡ÍˋÓÐÒˆýÐЈÐÓƒˋÍÐÐÐдÐÿ¥ÐÐШÕÍÐÐдÐÐÍÊÌÙÐÓʤÐÐӿШÐÊÐÐÎÿ¥ÌÕ¨ÒÈÍÊÌÐÛÍÊÌÙÐЈÐÒÏÈÕÍÕÀШÐÊÐÐÎÿ¥ÒˆÊÐÈÐÌ°ð£ÊÒÏÈÕÐÐÐÕÌ°ÐÐÐÐÐ´Ð¨Í Ðÿ¥Ì˜Ò´ÇÒ¨ÌÝÐÿ¥Ò´ÇÐÐÛÌÒçñШÕÌ°ÌÏÐÒˆÐÐÐÐÍ ÇÍШÐÐÐдÐÐӿШÐÊÐÐÎÿ¥ÌÕ¨ÒÈÍÊÌÍÊðƒÿ¥ÌÕ¨ÒÈÍÊÌÓ˜˜ð¡Í¯Ì°Í£ñÌÙÍÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÍÊÌݤУ̯Õÿ¥ÿ¥Íñ£ÿ¥Íñÿ¥Õ ÿ¥Ð¨ÕÍÐÐÎÍÊÌÙÐÐÕÌ°ÐÐÐÐ
ÓÛÐÐÐÐÐ̘À
(Ò´£)ð£ÛÍШð¢ÛÌÙÈÐÐЈÐˋÐÐÕÂð¢ÐÏÕ Ðð£ÈÐÐÈÐÎÐÐÍ ÇÍÐÐÐЃÐÐ
Ó˜˜ÿ¥ÐÍÍ₤ˋÐÛÍÊÌÙдÐÐÛÕÌ°ÌÏô ô ô 5
Ó˜˜ÿ¥Ð̘ҴÇÒ¨ÌÝШÐÊÐÐÎô ô ô 6
ÿ¥ÐÒˆÓÝÍ¢Ò´¥ð¡£ÓƒˋдÌÀÒ´¥Ì°Íô ô ô 6
(1)Ðð¤ÍÛÒˆÍÛдÌÀÒ´¥Ì°ÍÕÍô ô ô 6
(2)ÐÍÍ₤ˋÐÛÌÀÒ´¥Ì°ÍÕÍÐÛÌÎÒÎô ô ô 9
ÿ¥ÐÍÍ₤ˋÐÓ˜˜ð¡Í₤ˋÍÊÌݤШð£Ò´ÐÐÎÍ ÐÐÍÊÌÙШÐÊÐÐÎô ô ô 11
(1)ÐÍÐÂÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛÓÛÌðƒÒ¢¯ÐÛð¢ÀÓ´ÌÏÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎô ô ô 11
ÐÂÐÍ(ÿ§Ý)ÿ¥Í
ËÌÒ
ÐÛÒ¤¨ð§ð¡ÐÛÓÒñÀÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎô ô ô 12
ÐÊÐÍ(ÿ§ý)ÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛðƒÒ¢¯Í
ÍÛ¿ÐÛÍ
ñð§ÌÏÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎô ô ô 12
ÐÎÐÍ(ÿ§°)ÿ¥Ò̓
ÐÛð¤ÍÛ(1)Шð¢ÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛðƒÒ¢¯Í
ÍÛ¿Ðð¤Ò£Âð¡Ò£ÂÐÐÎÐÐÐдÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎô ô ô 14
дÐÍ(ÿ§Ç)ÿ¥Ò̓
ÐÛð¤ÍÛ(2)ÿ¥(4)Шð¢ÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛÐÀÐÂÿ¥ÌÌ¡ÐÛÒ´Ò¥ÿ¥Íð¤¤ÕÂҨШÐÐÐðƒÒ¢¯Í
ÍÛ¿ÐÛÕÈÐÕÐÓÙÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎô ô ô 16
(2)ÐÍÐÊÿ¥ÿ¥ˋÍаÿ¥ˆÐÛÍðƒÒ¢¯ÐÛð¢ÀÓ´ÌÏÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎô ô ô 19
(3)ÐÍÐÎÿ¥ÿ¥ÂÐÛÒ´¥Ò´ÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎô ô ô 23
(4)ô Íдÿ¥ÌÙÍ¿Í¡ÐÛÒÀÐÈÐÒˆ¢Ì£ÓçÌÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎô ô ô 24
(5)ô ÍЈÿ¥ÌÓʤð¤ÍÛÿ¥ÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎô ô ô 27
ÿ¥£ð£ÿ¥§ÍÍ₤ˋÐÒ´¥Ì ÐÌÌˋШ̓ÐÐÌ£ÌÕý̓À̰̿дÐÐÎÍÇð¡ÐÐÐдШÐÊÐÐÎô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô 27
(6)ÐÍШÿ¥ÌÓʤð¤ÍÛÿ¥ÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎô ô ô 29
ÿ¥ô ÍÍ₤ˋÐÓ˜˜ð¡Í₤ˋÐÛÍÊÌÙÐÍ¥Ó´ÐÐÎÌÓʤð¤ÍÛÐÛÓÍÛÌÏÐÒˆÐÐÍÊÌÙШÐÊÐÐÎô ô ô 30
(1)Ð̘ð£ÑÒ´ð¤ÿ¥ÿ¥ÿ¥Ð¨Ò´Ò¥ÐÐÐÌÓʤð¤ÍÛÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥Ò̓
ÐÛð¤ÍÛ(1)ЈÐÐ(4)ÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎô ô ô 30
ÐÂÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛðƒÒ¢¯ÐÛð¢ÀÓ´ÌÏШÐÊÐÐÎô ô ô 30
(ÿ§Ý)ÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛðƒÒ¢¯Í
ÍÛ¿ÐÍ
ñð§ÓÐÏÐÐÐдШÐÊÐÐÎô ô ô 30
(ÿ§ý)ÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛðƒÒ¢¯Ð₤ÿ¥ÐÐÛÌÐ
ÐÏð¤Ò£Âð¡Ò£ÂÐÐÎÐÐÐдô ô ô 31
(ÿ§°)ÐÓçÒ¨ô ô ô 37
ÐÊÐð£ÒÙñÒñÍÀÿ¥ˋÍаÿ¥ˆÐÛÍðƒÒ¢¯ÐÛð¢ÀÓ´ÌÏШÐÊÐÐÎô ô ô 38
ÐÎÐÒ´¥ð¤¤ÿ¥ÂÐÛÒ´¥Ò´Ð¨ÐÊÐÐÎô ô ô 38
дÐÌÙÍ¿Í¡ÐÛÍÛ̧ÐÐÒˆ¢Ì£Ð¨ÐÊÐÐÎô ô ô 39
(2)Ð̘ð£ÑÒ´ð¤ÿ¥ÿ¥Ð¨Ò´Ò¥ÐÐÐÌÓʤð¤ÍÛÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎô ô ô 39
ÿ¥ÐÍÍ₤ˋÐÓ˜˜ð¡Í₤ˋÐÛÍÊÌÙÐÍ¥Ó´ÐÐÎÌÓʤð¤ÍÛÐÓÍÛдð¢ÀÐÐÐдÐÛӡͧÌÏÐÛÍÊÌÙШÐÊÐÐÎô ô ô 42
(1)ÐÌÓʤð¤ÍÛÿ¥ÿ¥Ì˜ð£ÑÒ´ð¤ÿ¥ÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎô ô ô 43
(2)ÐÌÓʤð¤ÍÛÿ¥ÿ¥Ì˜ð£ÑÒ´ð¤ÿ¥ÿ¥ÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎô ô ô 46
(3)ÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿5ÐÐÛÍÌШÐÊÐÐÎô ô ô 47
Ó˜˜ÿ¥ÐÍÒ´ÇÒ¨ÌÝШÐÊÐÐÎô ô ô 48
ÿ¥ÐÍÍ₤ˋÐÿ¥Ó°Ó¨ð¤¤Ð¨ÐÐ̘ҴÇÌÒçñÒÀÓ¤ÐÒ´ÇÐÐÛÌÒçñÐÕ̰ЈÒÀӤдÐÐÎÕÌ°ÐÏÐÐдÍÊÌÙÐÐӿШÐÊÐÐÎô ô ô 49
ÿ¥ÐÍÍ₤ˋÐÿ¥Ó°Ó¨ð¤¤Ð¨ÿ¥ÌˆÌ§ÒÀÐÏÐÐÈÐÕ¨Õ§ÂÒ
Ò̓
ÕýÌÙÂÌ°ÐÛӨ̰ÒÑÈÌ´ÐÌÇÓ´Ðÿ¥Í
Õ´ÕÍ ÝÒ
ð¢ÒÙñÍаÍ
Õ´ÕÍ ÝÒ
ШÐÐð¡ÍˋÓÓÎÌÙÂÐÛÓƒˋÍÐÐÐдÐÿ¥ÐÐШÕÍÐÐдÐÐӿШÐÊÐÐÎô ô ô 51
ÿ¥ÐÍÒÀÓ¤ÐÛÒˆÍÛÐÛð¤ÍÛÒˆÊ҈ШÐÊÐÐÎô ô ô 53
(1)ÐÍÍ₤ˋÐ̯ÐШ҈˜ÓʤÐÍ ÐÐӿШÐÊÐÐÎô ô ô 53
(2)ÐÍÍ₤ˋÐÓ˜˜ð¡Í₤ˋÐÛÍÊÌÙÐÍ¥Ó´ÐÐÎÒˆÍÛÐÐÒÀӤШÐÊÐÐÎô ô ô 56
ÐÂÐÿ¥À̧ҴÙÕñÐÛÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ШÍ₤ƒÐÐÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÐÛÒÀÓ¤ÿ¥(1)ÐÂ(ÿ§Ý)ÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô 56
ÐÊÐÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÐÛÿ¥À̧ҴÙÕñÿ¥ÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÐÛÿ¥ÈÍ₤̧ҴÙÕñÿ¥ÿ¥Ìÿ¥ÌËÐÛÿ¥À̧ҴÙÕñÿ¥ÿ¥ÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÐÛÿ¥₤ÓÒÙñð¡£ð££ÐÛÍÒ´Íÿ¥(1)ÐÂ(ÿ§ý)ÿ¥(ÿ§°)ÿ¥(ÿ§Ñ)ÿ¥(ÿ§¥)ÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎô ô ô 57
ÐÎÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐШÍ₤ƒÐÿ¥ÒñÍÀð¥ÒٯШͤ͡ÙÐÐЈÐÐÈÐÐдÿ¥(1)ÐÂ(ÿ§ç)ÿ¥(2)ÐÂ(ÿ§ç)ÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎô ô ô 58
дÐÍÊÍÊÿ¥ð¤¤Ð´ÐÐÐдÿ¥(1)ÐÂ(ÿ§ç)ÿ¥(2)ÐÂ(ÿ§ç)ÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎô ô ô 58
ЈÐÍÛÑÌÒˆ˜Ìð¥ÐÏÿ¥Âдÿ¥ÛШÿ¥¿1Ó¤Ò´ÐÍÎÍÛÐÐÐÐдÿ¥(1)ÐÂ(ÿ§ñ)ÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô 59
ШÐÿ¥¿1дÿ¥¿1ШÍ₤ƒÐÐÌÍÛ°Ò° ÍÒ¨ÌÝð¤ð£ÑУ̘ҴÇÐÛÌÒçñÿ¥(1)ÐÂ(ÿ§¡)ÿ¥(2)ÐÂ(ÿ§Ñ)ÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎô ô ô 60
ÐÙÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ШÍ₤ƒÐÐÍÊÍð§Ó°£ÐÛÍÊÌÇдÍÊÍÍ ÇÌÐÛÍÊÌÇͧð£Êÿ¥(1)ÐÂã (ÿ§¿)ÿ¥(ÿ§£)ÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎô ô ô 60
ÐÝÐÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÐÛÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ШÍ₤ƒÐÐÿ¥À̧ҴÙÕñдÿ¥₤ÓÒÙñð¡£ð££ÐÛÒ´Íÿ¥(2)ÐÂ(ÿ§Ý)ÿ¥(ÿ§ý)ÿ¥(ÿ§°)ÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎô ô ô 64
Ó˜˜ÿ¥ÐÍÍ₤ˋÐÛÍÊÌÙдÐÐÛÕÌ°ÌÏ
̘ð£ÑÐ₤ÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿6ÿ¥ð£Ëð¡ÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿6ÐдÐÐÐÿ¥ÐÍñÓÙÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿5ÿ¥ð£Ëð¡ÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿5ÐдÐÐÐÿ¥ÐÐÐÛÓ¤ÒÀÐÐÿ§Ì¯ÒШÌýÒ¥ÐÐÓ°Ó¨ð¤¤ÐÛÒ´ÙÓ§ÛУÓçÍÑÐÐÿ§ÐÏÍ
ËÌÒ
ШÍ₤ƒÐÐÒ̓
ÐÒÀÐÐÐÎÐÐÌ´ÐÛÍÒ´ð¤Ð¨ÐÊÐÿ¥Ó°Ó¨ð¤¤Ðÿ¥ÿ§Ð¨ÐÐÐÒ̓
ÐÛð¤ÍÛÐ₤ЈÐÿ¥ð¤ÍÛШÍÐÐͧÒˋýÍÒ´ð¤Ð¨ÐÐÓ°Ó¨ð¤¤ÐÛð¢ÀÓ´ÍаÍÒˆÐÒÐÐÌЈÐÐÐдÐÐÎÿ¥ð¡Ì°ÒÀÓ¤ÿ¥Ì¯Ì°ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÌÀÿ¥Íÿ¥ÿ¥ÿ¥ÌÀÿ¥Íÿ¥ÿ¥ÿ¥ÌÀÿ¥Ð¨ÐÐÌÍÛ°Ò° ÍÒ¨ÌÝÌ´ˋШͤÐËÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿5Ðÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿3ÿ¥ð£Ëð¡ÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿3ÐдÐÐÐÿ¥ÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÿ¥ð£Ëð¡ÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐдÐÐÐÿ¥ÍаӡÌÌ¿ÿ¥¿2ÿ¥ð£Ëð¡ÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿2ÐдÐÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥ÍÐð§çÐÐÎÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿3ÐÐдÐÐÐÿ¥Ð¨ÿ¥ÍÌ
¯Ò˜ÌÍаÕ
Í£ÑÌÍÛ°ÕÐÛÌ₤ÌÐÌÝÐÐддÐШÿ¥ÍÒˆÍаð¢ÀÓ´ÐÛÍ̓ˋ̈ӧÛдÐÐÎÿ¥Ó°Ó¨ð¤¤ÿ¥¿5ШÍ₤ƒÐÿ¥Ò˜Ó§ˆÍ¤ÍÐÛÌýÒ¥ÐÌÝÐÐð¡Ì¿ÐÏÿ¥Ì˜ð£Ñ̘ҴÇÿ¥ÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÍаÍÿ¥¿1ÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥ÍÐð§çÐÐÎÿ¥ð£Ëð¡ÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÐдÐÐÐÿ¥Ðÿ¥ÿ§Ð¨ÐÐÐÒ̓
ÐÛð¤ÍÛÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿3Ð¨Í ÝÍÐÿ¥Í ÝÕÌˋÕÂÍÓʃÐÛÍÌШ͢ÐÐЈÐˋÐÐдÐÐÿ¥Ó°Ó¨ð¤¤ÐÛÍ¿¿Õ´ÒñÍÀÐÐÓ§çÍУÌÇÒ´ÐÍÐÿ¥ÐƒÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÐÐÐÒͧÐÛÍ ÝÍÐÐÐÎÐÐÐÐÛÐÐЈÌÝÐÐÍÐÐЈÐˋÐÛͨÐÐÐÐÐÐÿ¥ÐÐШÿ¥Ó°Ó¨ð¤¤ÐÐ̘ð£Ñ̘ҴÇÐÌÒçñÐÐÐЈÐˋÐÐдÐÐÎÿ¥ð¡Ì°ÒÀÓ¤ÿ¥Ì¯Ì°ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÌÀÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÌÀÿ¥Ð¨ÐÐÌÍÛ°Ò° ÍÒ¨ÌÝÌ´ˋШͤÐËÐÿ¥Ó°Ó¨ð¤¤Ð¨Í₤ƒÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÐÍÌ
¯Ò˜ÌÍаÕ
Í£ÑÌÍÛ°ÕÐÛÌ₤ÌÐÐÐÐÐÌÝÐÐð¤ÌÀÐÏÐÐÐ
ÐÐШÍ₤ƒÐÿ¥ÍÍ₤ˋÐ₤ÿ¥Ì˜ð£ÑÍÒ´ð¤ð¡Ùÿ¥Ó°Ó¨ð¤¤ÐÛÓʃð¥ÓÒˋðƒÀÐð§ð¡ÐÐÐд҈ÍÛÐÐÌÓʤð¤ÍÛШÐÊÐÐÎÿ¥ÓÍÛÌÏÐÛÒ´¥ÌÐÐÐÿ¥ÍÐ₤ÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿5ÐÐÐÐÛð¤ÍÛÐÓÍÛдð¢ÀÐÐШÐÊÐÐÎӡͧÐÛÓÓÝÐÐÐдÐÐÎÿ¥Ì˜Ò´ÇÒ¨ÌÝÐÌÈÍÇÐÐÐ
ð¡Ì¿ÿ¥ÍÒ´ÇÒ¨ÌÝШÐÊÐÐÎÐ₤ÿ¥Ó˜˜ð¡Í₤ˋÍÊÌݤð¡ÙÐÛÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÌÒ´ÇÕ´ÍÐÌÂÐÐÎÍÐÌÑÐÐÎÿ¥ÍÒ´ÇÒ¨ÌÝÐÍ
´ÐÎÒˆÍÛ¿ÐÐÐ
ÐÐÐÿ¥ð£Ëð¡Ð¨Ò¢¯Ð¿ÐдÐÐÿ¥ÐÐÐÐÛÍÊÌÙÐÓÓÝÐЈÐÐ
Ó˜˜ÿ¥Ð̘ҴÇÒ¨ÌÝШÐÊÐÐÎ
ÿ¥ÐÒˆÓÝÍ¢Ò´¥ð¡£ÓƒˋдÌÀÒ´¥Ì°Í
(1)Ðð¤ÍÛÒˆÍÛдÌÀÒ´¥Ì°ÍÕÍ
ÐÂÐ̯ð¤Ò´ÇÒ´Ì°ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÌÀÐ₤ÿ¥ÐÐÐÐÒˆÓÝÍ¢Ò´¥ð¡£ÓƒˋÐÌÀÓ´ÐÐÐдÐÌÍÛÐÿ¥ð¤ÍÛÐÛÒˆÍÛÐ₤ÿ¥ÐÍÈÕ ÙÍ¥Ò¨ÐÛÍ
´ÒÑÈÌ´ÍаҴ¥Ì Òˆ¢ÐÛÓçÌÐÐÐÐÕ
ÐÐÎÒÀÐЈÐÐЯЈÐЈÐÐÿ¥ÐÒˆÓÝЈ͢Ҵ¥ÐШÐÐÿ¥ð¤ÍÛШÐÊÐÐÎÐÛð¡£Í¥çÐÓÍÛд҈ÐÐÐÍÎÐÐÍÊÌÙÐÐÐÐÛдÐÐÎÐÐÐ
ÐÐÐÎÿ¥ÒˆÓÝÍ¢Ò´¥ð¡£Óƒˋдð¤ÍÛÒˆÍÛÐÛÕÂð¢Ð¨ÐÊÐÐÎÐ₤ÿ¥Ò´¥Ì ðƒÀÍÊÐÛÌÓÀÍаͥñÍ¥ÝÐÛÍÊÌÙÐ₤ÿ¥ÒÈÍÊÍÛÐÛÐЈХÐаÐШð££ÐÐÐÿ¥ÕÌËð¤ÍÛÐÐÓÇÌËð¤ÍÛÐÌ´ÒˆÐÐÓçÕ´ÍÍа̴҈ÐÕ£ÍÛ°ÐÐÓçÕ´ÍÐÛÍÌ´Õ¡ÌÐÿ¥ÒÈÍÊÍÛÐÛÒˆÓÝЈÍÊÌÙШÍÏÐÙÐÐÐÐдШЈÐÐÿ¥Ì°ÍÛÒ´¥Ì Ì°ÍÐÛÍÛÐÐðƒÍÊÐÐÐУÐÿ¥ÒÈÍÊÍÛÐÛÒˆÓÝЈÍÊÌÙУÐЈХÐаÐдÐÐÈÐÎÐÿ¥ÒÈÍÊÍÛÐÛÌÈÌÓÒˆÍÛÐÒ´ÝÐÐÐÐÐÐÏÐ₤ЈÐÿ¥ÍÓÓÐÏÓÒ¨ÓЈ̴ҨÐÍÌдЈÐÐÐÛдÐÐÐÎÐÐÿ¥ÕÇÌ´ÌÙÈÒÈÿ¥ÕÍÝÝÍÍ
Óñ´ÐÌ°´Õ̯ð¤Ò´ÇÒ´Ì°(4)Ðÿ¥Í ÒÊ̯ÍʈÕÿ¥ÿ¥Ð
ÐÊÐð¤ÍÛð¡ÐÛð¤Ó¿Ð¨ÐÊÐÐÎÿ¥ÐˋÐÛӴͤÎÐÛÒ´¥ÌÐÐÐЯÿ¥ÒÈÍÊÍÛÐð¡ÍÛÐÛð¤ÍÛÐÐÐÈÐдÐÐÍ¢Ò´¥ÐͧÂÌÐÐÎð¤ÍÛÒˆÍÛÐÐÎÐÐÐÐˋÐÐÐÍÕÀÐÏÐÐÿ¥Í¤Ì˜ÓÍÍÐ₤ÿ¥Ò´ÇÒ´ð¡ÐÛÓ¨Ò´¥Ð₤ÐըͤÎÐÛÒÓÑÌÏÐÐÒ´¥ÌÐÐÐдÐÏÐÐÿ¥ÐÐÛÍÊÌÙÐ₤ÐÕÍ¡¡ð¤¤ÐÓÐÐÍñÛÐÌЃЈÐӴͤÎШÓÍÛÌÏÐÛÓ¤ð¢ÀÐÌÐÀ̓ÐÐÐÛÐÐÏЈÐÐЯЈÐЈÐдÐÐÐдÐÏÐÐÐÐЈÐÐÀÿ¥ÌÕ¨ÒÈÍÊÌÐ₤ÿ¥ÐÒ´ÇÒ´ð¡ÐÛÓ¨Ò´¥Ð₤ÿ¥ð¡Ó¿ÐÛÓÓƒˋÐÒ´ÝÐЈÐÒˆÓÑÓÏÍÙÎÓÒ´¥ÌÐÏÐ₤ЈÐÿ¥ÓçÕ´ÍÐ¨Ó ÏÐÐÐÎÍ ´Ò´¥Ì ÐÓñÍÌÊÒ´Ðÿ¥Ó¿ÍÛÐÛð¤ÍÛÐÌ₤ÒˆÐ̓ÐӴͤÎÐÛÒÓÑÌÏÐÒ´¥ÌÐÐÐдÐÏÐÐÿ¥ÐÐÛÍÊÍÛÐ₤ÿ¥ÕÍ¡¡ð¤¤ÐÓÐÐÍñÛÐÌЃЈÐӴͤÎШÓÍÛÌÏÐÛÓ¤ð¢ÀÐÌÐÀ̓ÐÐÐÛÐÏÐÐÐдÐÍ¢ ÒÎдÐÿ¥ÐÐÊÿ¥ÐÐÐÏÒÑ°ÐÐÐÐÛÐÏÐÐÐÿ¥ÌÕ¨ÒÈÍÊÌÓ˜˜ð¤Í¯Ì°Í£ñÌÙÍÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥ÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËУ̯Õÿ¥ÿ¥Íñ£ÿ¥Íñÿ¥ÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÍÓ˜˜ð¡Í¯Ì°Í£ñÍ¿°Ìÿ¥Í¿Çÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌË̯Õÿ¥ÿ¥Íñ£ÿ¥Íñÿ¥ÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥Ð´Ðÿ¥ÐÒ´ÇÒ´ð¡ÐÛÍ ÌÕÂð¢ÐÛÓ¨Ò´¥Ð₤ÿ¥ð¡Ó¿ÐÛÓÓƒˋÐÒ´ÝÐÐЈÐÒˆÓÑÓÏÍÙÎÓÒ´¥ÌÐÏÐ₤ЈÐÐÿ¥ÓçÕ´ÍÐ¨Ó ÏÐÐÐÎÍ ´Ò´¥Ì ÐÓñÍÌÊÒ´Ðÿ¥Ó¿ÍÛÐÛð¤ÍÛÐÓ¿ÍÛÐÛÓçÌÓ¤ÓÐÌÌËÐÐÕÂð¢ÐÌ₤ÒˆÐ̓ÐըͤÎÐÛÒÓÑÌÏÐÒ´¥ÌÐÐÐдÐÏÐÐÿ¥ÐÐÛÍÊÍÛÐ₤ÿ¥ÕÍ¡¡ð¤¤ÐÓÐÐÍñÛÐÌЃЈÐӴͤÎШÓÍÛÌÏÐÛÓ¤ð¢ÀÐÌÐÀ̓ÐÐÐÛÐÏÐÐÐдÐÍ¢ ÒÎдÐÐдÒÏÈÐÐпÐÐÏÐÐÐÐÿ¥Ì°ÿ¥ÌÀÿ¥Õ ÐÛÒˆÍÛÐÛÒÎð£ÑдÐÐÐÎÐÐ̃ͯÓñÒçñÍ ÌÏШÐÊÐÐÎÐÿ¥ÒÎÒ´¥ð¤ÍÛШÐÊÐÐӡͧÐÛÒÓÑÌÏÐÐÐÓ¨Ò´¥ÐÐЯÒÑ°ÐÐдÐÐÐдÐ₤ÐÏÐЈÐÐÿ¥ÌÕ¨ÒÈÍÊÌÓ˜˜ð¡Í¯Ì°Í£ñÍ¿°Ìÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÍÊÌݤУÍÊÌÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥Íñÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥Ð´ÍÊÓʤÐÐÎÐÐÐ
ÐÎÐЃÐÿ¥ð¤ÍÛÐÛÒˆÍÛÐ₤ÿ¥ÒˆÓÝÍ¢Ò´¥ð¡£ÓƒˋÐÛÍÍШͤÐËÐÐÐÛÐÏÐÐÈÐÎÐÒ¨ÓÌ°ÍУÓçÕ´ÍШ̓Ðÿ¥ÍÓÓÓÓÝШͤÐËÐÐÎÐÐЈÐÐЯЈÐЈÐÐдÐ₤ÐÐЃÐÏÐЈÐÿ¥ÌḬ̈ͧÌШÐÐÐÎÿ¥ÍÊÐÐÛÌÕ¨ÒÈÍÊÌݤÐÏÐ₤ÿ¥ð¤ÍÛÒˆÍÛÐÛÕӴШÐÐÐÓçÕ´ÍÕÒÐð¡ÍÓÓÝдЈÐÐдÐÒˆÐÐÎÐÐÿ¥ÍÛÕÌ ð¡ÕÐð¡ÍÍ₤ˋÐÛÍÛÍð¡ÐÛÍÕÀÐÿ¥Ð
ÐÌÀÒ´¥Ì°ÍÕÒÐдÐ₤ÿ¥ðƒÐЯÿ¥ÌÌ¡ÐÛÌ´ÍÛЈÐˋÐÛÐÐЈ̰ÍÛÒ´¥Ì Ì°ÍШÕÍÐÐÍ ÇÍÐÛТÐÏÐ₤ЈÐÿ¥ÐÐÐÌÏ̯ð¤Ò´ÇÒ´Ì°ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÌÀШÐÐð¤ÍÛÒˆÍÛШÐÐÐÒˆÓÝÍ¢Ò´¥ð¡£ÓƒˋÐÛÍÓÓÐÐÐÒÑ
ÐÐÒˆÍÛÐÌÍ°ÐÐÐÐÛдÐÐÎÓ´ÐÐÐÐÎÐÐÐÐЈÐÐÀÿ¥ÒˆÓÝÍ¢Ò´¥ð¡£ÓƒˋÐ₤ÿ¥ÐÒ¨ÓÌ°ÍдÓçÕ´ÍШ̓ÐÈÐÍÓÓЈҴ¥Ì ÐÛÌÀÍÎÿ¥ð¤ÍÛÐÛÒˆÍÛÐÏЈÐÐЯЈÐЈÐдÐÐð¡ÌÐÛÌ°ÍÐÐÐÛÍÊÐÐÐÓ£ÐÐÐÐÛÐÏÐÐÿ¥ÐÐÛÌ°ÍÐÛÕÒÐÌÀÒ´¥Ì°ÍÕÒдÐÐÐÎÐÐÍ ÇÍÐÍÊÐÐÛÐÏÐÐÐдÐÐÿ¥ÍÛÒ°ˆÓШÐ₤ÿ¥ÓçÕ´ÍÕÒÿ¥ÓÓÝð¡ÍУÓÓÝÕ§Õ§˜Ð´Ó¯ÐˆÐдÐÐÐ₤ЈÐÿ¥Ð´ÐÐÐÎÐÐÿ¥ÍÛÕУÍÌýÿ¥ÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥Ð
дÐÐÐÐÎÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÌÀÐÛÍÛÐÐÐÌ°ð£ÊÐÛÒÏÈÕШÕÂÐÐÕÒÎЈð¤Õ
ÐдÐ₤ÿ¥ÌÕ¨ÒÈÍÊÌÐÌ°ð£ÊÒÏÈÕШÐÊÐÐÎÍÛÒ°ˆÓЈÍÊÌÙÐÓʤÐÍ¢
ÒÎÐÐÐð¤Õ
ÐÐÐдÐÐÿ¥Í
ñð§ÓШÐ₤ÿ¥ã ÌÕ¨ÒÈÍÊÌÐÛÍÊÌÙÐЈÐÒÏÈÕÍÕÀШÐÊÐÐÎÌÕ¨ÒÈÍÊÌÐÛÍÊÌÙÐÓʤÐпÐÍ ÇÍÿ¥ãÀÌÕ¨ÒÈÍÊÌÐ̓ÍÐÛÍÊÌÙÐÍÊÌÇÐпÐÍ ÇÍÿ¥ãÂÕ¨ÓÙÒÈÍÊÌÐÛÒˆÊÐÈÐÌ°ð£ÊÒÏÈÕÐÕ¨ÓÙÒÈÍÊÌÐÛÍÊÌݤдÐÐÎÓ¤ÍÛÐÐÐÐдÐÕˋͧÐÏЈÐÍ ÇÍÓÙÐÐÐШÐÐÐдÐÐÐÎÐÐÿ¥Ì°ÍÓ̯ð¤ÍÝÍð¤ÍÛÍÛÊÓñ´Ð£ð¡Íð¡ÓÙ̯̯ð¤Ò´ÇÒ´Ì°ÿ¥ÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥Ð´ÐÐÿ¥ÓçÕ´ÐÐÓý̓ÐÐÐð¤ÓˋШÕÂÐÐÓËÒÙÐÌ°ÍÐÐÓçÕ´ÍÐ₤ÌÏÌ°ð¡ÍÌÏШ̰ð£ÊШͨЃÐÿ¥ÍÍÊÌݤШÓçÕ´ÍÕÍÐÐÐÍ ÇÍШÐ₤ÿ¥ÐÐÐÓÓÝдÐÐÎð¡ÍÍÓÐÛÓ°Ó¨ÐÎÐÒÀÐÐдÐÐÏÐÐдÒÏÈÐÐÿ¥Í¤ÍÈÕ
ð¿
ÐÌÕ¨ÒÈÍÊÌШÍ₤ƒÐÐð¡ÍÐ̯̯ð¤Ò´ÇÒ´Ì°ð§Ó°£(4)ÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÿ¥ÌÕ¨ÒÈÍÊÌÐ₤ÿ¥ð¡ÍÐÛÓÓÝÐЈÐÍ ÇÍÐÏÐÐÈÐÎÐÿ¥ÐÍÊÌݤШͧÝÕ¢ÐÍÐ¥ÐÐдÐÌÐÐЈ̰ð£ÊÐÛÕÍÐÐÐдÐÐ₤ÿ¥ÍÍÊÌݤÐÓ ÇÌÈÐÐÐÐдÐÐÏÐÐдÐÐÐÎÐÐÐÛÐÏÿ¥Ì¯ð¤Ò´ÇÒ´Ì°ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÌÀÿ¥Õ
ÿ¥ÿ¥ÍÍÊÌݤÐÛÌÀÒ´¥Ì°ÍÕÍÐð¡ÍÍÓÓ°Ó¨ÐÎÐÛÓÓÝШЈÐ̓ÐдÒÏÈÐÐÐÛÐӡͧÐÏÐÐÿ¥Íƒ°Ó¯ÍÍ¿¡ÐÌÕ¨ÒÈÍÊÌШÍ₤ƒÐÐð¡Ò´ÇÍÑͤÎÐҘͤÏ̯̯ð¤Ò´ÇÒ´Ì°ã
Âÿ¥ÿ¥Õ ÍÓ
Ïÿ¥Ð
ÍÍ₤ˋÐÛÍÊÌÙÐÌÀÒ´¥Ì°ÍÐÛÕÍÐÐÐдÐÐÐð¤ðƒÐ´ÐÐÎÿ¥ðƒÐЯÿ¥ÌÕ¨ÒÈÍÊÌÓ˜˜ð¡Í¯Ì°Í£ñÍ¿°Ìÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥ÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÍÊÌݤУÍÊðƒÐ¢ÐÊРФÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥Íñÿ¥ÿ¥Õ ÐÐÐ
ЈÐÌÈÌÓЈ̢¨Ò´ÇШÐÐð¡Í¢
ÒÎШÕÍÊÏЈͧ¿ÍýÐÐÌÕ¨ÒÈÍÊÌÐÒÏÈ̃ÐÐÐпÐÿ¥ð¡ÍÓÓÝÐÍÑÕÐÐÐÐдÐ₤ÿ¥ÍÑͤÎдÐÐÎÍÍШÍÛ¿ÒˆÐÏÐÐдÐÐÐÏÐÐÐÿ¥ÍÕÂÿ¥Õ¨ÓÙÒÈÍÊÌ̯ð¤Õ´Ðÿ¥ÓÛÕ´ÐÐЈÐÕ¨ÒÈÓÛÀÍ
ШÐÐÐÎÐ₤ÿ¥ÒÈÍÊÍÛÿ¥ÌÛШÒÈÍÊÕñÐÛÒÐУÍÌÏШÐÐÈÐÎͯÍÌ₤ШÍÊðƒÐͧÂÌÐÐÐÎÐЃÐдÐÐð¤Ì
ÐÓÐÐÐдÐÐÐ̓ÐдÐÐÐÏÐÐÈÐÎÿ¥Íð¡Í§Í
ШÐÐÐÎÿ¥Ì°ÐÛÕӴШҴÝÐÕÈÐÍñÛÓ¯ÐÓÐÐÐдÐÌ°ÍÛÐÐÐÐ
ð¡ÍÍÓÐÌݤÍÛÐÐÐÐˋÐÐШÐÊÐÐÎÐ₤ÿ¥ÍÑͤÎÐÛÕˋÍЈÕӴдÐÐÒΰӿÐÍ Í°ÐÐÎÿ¥ÕˋÍШÐÐÐÐдÐð¡Í₤̘ ÐÏÐÐÐ
(2)ÐÍÍ₤ˋÐÛÌÀÒ´¥Ì°ÍÕÍÐÛÌÎÒÎ
ÐÂô ̘ð£ÑÐÏÐ₤ÿ¥ÌÇÒÀÒÀÓ¤ÐÓÛÌÐÐдÐÐðƒÒ¢¯ÐÐÐÐÐÛÐÛÿ¥ÐÐÐÒÈð£ÐÐÍÛÂÒΰÓЈҴ¥Ì ÐÍÙÍ´ÐÐÿ¥Ò¨ÍÓ¤Ò
Ð₤ÌÇÒÀÒÀÓ¤ÐÒÀÐÈÐÐдÐÌÓ¤ШÍÎÍÛÐÐÎÐÐÐÐÐÛÐÐÐˆÍ ÇÍÿ¥ÌÇÒÀÒÀÓ¤ÐÒˆÍÛÐÐÐдÐÐÐдÐ₤ÿ¥Ò¨ÍÓ¤Ò
ÐÓ₤Ó§ˆÒ
дÐÐÐШÓÙÐÐÐÐÛÐÏÐÐÈÐÎÿ¥Ó¡ÓÓƒÐÐÒ´¥Ì ÐÛЈÐÐÐÐÐÐÐÌÀÓ´Ðÿ¥ÐÐÐÐÌ´ÒÝÀÐÐÐдÐÐÍÊÌÙШÐÐÐÎÿ¥Ó¿Ð¨Ì
ÕЈÍÍ°ÐÐЈÐÐЯЈÐÐÿ¥ÍÛÂÒΰÓЈҴ¥Ì ÐЈÐð¡ÙÐÏÓÛÌðƒÒ¢¯Ð ÐÐÌ ¿Ì дÐÐÎÌÇÒÀÒÀÓ¤ÐÒˆÍÛÐÐÐдÐÐÐÛÐÏÐÐЯÿ¥ÓÛÌðƒÒ¢¯ÐÛð¢ÀÓ´ÌÏÐÛÓ¤ÍÛÌÏÐÌÝÐÐÐÐдÐÐЈÐÐЯЈÐЈÐÐ
ÐÐÐÎÿ¥ÐÐÛÍ ÇÍÿ¥ðƒÒ¢¯Í
ÍÛ¿ÐÍ
ñð§ÓÐÏÐÐдÐÐÎÐÿ¥ÓÇÐÀШÐÐÛð¢ÀÓ´ÌÏÐÕ¨ÐдÒˋðƒÀÐÏÐÐдÐ₤ÕÐЈÐÐÿ¥ÐÐШÿ¥ÓÛÌðƒÒ¢¯Ðÿ¥ð¥ÒÒ´¥Ì ШͧÐÐдÐÿ¥Ì§ÒÝÀÓÍ
ÍÛ¿ÐÏÐÐÍ ÇÍШÐ₤Ó¡Í¢ÐÛÍÍ°ÐÍ¢
ÒÎÐÏÐÐÐ
дÐÐÐÿ¥ÍÍ₤ˋÍÊÌÙÐ₤ÿ¥ÐÐÛÓ¿ÐÍ
´ÐÒÌ
ÛÐÐÐдЈÐÿ¥ÓÛÌðƒÒ¢¯ÐÛð¢ÀÓ´ÌÏÐÍÛÌШ҈ÐÐÎÿ¥ÌÇÒÀÐÛÍÙÍ´ÐÒˆÍÛÐÐÎÐÐÿ¥ðƒÒ¢¯Ò´¥Ì ÐÛð¢ÀÓ´ÌÏÐÛÒˋðƒÀШÐÐÐÎÌÀÒ´¥Ì°ÍШÕÒÐÐÕÌ°ÐÐÐÐ
ÐÊÐÍÌÓʤð¤ÍÛÐÛÓÍÛÌÏÐÛÒˆÍÛШÐÊÐÐÎÐÛÍ
ñð§ÓÌÊÒ´Ð₤ÿ¥ÍƒÐ¨Òˋ°ÓǯШÒÀÐÐддÐÐÐÿ¥ðƒÐЯÿ¥Ò̓
ÐÛð¤ÍÛ(1)ШÐÊÐÐÎÐ₤ÿ¥ÍÛÒ°ˆÓШÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛÒ´¥Ò´Ð ÐÐÏÐÐÛÍÙÍ´ÐÒˆÍÛÐÐÐÐÛÐÏÐÐÐÿ¥Ì˜ÀÐÛдÐÐÌÀÒ´¥Ì°ÍШÕÍÐÐÎÒˆÍÛÐÐÐÐÛдÐÐУÐЈÐÐ
ÐЈÐÐÀÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛðƒÒ¢¯ÐÛð¢ÀÓ´ÌÏÐÒÈð£ÐÐÐÐШӘ˜ð¡Í₤ˋÍÊÌݤÐÏÍÐð¡ÐÐÐÐÒÈÍˋð¤ÍÛÐ₤ÿ¥ÕÐÐÐÐÐÛÒ
ÐÐЃÐÐƒÓƒÍ ÇШÕÙÕÐÐÎÓÛÌÐÐдÐÐÐÐÐˆÍ ÇÍÐÛðƒÒ¢¯Ð¨ÐÊÐÐÎÐÏÐÐЯÿ¥Í§ÒˋýðƒÒ¢¯Ð¨Õ¨Ðð¢ÀÓ´ÌÏÐÒˆÐÐð¤Ì
дЈÐÐÏÐÐÐÐÐЈÐÐÀÿ¥ð£Ð¨ÓÇÌËÒ´¥Ì ÐÐÐÐ₤ð¡£ÒÎð¤ÍÛдÒñÕÂÐÛÒ¢ÐÕÌËÒ´¥Ì ÐЈÐÍ ÇÍÐÏÐÐÈÐдÐÐÎÐÿ¥ðƒÒ¢¯ð¡ÙШӃÐÐÍ
ñð§ÓÐÐÊÒˋ°ÓǯЈÍ
ÍÛ¿Ðÿ¥ðƒÒ¢¯Ðð¤ÍШÐ₤ÐдÐÐð¤ÍƒÐÏÐÐÈÐÎÐÍÛ¿ÌШÐ₤ð¤ÓËÐÏÐЈÐÐÐÛÐÏÿ¥ÐÐÊÍÐÐÐдÐÛÐÏÐЈÐÐÐЈÍÛÂÒΰÓð¤Ì
ШÍÒÇÐÐдÐÐ₤ÿ¥ÐÐÛÐд҈ð§Ð¨ÐÐÈÐÎÿ¥Ò´¥Ò´ÐÛð¢ÀÓ´ÌÏÐÕ¨ÐдÒˋðƒÀÐÐÐдÐÐÏÐÐÐÐ
ÐÐÐÿ¥ðƒÒ¢¯Ò
Ðÿ¥ÕñÌÕÿ¥Ì₤ÌËÐÛÐÐÐ¨ÓƒÍ ÇШÐÐÿ¥ð¡Ò´ÐÛÍÛÂÒΰÓð¤Ì
Ðð¤ÓËÐÐÎÐÐÐÐÐˆÍ ÇÍШÐ₤ÿ¥ÐÐÐÏÐÐШÐÐÐÐÐÐÿ¥ÐÐÛÐÐЈÍÛÂÒΰÓð¤Ì
ШӘÎÍÐЈÐÐÐÐˆÍ ÇÍШÐÐÐÎÿ¥Í§ÒˋýÒ´¥Ò´ÐÌÌËÐÐÓÓÝдЈÐÐдÐ₤ÐÐÈÐÎÐÿ¥ÍÛÂÒΰÓð¤Ì
Ðð¤ÓËÐÐÎÐÐÒ
ÐÏÐÐЯÍ₤ҧЈÒͧÐð£Í
ËÐÐ̧ÒÝÀÓЈÍÝÕ¤ÌÏÐÐÐð£Ëð¡ÿ¥ÍÛÂÒΰÓð¤Ì
ШÍ
ñð§ÓШӘÎÍÐÐÐдРÐÐÏÓÇÐÀШӡÓÓƒÐÐÒ´¥Ì ÐÌÌËÐÐУÐˋШЃÐÏÕ¨Ðð¢ÀÓ´ÌÏÐÒˆÐÐÐдЈÐˋÐÏÐÐÐÐÛÐÏÐ₤ЈÐÐÐÐÐÎÿ¥ÐÐШÿ¥ÕñÌÕÿ¥Ì₤ÌËÐÛÐÐÐ¨ÓƒÍ ÇШÐÐÿ¥ðƒÒ¢¯Ð¨Í
ñð§ÌÏÐÍ
ñÍÐÐÐÐдÐÐÏÐÐÓ¯ÍÂШÐÐÒ
ÐÛðƒÒ¢¯ÐÏÐÐЯÿ¥ÐˆÐÐÐÐÏÐÐÐ
ÐÐЯÐÐÐÿ¥Ó¿Ð¨Ì˜ð£ÑÐÏÐ₤ÿ¥ÌÇÒÀÒÀÓ¤ÐÛÌÓÀÐð¤Ó¿Ð´ÐˆÐÈÐÎÐЈÐÐÿ¥Í
ñð§ÓЈÌÇÒÀШÐÐÓÒñÀÓÙÐÛÍÛÂÒΰÓð¤ÍÛÐÒˆÐÐШÒÑ°ÐÐÒ´¥Ì ÐЈÐÿ¥Ó¿ÍÛÐÛÌÇÒÀÒÀÓ¤ÐÛÓÛÌÒ
дÒ¨ÍÓ¤Ò
ÐÛÓ¡ð¤Ð¨ÓÓƒÐÐðƒÒ¢¯ÐÍÙÐÐÐÛТÐÏÐÐÐ
Í ÐÐÎÿ¥Ò´ÇÒ´Ò°Ìð£Ëð¡Ð¨Í¤Ó₤ЈҴ¥Ì Ò°ÌШÍÑÓÇЈÐÓÇÌËÌËÐÐÐдÐÐÏÐÐÌÙÍ¿Í¡ÐÐÍÍËÐÛÍ
ñð§Óð¤ðƒÐ¨ÐÊÐÐÎÿ¥ÒÀÓ¤Ò
ÐÐÐÛÒÀÓ¤ÐÒ´¥Ì ÓÙШÐÐÓ¿ÍÛÐÐШÐ₤Ò°ÐЈÐÐÈÐÐдÍÊÌÙÐÐÎÐÐÐÛÐÏÐÐÐ
ÐÐÛÐÐЈÕÂÕÈÒ´¥Ì ÐÛÓÑ̰ШÐÐÐÎÿ¥ð¡£ÒÎð¤ÍÛШÕÂÐÐÒ´¥Ò´ÐÛÒ´¥ÌÍÐÐÐÐÐÒˆÐÐÐдÐ₤ÿ¥ÍÝÕ¤ÐÏÐÐÈÐÎÿ¥ÓÛÌÒ´¥Ò´Ð¨ÐÊÐÐÎÿ¥Ó¿Ð¨Ì
ÕЈÍÍ°ÐÐÐÐдÐÍ¢
ÒÎдЈÐÐ
ð¡Ò´Ì§ÒÝÀÓÍÝÕ¤ÐÌÌÙÐÐÐÐÍÎÍÛÐÐð§ÐÐЈÐÕÐÿ¥ÓÛÌÒ´¥Ò´ÐÍ₤ð¡ÐÛÒ´¥Ì дÐÐÎÓÇÐÀШÌÇÒÀÐÛð¤ÍÛÐÒˆÍÛÐÐÐÐÐÛÒ°ÌдÐÐÎÓ´ÐÐÐдÐ₤ÐÏÐЈÐÐ
ÐÐÐШÿ¥ÐÐð£ËÍÊÐÛÒ̓
ÐÛð¤ÍÛШð¢ÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛÓÛÌðƒÒ¢¯Ð₤ÿ¥ð¡Òý¨ÐÐÎÐÐÐÿ¥ÐÐÛÓ¿ÐÏÿ¥Ò̓
ÐÛð¤ÍÛ(1)Шð¢ÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛÓÛÌðƒÒ¢¯Ð₤ÐдÐÐÿ¥ð£ÐÛÒ̓
ÐÛð¤ÍÛШð¢ÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛÍðƒÒ¢¯ÐÛÍ
ÍÛ¿Ðÿ¥Í
´ð§Ð´ÐÐÎð¢ÀÓ´ÐÏÐЈÐÐÐÛдÐÐÐÐÐ̓ЈÐÐ
Í ÐÐÎÿ¥ÍÍ₤ˋÐÛÍÊÌÙÐ₤ÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ð£ËÍÊÐÛÓÛÌðƒÒ¢¯Ð¨ÐÊÐÐÎÿ¥ÍÌÏÐÛÌÀÒ´¥Ì°ÍÕÍÿ¥ÐÐÐÐ₤ÿ¥ðƒÒ¢¯ÐÛÓƒÐÌ¿ÿ¥ðƒÒ¢¯ÐÛ̧ÒÝÀÌÏÿ¥ð¥ÒÌÏÓÙШÕ
Ì
ÛÐЈÐÌÀÒ´¥Ì°ÍÕÍÐÐÐÐ
ÿ¥ÐÍÍ₤ˋÐÓ˜˜ð¡Í₤ˋÍÊÌݤШð£Ò´ÐÐÎÍ ÐÐÍÊÌÙШÐÊÐÐÎ
ÍÍ₤ˋÐ₤ÿ¥Ó˜˜ð¡Í₤ˋÍÊÌݤÐÍ¥Ó´ÐÐУÐÿ¥ÍÍÊÌݤÐð¤ÍÛÍаÓÓÝÐ̘ÐÛÐÓ˜˜ÿ¥ÐͧÒÈÍÊÌÐÛÍÊÌÙÐÐÛÿ¥ÿ¥ÍÍÊÌݤÿ¥Õ ÿ¥ÿ¥ÐÏÿ¥ÐÐШð£Ò´ÐÐдÐÐÎÒˆ˜ÓʤÐÍ ÐÐÎÐÐÐ
ÐÐÐЈÐÐÿ¥ÐÐÐÐÿ¥Ì₤ÒˆÐÐÐдÐÐÏÐЈÐÐÐÐÛÓÓÝÐ₤ÿ¥Ì˜ÀÐÛдÐÐÐÏÐÐÐ
(1)ÐÍÐÂÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛÓÛÌðƒÒ¢¯ÐÛð¢ÀÓ´ÌÏÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎ
ÐÂÐÍ(ÿ§Ý)ÿ¥Í
ËÌÒ
ÐÛÒ¤¨ð§ð¡ÐÛÓÒñÀÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎ
ÍÍ₤ˋÐ₤ÿ¥ÐÌÇÒÀÐÛð¤ÍÛШÐÊÐÿ¥ð¢ÀÓ´ÐпÐÓÛÌðƒÒ¢¯ÓÙÐÍÙÍ´ÐÐЯÿ¥Ò¤¨ð§Ð¨ÐÐÛÓÒñÀÐЈÐÐдÐÛТÐÐÐÈÐÎÿ¥ð¡Ò´ÌÇÒÀÐÛð¤ÍÛÐÍÎÍÛÐÐÐÐддЈÐÐÐÛÐÏÐ₤ЈÐÐÐд҈˜ÓʤÐÐÐ
ÐÐÐÿ¥Ó°Ó¨ð¤¤Ð₤ÿ¥ÐÐÐÐÐÐÛÐÐЈð¡£Í¥çÐ₤ÐÐÎÐЈÐÐÍÍ₤ˋШÐÐÐÎÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿5ÐÐÿ¥ÍÌÏШӰӨð¤¤ÐÛð¡£Í¥çÐÒˆÊÐÈÐÎÓÒÏÈÐÐÎÐÐÐÐÐÏÐÐÐÛÐÏÿ¥Ó°Ó¨ð¤¤Ð₤ÿ¥ÐÐÛÓ¿ÐÌÓ¤ШÌÙÈÐÐÎÐÐÐдÐÐÐÏÐÐÈÐÎÿ¥Í¿°Ìÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥ÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËð£Ð̤ÍÌ¡ÕÂÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐÐШÐÐÐÐÐÐÿ¥ÌÂÐÐÎð¡Ò´Òˆ˜ÓʤÐÍ ÐÐÍÍ₤ˋÐÛÒÐÐÿ¥Ó°Ó¨ð¤¤Ð¨Ð₤Í
´ÐÓÒÏÈÐÏÐЈÐÐ
ÐЈÐÐÀÿ¥ÿ¥ÂÐÛÒÀÐÈÐÌÇÒÀÐÛÍ̯УӴͤÎШÐÊÐÐÎÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛðƒÒ¢¯Í
ÍÛ¿Ð₤ÍÊÕñÐÐÐÿ¥Ó˜˜ÿ¥Í₤ˋÍÊÌݤÐÏÌÏÐÓÛШ҈ÍÛÐÐÐÍ̯УӴͤÎÐÏÐÐÈÐÎÐÿ¥ÐÐШҰÐЯÿ¥Ò¤¨ð§ÓÓÒñÀÐÐÐÒÓÑÌÏÐÕ¨ÐÐ₤ÐÐÏÐÐÐÿ¥ÐÐÐÍÙÍ´ÐÐÎÐЈÐð£Ëð¡ÿ¥ÍÛÂÒΰÓЈҴ¥Ì ÐЈÐð¡ÙÐÏÓÛÌðƒÒ¢¯Ð ÐÐÌ ¿Ì дÐÐÎÌÇÒÀÒÀÓ¤ÐÒˆÍÛÐÐÐдÐÐÐÛÐÏÐÐЯÿ¥ÓÛÌðƒÒ¢¯ÐÛð¢ÀÓ´ÌÏÐÛÓ¤ÍÛÌÏÐÌÝÐÐÐÐдÐÐЈÐÐЯЈÐЈÐдÐÐÿ¥Í§ÓÑÐÛÐдÐÒ¢¯Ð¿ÐÐ ÐÐÛÐдÐÏÐÐÐ
ÐÊÐÍ(ÿ§ý)ÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛðƒÒ¢¯Í
ÍÛ¿ÐÛÍ
ñð§ÌÏÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎ
ÍÍ₤ˋÐ₤ÿ¥ÐÌÏÒ´Çð¤¤ÐÛð¡£Í¥çÐ₤ÿ¥Ò¨ÌÏÒ´Çð¤¤ÿ¥¿1ÐÒͧÐÛð¤ÍÛÐÌÓÇÂÐÐÍÌˋÐÐÐÈÐÍ ÇÍШÍÎËͧÐÐð¡£Í¥çÐÏÐÐÿ¥Ð´Òˆ˜ÓʤÐÐÐ
ÐÐÐЈÐÐÿ¥ðƒÒ¢¯Í
ÍÛ¿ÐÛÍ
ñð§ÓÐÏÐÐÐдÐÿ¥ÐÐÛðƒÒ¢¯Ð¨Õ¨Ðð¢ÀÓ´ÌÏÐð¡ÐÐÐдÐÐÏÐÐÐÐˋÐÐÍÊÌÙÐ₤ÿ¥ðƒÒ¢¯Í
ÍÛ¿ÐÛÍ
ñð§ÌÏÐ₤ÿ¥ð¡Ò˜Ð¨ÐÐÛð¢ÀÓ´ÌÏÐÕ¨ÐÐдÐÐÐдÐÐ̓ÍÐÍ¢çÕ ÙШÐÐÎÿ¥Ð´ÐÐÐÐÍ
ÍÛ¿Òˆð§ÐÛÓÍÛÌÏÐÐÕÂÐÐÎÒΰÍ₤Ðÿ¥ÐÐÛðƒÒ¢¯ÐÛͧÂÌ
УÌÏÒ°ˆÐÍÍ°ÐÐÐÐÙУпÐÏÐÐÐÐÿ¥ÐˋÐÛÓ¿ÐÏÍ
ñð§ÓЈÐÛÐÿ¥ÐÐÛÍ
ñð§ÌÏÐͧÒˋýðƒÒ¢¯Ò
дÐÛÕÂð¢ÐÏÐˋÐÛÐÐЈÌÍ°ÐÌÐÊÐÐÛЈÐÛÐÐÓ¤҈ÐÐÐдÐ₤ÕÒÎÐÏÐÐÿ¥ð¡ÍÛÐÛÍÌˋÐÛÌÓÀдÐ₤ÍËИÐШÐÏÌÊÒ´ÐÐÐдÐÐÏÐÿ¥ÐÐÒˆð§ÌÓЈÌÒÕÓ´ÐÏÐÐÐ
Ó°Ó¨ð¤¤ÐÛð¡£Í¥çÐÿ¥ÍÍ₤ˋÐÒˆ˜ÓʤÐÐÐÐЈÍÌˋÐÐÐÍ ÇÍШÕÍÛÐÐÐÛÐ₤ÍÊÝͧÐÏÐÐÿ¥ÐˆÐÿ¥ÍƒÒ´ÐÛдÐÐÿ¥ÐÒ¨ÌÏÒ´Çð¤¤ÿ¥¿1ШÐÐÐÎÐдÐÐÒͧÐÛð¤ÍÛÐÒ¢¯Ð¿ÐÍÌˋÐÒÎͤÐÕÈÐÐдÌÙÍÛÐÐÓ¿ÐÒˆÊÐÈÐÍÊÌÙÐÏÐÐÐÿ¥Ð
ÐЈÐÐÀÿ¥Ó°Ó¨ð¤¤ÐÛÐÐÛð¡£Í¥çÒˆð§Ð₤ÿ¥ÐдÐÐÿ¥ðƒÒ¢¯Ð¨ÓƒÐÐÍ
ÍÛ¿ÐÍçð§Ð̓ÐÓ¨Í ÇШÐÐÐÐÿ¥ÓÇÐÀШӃШÍçð§ÐÐдÐÿ¥ÐÐÛÍ₤Ò§ÌÏÐÍ
ñð§ÓШ̰ÍÛÐÏÐÐдÐÐÐÐÛÐÏÐ₤ЈÐÿ¥ÓƒÐ¨Íçð§ÐÐÐÛÐÿ¥ÐÐÛÍ
ñð§ÓЈÍÝÕ¤ÐÐÐÐÐˋÐÐÐÛÌÊÒ´Ð₤ÿ¥ÍƒÒ´ÐÎÿ¥Ð´ÐÏÒ¢¯Ð¿ÐдÐÐÿ¥ÍËÐÛÒÎÓ¿ÐÐÍ
ñð§ÓШÒÀÐÐÐпÐÐÐÛÐÏÐÐÐÿ¥ÐÓ°Ó¨ð¤¤Ð₤ÿ¥ÐÐÛÐÐÐˆÓ¨Í ÇШ̧ÒÝÀÓЈÍÝÕ¤ÌÏÐÐÐÍ ÇÍШÿ¥Ì
ÕÐÏÐÐпÐÐдÐð¡£Í¥çÐÐÎÐÐÐÛÐÏÐÐÐ
ÐЈÐÐÀÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1Ð₤ÿ¥Í¿°Ìÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥ÌÌÀÓ´ÐÐÿ¥ÐÐð£ËÕÿ§ÿ¥ÕÐÏÍÊÍÐÿ¥ÐÐÛЃЃӃʹШҰÐÈÐÎÐÐÐÛÐÏÐÐÈÐÎÿ¥ð¿ÿ¥Âÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÊÐÍ
ËÍÛÊÐÐÎÐÐÿ¥ÿ¥ÿ¥ÍñÍÛÊÍ
Õ´ÐÛÌÏÕ Ð£ÌÏÌÐ₤ÐдÐÐÿ¥ÿ§ÐÛÍ£¤ÓˋÍ
´ð§ÿ¥ð¿ÿ¥Âÿ¥ÐÛÿ¥Ð£ÿ¥ÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎÐÓÓËÐÐÎÐÐЯÐÐÐÿ¥ÐÐÊÐÏÐð§Í¤ÎÐÏÐÿ¥ÓƒÍ ÇШÒçÇÐÐÎÓÑÌ°ÐÓ¤҈ÐÏÐÐÓ¨Í ÇШÐÐÿ¥ÐдÐÒ̓
ÐÛð¤ÍÛ(1)ÐÓÛÌÐÐÎÐЈÐÐÈÐдÐÐÎÐÿ¥Ì¤ð¡ÐÐÐÐ₤Óˋ¤Ì°ÐÛð¡ÙÐÏÿ¥Í
ñð§ÓШÍÓÌÏÐÐÐÈÐÍ ÇÕÂÐÍçð§ÌÏÌÐÐÐдÐÍ₤Ò§ÐˆÓ¨Í ÇШÐÐÐ
ЃÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1Ð₤ÿ¥Ò̓
ÐÛð¤ÍÛ(1)ÐÓÛÌÐÐдÐÐÌËÐÐÒ¨Í̘ð¤¤Í¯ÍÐÍÛ̧ÐÐÐЃÐÏÿ¥Í¿ÇÍÐÛÕÿ¥Í¿°Ìÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÐÛÓˆÓçÐÓÛÍÐШÿ¥ÐÕˋÐÐÛÍÛÌ
Í£ð¡Í¥ÐÐÐÍÐÌÇÒ´Òð¤¤ÐХРÐÏÐÍ¿ÇÍ₤ÐÐÒ̓
ÿ§Ëÿ§Ëÿ§Ëð£ÌËÐÍ₤ÍÛÊÐÏÌýÕ°ÇÐÐдÐÐУаУХÐñÐÏÐШЈÕÀÍÐÛÓ¿ÕЈÐˋÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐÐÐÊÐÐÛÐИÐÓˆÓçШ̥ͤÐÐÎÒˋÝÐÐÐÎÐÐУÐÿ¥ÓçÍÌÇ£ÍдÐÐÎÿ¥ÍÊ̯ÐÛÒÇÒÀÐÛÍÐÏÿ¥ÓÛÌÐÐдÐÐÍ
ÍÛ¿ÐÓ¿¯ÐÒ¢ÐÓ¤ÒÀ´ÐÐÌˋð¥Ð̓ÐÎÐÐÐÛÐÏÐÐÈÐÎÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÌÍ°ÓÐÏÐÐÐÿ¥ÓÀÌÒÙÐÏÐÐÐÐ₤дÐÐÐÿ¥ÕÐÛЈÐÍ
ñð§ÓЈÐÊÐÀХСÐͧÂÌÐÐÐÎÐÐÈÐÎÐð¡ÌÒÙ¯ÐÏÐ₤ЈÐÐ
ð£Ëð¡ÐÛдÐÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1Ð₤ÿ¥ÿ§ÐÏÓ´¥ÍÐÐÎÐÐÿ¥ÐÐÊÐÏÐÓƒÍ ÇШÒçÇÐÐÓ¨Í ÇШÐÐÈÐÐÐ´Ð¨Í Ðÿ¥Ò̓
ÍÕÀШÐÊÐÐÎÓ¤ÒÀ´Ð£Í ÝÍÐÐЈÐˋÐÛÌÇ£ÍÐÐÐÎÐÐÿ¥ðƒÒ¢¯ÐпÐÍ
ÍÛ¿ÐÒÈÍ¥ñУÍÂÍ¥ñÐÏÐÐÓÑ̰ШÐÐÈÐÐÐÐÛÐÐÐˆÓ¨Í ÇШÐÐÐÐдÐÐÈÐÎÓÇÐÀШðƒÒ¢¯ÐÍçð§ÐÒÌÏÐÏÐÐдÐÐÎð¢ÀÓ´ÌÏÐÍÎÍÛÐÐÐÐÐÛÐÏÐ₤ЈÐÐдÐ₤ͧÓÑÐÏÐÐÐÿ¥ÍÛÂÒΰÓð¤Ì
Ðð¤ÓËÐÐÎÐÐð¡Ò˜Ð¨ÐÐÛÐÐÐˆÓ¨Í ÇШÐÐÒ
ШÐ₤ÿ¥ÍÛÂÒΰÓð¤Ì
ШӘÎÍÐÐÐðƒÒ¢¯ÐÐÐÐдÐÐÏÐÿ¥ð¤ÍÛð¡ÒͧÐÌññÍ
ËÐÐ̧ÒÝÀÓÍÝÕ¤ÌÏÐÐÐÐдÐ₤ÍÎÍÛÐÏÐЈÐÐ
ðƒÒ¢¯ÐÛð¢ÀÓ´ÌÏÐÒˋðƒÀÐÐÐÐÐÏÿ¥ðƒÒ¢¯ÐÛÍ
ñð§ÌÏÐ₤ÿ¥ð¡Ò˜Ð¨Ð₤ÐÐÛð¢ÀÓ´ÌÏÐÒÈÍ¥ñÐÐÐÐШÌˋÒ§ÐÐдÐÐÎÐÿ¥ð¡Ò´ÐÛÐÐЈӡÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛÿ§ÐÏÐÛÓ´¥ÍÓÑÌ°ÿ¥Ò̓
ÍÕÀШð¢ÐÌÇ£ÍÓÑ̰ШÓ
ÏÐÐдÿ¥ðƒÒ¢¯ÐÛÍ
ñð§ÌÏÐÓʤÐÐÐÛдÐÐÎÓ˜˜ð¡Í₤ˋÍÊÌݤШÐÐÐÎÍÐð¡ÐÐÐÐÍð¤Ì
Ð₤ÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛðƒÒ¢¯ÐÛð¢ÀÓ´ÌÏÐÒÈÍ¥ñÐÐÐÐÛÐÏÐ₤ЈÐÿ¥ÐÐÐ ÐÐÏÿ¥Ó¡ð¤Ð¨ÓÓƒÐÐðƒÒ¢¯ÐÌÌËÐÏÐÐУÐˋШըÐð¢ÀÓ´ÌÏÐÒˆÐÐÐдÐ₤ÐÏÐЈÐÐ
ÐÎÐÍ(ÿ§°)ÿ¥Ò̓
ÐÛð¤ÍÛ(1)Шð¢ÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛðƒÒ¢¯Í
ÍÛ¿Ðð¤Ò£Âð¡Ò£ÂÐÐÎÐÐÐдÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎ
ÍÍ₤ˋÐ₤ÿ¥Ò̓
ÐÛð¤ÍÛ(1)ÿ¥ÿ¥ÊСÐÛÌÇÒÀÿ¥Ð¨ð¢ÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛðƒÒ¢¯Í
ÍÛ¿Ðÿ¥ÐÐÛÌÐ
ÐÏð¤Ò£Âð¡Ò£ÂÐÐÎÐÐÌ´ÐÛÓ°Ó¨ð¤¤ÐÛð¡£Í¥çÐÌÌËÐÐÎÐÐÐÿ¥ÐÐÛÓÓÝÐ₤ÿ¥ÓçÍÝÐÛдÐÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛðƒÒ¢¯ÐÍ
´ÕÂÓШÌÀÓ´ÐÐÎÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛðƒÒ¢¯Í
ÍۿШð¢ÀÓ´ÌÏÐÍÎÍÛÐÐÐӴͤÎÐÛÕÈÐÕÐÐ₤ЈÐдÐÐÐÐÛÐÏÐÐÈÐÎÿ¥ÍÊÝͧÐÏÐÐÐ
Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛðƒÒ¢¯Í
ÍÛ¿ÐÛÿ¥ÐÐÛÌÐ
ÐÏÐÛÕÈÐÕÐÐ₤ÿ¥Ì˜ÀÐÛдÐÐÿ¥ÍðƒÒ¢¯ÐÛð¢ÀÓ´ÌÏÐÒˋðƒÀÐÐШÐÐÐÈÐÎÒ£§ÒÎÐÏÐЈÐÐÐÛдÐÐЈÐÐЯЈÐЈÐÐ
ÿ§ÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1Ðÿ¥ÍÐÐÎÿ¥Í¿°Ìÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥Ìÿ¥ÌËÿ¥ÿ¥À̧ҴÙÕñШҢ¯Ð¿ÐÐÛÐ₤ÿ¥Ðÿ¥ÂÐÐÐÿ¥ÍˋÓ´Ò
ÐÛÒ
ÐÍ¥ÐÈÍ¥çÐÈÐÎÐÐÐÐÐÍ¥ÐÐÐҧдÐÐдÐÐÎÐÐÐÛÐÒÎÐÐÿ¥ÂÐÐÐÐ₤ÐШÐÐÎУÐÐÐÐÐÕ ÙÐÐҧдÐÐдÐÐÎÐÐÐÿ¥ÍˋÓ´Ò
Ð₤Òˆ¯ÐÒ´ÐЈÐÐÐÐдÐÐÍ
ÍÛ¿ÐÏÐÐÈÐÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐÛÿ¥Õ ÿ¥Ð
дÐÐÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛÌ̡ШÐ₤ÿ¥Ðÿ¥ÂÐÐÿ¥ÍÊÍÊÍ¡₤ÌÌ°Ìÿ¥ÿ¥Ê̯ÐÛÕ ÙÐð§Í¤ÎÐÍˋÐÿ¥ÌÕ°ÇÐÓÙÌÇÍÐÐЃÐÐÐÐдҴҥÐÐÐÎÐÐÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÌÇÒÀÐÛÌ
ÌÏÐÍ
´ÐӯЈÐÐÐÛÐÏÐÐÈÐÐ
ÐÐÐÎÿ¥ÐÍ¿°Ìÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËШÒÀÐÐÐÍð¤¤ÕÂҨШÐÐÐÎÿ¥Ò¨Íÿ¥¿1Ð₤ÿ¥ð§ÍÍˋÐÐÐÐ₤ð¡ÌдҢ¯Ð¿ÐÐдÐÒˆÐÐÐÐÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥Ðÿ¥Ó˜˜ð¡Í₤ˋÍÊÌݤÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÿ¥ÒÀÓÛÐÐÿ¥ÿ¥ÒÀÓÛÿ¥ÐÐЈÐÐÀÿ¥Ó°Ó¨ð¤¤ÐÍÛ̧ÐÐÍð¤¤ÕÂÒ¨ÐÛÓçÌÐÕÓÇÐÐÒ°Ìÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐÛÒçÊð£ÍÓ´ÓÇÐÛ̓ÐÛÿ¥ÿ¥ÐˆÐÐÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥Ð¨ÐÐˋÐÛð§ÿ¥ð§ÍÍˋÐÐÐÐ₤ð¡Ìÿ¥ÿ¥ÿ§ÿ¥ÍУÿ¥ÿ§ÿ¥Íÿ¥Ðÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐÛÒçÊð£ÍÓ´ÓÇÐÛ̓ÐÛÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÿ¥ÐÍ₤̧ҴÙÕñШÍ₤ƒÐÐÎÿ¥ÿ¥ÂCWÐÿ¥Ê̯ÐÛÕ ÙÐÍˋÐÐÛÐÒÎÐÐÿ¥ÐˋÐÛð§ÿ¥ð§ÍÍˋÐÐÐÐÐ₤ÐÈÐÐÐЈÐдҢ¯Ð¿ÐÎÐÐÐÐÐÐÏÿ¥Í₤̧ҴÙÕñÐÿ¥ÌÕÐÍ̯ÐͯÐÙÐÎТÐÐÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥Íÿ¥ÿ¥ÍÐÐÿ¥ÍÐÐÐдÌÌÏЈ҈˜ÌÐÛЃЃÓçÐÐÈÐÎÐÐÐÐÛÐÏÐÐÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐÛÒçÊð£ÍÓ´ÓÇÐÛÍÐÛÿ¥Õ ÿ¥Ð
ÿ¥ÈÍ₤̧ҴÙÕñÐÒ¢¯Ð¿ÐдÐÐÿ¥ÐÐÐÛ̓ÐÛÕÂÒ¨ÐÏÐ₤ÿ¥ÿ¥¿1CWÐ₤ÿ¥ÍˋÐÐÌÕÿ¥Í̯ÐЃÐÀЃÐÀÐÏÿ¥ÐÐÛէͤÎÕÐÈÐÎÐЃÐÐÐÿ¥ÐÐÌÐ₤ÿ¥ÿ§ÿ¥Íÿ¥ÐÐÌÐ₤ÿ¥ÿ¥Ýð¤ÍÍÝÕñÐÛÕÂÒ¨ÿ¥ÿ¥ÿ¥Íÿ¥ÐÐÌÐ₤ÌÕÐÒ´ÐÈÐÎÐЈÐÐÛÐÏÍÐÐЈÐÿ¥Ðÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐÛÿ¥Õ ÿ¥Ð´ÿ¥ÌÕÿ¥Í̯ЈÐˋÌÇÒÀÐÛӴͤÎШÕÂÐÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛðƒÒ¢¯Ð₤ÿ¥ð¤Ò£Âð¡Ò£ÂÐÐÎÐÐÈÐÐ
Í¿°Ìÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÐÛÿ§Ì¯ÒÌÍШÌýÒ¥ÐÐÐ̘ð£ÑÒ´ð¤ÿ¥Ð¨Ð₤ÿ¥Ðð§ÍÓ¤ÐÐÐÐÓÑÐÐÐÐдҴҥÐÐÐÎÐÐÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿6дÐÐÎÐ₤ÍÒ´ð¤ÐÍñÓÙÐÐШͧÐÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛÓÛÌðƒÒ¢¯Ð¨Í
´ÕÂÓШðƒÌ ÐÐУÐЈÐÐдÐÐÐÐÎÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1Ð₤ÿ¥ÐÐÛдÐÐÒ¢¯Ð¿ÐÐÐÛдÒÐÐÐÐÿ¥ÿ¥¿1Òˆ¢Ì¡ÿ¥ÍÍ₤ˋÿ¥ÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÒÀÓÛÐÐÿ¥ÿ¥ÒÀÓÛÿ¥ÐÐÐÐÎÿ¥ÐÒ¨Íÿ¥¿6Ð₤ÿ¥Í¿°Ìÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÐÐÿ¥Ò¨Íÿ¥¿1ÍаÒ¨Íÿ¥¿1ÐÍÌÐÿ¥Ò̓
ÒÀӤШÐÊÐÐÎÿ¥Í ÍÛ°Ò
ÍаÒ¨ÍÛ°Ò
ÿ¥ÌÇÒÀÐÛÌ
ÌÏÓÙШÐÊÐÐÎÒˋ°ÓǯШÒˋÝÐÒÐддÐШÿ¥Ò¨Íÿ¥¿1ÍаÒ¨Íÿ¥¿1Ðÿ¥ÍÍ¿Çÿ¥ÌÐÐÐÐÒ´Ò¥ÐÐÎÐÐÒ̓
ÒÀӤШÕÂÐÐÐÀÐÂÐÛÍÐÐÍÐÍÐÈÐÐÿ¥ð¿ÿ¥Àÿ¥ÿ¥Ðÿ¥Ó˜˜ð¡Í₤ˋÍÊÌݤÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÒÀÓÛÐÐÿ¥ÿ¥ÒÀÓÛÿ¥Ð
дÐÐÐÿ¥Ò¨Í̘ð¤¤Í¯ÍШÐÐÐÎÐ₤ÿ¥Ó˜˜ð¡Í₤ˋÐÐÐÛЃЃͥӴÐÐдÐÐÿ¥ÐÍ̯Ð₤Í°Í₤ШÐ₤̯ÐÐÎÐЃÐÐÐÿ¥Ì¯Ó¤ÐÏÐ₤ЈÐÿ¥ÿ¥ÿ¥Ó¤ð£Ëð¡Ð дҴÌÑÐÐÎÐЃÐÐÐдҢ¯Ð¿ÐШҰÐÈÐÐÛÐÏÐÐÐ
ÐÐÐÎÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛÍÍ₤ˋÌ°Í£ñШÐÐÐðƒÒ¢¯Ðÿ¥ÿ¥Í¤ÎÓÛÐÛÌ°Í£ñÐÏÐÐШÐÐÐÐÐÐÿ¥ÌÕÐÍ°ÐÈÐÎÐЈÐÐдÐӃШÿ¥ÌÌÏÐÏÌËçÐÐÎÌÙ₤ÍÐÐ̈ÐÍ
ÍۿдЈÐÈÐÎÐÐÿ¥ÿ¥¿1Òˆ¢Ì¡ÿ¥ÍÍ₤ˋÿ¥ÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÒÀÓÛÐÐÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÿ¥ÒÀÓÛÿ¥Ð
ÿ§ÐÓ˜˜ð¡Í₤ˋÐ₤ÿ¥Ì˜ð£ÑÒ´ð¤ÿ¥ÐÒ´Ò¥ÐÐÐð§ÍÓ¤ÐÐÐÐÓÑÐÐÐдÐÐð¤ÍÛШÐÊÐÐÎÿ¥ð¡Ò´ÐÛдÐÐÿ¥ÐÓÍÐÌÛÐÐдÐÿ¥Ð̘ð£ÑÒ´ð¤ÿ¥ÐÛÒ´Ò¥Ð₤Í¢
ÐÐÐÌÙÈÓ¤ЈÐÐÛдÐ₤ÐÐЈÐÐÿ¥Ó˜˜ð¡Í₤ˋÍÊÌݤÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÿ¥ÒÀÓÛÐÐÿ¥ÿ¥ÒÀÓÛÿ¥Ð´ÐЈÐÐÿ¥ÐͧÒˋýÌÇÒÀШÐÊÐÐÎÐ₤ÿ¥Ðð¡ÍÛÌÕÿ¥Í¯ÐˆÐдÐÿ¥ÿ¥Íð£Ëð¡ÐÐÐÐÐд҈ÐÐÐÐÐдÐÐÎÐÐÐ
ÐÐÐЈÐÐÿ¥ÌÇÒÀÐÛӴͤÎÐ₤ÿ¥Í§ÒˋýÌÇÒÀÒÀÓ¤ÐÛÌÏÌ ¥ÐͤÓÊð£ÐÐ̘ͤÓÒÎÓÇ ÐÏÐÐÈÐÎÿ¥ÓÛÌÐÐÍ ÇÍШÐ₤ӿШͯÒÝÀШÌÛÐÈÐÎÐÐÐпÐð¤Õ
ÐÏÐÐÐÐÿ¥Ò̓
ÐÛð¤ÍÛ(1)ШÐÊÐÐÎÐÛðƒÒ¢¯Ð¨ÐÊÐÐÎÐÛð¡Ò´ÐÛÐÐЈÍÊÕñÐÐÐÐ₤Õ§Õ§˜ÐÒ£§ÒÎÐÐÎÿ¥Ó¡Ûͯ҈ÍÛÐÐЯÒÑ°ÐÐдÐÐÐдÐ₤ÐÏÐÐÿ¥Íð¤ÍÛШð¢ÐðƒÒ¢¯ÐÛð¢ÀÓ´ÌÏÐÐÛÐÐÛÐÓÐÐÐÐÐÛÐÏÐÐдÐÐпÐÐÏÐÐÐ
дÐÍ(ÿ§Ç)ÿ¥Ò̓
ÐÛð¤ÍÛ(2)ÿ¥(4)Шð¢ÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛÐÀÐÂÿ¥ÌÌ¡ÐÛÒ´Ò¥ÿ¥Íð¤¤ÕÂҨШÐÐÐðƒÒ¢¯Í
ÍÛ¿ÐÛÕÈÐÕÐÓÙÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎ
ÍÍ₤ˋÐ₤ÿ¥ÿ¥ËÍаÿ¥ÏСÐÛÒ̓
ÿ¥Ò̓
ÐÛð¤ÍÛ(2)ÿ¥(4)ÿ¥Ð¨ÐÊÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛÐÀÐÂÿ¥ÌÌ¡ÿ¥ÍÍËÕÂÒ¨ÐÏÐÛðƒÒ¢¯Í
ÍÛ¿ÓÙШð¢ÐÓ°Ó¨ð¤¤ÐÛð¡£Í¥çÐÌÌËÐÐÎÐÐÐÐÐÐÿ¥ÐÐÛÒˆ˜ÓʤÐ₤ÿ¥ÓçÍÝÐÛдÐÐÿ¥Í
´ÕÂÓШÌÀÓ´ÐÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛðƒÒ¢¯Í
ÍÛ¿ÐÒÓÑÌÏÐÛÐÐÕ¨ÐЈÐÓçÕ´ÍÐÓ´ÐÐÎÐÐÐÐÛÐÏÐÐÈÐÎÿ¥ÓÓÝÐЈÐÐ
̘ÀÐÛдÐÐÿ¥ÐÀÐÂÿ¥ÌÌ¡ÿ¥ÍÍËÕÂҨШÐÐÐҴҥУðƒÒ¢¯ÐÛÌÓÀÿ¥ÕÈÐÕÐÿ¥ðƒÒ¢¯Í
ÍÛ¿ÓÙÐ₤ÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛðƒÒ¢¯ÐÛð¢ÀÓ´ÌÏÐÒˋðƒÀÐÐШÐÐÐÈÐÎÒ£§ÒÎÐÏÐЈÐÐÐÛдÐÐЈÐÐЯЈÐЈÐÐ
(ÿ§Ý)ÐÒ̓
ÐÛð¤ÍÛ(2)Íа(4)ШÐÊÐÐÎÿ¥Ì˜ð£ÑÓ°Í
ËÌ¡Ìñ£ð£ÐÛÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛÐÀÐÂШͧÒˋýÌÇÒÀШÕÂÐÐÒ´Ò¥ÐЈÐÿ¥ÐƒÐÿ¥Í¿°Ìÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËШÒÀÐÐÐÍð¤¤ÕÂҨШÐÐÐÎÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐͧÒˋýÌÇÒÀШҴÍÐÐÎÐЈÐЯÐÐÐÏЈÐÿ¥Ó°Ó¨ð¤¤ÐÍ¿°Ìÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËШÍÛ̧ÐÐÍð¤¤ÕÂҨШÐÐÐÎÐ₤ÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1Ð₤ÿ¥ÐÐÐÛÿ¥ð£ÑÐ ÐÓÛÌÐÐÎÐÐÿ¥ÐÐÛð£ÐÛÒÀÓ¤Ð₤ð¤¤ð¥ÐÐÏÒÐÐÐдÐÐÐÐÐдҢ¯Ð¿ÐÎÐÐÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐÛÒçÊð£ÍÓ´ÓÇÐÛ̓ÐÛÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥Ð
ЃÐÿ¥ÌÌ¡ÓÛÝШÌͧÐÐÐÿ¥¿1ÐÛÌÌ¡ÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥Ð¨Ð₤ÿ¥Ò̓
ÐÛð¤ÍÛ(1)ÐÛТÐÓÇÌËÓÛÌÐÐÐÐÛдÐÐÎÒ´Ò¥ÐÐÐÎÐÐÿ¥Ò̓
ÐÛð¤ÍÛ(4)Ð₤ÿ¥ÐÐÐÛð£ÿ¥ÿ¥Ï̯ШÐÌÝÐÐдҴÐÈÐÎÌÇÍÐÐÈÐÐÐÐÏÐÐÐдð¥ÒдÐÐÎÒ´Ò¥ÐÐÿ¥Ò̓
ÐÛð¤ÍÛ(2)ШÒˋýͧÐÐÒ´Ò¥Ð₤ЈÐÐ
(ÿ§ý)ÐÍð¤¤ÕÂҨШÐÐÐÎÿ¥Ò̓
ÐÛð¤ÍÛ(2)ÍаÍ(4)ШÐÊÐÐÎÒ´ÍÐЈÐÐÈÐÐдШÐÊÐÐÎÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1Ð₤ÿ¥ÍÍ₤ƒÍ¯ÍШÐÐÐÎÐ₤ÐͧÌÐÛÿ¥ÈÍ₤̧ҴÙÕñдÕÂÒ¨ÐÐдÐШÒˋÝÐÐÐÛÐ₤Ð ÐÐÛð£ÑÐÒ´ÐЃÐÐÐÐÐдÐÐÒ°ˆÍШÍ₤ƒÐÿ¥ÐУÐÐÛð£ÑШÐÊÐÐÎÐ₤ÿ¥ÐÐÐÐÛдÐÿ¥ÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÐÛÌÓ¿ÐÏÿ¥ÒˆÍÐÛÌÌ
ÐÛð¡ÙÐÏÿ¥Ì§Ò´ÙÐÿ¥ÂÐÐÐÛУÐШÿ¥ÒˋÐÌÐÈÐÎÐÐЈдÐÐÿ¥Ðдÿ¥ÐÐÛЃЃÐÐÛÍÕÀÐÐÐÐÐШÐÐÐÎÐЃÐЈÐÈÐÎÐÐ̯ÌÐÀÐдÐÎÐÍ¥ñÐÐÈÐÐÛÐÏÐÿ¥ÐÊÒ´ÐÈÐÎÐÎÐð§ÐÐÐÎÐÐЈÐÿ¥ÐÏÿ¥Ð£ÐШÌÌ¡ÐÐÎÐð¤¤ÐÐÐÐÐÐÐÐÈÐÎÒÐÐÎÐÐÐÛШÿ¥Ì˜ð¤¤ÐÐÐÈÐÎЈÐÐÈÐÎЈÐÈÐÐð§ÐÐÐЈÐдÐÐÍÏ¢ÍÂШÐÊÐÐÎÿ¥ÍÊÏÍÊÐÐ₤Ðÿ¥ÐÐÐÐð£Ëð¡ð§ÐÒ´ÐÈÐÎÐдÐÐ̯ÌÐÀÐ₤ÐÐЃÐÐÐÐдÌÓ¤ШҢ¯Ð¿ÿ¥Í¥ÐÓÑÐÒÈÍÊÕñÐÛÐÐÓÙÐÐÕð¡ÙÐ ÐÈÐÐÐÐÏÐÐÿ¥ÓÑÐÐÎÐÐÈÐÐÐÈÐÎÐÐÐ ÐЃÐÐÐÐÛÒ°ˆÍШÍ₤ƒÐÐÎÐÿ¥Ðÿ¥ÊÐÐÐÛÐдÐÐÒ´ÐÈÐÎЈÐдÐÐÐÛÐ₤ÿ¥Ì¯ÌÐÀÓШÐ₤ÿ¥ÐÐÛдÐШÐÐÿ¥ÐÌÐÐÐÐÐÈÐÎÐÐÐÛÐÏÿ¥ð§ÐÐÐÎÐÐÐЈÐÐРЈдÐÐ̯ÌÐÀÐÍ¥ñÐÐÈÐÐÐÐÏÐÐÐд҈˜ÌÐÐÎÐÐÿ¥ÿ¥¿1Òˆ¢Ì¡ÿ¥Ó˜˜ð¡Í₤ˋÿ¥ÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÿ¥ÒÀÓÛÐÐÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÒÀÓÛÿ¥Ð
ÐÐÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1Ð₤ÿ¥ð¡£Í¯ÍШÐÐÐÎÐ₤ÿ¥Ðÿ¥ð¤¤Ð₤ÿ¥ÐЈÐÐÛÒˋÝÐÒÐÐÎÿ¥ÌÇÍÐ₤ÿ¥ÐÐÐ₤ЈÐÐРдÿ¥ÐЈÐÐÒ´ÐÈÐÎÐÐдÐ₤ÐˋÐÐð¤ÍÛдÿ¥ÍÛÂÒΰÓЈð¤ÍÛÐÿ¥ÐÐÐÐ₤УÐÐÛð¤¤ÐÛÒ´ÐÈÐÎÐð¤ÍÛдÕÐÐРдÿ¥Ð ÐÐÿ¥Ì˜Í§Ð₤ÌÇÍÐ₤ЈÐÐРдÐÐÐÐЈÍ₤ƒÍ¢ÐˆÐÛÐÿ¥ÐÐдÐÿ¥ÐЈÐÐÐÐÈÐÝÐÒ´ÐÈÐÎÐÐдÐ₤ÿ¥ÐÐÐ₤ÐÐÐÐÐÐЈÐÿ¥ÐÐÐð¤ÍÛÐÐÐÐЈÐдÐÐÍ₤ƒÍ¢ÐˆÐÛÐÿ¥ÐÐÛÒƒ¤ÐÛÐÐËÐÂапÐ₤ÐÐдÐÐÒ°ˆÍШÍ₤ƒÐÿ¥ÐÐÐÐÐÐÐЈÐдÐÐÐÐЈÿ¥ÓÏÐÛÒˋÝÐÿ¥ÐÐÐÐÐÐЈÐÐÈÐÎÐÐÐÿ¥ÐÐÐÐÐдÐÐÐÈÐÐРЈдÐÐÐÐШÒÐÐÎÐÐÐдÐÐÐçÐШÓÏÐ₤ÌÐЃÐÐÐÐÐÐÐÛдÐШÐ₤ÿ¥Í₤̧ҴÙÕñÐð¡£ð££ÐÐÀÐÿ¥ÓÏÐÛð£Ì§Ò´ÙÍ
ÐÏÓ§ÛÐÐÐÎÐÐÓ¨Í ÇШÍ₤ƒÐÐÎÿ¥ÍÊÏÍÊÐ ÿ¥Ð¢ÐЈШÍñÐÐÐÐÐÎÐдÐÐÐÐÐÐдÐ₤ÿ¥ÐÐÿ¥ÐÌÐÐÐÐÏÍÐÐÈÐÎÐÐÐÛÐÏÿ¥ÍÊÏÍÊÐ ÐÙдÐÐÐдÐÏÿ¥ÐÐÐÐÍȯÌÐЈÐˋÐÐÐÈÐÐÐШÌÐЃÐÐÐдð¡£ÒΰÓШ͢ÐÐÎÐÐдðƒÒ¢¯ÐÐÎÐÐÿ¥ÿ¥¿1Òˆ¢Ì¡ÿ¥Ó˜˜ð¡Í₤ˋÿ¥ÐÛÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÿ¥ÒÀÓÛЈÐÐÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÿ¥ÒÀÓÛÿ¥Ð
ð¡Ò´ÍÍ₤ƒÍ¯ÍШÐÐÐÒˆ˜ÌÐ₤ÿ¥ð¡Ò´ð¡£Í¯ÍШÐÐÐÍÓÙдÌÇÍÐÐÎÐÐÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1Ðÿ¥ÓÍÛÿ¥Ò̓
ÐÛð¤ÍÛ(2)ÍаÍ(4)ÐÓÛÌÐÐÎÐÐÐÛÐÏÐÐЯÿ¥ÌÂÐÐÎÒ´ÍÐÐÐдÐÌÏÐÐÓÓÝдÐÐÎÐ₤ð¡ÍÍÐÏÐÐдÐÐÐÐÐ̓Ðÿ¥Íƒð£ÐÐÛÓÓÝдÐÐÒÐÐÐЈÐÐ
Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1Ð₤ÿ¥ð¡Ò´ÐÛÐÐШ҈˜ÌÐÐÍð¤¤ÕÂҨШÐÐÐÎÐ₤ÿ¥ÒͧÐÛð¤ÍÛÐÒ¢¯Ð¿ÐÐдШÐÊÐÐÎÿ¥Í¢ÓÓÌçÌÐÐÐÈÐдÐÐÐдÐÍÛ¿ÌШ̴Í₤ÐÐÐдÐÐÏÐÐÐ
(ÿ§°)ÐЃÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛÕ°Ò¢¯Ì¡ÿ¥ð¿ÿ¥Âÿ¥ÿ¥ÿ¥ð¡ÙШÐ₤ÿ¥Ðð¤ÌÀ(2)д(4)ШÐÊÐÐÎÐ₤ÿ¥ÓÛÌÐÐÌËð£ÐÐÐ₤ÐÈÐÐÒÎÐÐÎÐЈÐÐÈÐÐÛÐÏÿ¥ÿ¥ÌÐ₤ÐÐÐÛÌÛçÕÐÏÐ₤ÌÌ¡ÐÐÿ¥Òˋ°ÐÐÒÐÐÐÐдÐÐÐдÌÐÈÐÎÐÐÐÛÐÏÐÐÛÌÐ₤ÒˋÝÐÐÐдÒÐÐÎÐЃÐÐÐÐдÐÛÒ´Ò¥Õ´ÍÐÐÐÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥Ð
ÐÐÐÿ¥ð¡Ò´Òˆ˜ÌШÍÐÐÎÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛÌÌ¡ÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ð¡ÙШÐ₤ÿ¥Ò̓
ÐÛð¤ÍÛ(4)ШÕÂÐÐÎÐÿ¥ÐÐÐÛð£ÿ¥ÿ¥Ï̯ШÐÌÝÐÐдҴÐÈÐÎÌÇÍÐÐÈÐÐÐÐÏÐÐÐдÐÛÒ´Ò¥ÐÐÐÿ¥ð¡Ò´Ð₤ð¡ÍÓЈ҈˜ÌÐÏÐÐÐÌÌ¡Òˆð§Í¢ÍÐÏÓ¨₤ÓñдЈÐÐÛÐÏÐÐÐÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÒˆÒ¤¨ÿ¥Ò̓
ÐÛð¤ÍÛ(1)ШÕÂÐÐÎÐÿ¥ÌÌ¡ð¡ÙÐÏÿ¥ÌËð£ÐÐÓ¿ÍÛÐÐÎÒ´Ò¥ÐÐÎÐÐÐÐÐÏÐ₤ЈÐÐÛÐÏÐÐÐÐÿ¥ÐÐÛÌÓ¿ÐÏÿ¥ÓÍÛÓÛÌÐÐÐÛÐÏÐÐЯÐÐÛдÐÐÒ´Ò¥ÐÐÐÛÐÒˆÓÑÐÏÐÐÿ¥ÍÐÐÌËð£ÐÐÓ¿ÍÛÐÐÎÐЈÐð£ÐÛÒ
ÐÛÓÛÌÿ¥ð¥Òÿ¥Ð ÐÐÒ´Ò¥ÐÐÐдШÍÓÌÏÐ₤ÒˆÐÐÐЈÐдÐÐпÐÐÏÐÐÐ
(2)ÐÍÐÊÿ¥ÿ¥ˋÍаÿ¥ˆÐÛÍðƒÒ¢¯ÐÛð¢ÀÓ´ÌÏÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎ
ÍÍ₤ˋÐ₤ÿ¥ÐÓÎÓȨ̈ҴÙÐÛð¡ÙÐÏÍÍÐÛð£ÒÙñÒñÍÀÐÍ
ËÌÒ
ШÌÇÍÐÌ₤ÐÐÈÐÎÐÐдÐÛð¤ÍÛÐ₤ÿ¥ð£ÒÙñÒñÍÀдÐÐÎÐ₤ÿ¥ÕýÐÐÏÒ´ÐÐдÐÐ₤ЯÐÐÐÐð¤ÍÛÐÏÐÐÿ¥ÒˆÐÐÛðƒÒ¢¯Ð¨Í¤ÐËÐÐÐÛÒñÍÀÐð§ÐÐÐÛÍÎÍÐÍÐÐÐÐÐÐЈÐÐдÐð¤Ì°ÐÐÐð¡ÙÐÏЈÐÐÐð¡Ò´ÍðƒÒ¢¯Ð₤ÿ¥ÐÐÛÒñÍÀШÌÂÐÐÎð¡ÍˋÓÐð¡ÐÐÐÓÓÝÐЈÐð£Ëð¡ÿ¥ÐÐÛð¢ÀÓ´ÌÏÐӡͧӴͤÎÕ¨ÐдÐÐпÐÐÏÐÐÐÐдÐÐÎÿ¥Ì§ÒÝÀÓУð¡Ò˜ÓЈИÐШÐÛÓçÕ´ÍÐÒÌ₤дÐÐÕÀÍÓÍÊÌÙÐÒˆ˜ÓʤÐÐÐдШÐÐÈÐÎÿ¥ÐÐÛӿШð¢ÐÓ°Ó¨ð¤¤ÐÛð¡£Í¥çÐÌÌËÐÐÐ
ÐÐÐЈÐÐÿ¥ð¡Ò´Òˆ˜ÓʤÐÛÕÐÐÏÐ₤ÿ¥ð¡ÍÛÐÛÕÀÍÓÍÊÌÙдÐÐÎÌÙÈÐÐдÐÐÎÐÿ¥ÌÓçÓШÿ¥Íð¤¤ÕÂÒ¨ÐÏÐÛÿ¥ˋÍаÿ¥ˆÐÛÍðƒÒ¢¯ÐÌÀÓ´ÐÐÐÐˋÐÐШÐÊÐÐÎÐ₤ÿ¥Íð¤¤ÕÂÒ¨ÐÛÓÛÓУÌÏÒ°ˆÐ£ÓÑÌ°ÿ¥ÍðƒÒ¢¯ÐÒ´Ò¥ÐÐÐÒ°ÌÐÛÌÏÒ°ˆÐ£ð§ÌÕÓ´ÿ¥ðƒÒ¢¯Ð¨ÐÊÐÐÎÍ
ÍÛ¿ÐÛ̧ÒÝÀÌÏУð¥ÒÌÏÐÒ£§ÒÎÐÐÐдЈÐÓñÍÓШÍÊÌÙÐÐÐпÐÐÐÛÐÏÐÐÐ
ÐÐÐÒΰӿÐÐÐÐдÿ¥Ì˜ÀÐÛдÐÐÿ¥ð¡Ò´ðƒÒ¢¯Ð₤ÿ¥ÐÐÛÌÏÒ°ˆð¡ÕÀÍÓШð¢ÀÓ´ÌÏÐð§ÐдÐÐЈÐÐЯЈÐЈÐÐ
ÐЈÐÐÀÿ¥Ó˜˜ð¡Í₤ˋÐ₤ÿ¥ÿ¥ˋÍаÿ¥ˆÐÛÍðƒÒ¢¯Ðÿ¥Ò̓
ÐÛð¤ÍÛ(2)ÿ¥ÿ¥Ëÿ¥ÐÛÒˆÍÛШÐÐÐÎÓ˜˜ð¡Í₤ˋÍÒ´ÇÍÍÿ¥¿1ÐÛðƒÒ¢¯ÐÒÈÍ¥ñÐÐÐÐÐÛÒ´¥Ì дÐÐÎÿ¥ÿ¥ˋÐÛðƒÒ¢¯ÐÒ̓
ÐÛð¤ÍÛ(3)ÿ¥ÿ¥ÎСÐÛÌÇÒÀÿ¥ÐÒˆÍÛÐÐÍ₤ð¡ÐÛÒ´¥Ì дÐÐÎÐÐÐÐÌÀÓ´ÐÐÎÐÐÐÿ¥Ì˜ÀÐÛдÐÐÓÓÝÐЈÐÐ
ÐÂÐÓ˜˜ð¡Í₤ˋÐÿ¥Ò̓
ÐÛð¤ÍÛ(2)Шð¢Ðÿ¥ˋÍаÿ¥ˆÐÛÍðƒÒ¢¯ÿ¥Ò̓
ÐÛð¤ÍÛ(3)Шð¢Ðÿ¥ˋÐÛðƒÒ¢¯ÐÛÍð¢ÀÓ´ÌÏÐÒˆÐÐÌ ¿Ì Ð₤ÿ¥Ì˜ÀÐÛã ЈÐÐãÂÐÏÐÐÿ¥Ó˜˜ð¡Í₤ˋÍÊÌݤÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÿ¥ÒÀÓÛÐÐÿ¥ÿ¥ÒÀÓÛÿ¥ÿ¥ÿ¥ÒÀÓÛÐÐÿ¥ÿ¥ÒÀÓÛÿ¥Ð
ã ÐÐÿ§Ð¨ÐÐÐÎÍ
ËÍÝ
Ò
ШÍ₤ƒÐÐÌÇÒÀÒÀÓ¤ÐÍÕÀдÐÐÐÎÐÐÌÌÐÛÐÐÛÐÏÐÐÈÐÐдÐ
ãÀÐÐÍÍÒˆÒ¤¨ÐÍÛ̧ÐÐÍ
Õ´Òˆ¢Ì£ÐÏÐÛðƒÒ¢¯ÐÏÐÐÈÐÐдÐ
ãÂÐÐÿ¥ˋÍаÿ¥ˆÐÿ¥ÌÛÌÇÒͧÐÛð¤ÍÛÐÒ¢¯Ð¿ÐÍÌˋÓÙÐ₤ÐÐÐÐÐЈÐÐдÐ
ÐÐÐÎÿ¥ÍÍ₤ˋÐÛð¡Ò´Òˆ˜ÓʤÐÿ¥ð¡Ò´ÐÛдÐÐÿ¥Ó˜˜ð¡Í₤ˋÐÛÐÐÍÊÌÙШÕð¡ÒÑ°ÐÒÈÐÒÀ´ÓƒÐÍÊÐÐÎÒÀÐÐÐÛÐÏÐÐÐÿ¥ÐÐÐÐ₤ÿ¥ð¤¤ÕÒÀÍÐÛÕÀð¥¥ÌÏÿ¥ÐÐÛÒÓÑÌÏШͤÐËÐÓçÕ´ÍÐÍÌдÐÐÐÐÛдÐÐÎÿ¥ð¡Ò´ÐÛÐÐЈð¤Ì
ÐÌ ¿Ì дÐÐÐÐÛд̴Í₤ÐÐÐÐ
ÐÐÐÿ¥Ì§ÒÝÀÓШÿ¥ð¤¤ÕÒÀÍÐÛÕÀð¥¥ÌÏÿ¥ÐÐÛÒÓÑÌÏШͤÐËÐÓçÕ´ÍÐÒˆÐÐÛÐÏÐÐЯÿ¥ÌÙÍ¿Í¡ÐÐÌͯÐÐÐÿ¥ÓÇÐÀШͿ°Ìÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÿ¥ÓƒÍ ÇÐÛÍȯÐÒÐÐÐÐÛÒñÍÀð¥ÒÙ¯ÐÕ͘ÐÐÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥Ò̓
ÍÕÀÐÍÐð¡ÐÐÐÐÎÐÐͧÌÐÛÓÑ̰ШÐÐÐÎÿ¥ÐÐð£ËÕШÐÐÐÎÒ̓
ÒÀӤЃÐÐ₤ð¡ÕˋÍÍÎÕÐÌÂÒÀÐÐÐ₤ÐÐЈÐдÐÐÐдÐÐÐÐÐ₤ÐÐÏÐÐÈÐÎÿ¥Ó˜˜ð¡Í₤ˋÐÌ ¿Ì дÐÐÎÌýÐÐð¤Ì
дÐÛÕШҰˆÓÍñÛÓ¯Ð₤ЈÐÐ
ÐÐÒ
ÐÛÓ₤Ó§ˆÓÒÀӤШÐÊÐÐÎÿ¥ÍÛÂÒΰÓЈÒÈð£ÐÐТÐÐÐЈÐШÐÐÐÐÐÐÿ¥ÓÛÌÒ
ÐÛðƒÒ¢¯ÐÐÍÙÍ´ÐÐÎÐЈÐÐÐЈ̘ð£ÑÐÛÐÐЈÓÑÌ°ð¡Ð¨ÐÐÐÎÐ₤ÿ¥ÌÇШÌ
ÕЈÍÍ°ÐÐЈÐЃЃÿ¥ð¡Ò´ð¤Ì
Ð ÐÐÐÐÈÐÎÍÛÍÓÿ¥ÕÀÍÓÿ¥Í§ÂÍ¥ÓШÍÊÌÙÐÐÎÿ¥ÒÈÍ¥ñÐÐͧ¿ÍýÐÌÐÐÐÐÿ¥ÐÐШÐ₤ÐÐÐ ÐÐÏÒˆÐÐЈÐˋÿ¥Õ¨Ðð¢ÀÓ´ÍÐÌÐÊÒ´¥Ì дÐÐÎÌÀÓ´ÐÐÐÛÐ₤ÿ¥ÌÐÐШÒÀÐÕÐÐÏÐÐÐ
ÐÊÐÿ¥ˋÍаÿ¥ˆÐÛÍðƒÒ¢¯Ðÿ¥ÐÍËÐÛÌˋð¥ÐШÐÊÐÐÎÐÛÐÐÛÐÏÐÐÐдÐ₤ÿ¥Ì˜ð£ÑÓ°Í
ËÌ¡ÐÛÒ´Ò¥ÐÐÌÐÐÐÏÐÐÿ¥ð¿ÿ¥Âÿ¥ÐÛÿ¥(2)ÿ¥ÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÐÐÐÐÐÒˆÐÐÎÐÐÿ¥Ó˜˜ð¡Í₤ˋÍÊÌݤÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÿ¥ÒÀÓÛÿ¥ÐÍð¡ÒñÍÀÐÛÍð¡Í
ËÌÒ
ШÍ₤ƒÐÐÒÀӤдÐ₤ÐÐÿ¥ÐÍËÐÛÌˋð¥ÐÐÛÓÛÌðƒÒ¢¯Ðð¤ÐШÐˋÐÛӴͤÎÒÈÍ¥ñÐÏÐÐÐÛÐÍÊÏÐШÓÍÐÏÐÐÐ
Í ÐÐÎÿ¥ÕÈÍ ÐÏÐÛÕÈð¤Ð¨Ð₤ÿ¥ÍÊ̯ÐÛð£ÒÙñÒñÍÀÐÍÍ ÐÐÐÛШÿ¥ð£ÐÛð£ÒÙñÒñÍÀШÐÐÍð¡Ìˋð¥ÐÛðƒÒ¢¯ÐÍÙÍ´ÐЈÐÐдÐÒ£§ÒÎÐÏÐЈÐð¤Ì
ÐÏÐÐÐ
ÐÎÐÿ¥ˋÍаÿ¥ˆÐÛÍðƒÒ¢¯Ð₤ÿ¥Ì°Í£ñÐÏÐÛðƒÒ¢¯ÐЈÐÐдÐ₤ÐÐÀÐÐÿ¥ÒˆÐÐð§ÌÐÐÕ°Ò¢¯Ì¡ÐÍÙÍ´ÐÐÐÐÐÏÐЈÐÿ¥Ì˜ÀÐÛдÐÐÿ¥ÐÐÐÐÿ¥Ó°Ó¨ð¤¤ÐÍÛ̧ÐÐÍð¤¤ÕÂÒ¨ÐÛÓçÌÐÿ¥ÿ¥ÈÍ₤̧ҴÙÕñÐЃдÐÐÒ°Ìÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐÛÒçÊð£ÍÓ´ÓÇÐÛ̓ÐÛÿ¥ÿ¥ÐˆÐÐÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥Ð¨ÓƒÐÐÐÐÛÐÏÐÐÈÐÎÿ¥ÐÐÛÌÏÒ°ˆð¡ÐÛÒ´¥Ì ðƒÀÍÊÐ₤ð§ÐдÐÐÐÐÐ̓ЈÐÐ
(ÿ§Ý)Ðÿ¥¨ÐÛÕ°Ò¢¯Ì¡ÿ¥ð¿ÿ¥Âÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐÛð¡ÙШÿ¥Ðÿ¥ˆÒñÍÀÐÕÈÍ ÐÏÿ¥ËÐÐÐÛÕ ÙÐÍˋÐÐÛÐÒÎÐÐÿ¥ˋÒñÍÀÐÕÈÍ ÐÏÿ¥ËÐÐÐÛÕ Ùдÿ¥ÎÐÐÐÛÕ ÙÐÍˋÐÐÛÐÒÎÐÐÐдÐÛÒ´Ò¥ÐÐÐÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥Ð
ЃÐÿ¥Ó°Ó¨ð¤¤ÐÍÛ̧ÐÐÍð¤¤ÕÂÒ¨ÐÛÓçÌÐÕÓÇÐÐÒ°ÌÐÛð¡ÙШÿ¥ÿ¥ˋШÐÊÐÐÎÐ₤ÿ¥Ðã Ðÿ¥ÌÕ ÿ¥ÿ¥Âð£ÒÙñÒñÍÀÐÍ
ËÍÝ
Ò
ÿ¥ÿ¥Î̯Уÿ¥Ë̯ÿ¥ÐÐÐÐÐÊÐÏÌÛÇÐÈÐÎÐÐÐÐдҴҥÐÐÿ¥ÒçÊð£ÍÓ´ÓÇÐÛ̓ÐÛÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÿ¥ÿ¥ˆÐ¨ÐÊÐÐÎÐ₤ÿ¥Ðã Ðÿ¥Âð£ÒÙñÒñÍÀÐÌÕÈ̓ҘÐÕÈýЃЈÐÐÈÐÍ
ËÍÝ
Ò
ÿ¥ÿ¥Ë̯ÿ¥ÐÛÕ ÙÐÍˋÐÐÿ¥ÿ¥ÐÑÌð£Ëð¡ÍÐÛÍÊÍÊÌÐÐÛÌÿ¥ÐдÐÐÐÛТÐÏÐÐÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐÛÒçÊð£ÍÓ´ÓÇÐÛ̓ÐÛÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥Ð
(ÿ§ý)ÐÓýÿ¥ÿ¥ÿ¥ð¡ÙÐÛÒ°ÌÐ₤ÿ¥ÒñÍÀÐдШÍÒˆÐÍð¤¤ÕÂÒ¨ÐÏÒ¢¯Ð¿ÐÍ
ÍÛ¿Ðÿ¥Ó¤Ò´ÐÐÍ
ñð§ÌÏÐÐпÐÎÍÌ ÐÐЈÐÐЃдÐÐÐÐÛÐÏÐ₤ÐÐÐÿ¥ÿ¥ÈÒˆ¢Ì¡ÿ¥Õ ÿ¥ÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛðƒÒ¢¯ÐÛÒ´¥Ì ðƒÀÍÊÐÛÍÊÌÙШÐÐÐÎÓ˜˜ð¡Í₤ˋÐÒˆ˜ÓʤÐÐÐÐЈÍ
ñð§ÌÏÐÓ¿ÍÛÌÏÐÐÐÒˆÐÐÐдÐÐÏÐЈÐÐ
ЃÐÿ¥Íð¤¤ÕÂҨШÐ₤ÿ¥ÿ¥ÈÍ₤̧ҴÙÕñÐÐ₤ÿ¥ÐÏÐÐÐ ÐͧÒˋýÒñÍÀÐÛÍÈÐÐÐÐÐÐЈÐдÐÒÐÐдÐÐÎÍÐÓçÐÐÏÐÐÿ¥ÍÒˆ¢Ð¿ÐÛÐÐШÓͧÐÓ¤ÐÐÐÐÐЈÐдÐ₤ÐÐÎÐÐÐÿ¥ÿ¥ÈÒˆ¢Ì¡ÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÿ¥ÐˆÐÐÿ¥ÿ¥ÒÀÓÛÿ¥ÿ¥ÕÓÇÐÐÐÍðƒÒ¢¯Ð₤ÿ¥ð¥ÒðƒÒ¢¯ÐÛЃЃÐÏÐÐÿ¥ÐÐÛÓÍÛÌÏÐÌ
ð¢ÐÐÐÎÐÐÐÐÐÏÐ₤ЈÐÐ
ÐÐÐÿ¥Í¿°Ìÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÐÛÍð¤¤ÕÂÒ¨ÐÛÕÿ¥ÿ¥˜ÐÒ¢¯Ð¿Ðÿ¥ÿ¥Âдÿ¥´Ðð¡ÓñÐÛÕÐÛÍ
ÍÛ¿Ð₤ÿ¥ÐãÀÐÿ¥´ð£ÒÙñÒñÍÀÐÍ
ËÍÝ
Ò
ÿ¥ÿ¥Ï̯ÿ¥Ð¨ÐÌˋÐÒçñÐЈÐÐÐдÕÇÐÏÕ ÙÐÌÛÇÐÐÐÐÛÌÿ¥ÌÙÂÐÐÐÐÒ´ÐÈÐÐÌÙÂÐЈÐÐÈÐÐЃÐÐÐÛÌÿ¥ÿ¥Âð£ÒÙñÒñÍÀÐð¡ÓñШÐÐÐÌÙÂÐÐÐдÐЈÐÐÒçñÐЈÐдÍÊÏÍÊЈÐдШЈÐÐдÍ
ËÍÝ
Ò
ШҴÐÈÐÎÐÐÐ̓ÌËÐЃÐÕÇÐÏÌÛÇÐÈÐдпÐÐ¥ÐñÐÏаÐÏð¥ÒˋÝÐÐÐÎÐÐÐÐÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐÛÒçÊð£ÍÓ´ÓÇÐÛ̓ÐÛÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÐÏÐÐÈÐÎÿ¥ÿ¥ÂШÐÊÐÐÎÐ₤ÌÇÒÀÒÀÓ¤ÐÒ¢¯Ð¿ÐÎÐ₤ÐÐÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1Ðð¥ÒÐÐÿ¥˜ÐÛðƒÒ¢¯Ð´Ð₤ÕÈÐÕÐÐÛÐÏÐÐÈÐÎÿ¥ÐÐÛÐÐÐˆÍ ÇÍÿ¥ð¥ÒðƒÒ¢¯ÐÏÐÐÐ ÐШÿ¥Ó¡Í¢ÐÛÍÍ°ÐÐÐÐÎÐÐÐпÐÐÏÐÐÐ
дÐÿ¥ˋÿ¥ÿ¥ˆÐÛÍðƒÒ¢¯Ð₤ÿ¥ÍÒ´ÐÎÐÛдÐÐÿ¥ÌÏÒ°ˆð¡ÿ¥ÕÀÍÓШð¢ÀÓ´ÌÏÐð§ÐдÐÐпÐдÐÐÿ¥Í¯ÐˆÐдÐÍÒ´ÐÊÐÛÐÐЈÓÍÐÐÐð£Ëð¡ÿ¥ð£Ð¨ÍðƒÒ¢¯ÐÛð¢ÀÓ´ÌÏÐÒÈÍ¥ñÐÐð¤Ì ÐÒˆÐÐÐЈÐÕÐÿ¥ÍÒ´ÐÂÐÏÒ¢¯Ð¿ÐдÐÐÿ¥Ó˜˜ð¡Í₤ˋÐÌÐÀͤÐÐÐÐЈÍÛÍÓÿ¥ÕÀÍÓÿ¥Í§ÂÍ¥ÓЈð¤Ì ШÐÐÈÐÎÿ¥Ò̓ ÐÛð¤ÍÛ(2)ШÕÂÐÐÎÿ¥ÿ¥ˋÍаÿ¥ˆÐÛÍðƒÒ¢¯Ð¨ÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛðƒÒ¢¯ÐÒÈÍ¥ñÐÐͧ¿ÍýÐð¡ÐÐÐÿ¥ÿ¥ˋðƒÒ¢¯Ð¨ÿ¥ÐÐÐ ÐÐÏÓÇÐÀШÒ̓ ÐÛð¤ÍÛ(3)ÐÒˆÐÐУÐˋÐÛÕ¨Ðð¢ÀÓ´ÍÐÒˆÐÐÐдÐ₤ÐÏÐЈÐÐ
(3)ÐÍÐÎÿ¥ÿ¥ÂÐÛÒ´¥Ò´ÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎ
ÍÍ₤ˋÐ₤ÿ¥Ð̘ð£ÑШÐÐÐÎÿ¥Ò¨ÌÏÒ´Çð¤¤ÿ¥¿1Ðÿ¥ÿ¥ÂШÐÐÒ̓
ÒÀÓ¤ÐÓÛÌÐÐдÐÛÒˋ°ÓǯÐÐÊÍ
ñð§ÓЈðƒÒ¢¯ÐÐÐÎÐÐÿ¥ÐÐÐðƒÒ¢¯ÐÒͧРдÐÐЯÿ¥Ò¨ÌÏÒ´Çð¤¤ÿ¥¿1ШÒͧÐÛðƒÒ¢¯ÐÐÐÍÌˋÐÐÐÐ₤ÐÐÏÐÐÐÛШÿ¥ÿ¥ÂШÐÐÐÎÒͧðƒÒ¢¯ÐÛÍÓÓЈÍÌˋÐÌÓʤÐ̓ЈÐÐÈÐÐдÐÐÿ¥Ò¨ÌÏÒ´Çð¤¤ÿ¥¿1ÐÛðƒÒ¢¯Ð₤ð¢ÀÓ´ÐÏÐÐÐдШЈÐÐ ÐÐÏÐÐÐдÿ¥ÐÐÐÐÍͯÓЈÓçÌÐÏÐÐШÕÐЈÐÐÐÛÐÐШ҈˜ÓʤÐÐÐ
ÐÐÐЈÐÐÿ¥ð¡Ò´Òˆ˜ÌÐ₤ÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1дÿ¥ÂдÐÛÍ₤ƒÍ°ÐÌ°ÍÛÐÐÎÿ¥Ðÿ¥ÂШÐÐÐÎÒͧðƒÒ¢¯ÐÛÍÓÓЈÍÌˋÐÌÓʤÐ̓ЈÐÐÈÐÐдÐÐÿ§Ëÿ§Ëÿ§Ëÿ§Ëÿ§Ëÿ§ËÐдÐÐÐÐÛÐÏÐÐÈÐÎÿ¥Òˆ˜ÓʤÒÀ´ÓƒÐ¨ÐÐÐÐÐÿ¥Í¢Ò´¥Í§ÂÌШÐÐÐÎÐ₤ÿ¥ÿ¥ÂÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛÒͧðƒÒ¢¯ÐÛÍÌˋÐÍÓÓШ҈˜ÌÐÏÐЈÐÐÈÐÐд҈ð§Ðÿ¥Ò̓
ÒÀÓ¤ÐÒÀÐÈÐÎÐЈÐдÐÛÿ¥ÂðƒÒ¢¯ÐÛð¢ÀÓ´ÌÏÐÍÎÍÛÐÐÓÓÝдÐÐÎÐÐÐдÐÓˆ¤ÐÐÐÐ
ЈÐÿ¥ÍÍ₤ˋÐ₤ÿ¥Ðÿ¥ÂШÐÐÐÎÒͧðƒÒ¢¯ÐÛÍÓÓЈÍÌˋÐÌÓʤÐ̓ЈÐÐÈÐÐдÌÙÍÛÐÐÐÿ¥ÐÐÛÐÐШҴÐÍÐÐдШÐ₤ÓÍÐÐÐÐ
ÐЈÐÐÀÿ¥Ó˜˜ð¡Í₤ˋÐ₤ÿ¥ÐÒ´¥ð¤¤ÿ¥ÂÐÛÒ´¥Ò´Ð¨ÐÐЯÿ¥Ò¨Íÿ¥¿1дÿ¥ÂÐÐÐÐÐÛÐ₤Í¿°Ìÿ¥ÿ¥Í¿ÇÐÐÐÏÐÐÿ¥ÿ§ÐÏÒñÍÀÐÛÌÇÒÀÒÀÓ¤ÐÛÍÕÀдЈÐÿ¥Í¿ÇÐÍÐÛÐдÐÏÐÐð¡ÿ¥ÐÐð£ËÍÊШÿ¥ÂдÒ¨Íÿ¥¿1дÐð£ýÕÐÐÐÐÐЈÐдÐ₤ЈÐÐÈÐÐдÐÐÐÐЯÿ¥Ò¨Íÿ¥¿1ÐÌÛÌÇÒͧÐÛðƒÒ¢¯ÐÐÐÍÌˋÓÙÐ₤ÒˆÐÕÈÐÐдÐÐÐ
ÐÐÐЈÐÐÿ¥ÌݤÍÛÓЈÍ₤ƒÓ¨Ð̓ШͯƒÐÍ¥ÐдÐÐÐдÐÐÐÐЈÐÐÐÐÏÐ₤ЈÐÿ¥ÿ¥ÂÐÛÒˆ˜ÌÐÍÎÍÛÐÐÐÐдÐ₤ÐÏÐЈÐÐ
Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÒͧðƒÒ¢¯ÐÐÐÍÌˋШÕÂÐÐÿ¥ÂÐÛÒˆ˜ÌÐ₤ÿ¥Ó˜˜ð¡Í₤ˋÐÐÒ¨Íÿ¥¿1дÐ₤ÿ¥ð£ËÍШð¡ÌÐÐÐÐдÐÐÐÐдÒÀ´ÕÂÓШÒÎÓÇÐÐÍ
ÍÛ¿ÿ¥Ó˜˜ð¡Í₤ˋÍÊÌݤÐÛÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥Ð¨Í¯§ÐÐÐÐÛÐÏÐ₤ЈÐÿ¥ÐÐÛÍÛÒ°ˆÐ₤ÿ¥ÿ¥¿1ÐÐÐÛÕ ÒΈÍ₤Шð¤ÊÕÐÐÎÐÐÓ¯ÌÏдÐÛÕÂð¢Ð¨ÕÍÊÏЈͧÝÕ¢Ðð¡ÐÐÐÙЈÐÐдШÕÂÐÐÐÐÛÐÏÐÐÈÐÎÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐÛÿ¥Õ ÿ¥ÿ¥ÍÒ´ÐÛдÐÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛðƒÒ¢¯Ð₤ð¡Òý¨ÌÏÐЈÐÿ¥Í¿°Ìÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÿ¥ÿ¥À̧ҴÙÕñШÒ̓
ÐÛð¤ÍÛ(1)ШÕÂÐÐÍ ÝÍÐÐÐð£ËÕÿ¥ÐдÐдÓÛÌÐÐдÐÐð¤ÍÛШÐÊÐÐÎÐ₤ÌÇÒÀÐÛӴͤÎÐÌ¢ÐÐЈÐÿ¥ÓÛÌÐÐдÐÐÒÀÓ¤ÐÛÓ₤ÍýÐÌÀÍÊÏÐÐÎÐÐÐдШÓ
ÏÐÐдÿ¥Í¯ÐˆÐдÐпТХÐÌÐÛÍÌˋÐÛÒˆ˜ÌдÐÐÎÐ₤ÿ¥ð¡ÍÛÐÛÍÓÌÏÐÒˆÐÐÐдÐÐÏÐÐÐ
ÿ¥ÂÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1Ðÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿3ÐÛð¡Õ´ÍÈð§ÐÏÐÐÿ¥ÿ§ÐÛð£ÒÙñÒñÍÀÐÛÍÊ̯ÐÍ Í
ËÐÐÎÐÐÿ§ÐÎÐЈаÐÛÓçÍÍÀÐÏÐÐÈÐдÐÐÿ¥ð¡ÙÍ¢ÓШÌÇ£ÍÐÐÎÐÐÿ¥ÂÐÿ¥ÍÐÎÐЈаÐÌͯÐÐÎÐÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿3ÐÛÌ¡Ò´ÕñÐÏÐÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿4дÍ₤ƒÓ¨Ðÿ¥ÐÐÐÒÝÕÐÐдÐÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÿ¥ÿ¥˜ÐÕÊÐÿ¥Í Í
ËÐÐÎÐÐУдÐÐˋÐÛÓçÍÍÀÐÿ¥ÂШҢ§ÕÐÐÎÒÝÕÐÐÐдÐÐÐÿ¥Í¯ÐˆÐдÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1дÐÛ̓ÌËÐÐÐÛ̧ʹÓЈÍ₤ƒÓ¨ÐÛÍÙÍ´ÐÓˆ¤ÐÐÐдÐÐÐÏÐÐÐ
Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛÍÌˋÐÒ¨ÐÐШͧÐÐÈÐÎÿ¥ð¡ÍÛÌÌÐÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1Ðÿ¥Ò̓
ÍÕÀШÐÊÐÐÎÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿3ÐÛÌÇ£ÍдÐÐÎÒÀÍÐÐÐдШЈÐÈÐÐдШÓ
ÏÐÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿4ÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿3ÐÛÌÍÐÍ¥ñÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ШÍÐÓÑÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÐÐÐÍÍÛ¿ÐÐÎÐÐÈÐÐдÐÒÌ
ÛÐÐÍ¢
ÒÎÐÐÐÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛÐÂÐÐÐ¥ÐñÐÏаШӡÌÌ¿ÿ¥¿4ÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿3ÐÛͧÝÕ¢ÍÐÍÊÏÐÐÍÐÐÎÐÐÐдÐ₤Ò£§ÒÎÐÏÐЈÐð¤Ì
ÐÏÐÐÐ
(4)ô Íдÿ¥ÌÙÍ¿Í¡ÐÛÒÀÐÈÐÒˆ¢Ì£ÓçÌÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎ
ÍÍ₤ˋÐ₤ÿ¥ÐÌÙÍ¿Í¡ÐÒÀÐÈÐÒˆ¢Ì£ÓçÌÐÿ¥ÐÍÍËÐÛÍ
ñð§ð¤ðƒ(ÐÐ)ШÐÊÐÐÎÿ¥ÒÀÓ¤Ò
ÐÐÐÛÒÀÓ¤ÐÒ´¥Ì ÓÙШÐÐÓ¿ÍÛÐÐШÐ₤Ò°ÐЈÐÐÈÐÐÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐдÐÐÐÐÛÐÐÏÐÐÈÐдÐÐÎÐÿ¥ÐÐÛÐдШÐÐÈÐÎÿ¥Ò´ÇÒ´ÌÓÑШ̓ÐÈÐÎЈÐÐÐ̧ҴÙÐÛð£ÒÙñÒñÍÀÐÛÒ´¥Ò´ÓÙШÐÐÒ̓
ÐÛð¤ÍÛÐÛÒˆÍÛÐÍñÎÍ°ÐÐÐÐÐÛÐÏÐ₤ЈÐÐÐдÐÐÐ
ÐÐÐÿ¥ÌÙÍ¿Í¡ÐÛÒÀÐÈÐÒˆ¢Ì£ÓçÌШÐÊÐÐÎÐ₤ÿ¥Ì˜ÀÐÛÓ¿ÐÓÌÐпÐÐÏÐÐÐ
ÐÂÐÌÙÍ¿Í¡ÐÛÒˆ¢Ì£Í ÝÍÌ¡ÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐÏÐÍÍËÐÛÍ
ñð§Óð¤ðƒÐ¨ÐÊÐÐÎÿ¥ÒÀÓ¤Ò
ÐÐÐÛÒÀÓ¤ÐÒ´¥Ì ÓÙШÐÐÓ¿ÍÛÐÐШÐ₤Ò°ÐЈÐÐÈÐÐдÐÐÐÛÐ₤ÿ¥ÍШ҈¢Ì£ÐÛÓÛÓÐÐÍ¢
ÒÎÐЈÐÐÐÒ´Ò¥ÐЈÐÐÈÐдÐÐÐдÐÏÐ₤ЈÐÐÍÒˆ¢Ì£Í ÝÍ̡ШÐÐÐÎÿ¥Ò´ÇÒ´Ò°Ìð£Ëð¡Ð¨Í¤Ó₤ЈҴ¥Ì Ò°ÌШÍÑÓÇЈÐÓÇÌËÌËÐÐÎÒˆ¢Ì£ÐÍÛ̧ÐÐÌÙÍ¿Í¡Ð₤ÿ¥ÐÐÐÏÐЈÐÿ¥ÐÍÍËÐÛÍ
ñð§Óð¤ðƒÐ¨ÐÊÐÐÎÒÀÓ¤Ò
ÐÐÐÛÒÀÓ¤ÐÒ´¥Ì ÓÙШÐÐÓ¿ÍÛÐÐШÐ₤Ò°ÐЈÐÐÈÐÐдÐÐÍÊÌÙÐÐÛÐÐÛÐÓʤÐÐÎÐÐÐÛÐÏÐÐÐÐЈÐÐÀÿ¥ÐÌÙͿ͡ШӰÍÐÛÐÐÈÐÐÐЈð¤ÍÛÕÂð¢ÐÒˆÐÐÐÐÐÐШÐÊÐÐÎÿ¥ÐÐÐÓ¤҈ÐÐÐÐÏÐЈÐÐÈÐдҢ¯Ð¿ÐÎÐÐÐÛÐÏÐÐÐ
ÍÍ₤ˋÐÛÐÐШÿ¥ÌÙÍ¿Í¡ÐÛÒˆ¢Ì£ÐÛÓÛÓÐÍÎð§Ð¨ÌÐÐÐдÐÿ¥ÌÙÍ¿Í¡Ðÿ¥ÌÙͿ͡ШӰÍÐÛÐÐÈÐÐÐЈð¤ÍÛÕÂð¢Ðÿ¥ÌËÐÐͤÓ₤ЈҴ¥Ì Ò°ÌШÓ
ÏÐÐÐÎÐÒˆÐÐШҰÐЈÐÐÈÐдÍÊÌÙÐÐÐдÐ₤ÌÐÐЈÐдÐÏÐÐÐ
ЃÐÿ¥Í¯ÐˆÐдÐÿ¥ÍÍ₤ˋÐÛÐÐШÓÛÌÒ
ÐÛÒ´¥Ò´ÐÛð¢ÀÓ´ÌÏÐÕ¨ÐÐÌˋÒ§ÐÌÐÐÐÐÛдÐÐÐдÐ₤ÐÏÐЈÐÐÛÐÏÐÐÐ
ÐÊÐÌÙÍ¿Í¡Ð₤ÿ¥Í¿°Ìÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥ÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÍÓÍÏÍÀð¥Ò°ÌÐÏÐÐÐÓ¿ÍËÕÊÒÙñÒð¤¤ÐХРÿ§ÐÛÒˆ¢Ì£ÓçÌШÐÊÐÐÎÐдÕÀÐÐÒ°Ìÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐÌÓʤÐÿ¥Ðÿ¥ÐÒˆ¢Ì£ÓçÌÐдÐÐÎÿ¥ÐÍÍËÐÛÍ
ñð§Óð¤ðƒÐ¨ÐÊÐÐÎÿ¥ÒÀÓ¤Ò
ÐÐÐÛÒÀÓ¤ÐÒ´¥Ì ÓÙШÐÐÓ¿ÍÛÐÐШÐ₤Ò°ÐЈÐÐÈÐÐÿ¥Í§Òˋý̧ҴÙÐÛÒñÍÀÐÍ
ËÌÒ
ÍÛÑÌÐÐÐÛӡ̯ͧÐÛÍ
ñð§ÓЈҴ¥Ò´Ðð£ÒÙñÒ´ÕýЈÐˋͧÒˋý̧ҴÙШÐÐÐÕÂð¢Ì¡ÕÀÐÛÒ´ÕýÓÙÐÐÿ¥Ò̓
ШÐÐÈÐÎÓÐÐÍ₤Ò§ÌÏÐÛÐÐÓçÌÐÒˆÐÐÐÐÐÐÐ´Í ÝÍÐÐÐ
ÐЈÐÐÀÿ¥ÌÙÍ¿Í¡Ð₤Ò´ÇÒ´Ò°Ìð£Ëð¡Ð¨Í¤Ó₤ЈҴ¥Ì Ò°ÌШÍÑÓÇЈÐÓÇÌËÌËÐÐÎÒˆ¢Ì£ÐÍÛ̧ÐÐÐÐÛÐÏÐÐÈÐÎÿ¥ÐÐÐÏÐЈÐÐÍÍËÐÛÍ
ñð§Óð¤ðƒÐ¨ÐÊÐÐÎÿ¥ÒÀÓ¤Ò
ÐÐÐÛÒÀÓ¤ÐÒ´¥Ì ÓÙШÐÐÓ¿ÍÛÐÐШÐ₤Ò°ÐЈÐÐÈÐÐÐÛÐÏÐÐÐ
ÐÐÈдÐÿ¥ÌÙÍ¿Í¡Ð₤ÐͧÒˋý̧ҴÙÐÛÒñÍÀÐÍ
ËÌÒ
ÍÛÑÌÐÐÐÛӡ̯ͧÐÛÍ
ñð§ÓЈҴ¥Ò´Ðð£ÒÙñÒ´ÕýЈÐˋͧÒˋý̧ҴÙШÐÐÐÕÂð¢Ì¡ÕÀÐÛÒ´ÕýÓÙÐÐÿ¥Ò̓
ШÐÐÈÐÎÓÐÐÍ₤Ò§ÌÏÐÛÐÐÓçÌÐÒˆÐÐÐÐÐÐдÐÍ ÝÍÐÐÎÐÐÐÛÐÏÿ¥ÐÐÛӿШÐÊÐÐÎð£Ò´ÐÐÐ
(ÿ§Ý)ÐÌÙÍ¿Í¡Ðÿ¥ÐÒ̓
ШÐÐÈÐÎÓÐÐÍ₤Ò§ÌÏÐÛÐÐÓçÌÐдÒÀ´ÓƒÐÐÐÛÐ₤ÿ¥ÐÐЈÐˋÐÛÒ¤¨ð§ÓÓÒñÀÐÌÐдÒÐÐÐÐÐ
ÐÐÐÿ¥Õ¨Õ§ÂÒ
ÿ¥Ó¿Ð¨ÒˆÓËÓÐÕýÐÐÏÐÐÍ ÇÍÿ¥ÍÐÐÍ
ËÌÐÍÌдÐÐÓ
ÕÂЈÐˋШÌ₤пÐдÿ¥Ò¤¨ð§ÓÓÒñÀÐÓÐÐÐдÐÌ ¥ÌÛçШÍÊÐдÐÐÿ¥Ó¿ÍËÕÊÒÙñÒð¤¤ÐХРШÐÐÐÒ¤¨ð§ÓÓÒñÀÐÛÓ¤ÓШð¢ÐÓçÝÒ´ÐЈÐÿ¥ÿ§ÐÏÓ¤҈ÐÐÐ̯ÍÙÒˆð§Ðð£Ð´Ì₤пըÐÐÐÛЈÐÛÐÐÍÊÓÑдÐЈÐÐ
ÐÐÐÎÿ¥Ò¤¨ð§ÓÓÒñÀÐÛÌÏÓÑÐ ÐÐÒÎÐÎÐÿ¥ÍÊÐÐÛÍ ÇÍÿ¥ÐÐÐ ÐÐÏÍÍ ÐÍÊÌÐЈÐÐÌÙÍ¿Í¡ÐÛÒˆ¢Ì£Ð¨ÐÐÐÈÐÌ
ͧÒ
Ðÿ¥ÓƒÍ ÇШ̓ð¤ÐÐÐдÐÛÐÐÓçÕ´Ò
ÐÏÐЈÐÿ¥ÐƒÐÿ¥ÌÙÍ¿Í¡ÐÓ¤҈ÐÐÐÛÐ₤ÿ¥ÐпÐÎÐð£ÒÙñÒ´ÕýЈÐˋͧÒˋý̧ҴÙШÐÐÐÕÂð¢Ì¡ÕÀÐÛÒ´ÕýÐð¡ÙÐÛҴҥШÐÐÈÐÎÐÏÐÐÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÐÛÿ¥(2)ÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÿ¥ÿ¥Ò¤¨ð§ÓÓÒñÀÐÛÒ´Ò¥ÐÐÐÈÐÐд҈ð§ÐÐÐÒ̓
ШÐÐÈÐÎÓÐÐÍ₤Ò§ÌÏÐÐÌ´Ò¨ÐÐÐдÐ₤ÐÏÐЈÐÐ
(ÿ§ý)ÐÌÙÍ¿Í¡Ð₤ÐͧÒˋý̧ҴÙÐÛÒñÍÀÐÍ
ËÌÒ
ÍÛÑÌÐÐÐÛӡ̯ͧÐÛÍ
ñð§ÓЈҴ¥Ò´ÐÐ´Í ÝÍÐÐÐ
ÒñÍÀÐÛÍ
ñð§ÓЈҴ¥Ò´ÐÛÍ
ÍÛ¿Ð₤ÌÐÐШÐÐÐÎÐЈÐÐÿ¥Ó°Ó¨ð¤¤ÐÍÛ̧ÐÐÍð¤¤ÕÂÒ¨ÐÛÓçÌдÍÌÏÐÛÐÐÛÐÏÐÐÐд̴̡˜ÐÐÐÐÐÐÐÏÐÐЈÐЯÿ¥ÐÐÐÐ₤ÿ¥Í
ñð§ÓÐÏÒˋ°ÓǯЈÐÐÛÐÏÐ₤ЈÐÿ¥Ì¯Ð¯ÐÐÐШÐÎаÐÐÐÎÿ¥Í
ËÌÒ
ШÍ₤ƒÐÐÌÇÒÀÓÙÐÓ¿¯ÐÒ¢ÐÐÐÎÐÐÐÐÛÐÐШÌÙÒ´ÐÐÐдÐ₤ÐÏÐЈÐÐ
ÐдÐÐÒñÍÀÐÛÒ´¥Ò´ÐпÐÎÐð¢ÀÓ´ÐÏÐЈÐЈÐˋдÌÙÍÛÐÐÐдÐÐÏÐЈÐÐдÐ₤Ò´ÐЃÐÏÐЈÐÐÿ¥ÌÙÍ¿Í¡ÐÐÐÓ°Í
ËÌ¡ÐШҴҥÐÛÒ¤¨ð§ÓÒ̓
ð¤ðƒÿ¥ð£ÑШÐÊÐÐÎÐ₤ÿ¥ÓÛÌÿ¥Íÿ¥ð¥Òÿ¥ÿ¥ÍÐÛÒ´¥Ì Ð̓ÐÐÐдÐЈÐÐÐÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÐÛÿ¥Õ ÿ¥ÿ¥ÐÍÍËÐÛÍ
ñð§Óð¤ðƒÐ¨ÐÊÐÐÎÿ¥ÒÀÓ¤Ò
ÐÐÐÛÒÀÓ¤ÐÒ´¥Ì ÓÙШÐÐÓ¿ÍÛÐÐШÐ₤Ò°ÐЈÐÐÈÐÐдÐÐÎÐÐÐдШÓÓÛÐпÐÐÏÐÐÐ
(ÿ§°)ÐÕ¨Õ§ÂШЈÐÈÐÍˋÓ´Ò
ÐÍ¿°ÓˋЈÓÌÇ£ÐÐÏÐÐÐдÐÕÀÐÈÐÎ̧ҴÙÐ¨Õ ÐÐÍÛÑÌÐÿ¥ÍˋÓ´Ò
ÐÛÍÊÒˆ¢Ð¨ÐÊÐÿ¥Ì§Ò´ÙÐÛð¡ÕˋÍЈÍÎÕÐÓÐÍ¢Ì
Ð₤ÍÍШÓÒÏÈÐÏÐÐÐ
ÐÐÐЈÐÐÿ¥ÍƒÒ´ÐˆÐÛдÐÐÿ¥Í
ËÌÒ
ШÌÓ¤ЈҤ¨ð§ÓÓÒñÀÐÒˆÐÐÐÿ¥Í
ËÌÒ
Ðð£ÒÙñÒñÍÀÐÛÌÇÒÀÒÀӤШÐÐÈÐÎÓÐÐдҢ¯Ð¿ÐÎÐÐÍ ÇÍÐÐÈÐÎÐÿ¥ÍÛÂÒΰÓÒ´¥Ì ШÓ
ÏÐÐдÿ¥ð£ÒÙñÒñÍÀÐÛÌÇÒÀÒÀӤШÐÐÈÐÎÓÐÐÐÐÛÐÏÐ₤ЈÐÐдÐÐÐÐ
ð£ÒÙñÒñÍÀÐÛÌÇÒÀÒÀӤШÐÐÈÐÎÓÐÐÐÐÛÐÏÐ₤ЈÐÐдШÐÐÐÓÐÐÍñÛÐÌÐð§Í¯ÐÛЈÐÍ ÇÍÐÏÐÐÈÐÎÐÿ¥ÒˆÓËÓÐÕýÐÐ Õ¨Õ§ÂÐÛÍ
ËÌÒ
ÐÛð¡ÙШÐ₤ÿ¥ÐÍÊð¡ÙШÐÍ
ÐÀÐÐÐÌËÐÎÌÛÇÐÈÐÐдҴÐÐдÐÐÐÿ¥ÍÛÑÌдÐÐÎÐÐÐÐÐÛЃЃÍÐÍÐÐдÐÐÐÐÿ¥ÐÐÛÐÐЈÐдÐÌݤÐÐÎÓ¯ðƒÐ´Ð₤ÐÐЈÐÐÛÐÿ¥Ó¿ÍËÕÊÒÙñÒð¤¤ÐХРÐÛÍÛÌ
ÐÏÐÐÐ
Í
ËÌÒ
ÍÛÑÌÐÛÒˆÐð¡ð¢ÀШÐÊÐÐÎÐÿ¥Ì¯Ð¯ÐÐÐШÐÎаÐÐÐÎÿ¥Í
ËÌÒ
ШÍ₤ƒÐÐÌÇÒÀÓÙÐÓ¿¯ÐÒ¢ÐÐÐÎÐÐÐÐÛÐÐШÌÙÒ´ÐÐÐдÐ₤ÐÏÐЈÐÐ
(5)ô ÍЈÿ¥ÌÓʤð¤ÍÛÿ¥ÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎ
ÿ¥£ð£ÿ¥§ÍÍ₤ˋÐÒ´¥Ì ÐÌÌˋШ̓ÐÐÌ£ÌÕý̓À̰̿дÐÐÎÍÇð¡ÐÐÐдШÐÊÐÐÎ
ÍÍ₤ˋÐ₤ÿ¥ÐÌÏÒ´Çð¤¤Ð₤ÿ¥ÌÓʤð¤ÍÛÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎÿ¥Ò´¥Ì ШÐÐЯÿ¥ÌÏÒ´Çð¤¤ÐÛð£ÒÙñÒñÍÀÐÿ¥ÊÐÌÛÇÐÈÐÐдÐ₤ÐÐ̓ЈÐÌ´ð¡£Í¥çÐÐÐÐдÐÐÎÿ¥ÐÌÏÒ´Çð¤¤ÐÐÐÛÌ ¿Ì дÐÐÎÌͤÐÐÒ´¥Ì ÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐˆÐÐÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥Ð₤ÿ¥ÌÌˋШ̓ÐÐÌ£ÌÕý̓À̰̿дÐÐÎÍÇð¡ÐÐÐÎÐÐÿ¥ÐÐÌ
ÿ¥Ò¨ÌÏÒ´Çð¤¤ÿ¥¿5ÐÐÛÍÒ¨ÿ¥ÍÒ´¥ÐÐÐÐÎÐÐÐÿ¥ÐÐÐÐÐдШÌÓʤð¤ÍÛÿ¥ÐÛÓÍÛÌÏÐÍÊÌÙÐÐÐÛÐ₤ӡͧÐÏЈÐÐÐд҈˜ÓʤÐÐÐ
ÐÐÐЈÐÐÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐˆÐÐÿ¥ÿ¥ÿ¥Ð₤ÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿5ÐÐÿ¥ÍÍ₤ˋШÐÐÐÎÍÐÐÎÿ¥ÍÛÕШÍÌÐÐдÐÐÐÛÐÏÐÐЯÿ¥ÐÐÛÕÂð¢ð¡ÿ¥Ó˜˜ð¡Í₤ˋÐÏÐÍÛ¿ÌШÌͤÐÏÐÐÐÏÐÐÐÿ¥ÊÐÛÍÙ¨ÐÏÐÐÿ¥ÊãÐÛÕ°Ò¢¯Ì¡ÿ¥ð¿ÿ¥Àÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÊãÐÛÍÓÿ¥ÿ¥Àÿ¥ÿ¥ÐÛÿ¥Ð£ÿ¥ÿ¥ÐÍÍ₤ˋШÐÐÐÎÍÐÐÎÌͤÐÐÐÐÿ¥ÍÍ₤ˋШÐÐÐÌ£ÌÕý̓ÀÐÛÍ¢
ÒÎÐÐÌͤÐÐÐÐÛÐÏÐÐÐ
ÌÕ¨ÒÈÍÊÌÍÊðƒÐ₤ÿ¥ÐÌÏÒ´ÇÍ₤ˋШÐÐÐÎÍÐÐÎÌͤÐÐÌ£ÌÕý̓ÀÐÛÌ¿Ì°Ðÿ¥Ì¯Ò´ÇÓ˜˜ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÌÀШÐÐÐÐÌÌˋШ̓ÐÐÐÐÍÎÐÐ₤ÿ¥Ó˜˜ð¡Í₤ˋðƒÕ ¥ÐÛÒ´ÇÒ´ÌÓÑÐÛÓçÕÐÕÕÂÐÐÎÐÐÐÍÊÌÙÐпÐÿ¥ÌÌˋШ̓ÐÐÌ£ÌÕý̓ÀÐÛÌ¿Ì°ÐÏÐÐÈÐÎÐÿ¥Í§ð¤Ò
ШÌ
ÌЃÐÐ₤ÕÍÊÏЈÕÍÊÝÐÍÙÐÿ¥ÐÐÊÒ´ÇÒ´ÐÛÍÛÓçÐÕ
Í£ÑÐÐÐÐÍ ÇÍÐÏЈÐÐЯÿ¥ÍÌÀШÐÐÐÐÐÍÇð¡Ð̓ЈÐÐÐÛдÒÏÈÐпÐÐÏÐÐÐÐÌ´ÍÊÓʤÐÐÎÐÐÿ¥ÌÕ¨ÒÈÍÊÌÓ˜˜ð¡Í¯Ì°Í£ñÌÙÍÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥Ìÿ¥ÌËУ̯Õÿ¥Íñ£ÿ¥Íñÿ¥ÿ¥ÿ¥Õ ÐÛÍÊÌݤÒÎÌ´ÿ¥ÿ¥ÌÌËÐÛÕýÒÀÕӴШÓ
ÏÐÐÐÎÐÿ¥ð¡Ò´ð¤Ì
ШÐÐÐÎÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐˆÐÐÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐÓÇÐÀШÍÇð¡ÐÐð¡Ò´ÍÍ₤ˋÍÊÌÙÐ₤ÿ¥ð¡Ò´ÌÕ¨ÒÈÍÊÌݤШÕÍÐÐÐÐÛÐÏÐÐÈÐÎÿ¥ÌÐÐШÕÌ°ÐÏÐÐÐ
ÐÐÐÎÿ¥ÌÏÒ´ÇÍ₤ˋШЈÐÈÐÎÌͤÐÐÐÒ´¥Ì Ðð§çÐÒÌ
ÛÐÐдÿ¥Ì˜ÀÐÛÐÐШÒÐÐÐÛÐдÐÐÏÐÐÐ
ÐЈÐÐÀÿ¥ÍÍ₤ˋШÐÐÐÎÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿5ÐÐ₤ÿ¥ÿ¥ÊãÐÛÕ°Ò¢¯Ì¡ÿ¥ð¿ÿ¥Àÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐÐÐÛÍÓÿ¥ð¿ÿ¥Àÿ¥ÿ¥ÐÛÿ¥Ð£ÿ¥ÿ¥ÐÌͤÐÐÐ
ð¡Ò´ÍÓШÍÐÐÐÐÐÐ₤ÿ¥ÌËçÐÐÎÒÀÌÓЈÐÐÛÐÏÐÐÐÐÿ¥ÿ¥ÊãÐ₤ÿ¥ÍˋÓ´Ò
ÐÛÍÛÑÌдÐÐÎÿ¥ð¡Ò´Õ°Ò¢¯Ì¡ÿ¥ð¿ÿ¥Àÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐÛð¡ÙÐÏÿ¥ÐÓËÌ₤Ð₤ÿ§Ð¨ÐÐÐÐÿ¥Ó§Í
ÕÐÏÒÎÍÐð§ð¡ÐÐÎÐЃÐÐÐÿ¥ÐÐÛÍÿ¥ÒÇÍÐÐÐÈÐÐÐÐÎÐЃÐÐÐÒˆÍШÌÇÍÐÐçÐÐÈÐð¤¤ÐÛÐдÐÿ¥ÐÐÛÍȯÒýÐÐÿ¥ÐÒËÐÐÍ
ÐÀÐÐÐдÍÊÌÙÐÐÐÛРдÌÐЃÐÐÐЈÐˋдÐÐÈÐÌ´Ò¨ÐÒ¢¯Ð¿ÐÎÐÐÐ
ÐÐÐЈÐÐÿ¥ÿ¥ÊÐÒ´ÐÈÐÎÐÐÐÍÊð¡ÙШÐÍ
ÐÀÐÐÐÌËÐÎÌÛÇÐÈÐÐдÐÐÐдÐ₤ÿ¥ÍÛÂÒΰÓÒ´¥Ì ШÓ
ÏÐÐÐÎÐÐ̓ЈÐÐдЈÐÛÐÏÐÐÐ
ÐЈÐÐÀÿ¥ÿ¥ÊÐÛÒ¤¨ð§ÓÓÒñÀÐ₤ÿ¥Í¿°Ìÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÍÍÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÍШÿ¥ÍÛð¢ð£ÒÙñÒñÍÀШÐÐÈÐÎÓ¤ÒÎÐÐÿ¥ÍÍÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÍШÌÙÎÍýÀÓÒÙñÍ¡¨ÐÓ¤҈ÐÐÎÐÐÿ¥ÐÐÛÐдÐ₤ÿ¥ÊÐÛÓÒÙñÒ´ÕýÐÛÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÐÛ̘ÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐÛÒ°ÌÐÛÿ¥ÐÛÿ¥ÿ¥ÍÒˆ¢Ì£Í ÝÍÌ¡ÐÏÐ₤ÿ¥ÒçÊÓÇШÐÐÈÐÎð£ÍÐÐÐÍÐÛÕ´ÍÐÛ̓Íÿ¥ÒÀ´ÓÇÐÍ
ËÐÐÎÿ¥ÿ¥ÌÓÛð£ËÕÿ¥Ð¨ÿ¥Ì˜ÌШÓÇÌËÓЈҰÌÐÐÐÐ₤ÐÂÐÐÐÒ°ÌÓˆÍñÐð£ÐÐÎÓÑÇÐÐÐÎÐÐÐÓýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐÛУÐÿ¥ð£ÒÙñÒ´Õýÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÎÓÒÙñÌËÒˆÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÍÌËÐÛÿ¥ÿ¥ÎÓÒÙñÌËÒˆÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥Ð¨ÐÒ´Ò¥ÐÐÐÎÐÐÐ
ð¡Ò´Ò¤¨ð§ÓÓÒñÀÐÓÐÐÌÌÐ₤ÿ¥ÍÍ¿Çÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÐÛÍ¥ÓÑÌÐÐÍÌÿ¥ÿ¥ÌËШÐÐÐÎÐÏÐÐдÒÐÐÐÐÐÿ¥Í¿°Ìÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥ÌÐÛÿ¥ÿ¥Îð£ÒÙñÒñÍÀÍÊÍÒÀ´ÿ¥ÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÿ§ÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÿ¥ÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐÛÿ¥Ð£ÿ¥ÿ¥ð¿ÿ¥Âÿ¥ÿ¥ÐÛÿ¥ÿ¥ÐÓ¤҈ÐÐдÿ¥ÓñÌÏÐÛð£ÒÙñÒñÍÀÐ₤ÿ¥ÕШÍÊÍÊÐÐÎÐЈÐÐ
ÐÐШÿ¥Í¢çÐÛÐÐÒˆ¢Ì£ÐÐдÐÐÿ¥Í¿°Ìÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥ÌÐÛÿ¥ÿ¥Îð£ÒÙñÒñÍÀÍÊÍÒÀ´ÿ¥ÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÿ§ÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÿ¥ÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐÓ¤҈ÐÐдÿ¥ÐÐÛÕÿ¥ÿ¥ÕÐÏÐÍÊÍÊдÐÐÐÎÐÐÓñÌÏÐÛð£ÒÙñÒñÍÀÐ₤ÐÐÐÿ¥ÓñÌÏð£ÒÙñÒñÍÀÿ¥ÿ¥Íÿ¥ÐпÐÎÐÛТÐÊРШХÐÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐˆÐÐÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐÓ¤҈ÐÐдÿ¥ÐÐÛÌÕÍ¡₤ШÍÊÍÐÐÎÐЈÐÐ
ÐÐÐÐÈÐÎÿ¥ÿ¥ÊÐÐÍÊð¡ÙШÒËÐÐÍ
ÐÀÐÐÐÌËÐÎÌÛÇÐÈÐÐÐдÐ₤ÐÐ̓ЈÐÐÛÐÏÐÐÐ
(6)ÐÍШÿ¥ÌÓʤð¤ÍÛÿ¥ÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎ
ÍÍ₤ˋÐÛÐÐÐÏÐÛÒˆ˜ÓʤÐ₤ÿ¥Ó°Ó¨ð¤¤ÐÛð¡£Í¥çÐÌÌËÐÐÐÐÐ ÐÐÛͧÂÍ¥ÓЈҨÕÈÐÏÐÐдÐÐÒ´ÐÌÏÐЈÐÐ
ÐÍ
ÒñÍÀÐÐÛÓ¤Ò´Í
ÍÛ¿ÐÌÙͿ͡ШÍ₤ƒÐÐÎÐЈÐÐÐÐÐÛÐÐˋÐÐÐÿ¥Ò¨ÌÏÒ´Çð¤¤ÿ¥¿6ÐÌÙÍ¿Í¡ÐÛÌ
ͧÒñÍÀШÓ¤҈ÐÐÐÍÎÐШÐÊÐÐÎÿ¥Ò¨ÌÏÒ´Çð¤¤ÿ¥¿5ÐдÌÙÍ¿Í¡ÐÛÕШÒÎÒÏÈÐÛÓ¡ÕÐÐÐÿ¥ð¿ÿ¥Àÿ¥ÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐдÐÐÐдÐ₤Ó¯ðƒÐˆÐдÐÏÐÐÈÐÎÿ¥Ò£§ÒÎÐÐÐпÐð¤Ì
ÐÏÐ₤ЈÐÿ¥ÐÐÛÐÐШÿ¥ÍÌÌ¿Ì°ÐÐÛÐÐÛШÐÊÐÐÎÿ¥ÍÌÒ
дÒ¨ÍÌÒ
ÐÛÕШÍÊÏÐЈÒÎÒÏÈÐÛÓ¡ÕÐͤÐÐд҈ð§ÿ¥ÍÌÌ¿Ì°ÐÛð¡ÕˋÍÐÐÌ´ÒˆÐÐÐÐ
ÐÐÐШÿ¥ÍÍ₤ˋÐ₤ÿ¥ð§ÐÓÓÝÐÓʤÐÐдЈÐÿ¥Ðð£ÛШÌÙÍ¿Í¡ÐÍ
˜Í¥Ð¨ð¡Ò´Ó¤҈ÐÒÀÐЈÐÐÈÐдÐÐÎÐÿ¥ÐÐÐ ÐÐÏÿ¥Ò¨ÌÏÒ´Çð¤¤ÿ¥¿6ÐÛÍÌÌ¿Ì°ÐӡͧÌÏÐ̘ ÐдÐÐÐдШÐЈÐЈÐÐÐдÍÊÌÙÐÐÎÐÐÐÛÐÏÐÐÐ
ЈÐÿ¥ÌÓʤð¤ÍÛÿ¥Ð₤ÐдÐÐÿ¥ÐÐШÕÐÐÿ¥Ò¨ÌÏÒ´Çð¤¤ÿ¥¿6ÐÛÍÌÌ¿Ì°ÐӡͧÌÏÐ̘ ÐÐÐÛÐÏÐÐÈÐÐдÐ₤ÿ¥ÍƒÒ´ÿ¥ÐÛдÐÐÐÏÐÐÐ
ÿ¥ô ÍÍ₤ˋÐÓ˜˜ð¡Í₤ˋÐÛÍÊÌÙÐÍ¥Ó´ÐÐÎÌÓʤð¤ÍÛÐÛÓÍÛÌÏÐÒˆÐÐÍÊÌÙШÐÊÐÐÎ
(1)Ð̘ð£ÑÒ´ð¤ÿ¥ÿ¥ÿ¥Ð¨Ò´Ò¥ÐÐÐÌÓʤð¤ÍÛÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥Ò̓
ÐÛð¤ÍÛ(1)ЈÐÐ(4)ÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎ
ÐÂÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛðƒÒ¢¯ÐÛð¢ÀÓ´ÌÏШÐÊÐÐÎ
(ÿ§Ý)ÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛðƒÒ¢¯Í
ÍÛ¿ÐÍ
ñð§ÓÐÏÐÐÐдШÐÊÐÐÎ
Ó˜˜ð¡Í₤ˋÐ₤ÿ¥Ò̓
ÐÛð¤ÍÛ(1)ÿ¥Í(2)ÍаÍ(4)ШÐÊÐÐÎÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛÍÓÛÌðƒÒ¢¯Ðð¢ÀÓ´ÐÐÐдÐÐÏÐÐÍ
ÝÕÐÛÓÓÝдÐÐÎÿ¥ÐÐÛðƒÒ¢¯Í
ÍÛ¿ÐÍ
ñð§ÓÐÏÐÐÐдÐÓ´ÐÐÎÐÐÐ
Ó¤ÐШÿ¥ðƒÒ¢¯ð¡ÙШӃÐÐÍ
ñð§ÓÐÐÊÒˋ°ÓǯЈÍ
ÍÛ¿Ðÿ¥ðƒÒ¢¯Ò
ÐÍÛ¿ÌШð¤ÓËÐÏÐÐÿ¥ÐÐÊÍÐÐÐдÐÛÐÏÐЈÐÐÐЈÍÛÂÒΰÓð¤Ì
ШÍÒÇÐÐдÐÐ₤ÿ¥ÐÐÛÐд҈ð§Ð¨ÐÐÈÐÎÿ¥ðƒÒ¢¯ÐÛð¢ÀÓ´ÌÏÐÕ¨ÐдÒˋðƒÀÐÐÐдÐÐÏÐÐÐÿ¥ðƒÐЯÿ¥ÓƒÍ ÇШÕÐÐÐÐÐÛÒ
ÐÛðƒÒ¢¯Ðÿ¥Í
´ÐÕÎÇÌТÐÛЈÐÍÛÂÒΰÓð¤Ì
ШӘÎÍÐÐÎÐÐÐÐÐˆÍ ÇÍÐÿ¥Ð
ÐÐÐÿ¥ÍÛÂÒΰÓð¤Ì
Ðð¤ÓËÐÐÎÐÐÒ
ШÐÊÐÐÎÐ₤ÿ¥ÌÍ°ÐÐЯÿ¥ð¤ÓËÐÐÎÐÐÍÛÂÒΰÓð¤Ì
ШӘÎÍÐÐÐÒͧÐÛÍ
ÍÛ¿ÐÍçð§ÐÐÐдÐÍ₤Ò§ÐÏÐÐÿ¥ÍÛÂÒΰÓð¤Ì
ШӘÎÍÐЈÐÐÐÐˆÍ ÇÍШÿ¥Í§ÒˋýðƒÒ¢¯ÐÌÌËÐÐÓÓÝдЈÐÐдÐ₤ÐÐÈÐÎÐÿ¥ÐÐÛÐÐЈ̧ÒÝÀÓÍÝÕ¤ÌÏÐÐÐð£Ëð¡ÿ¥ÍÛÂÒΰÓð¤Ì
ШÍ
ñð§ÓШÌÇÍÐÐÐÐдÐÐÈÐÎÿ¥ÐÐÐ ÐÐÏÓÇÐÀШըÐð¢ÀÓ´ÌÏÐÒˆÐÐÐдÐ₤ÐÏÐЈÐдÐÐЈÐÐЯЈÐЈÐÐ
ÐÐÐÎÿ¥Ì˜ð£ÑÐ₤ÿ¥Ò̓
ÒÀÓ¤ÐÛÌÓÀÐð¤Ó¿Ð´ÐˆÐÈÐÎÐЈÐÐÿ¥Í
ñð§ÓЈÌÇÒÀШÐÐÓÒñÀÓÙÐÛÍÛÂÒΰÓð¤ÍÛÐÒˆÐÐШÒÑ°ÐÐÒ´¥Ì ÐЈÐÿ¥Ó¿ÍÛÐÛÒ̓
ÒÀÓ¤ÐÓÛÌÐÐдÐÐÒ
дÒÀÓ¤Ò
дÐÐÐÒ
ÐÛÓ¡ð¤Ð¨ÓÓƒÐÐðƒÒ¢¯ÐÍÙÐÐÐÛТÐÏÐÐдÐÐð¤ÌÀÐÏÐÐÐ
ÐÐÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1Ð₤ÿ¥ÿ§ÐÏÓ´¥ÍÐÐÎÐÐÿ¥ÐÐÊÐÏÐÓƒÍ ÇШÒçÇÐÐÓ¨Í ÇШÐÐÈÐÐÐ´Ð¨Í Ðÿ¥Ò̓
ÍÕÀШÐÊÐÐÎÓ¤ÒÀ´Ð£Í ÝÍÐÐЈÐˋÐÛÌÇ£ÍÐÐÐÎÐÐÿ¥ðƒÒ¢¯ÐпÐÍ
ÍÛ¿ÐÒÈÍ¥ñУÍÂÍ¥ñÐÏÐÐÓÑ̰ШÐÐÈÐÐÐÐÛÐÐÐˆÓ¨Í ÇШÐÐÐÐдÐÐÈÐÎÓÇÐÀШðƒÒ¢¯ÐÍçð§ÐÒÌÏÐÏÐÐдÐÐÎð¢ÀÓ´ÌÏÐÍÎÍÛÐÐÐÐÐÛÐÏÐ₤ЈÐÐдÐ₤ͧÓÑÐÏÐÐÐÿ¥ÍÛÂÒΰÓð¤Ì
Ðð¤ÓËÐÐÎÐÐð¡Ò˜Ð¨ÐÐÛÐÐÐˆÓ¨Í ÇШÐÐÒ
ШÐ₤ÿ¥ÍÛÂÒΰÓð¤Ì
ШӘÎÍÐÐÐðƒÒ¢¯ÐÐÐÐдÐÐÏÐÿ¥ð¤ÍÛð¡ÒͧÐÌññÍ
ËÐÐ̧ÒÝÀÓÍÝÕ¤ÌÏÐÐÐÐдÐ₤ÍÎÍÛÐÏÐЈÐÐ
Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛðƒÒ¢¯Ð¨ÐÊÐÐÎÿ¥Í
ÍÛ¿ÐÍ
ñð§ÓÐÏÐÐÐдÐÐð¡ÍÛИÐШÐÛð¢ÀÓ´ÌÏÐð£ð¡ÐÐÐдÐÐÏÐÐдÐÐÎÐÿ¥ÿ§ÐÏÐÛÓ´¥ÍÓÑÌ°ÐÌÇ£ÍÓÑ̰ШÓ
ÏÐÐдÿ¥ÐÐÐ ÐÐÏÿ¥Ó¡ð¤Ð¨ÓÓƒÐÐðƒÒ¢¯ÐÌÌËÐÏÐÐУÐˋШըÐð¢ÀÓ´ÌÏÐÒˆÐÐÐдÐ₤ÐÏÐЈÐÐ
(ÿ§ý)ÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛðƒÒ¢¯Ð₤ÿ¥ÐÐÛÌÐ
ÐÏð¤Ò£Âð¡Ò£ÂÐÐÎÐÐÐд
ÿ§ÐÓ˜˜ð¡Í₤ˋÐ₤ÿ¥Ò̓
ÐÛð¤ÍÛ(1)ÿ¥ÿ¥ÊСÐÛÌÇÒÀÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛðƒÒ¢¯Ðÿ¥ÐÒ¨Íÿ¥¿1Ð₤ÿ¥ÍÍÐÛÍÛ̧ÐÐÍð¤¤ÕÂÒ¨ÌÐÐð¡Òý¨ÐÐÎÿ¥ÂÐÛÿ¥ÊШÍ₤ƒÐÐÌÇÒÀÐÓÛÌÐÐÌ´Ò¢¯Ð¿ÐÎÐÐÐд҈˜ÓʤÐÐÿ¥Ó˜˜ð¡Í₤ˋÍÊÌݤÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÒÀÓÛÐÐÿ¥ÒÀÓÛÿ¥Ð
ÐÐÐÿ¥Ðð¡Òý¨ÐÐÎÐÐÐдÐÐÈÐÎÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1Ðÿ¥ð¡Ò´ÐÛ̧ÒÝÀÓÓçÒ¨ÐÓÑÙÌÐÐÎÐÐдÐÐÕÐШÐÐÐÎð¡Òý¨ÌÏÐÒˆÐÐÐÐШÐÐÐÿ¥Ì˜ÀÐÛдÐÐÿ¥ÐÐÛÌÐ
ÐÏð¤Ò£Âð¡Ò£ÂÐÐÎÐÐÿ¥Í
´Ðð¡Òý¨ÌÏÐЈÐдÐÐЈÐÐЯЈÐЈÐÐ
ÿ§ÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1Ðÿ¥ÍÐÐÎÿ¥Í¿°Ìÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥Ìÿ¥ÌËÿ¥ÿ¥À̧ҴÙÕñШҢ¯Ð¿ÐÐÛÐ₤ÿ¥Ðÿ¥ÂÐÐÐÿ¥ÍˋÓ´Ò
ÐÛÒ
ÐÍ¥ÐÈÍ¥çÐÈÐÎÐÐÐÐÐÍ¥ÐÐÐҧдÐÐдÐÐÎÐÐÐÛÐÒÎÐÐÿ¥ÂÐÐÐÐ₤ÐШÐÐÎУÐÐÐÐÐÕ ÙÐÐҧдÐÐдÐÐÎÐÐÐÿ¥ÍˋÓ´Ò
Ð₤Òˆ¯ÐÒ´ÐЈÐÐÐÐдÐÐÍ
ÍÛ¿ÐÏÐÐÈÐÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐÛÿ¥Õ ÿ¥Ð
дÐÐÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛÌ̡ШÐ₤ÿ¥Ðÿ¥ÂÐÐÿ¥ÍÊÍÊÍ¡₤ÌÌ°Ìÿ¥ÿ¥Ê̯ÐÛÕ ÙÐð§Í¤ÎÐÍˋÐÿ¥ÌÕ°ÇÐÓÙÌÇÍÐÐЃÐÐÐÐдҴҥÐÐÐÎÐÐÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÌÇÒÀÐÛÌ
ÌÏÐÍ
´ÐӯЈÐÐÐÛÐÏÐÐÈÐÐ
ÐÐÐÎÿ¥ÐÍ¿°Ìÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËШÒÀÐÐÐÍð¤¤ÕÂҨШÐÐÐÎÿ¥Ò¨Íÿ¥¿1Ð₤ÿ¥Ðð§ÍÍˋÐÐÐÐ₤ð¡ÌдҢ¯Ð¿ÐÐдÐÒˆÐÐÐÐÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥Ðÿ¥Ó˜˜ð¡Í₤ˋÍÊÌݤÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÿ¥ÒÀÓÛÐÐÿ¥ÿ¥ÒÀÓÛÿ¥ÐÐЈÐÐÀÿ¥ÍÍÐÍÛ̧ÐÐÍð¤¤ÕÂÒ¨ÐÛÓçÌÐÕÓÇÐÐÒ°Ìÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐÛÒçÊð£ÍÓ´ÓÇÐÛ̓ÐÛÿ¥ÿ¥ÐˆÐÐÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥Ð¨ÐÐˋÐÛð§ÿ¥ð§ÍÍˋÐÐÐÐ₤ð¡Ìÿ¥ÿ¥ÿ§ÿ¥ÍУÿ¥ÿ§ÿ¥Íÿ¥Ðÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐÛÒçÊð£ÍÓ´ÓÇÐÛ̓ÐÛÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÿ¥ÐÍ₤̧ҴÙÕñШÍ₤ƒÐÐÎÿ¥ÿ¥ÂCWÐÿ¥Ê̯ÐÛÕ ÙÐÍˋÐÐÛÐÒÎÐÐÿ¥ÐˋÐÛð§ÿ¥ð§ÍÍˋÐÐÐÐÐ₤ÐÈÐÐÐЈÐдҢ¯Ð¿ÐÎÐÐÐÐÐÐÏÿ¥Í₤̧ҴÙÕñÐÿ¥ÌÕÐÍ̯ÐͯÐÙÐÎТÐÐÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥Íÿ¥ÿ¥ÍÐÐÿ¥ÍÐÐÐдÌÌÏЈ҈˜ÌÐÛЃЃÓçÐÐÈÐÎÐÐÐÐÛÐÏÐÐÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐÛÒçÊð£ÍÓ´ÓÇÐÛÍÐÛÿ¥Õ ÿ¥Ð
ÿ¥ÈÍ₤̧ҴÙÕñÐÒ¢¯Ð¿ÐдÐÐÿ¥ÐÐÐÛ̓ÐÛÕÂÒ¨ÐÏÐ₤ÿ¥ÿ¥¿1CWÐ₤ÿ¥ÍˋÐÐÌÕÿ¥Í̯ÐЃÐÀЃÐÀÐÏÿ¥ÐÐÛէͤÎÕÐÈÐÎÐЃÐÐÐÿ¥ÐÐÌÐ₤ÿ¥ÿ§ÿ¥Íÿ¥ÐÐÌÐ₤ÿ¥ÿ¥Ýð¤ÍÍÝÕñÐÛÕÂÒ¨ÿ¥ÿ¥ÿ¥Íÿ¥ÐÐÌÐ₤ÌÕÐÒ´ÐÈÐÎÐЈÐÐÛÐÏÍÐÐЈÐÿ¥Ðÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐÛÿ¥Õ ÿ¥Ð´ÿ¥ÌÕÿ¥Í̯ЈÐˋÌÇÒÀÐÛӴͤÎШÕÂÐÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛðƒÒ¢¯Ð₤ÿ¥ð¤Ò£Âð¡Ò£ÂÐÐÎÐÐÈÐÐ
Í¿°Ìÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÐÛÿ§Ì¯ÒÌÍШÌýÒ¥ÐÐÐ̘ð£ÑÒ´ð¤ÿ¥Ð¨Ð₤ÿ¥Ðð§ÍÓ¤ÐÐÐÐÓÑÐÐÐÐдҴҥÐÐÐÎÐÐÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿6дÐÐÎÐ₤ÍÒ´ð¤ÐÍñÓÙÐÐШͧÐÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛÓÛÌðƒÒ¢¯Ð¨Í
´ÕÂÓШðƒÌ ÐÐУÐЈÐÐдÐÐÐÐÎÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1Ð₤ÿ¥ÐÐÛдÐÐÒ¢¯Ð¿ÐÐÐÛдÒÐÐÐÐÿ¥ÿ¥¿1Òˆ¢Ì¡ÿ¥ÍÍ₤ˋÿ¥ÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÒÀÓÛÐÐÿ¥ÿ¥ÒÀÓÛÿ¥ÐÐÐÐÎÿ¥ÐÒ¨Íÿ¥¿6Ð₤ÿ¥Í¿°Ìÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÐÐÿ¥Ò¨Íÿ¥¿1ÍаÒ¨Íÿ¥¿1ÐÍÌÐÿ¥Ò̓
ÒÀӤШÐÊÐÐÎÿ¥Í ÍÛ°Ò
ÍаÒ¨ÍÛ°Ò
ÿ¥ÌÇÒÀÐÛÌ
ÌÏÓÙШÐÊÐÐÎÒˋ°ÓǯШÒˋÝÐÒÐддÐШÿ¥Ò¨Íÿ¥¿1ÍаÒ¨Íÿ¥¿1Ðÿ¥ÍÍ¿Çÿ¥ÌÐÐÐÐÒ´Ò¥ÐÐÎÐÐÒ̓
ÒÀӤШÕÂÐÐÐÀÐÂÐÛÍÐÐÍÐÍÐÈÐÐÿ¥ð¿ÿ¥Àÿ¥ÿ¥Ðÿ¥Ó˜˜ð¡Í₤ˋÍÊÌݤÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÒÀÓÛÐÐÿ¥ÿ¥ÒÀÓÛÿ¥Ð
дÐÐÐÿ¥Ò¨Í̘ð¤¤Í¯ÍШÐÐÐÎÐ₤ÿ¥Ó˜˜ð¡Í₤ˋÐÐÐÛЃЃͥӴÐÐдÐÐÿ¥ÐÍ̯Ð₤Í°Í₤ШÐ₤̯ÐÐÎÐЃÐÐÐÿ¥Ì¯Ó¤ÐÏÐ₤ЈÐÿ¥ÿ¥ÿ¥Ó¤ð£Ëð¡Ð дҴÌÑÐÐÎÐЃÐÐÐдҢ¯Ð¿ÐШҰÐÈÐÐÛÐÏÐÐÐ
ÐÐÐÎÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛÍÍ₤ˋШÐÐÐðƒÒ¢¯Ðÿ¥ÿ¥Í¤ÎÓÛÐÛÌ°Í£ñÐÏÐÐШÐÐÐÐÐÐÿ¥ÌÕÐÍ°ÐÈÐÎÐЈÐÐдÐӃШÿ¥ÌÌÏÐÏÌËçÐÐÎÌÙ₤ÍÐÐ̈ÐÍ
ÍۿдЈÐÈÐÎÐÐÿ¥ÿ¥¿1Òˆ¢Ì¡ÿ¥ÍÍ₤ˋÿ¥ÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÒÀÓÛÐÐÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÿ¥ÒÀÓÛÿ¥Ð
ÿ§ÐÓ˜˜ð¡Í₤ˋÐ₤ÿ¥Ì˜ð£ÑÒ´ð¤ÿ¥ÐÒ´Ò¥ÐÐÐð§ÍÓ¤ÐÐÐÐÓÑÐÐÐдÐÐð¤ÍÛШÐÊÐÐÎÿ¥ð¡Ò´ÐÛдÐÐÿ¥ÐÓÍÐÌÛÐÐдÐÿ¥Ð̘ð£ÑÒ´ð¤ÿ¥ÐÛÒ´Ò¥Ð₤Í¢
ÐÐÐÌÙÈÓ¤ЈÐÐÛдÐ₤ÐÐЈÐÐÿ¥Ó˜˜ð¡Í₤ˋÍÊÌݤÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÿ¥ÒÀÓÛÐÐÿ¥ÿ¥ÒÀÓÛÿ¥Ð´ÐЈÐÐÿ¥ÐͧÒˋýÌÇÒÀШÐÊÐÐÎÐ₤ÿ¥Ðð¡ÍÛÌÕÿ¥Í¯ÐˆÐдÐÿ¥ÿ¥Íð£Ëð¡ÐÐÐÐÐд҈ÐÐÐÐÐдÐÐÎÐÐÐ
ÐÐÐЈÐÐÿ¥ÌÇÒÀÐÛӴͤÎÐ₤ÿ¥Í§ÒˋýÌÇÒÀÒÀÓ¤ÐÛÌÏÌ ¥ÐͤÓÊð£ÐÐ̘ͤÓÒÎÓÇ ÐÏÐÐÈÐÎÿ¥ÓÛÌÐÐÍ ÇÍШÐ₤ӿШͯÒÝÀШÌÛÐÈÐÎÐÐÐпÐð¤Õ
ÐÏÐÐÐÐÿ¥Ò̓
ÐÛð¤ÍÛ(1)ШÐÊÐÐÎÐÛðƒÒ¢¯Ð¨ÐÊÐÐÎÐÛð¡Ò´ÐÛÐÐЈÍÊÕñÐÐÐÐ₤Õ§Õ§˜ÐÒ£§ÒÎÐÐÎÿ¥Ó¡Ûͯ҈ÍÛÐÐЯÒÑ°ÐÐдÐÐÐдÐ₤ÐÏÐÐÿ¥Íð¤ÍÛШð¢ÐðƒÒ¢¯ÐÛð¢ÀÓ´ÌÏÐÐÛÐÐÛÐÓÐÐÐÐÐÛÐÏÐÐдÐÐпÐÐÏÐÐÐ
ÿ§ÐЈÐÿ¥ÌÇÒÀÐÐÐÈÐÎÐÍ¡¡Ð¨ÍÛÂÒΰÓÓÒñÀÐÌÛÐдЃÐÏÐ₤ÌÙÍÛÐÏÐЈÐÐÐÛÐÛÿ¥Õ¨Õ§ÂÒ
ÐÐð¡ÍÛÌÕÿ¥Í¯ÐˆÐдÐÿ¥ÿ¥Íð£Ëð¡ÐÐÐÐÐÐÛÐÏÐÐЯÿ¥ÍÛÂÒΰÓÓÒñÀÐÌÛÐÒÓÑÌÏÐÕ¨ÐÐ₤ÐÐÏÐÐÐ
ÐÐÐШÿ¥ð£ÒÙñÒ´Õýÿ¥ÓÒÙñÒ´ÕýÐÛÐÐÐШÐÿ¥ÐÐÛÐÐЈҴҥÐ₤ЈÐÿ¥ÐÐÛÐÐЈÓÒñÀÐÒÎÐдÐÐÒ
ÐÐЈÐÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÐÐÒ̓
ÒÀÓ¤(1)ÐÐÐÈÐдÐÐÐÛÐ₤Í¿°Ìÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÐÏÐÐÐÿ¥Ó¢ÿ¥ÿ¥ÌËÿ¥ÿ¥ÿ¥ÌËШÿ¥ÿ¥ÊÐÛÍÙ¨ÐÌËÌÐÕÂð¥ÐÐÎÐÐÐÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐÛÒçÊÓÇÐÛÍÐÛÿ¥Õ дҰÌÿ¥ÐÛÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥Ó¿Ð¨ð§ÐÐÓ°Ò¢¯ÐÐÐдÐЈÐÿ¥ÕðƒÐˋÐÐÍ¡¯ÐÈÐÎÐÐÐÿ¥ÊÐÛÍÛÑÌÐ₤ÿ¥ÍÛÑÌÒˆ˜Ìð¥Ð¨Í¤Í¡ÙÐÿ¥Ð°ÐШÐÊÐÐÎÒ¢¯Ð¿ÿ¥ð¿ÿ¥Âÿ¥ÐÛÿ¥Õ ð£Ëð¡ÿ¥ÿ¥Ó˜˜ð¡Í₤ˋÐÛÒˆÍÛШÐÐЯÿ¥ÿ¥ÊÐÛÕÀШÐÏÐÐÐÐÐÛÍÓÐÓʤÐÐдÐÐÐÎÐÐÿ¥Ó˜˜ð¡Í₤ˋÍÊÌݤÿ¥ÿ¥Õ ÍÓ
Ïÿ¥ÿ¥ÿ¥ÊÐÛÓÑ̰ШÐ₤ÌËçÐÐÎÕÂÍ¢ÐÕ¨ÐÐÈÐÐдÐÓˆ¤ÐÐÐÐ
ÍÛÂÒΰÓÓÒñÀÐÌÛÐÒÓÑÌÏÐÕ¨ÐÍ ÇÍШÿ¥ÐƒÐÈÐÐÍÛÂÒΰÓÓÒñÀÐЈÐÐÛÐÏÐÐÐÐÿ¥ÌݤÍÛÓÐÏÐ₤ЈÐШÐÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛðƒÒ¢¯ÐÛÌÀӴШÐ₤Ì
ÕШЈÐÐÐÐ̓ЈÐð¤Ì
дÐÐÎÒÌ
ÛÐпÐÐÏÐÐÐ
ÿ§
ÐÓ˜˜ð¡Í₤ˋÐ₤ÿ¥Ò̓
ÐÛð¤ÍÛ(2)ÿ¥ÿ¥ËСÐÛÌÇÒÀÿ¥ÿ¥Ò̓
ÐÛð¤ÍÛ(4)ÿ¥ÿ¥ÏСÐÛÌÇÒÀÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎÐ₤ÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛÐÀÐÂШҴҥÐÐÐÎÐÐÐÿ¥Íð¤¤ÕÂҨШÐÐÐÎÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÒ´ÍÐÐÎÐÐÐÿ¥Ò̓
ÐÛð¤ÍÛ(1)дÍÌÏÐÛð¡Òý¨ÌÏÐ₤ÒˆÐÐÐЈÐÿ¥ÐˆÐÿ¥ÍÒ
ШÐÊÐÐÎÐ₤ÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛÌ̡ШÐÍ
´ÐÒ´Ò¥ÐЈÐÐÛÐÏÐÐÐÿ¥Ó˜˜ð¡Í₤ˋÐ₤ÐÐÛӿШҴÍÐÐÎÐЈÐÐÿ¥Ð
ÐЈÐÐÀÿ¥Ò̓
ÐÛð¤ÍÛ(2)ШÐÊÐÐÎÐ₤ÿ¥ÿ¥ˋÍаÿ¥ˆÐÛÍð¤¤ÕÂҨШÐÐÐÍðƒÒ¢¯ÐÌÀÓ´ÐÐÐдШÐÐÈÐÎÒÈÍ¥ñÐÿ¥Ó˜˜ð¡Í₤ˋÍÊÌݤÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÒÀÓÛÐÐÿ¥ÿ¥ÒÀÓÛÿ¥ÿ¥Ò̓
ÐÛð¤ÍÛ(4)ШÐÊÐÐÎÐ₤ÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛÌ̡Шÿ¥ÏШÕÂÐÐÒ´Ò¥ÐÐÐÐдÐÐÐÈÐÎÿ¥Ó˜˜ð¡Í₤ˋÍÊÌݤÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÿ¥ÐÐÿ¥ÿ¥ÒÀÓÛÿ¥ÿ¥ð¢ÀÓ´ÌÏÐÍ̓ˋÐÐÐÒˆ˜ÓʤÐÐÐÎÐÐÐÛÐÏÐÐÐ
ÐÐÐЈÐÐÿ¥Ò̓
ÐÛð¤ÍÛ(2)ШÐÊÐÐÎÐ₤ÿ¥ÿ¥ˋÍаÿ¥ˆÐÛÍÒ´ÍðƒÒ¢¯Ð₤ÿ¥ÍËÐÛÌˋð¥ÐÛÓÛÌðƒÒ¢¯ÿ¥ð¿ÿ¥Âÿ¥ÐÛÿ¥(2)ÿ¥ÐÏÐÐÐÿ¥ÐÐÛÐÐЈͧ¿ÍýÐð¡ÐÐШÒÑ°ÐÐÒ´¥Ì ðƒÀÍÊÐÌÐÊÐÐÛÐÏЈÐÐдÐ₤ÿ¥ÍƒÒ¢¯ÐÐдÐÐÐÏÐÐÐЃÐÿ¥Ò̓
ÐÛð¤ÍÛ(4)ШÐÊÐÐÎÐ₤ÿ¥Ðÿ¥Ï̯ШÐÌÝÐÐдҴÐÈÐÎÌÇÍÐÐÐÈÐÐÐÐÏÐÐÐдÐÐð¥ÒÐÒ´Ò¥ÐÐÌÌ¡Ðÿ¥ÐˆÐÿ¥ÓÇÌËÓÛÌÐÐÌ´ÐÛðƒÒ¢¯ÐÛð¢ÀÓ´ÌÏÐÒÈÍ¥ñÐÐÌÌдЈÐÐÛÐÍ
´Ðð¡Í₤ÒÏÈÐÏÐÐÐ
ÿ§ÐÒ̓
ÐÛð¤ÍÛ(2)Íа(4)ШÐÊÐÐÎÿ¥Ì˜ð£ÑÓ°Í
ËÌ¡Ìñ£ð£ÐÛÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛÐÀÐÂШͧÒˋýÌÇÒÀШÕÂÐÐÒ´Ò¥ÐЈÐÿ¥ÐƒÐÿ¥Í¿°Ìÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËШÒÀÐÐÐÍð¤¤ÕÂҨШÐÐÐÎÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐͧÒˋýÌÇÒÀШҴÍÐÐÎÐЈÐЯÐÐÐÏЈÐÿ¥Ó°Ó¨ð¤¤ÐÍ¿°Ìÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËШÍÛ̧ÐÐÍð¤¤ÕÂҨШÐÐÐÎÐ₤ÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1Ð₤ÿ¥ÐÐÐÛÿ¥ð£ÑÐ ÐÓÛÌÐÐÎÐÐÿ¥ÐÐÛð£ÐÛÒÀÓ¤Ð₤ð¤¤ð¥ÐÐÏÒÐÐÐдÐÐÐÐÐдҢ¯Ð¿ÐÎÐÐÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐÛÒçÊð£ÍÓ´ÓÇÐÛ̓ÐÛÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥Ð
ЃÐÿ¥ÌÌ¡ÓÛÝШÌͧÐÐÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛÌÌ¡ÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥Ð¨Ð₤ÿ¥Ò̓
ÐÛð¤ÍÛ(1)ÐÛТÐÓÇÌËÓÛÌÐÐÐÐÛдÐÐÎÒ´Ò¥ÐÐÐÎÐÐÿ¥Ò̓
ÐÛð¤ÍÛ(4)Ð₤ÿ¥ÐÐÐÛð£ÿ¥ÿ¥Ï̯ШÐÌÝÐÐдҴÐÈÐÎÌÇÍÐÐÈÐÐÐÐÏÐÐÐдð¥ÒдÐÐÎÒ´Ò¥ÐÐÿ¥Ò̓
ÐÛð¤ÍÛ(2)ШÒˋýͧÐÐÒ´Ò¥Ð₤ЈÐÐ
ÿ§ÐÍð¤¤ÕÂҨШÐÐÐÎÿ¥Ò̓
ÐÛð¤ÍÛ(2)ÍаÍ(4)ШÐÊÐÐÎÒ´ÍÐЈÐÐÈÐÐдШÐÊÐÐÎÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1Ð₤ÿ¥ÍÍ₤ƒÍ¯ÍШÐÐÐÎÐ₤ÐͧÌÐÛÿ¥ÈÍ₤̧ҴÙÕñдÕÂÒ¨ÐÐдÐШÒˋÝÐÐÐÛÐ₤Ð ÐÐÛð£ÑÐÒ´ÐЃÐÐÐÐÐдÐÐÒ°ˆÍШÍ₤ƒÐÿ¥ÐУÐÐÛð£ÑШÐÊÐÐÎÐ₤ÿ¥ÐÐÐÐÛдÐÿ¥ÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÐÛÌÓ¿ÐÏÿ¥ÒˆÍÐÛÌÌ
ÐÛð¡ÙÐÏÿ¥Ì§Ò´ÙÐÿ¥ÂÐÐÐÛУÐШÿ¥ÒˋÐÌÐÈÐÎÐÐЈдÐÐÿ¥Ðдÿ¥ÐÐÛЃЃÐÐÛÍÕÀÐÐÐÐÐШÐÐÐÎÐЃÐЈÐÈÐÎÐÐ̯ÌÐÀÐдÐÎÐÍ¥ñÐÐÈÐÐÛÐÏÐÿ¥ÐÊÒ´ÐÈÐÎÐÎÐð§ÐÐÐÎÐÐЈÐÿ¥ÐÏÿ¥Ð£ÐШÌÌ¡ÐÐÎÐð¤¤ÐÐÐÐÐÐÐÐÈÐÎÒÐÐÎÐÐÐÛШÿ¥Ì˜ð¤¤ÐÐÐÈÐÎЈÐÐÈÐÎЈÐÈÐÐð§ÐÐÐЈÐдÐÐÍÏ¢ÍÂШÐÊÐÐÎÿ¥ÍÊÏÍÊÐÐ₤Ðÿ¥ÐÐÐÐð£Ëð¡ð§ÐÒ´ÐÈÐÎÐдÐÐ̯ÌÐÀÐ₤ÐÐЃÐÐÐÐдÌÓ¤ШҢ¯Ð¿ÿ¥Í¥ÐÓÑÐÒÈÍÊÕñÐÛÐÐÓÙÐÐÕð¡ÙÐ ÐÈÐÐÐÐÏÐÐÿ¥ÓÑÐÐÎÐÐÈÐÐÐÈÐÎÐÐÐ ÐЃÐÐÐÐÛÒ°ˆÍШÍ₤ƒÐÐÎÐÿ¥Ðÿ¥ÊÐÐÐÛÐдÐÐÒ´ÐÈÐÎЈÐдÐÐÐÛÐ₤ÿ¥Ì¯ÌÐÀÓШÐ₤ÿ¥ÐÐÛдÐШÐÐÿ¥ÐÌÐÐÐÐÐÈÐÎÐÐÐÛÐÏÿ¥ð§ÐÐÐÎÐÐÐЈÐÐРЈдÐÐ̯ÌÐÀÐÍ¥ñÐÐÈÐÐÐÐÏÐÐÐд҈˜ÌÐÐÎÐÐÿ¥ÿ¥¿1Òˆ¢Ì¡ÿ¥Ó˜˜ð¡Í₤ˋÿ¥ÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÿ¥ÒÀÓÛÐÐÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÒÀÓÛÿ¥Ð
ÐÐÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1Ð₤ÿ¥ð¡£Í¯ÍШÐÐÐÎÐ₤ÿ¥Ðÿ¥ð¤¤Ð₤ÿ¥ÐЈÐÐÛÒˋÝÐÒÐÐÎÿ¥ÌÇÍÐ₤ÿ¥ÐÐÐ₤ЈÐÐРдÿ¥ÐЈÐÐÒ´ÐÈÐÎÐÐдÐ₤ÐˋÐÐð¤ÍÛдÿ¥ÍÛÂÒΰÓЈð¤ÍÛÐÿ¥ÐÐÐÐ₤УÐÐÛð¤¤ÐÛÒ´ÐÈÐÎÐð¤ÍÛдÕÐÐРдÿ¥Ð ÐÐÿ¥Ì˜Í§Ð₤ÌÇÍÐ₤ЈÐÐРдÐÐÐÐЈÍ₤ƒÍ¢ÐˆÐÛÐÿ¥ÐÐдÐÿ¥ÐЈÐÐÐÐÈÐÝÐÒ´ÐÈÐÎÐÐдÐ₤ÿ¥ÐÐÐ₤ÐÐÐÐÐÐЈÐÿ¥ÐÐÐð¤ÍÛÐÐÐÐЈÐдÐÐÍ₤ƒÍ¢ÐˆÐÛÐÿ¥ÐÐÛÒƒ¤ÐÛÐÐËÐÂапÐ₤ÐÐдÐÐÒ°ˆÍШÍ₤ƒÐÿ¥ÐÐÐÐÐÐÐЈÐдÐÐÐÐЈÿ¥ÓÏÐÛÒˋÝÐÿ¥ÐÐÐÐÐÐЈÐÐÈÐÎÐÐÐÿ¥ÐÐÐÐÐдÐÐÐÈÐÐРЈдÐÐÐÐШÒÐÐÎÐÐÐдÐÐÐçÐШÓÏÐ₤ÌÐЃÐÐÐÐÐÐÐÛдÐШÐ₤ÿ¥Í₤̧ҴÙÕñÐð¡£ð££ÐÐÀÐÿ¥ÓÏÐÛð£Ì§Ò´ÙÍ
ÐÏÓ§ÛÐÐÐÎÐÐÓ¨Í ÇШÍ₤ƒÐÐÎÿ¥ÍÊÏÍÊÐ ÿ¥Ð¢ÐЈШÍñÐÐÐÐÐÎÐдÐÐÐÐÐÐдÐ₤ÿ¥ÐÐÿ¥ÐÌÐÐÐÐÏÍÐÐÈÐÎÐÐÐÛÐÏÿ¥ÍÊÏÍÊÐ ÐÙдÐÐÐдÐÏÿ¥ÐÐÐÐÍȯÌÐЈÐˋÐÐÐÈÐÐÐШÌÐЃÐÐÐдð¡£ÒΰÓШ͢ÐÐÎÐÐдðƒÒ¢¯ÐÐÎÐÐÿ¥ÿ¥¿1Òˆ¢Ì¡ÿ¥Ó˜˜ð¡Í₤ˋÿ¥ÐÛÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÿ¥ÒÀÓÛЈÐÐÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÿ¥ÒÀÓÛÿ¥Ð
ð¡Ò´ÍÍ₤ƒÍ¯ÍШÐÐÐÒˆ˜ÌÐ₤ÿ¥ð¡Ò´ð¡£Í¯ÍШÐÐÐÍÓÙдÌÇÍÐÐÎÐÐÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1Ðÿ¥ÓÍÛÒ̓
ÐÛð¤ÍÛ(2)ÍаÍ(4)ÐÓÛÌÐÐÎÐÐÐÛÐÏÐÐЯÿ¥ÌÂÐÐÎÒ´ÍÐÐÐдÐÌÏÐÐÓÓÝдÐÐÎÐ₤ð¡ÍÍÐÏÐÐдÐÐÐÐÐ̓Ðÿ¥Íƒð£ÐÐÛÓÓÝдÐÐÒÐÐÐЈÐÐ
Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1Ð₤ÿ¥ð¡Ò´ÐÛÐÐШ҈˜ÌÐÐÍð¤¤ÕÂҨШÐÐÐÎÐ₤ÿ¥ÒͧÐÛð¤ÍÛÐÒ¢¯Ð¿ÐÐдШÐÊÐÐÎÿ¥Í¢ÓÓÌçÌÐÐÐÈÐдÐÐÐдÐÍÛ¿ÌШ̴Í₤ÐÐÐдÐÐÏÐÐÐ
ÿ§ÐЃÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛÕ°Ò¢¯Ì¡ÿ¥ð¿ÿ¥Âÿ¥ÿ¥ÿ¥ð¡ÙШÐ₤ÿ¥Ðð¤ÌÀ(2)д(4)ШÐÊÐÐÎÐ₤ÿ¥ÓÛÌÐÐÌËð£ÐÐÐ₤ÐÈÐÐÒÎÐÐÎÐЈÐÐÈÐÐÛÐÏÿ¥ÿ¥ÌÐ₤ÐÐÐÛÌÛçÕÐÏÐ₤ÌÌ¡ÐÐÿ¥Òˋ°ÐÐÒÐÐÐÐдÐÐÐдÌÐÈÐÎÐÐÐÛÐÏÐÐÛÌÐ₤ÒˋÝÐÐÐдÒÐÐÎÐЃÐÐÐÐдÐÛÒ´Ò¥Õ´ÍÐÐÐÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥Ð
ÐÐÐÿ¥ð¡Ò´Òˆ˜ÌШÍÐÐÎÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛÌÌ¡ÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ð¡ÙШÐ₤ÿ¥Ò̓
ÐÛð¤ÍÛ(4)ШÕÂÐÐÎÐÿ¥ÐÐÐÛð£ÿ¥ÿ¥Ï̯ШÐÌÝÐÐдҴÐÈÐÎÌÇÍÐÐÈÐÐÐÐÏÐÐÐдÐÛÒ´Ò¥ÐÐÐÿ¥ð¡Ò´Ð₤ð¡ÍÓЈ҈˜ÌÐÏÐÐÐÌÌ¡Òˆð§Í¢ÍÐÏÓ¨₤ÓñдЈÐÐÛÐÏÐÐÐÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÒˆÒ¤¨ÿ¥Ò̓
ÐÛð¤ÍÛ(1)ШÕÂÐÐÎÐÿ¥ÌÌ¡ð¡ÙÐÏÿ¥ÌËð£ÐÐÓ¿ÍÛÐÐÎÒ´Ò¥ÐÐÎÐÐÐÐÐÏÐ₤ЈÐÐÛÐÏÐÐÐÐÿ¥ÐÐÛÌÓ¿ÐÏÿ¥ÓÍÛÓÛÌÐÐÐÛÐÏÐÐЯÐÐÛдÐÐÒ´Ò¥ÐÐÐÛÐÒˆÓÑÐÏÐÐÿ¥ÍÐÐÌËð£ÐÐÓ¿ÍÛÐÐÎÐЈÐð£ÐÛÒ
ÐÛÓÛÌÿ¥ð¥Òÿ¥Ð ÐÐÒ´Ò¥ÐÐÐдШÍÓÌÏÐ₤ÒˆÐÐÐЈÐдÐÐпÐÐÏÐÐÐ
(ÿ§°)ÐÓçÒ¨
ð£Ëð¡ÐÛдÐÐÐÏÐÐÈÐÎÿ¥Ò̓
ÒÀÓ¤ÐÛÌÓÀÐð¤Ó¿Ð´ÐˆÐÈÐÎÐЈÐÐÿ¥Í
ñð§ÓЈÌÇÒÀШÐÐÓÒñÀÓÙÐÛÍÛÂÒΰÓð¤ÍÛÐÒˆÐÐШÒÑ°ÐÐÒ´¥Ì ÐЈÐÿ¥Ó¿ÍÛÐÛÒ̓
ÒÀÓ¤ÐÓÛÌÐÐдÐÐÒ
дÒÀÓ¤Ò
дÐÐÐÒ
ÐÛÓ¡ð¤Ð¨ÓÓƒÐÐðƒÒ¢¯ÐÍÙÐÐÐÛТÐÏÐÐ̘ð£ÑШÐÐÐÎÿ¥Ò̓
ÐÛð¤ÍÛ(1)ÿ¥ÿ¥ÊСÐÛÌÇÒÀÿ¥Ð¨ÕÂÐÿ¥ÌÇÒÀÐÛӴͤÎÐ₤ÿ¥Í§ÒˋýÌÇÒÀÒÀÓ¤ÐÛÌÏÌ ¥ÐͤÓÊð£ÐÐ̘ͤÓÒÎÓÇ ÐÏÐÐÈÐÎÿ¥ÓÛÌÐÐÍ ÇÍШÐ₤ӿШͯÒÝÀШÌÛÐÈÐÎÐÐÐпÐð¤Õ
ÐÏÐÐÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛÌÕÿ¥Í̯ШÐÊÐÐÎÐÛÒˆ˜ÌÐ₤ÿ¥ÐÐÛÌÐ
ÐÏð¤Ò£Âð¡Ò£ÂÐÐÎÐÐÿ¥Í
´Ðð¡Òý¨ÌÏÐЈÐÐдÿ¥ð£ÛШÌÇÒÀÐÛӴͤÎÐÓ¡Ûͯ҈ÍÛÐÐдÐÐÎÐÿ¥ð¡ÍÛÌÕÿ¥Í¯ÐˆÐдÐÿ¥ÿ¥Íð£Ëð¡ÐÐÐÐдÐÐЯÿ¥ÍÛÂÒΰÓÓÒñÀÐÌÛÐÒÓÑÌÏÐÕ¨ÐÐÿ¥ð§ÐÐÛÓÒñÀÐÒÎͧÐÐЈÐÐдÓÙШÓ
ÏÐÐдÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛðƒÒ¢¯Ð¨ÿ¥ÐÐÐ ÐÐÏÓÇÐÀШÒ̓
ÐÛð¤ÍÛ(1)ÐÒˆÐÐÐдÐÐÏÐÐУÐˋÐÛÕ¨Ðð¢ÀÓ´ÌÏÐÒˆÐÐÐдÐ₤ÐÏÐЈÐÐ
ЃÐÿ¥Ò̓
ÐÛð¤ÍÛ(2)ÿ¥ÿ¥ËСÐÛÌÇÒÀÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎÐ₤ÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛÐÀÐÂШÐÌ̡ШÐÒ´Ò¥ÐЈÐÿ¥Íð¤¤ÕÂҨШÐÐÐÎÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÒ´ÍÐÐÎÐÐÐÿ¥ÐÐÛÍÓÓЈ҈˜ÌÐ₤ÒÎͧÐÐЈÐÐÐ´Ð¨Í Ðÿ¥ÐÐÐÈÐÎÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1Ð₤ÿ¥Íð¤¤ÕÂҨШÐÐÐÎÿ¥Ò̓
ÐÛð¤ÍÛ(1)Ð ÐÐÓÛÌÐÐдҢ¯Ð¿ÐÎÐÐÐдШÓ
ÏÐÐдÿ¥ÍËÐÛÌˋð¥ÐÛÓÛÌШð¢Ðÿ¥ˋÍаÿ¥ˆÐÛÍð¤¤ÕÂҨШÐÐÐÍðƒÒ¢¯ÐÏÒÈÍ¥ñÐÐдÐÐÎÐÿ¥Ò̓
ÐÛð¤ÍÛ(2)ÐÒˆÐÐÐдÐÐÏÐÐУÐˋÐÛÕ¨Ðð¢ÀÓ´ÌÏÐÒˆÐÐÐдÐ₤ÐÏÐЈÐÐ
ÐÐÐÎÿ¥Ò̓
ÐÛð¤ÍÛ(4)ÿ¥ÿ¥ÏСÐÛÌÇÒÀÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎÐÿ¥Ò̓
ÐÛð¤ÍÛ(2)дÍÌÏÐÏÐÐÐÐ´Ð¨Í Ðÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛÐÀÐÂШÐ₤ÿ¥ÏСÐÛÌÇÒÀШÐÊÐÐÎð¥ÒÐÐÌ´ÐÛÒ´Ò¥ÐÐÐÿ¥ÓÇÌËÓÛÌÐÐÐддÌÓ¤ШӡÍÐÐÐÐÛÐÏÐÐð£Ëð¡ÿ¥ÒˆÐÓÛÌÐÐÌ´ÐÛÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛðƒÒ¢¯ÐÌÀÓ´ÐÐÐдÐ₤ÐÏÐЈÐÐ
ÐÊÐð£ÒÙñÒñÍÀÿ¥ˋÍаÿ¥ˆÐÛÍðƒÒ¢¯ÐÛð¢ÀÓ´ÌÏШÐÊÐÐÎ
Ó˜˜ð¡Í₤ˋÐ₤ÿ¥ÿ¥ˋÍаÿ¥ˆÐÛÍðƒÒ¢¯Ðÿ¥Ò̓
ÐÛð¤ÍÛ(2)ÿ¥ÿ¥Ëÿ¥ÐÛÒˆÍÛШÐÐÐÎÓ˜˜ð¡Í₤ˋÍÒ´ÇÍÍÿ¥¿1ÐÛðƒÒ¢¯ÐÒÈÍ¥ñÐÐÐÐÐÛÒ´¥Ì дÐÐÎÿ¥ÿ¥ˋÐÛðƒÒ¢¯ÐÒ̓
ÐÛð¤ÍÛ(3)ÿ¥ÿ¥ÎСÐÛÌÇÒÀÿ¥ÐÒˆÍÛÐÐÍ₤ð¡ÐÛÒ´¥Ì дÐÐÎÐÐÐÐÌÀÓ´ÐÐÎÐÐÐÿ¥ÓÓÝÐЈÐÐдÐ₤ÿ¥ÍÒ´Ó˜˜ÿ¥ÐÛÿ¥(2)ÐÏÒ¢¯Ð¿ÐдÐÐÐÏÐÐÐ
ÐÎÐÒ´¥ð¤¤ÿ¥ÂÐÛÒ´¥Ò´Ð¨ÐÊÐÐÎ
Ó˜˜ð¡Í₤ˋÐ₤ÿ¥Ò´¥ð¤¤ÿ¥ÂÐÛÒ´¥Ò´Ð¨ÐÊÐÐÎÿ¥ð¡Õ
ÐÒ´ÙÐÿ¥ÿ¥ÂÐÒˆÍЈÐШ̴̡˜ÐÐÎÒ¢¯Ð¿Ðÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÒͧÐÛðƒÒ¢¯ÐÐÐÍÌˋÍ
ÍÛ¿ÐÓ¯ÀÍШÌÌËÐÐÐÐÿ¥Ò´¥ð¤¤ÿ¥ÂÐÛÒ´¥Ò´Í
´ð§ÐÛð¢ÀÓ´ÌÏÐÓÐÐÐÐÐÛдÐÐÎÌÌËÐÐÎÐÐÐ
ÿ¥ÂÐÛÒ´¥ð¤¤Í¯ÍШÐÐÐÎÐ₤ÿ¥ÿ¥ÂÐÛÒ´¥Ò´ð¡ÙШÿ¥Ò´ÒÒÑ°ÐÐÐÏÐÐÈÐÐÓ´ÌЈ҈˜ÌÐÓÛШð£ÐÐÐÿ¥ð¤¤ÕÐÛÒ§ÍУÌÏÌ ¥ÓÙÐ₤ÍÍñÛð¡ÍËÐÏÐÐÈÐÎÿ¥Ò´ÒÒÑ°ÐÐÐÏÐÐÈÐÐÓ´ÌЈ҈˜ÌÐ̃ÐÐÐÐЯÐÐÐÏÿ¥ÍÍЈÍÍ°ÐÐÐÐдЈÐÒ´¥Ò´Í
´ð§ÐÛð¢ÀÓ´ÌÏÐÍÎÍÛÐÐÐдÐÐÐÛÐ₤ÍÕÀÐÏÐÐÐÌÛШÿ¥ÿ¥ÂÐ₤ÿ¥Ì˜ð£ÑÐÏÐ₤ÿ¥Ó₤Ó§ˆÒ
дÌݤÐð£ÐÐÐÐÐÛдÍÌÏÐÛÓ¨Í ÇШÐÐÿ¥ÒˆÍñÝÐÛÓÀÍÛÐÌÐÐШÐÐÐдÐÐÐЃÐÿ¥Í¢
ÒÎð£Ëð¡Ð¨Í¥ÒÏÈÐÐÐÐÿ¥ÐÐÛÓçÌÓÀÓЈͥÒÏÈдЈÐÐдÐЃÐÍ¢Ì
ÓШÓÒÏÈÐÏÐÐдÐÐÐÏÐÐÐ
ÐÐÐÐÍð¤Ò¨Íð¤¤Ð´ÍÛÒ°ˆÓШÍÌÏÐÛÓ¨Í ÇШÐÐÒ
Ð₤ÿ¥ÓÛÌÒ
ÐÒͧÐÛðƒÒ¢¯ÐÐÐÍÌˋÐÍÓÓШ҈˜ÌÐЈÐÐЯЈÐЈÐÓƒˋÍЈÐˋÐÒý ÐЈÐÐÿ¥ÒͧÐÛðƒÒ¢¯ÐÐÐÍÌˋÐ₤ͧð¤¤ÐÛÍ
Í¢ÐÛÍÕÀÐÏÐÐÈÐÎÿ¥ÐÐÐÍÓÓШ҈˜ÌÐÏÐЈÐÐÐдÐÐÈÐÎÿ¥Ò´¥ð¤¤ÿ¥ÂÐÛÒ´¥Ò´ÐÛð¢ÀÓ´ÌÏÐÓÐÐÐð¤Ì
дÐÐÎÍÐð¡ÐÐÐдÐ₤ÐÏÐЈÐÐ
дÐÌÙÍ¿Í¡ÐÛÍÛ̧ÐÐÒˆ¢Ì£Ð¨ÐÊÐÐÎ
ÌÙÍ¿Í¡Ð₤ÿ¥Í¿°Ìÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥ÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÍÓÍÏÍÀð¥Ò°ÌÐÏÐÐÐÓ¿ÍËÕÊÒÙñÒð¤¤ÐХРÿ§ÐÛÒˆ¢Ì£ÓçÌШÐÊÐÐÎÐдÕÀÐÐÒ°Ìÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐÌÓʤÐÿ¥Ðÿ¥ÐÒˆ¢Ì£ÓçÌÐдÐÐÎÿ¥ÐÍÍËÐÛÍ
ñð§Óð¤ðƒÐ¨ÐÊÐÐÎÿ¥ÒÀÓ¤Ò
ÐÐÐÛÒÀÓ¤ÐÒ´¥Ì ÓÙШÐÐÓ¿ÍÛÐÐШÐ₤Ò°ÐЈÐÐÈÐÐÿ¥Í§Òˋý̧ҴÙÐÛÒñÍÀÐÍ
ËÌÒ
ÍÛÑÌÐÐÐÛӡ̯ͧÐÛÍ
ñð§ÓЈҴ¥Ò´Ðð£ÒÙñÒ´ÕýЈÐˋͧÒˋý̧ҴÙШÐÐÐÕÂð¢Ì¡ÕÀÐÛÒ´ÕýÓÙÐÐÿ¥Ò̓
ШÐÐÈÐÎÓÐÐÍ₤Ò§ÌÏÐÛÐÐÓçÌÐÒˆÐÐÐÐÐÐÐ´Í ÝÍÐÐÐÐЈÐÐÀÿ¥ÌÙÍ¿Í¡Ð₤Ò´ÇÒ´Ò°Ìð£Ëð¡Ð¨Í¤Ó₤ЈҴ¥Ì Ò°ÌШÍÑÓÇЈÐÓÇÌËÌËÐÐÎÒˆ¢Ì£ÐÍÛ̧ÐÐÐÐÛÐÏÐÐÈÐÎÿ¥ÐÐÐÏÐЈÐÐÍÍËÐÛÍ
ñð§Óð¤ðƒÐ¨ÐÊÐÐÎÿ¥ÒÀÓ¤Ò
ÐÐÐÛÒÀÓ¤ÐÒ´¥Ì ÓÙШÐÐÓ¿ÍÛÐÐШÐ₤Ò°ÐЈÐÐÈÐÐÐÛÐÏÐÐÐ
Òˋ°ÓǯÐ₤ÿ¥ÍÒ´ÿ¥(4)ÐÏÒ¢¯Ð¿ÐдÐÐÐÏÐÐÐ
(2)Ð̘ð£ÑÒ´ð¤ÿ¥ÿ¥Ð¨Ò´Ò¥ÐÐÐÌÓʤð¤ÍÛÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎ
ÐÂÐ̘ð£ÑÒ´ð¤ÿ¥ÿ¥Ð₤ÿ¥Ì˜Ò´ÇÌÒçñ̓ÿ¥ÐÌÒ¢ÐÐÓçÐÍ¿°Ìÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËð£Ðÿ§Ì¯ÒÐÛÌÍШÌýÒ¥ÐÐÐÒ´ð¤ÐÏÐÐÿ¥ÌÓʤð¤ÍÛÿ¥Ð₤ÿ¥ÐÍÊÕÐÛÓÌ¢ÐÐÐÐЈÐЈÐˋÐÛð¡ÕˋÍЈð£ÒÙñÐ₤ÿ¥Í¿°Ìÿ¥ÿ¥Í¿ÇШÍ
ËÐÈÐÎÐÓÑÐÐÎÐÐÐÐÐÛÐдÐð¡Í¡Ð¨Í ÝÍÐÐÐÿ¥ð§ÐÛÍ₤ƒÍ¢ÐÐÐÐÎÐЈÐÐÐдÐÐð¤ÍÛÐÏÐÐÐ
Ó˜˜ð¡Í₤ˋÐ₤ÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿3ÐÕ͘ÐÐÍ ÝÍÕð¥Ð¨ÐÐÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛÍ ÝÍÍ
ÍÛ¿Ðð¢ÀÓ´ÐÐÐдÐÐÏÐÐдÐÿ¥ÐÐÐ ÐÐÌ ¿Ì дÐÐÎÓÇÐÀШÿ¥Ì˜ð£ÑÒ´ð¤ÿ¥ÿ¥Ð¨ÌÓʤÐÐÐÌÓʤð¤ÍÛÿ¥Ð₤ÓÍÛд҈ÐÐÎÐÐÐ
ÐÐÐÎÿ¥Ó˜˜ð¡Í₤ˋÐ₤ÿ¥ÐÒ¨Íÿ¥¿1Ð₤ÿ¥Ì˜Ì°Í£ñШÐÐÐÎÐÍ¿°Ìÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥ÌШӤÒÎÐÐÒñÍÀÐÛÒ̓
ÒÀӤШÐÊÐÐÎͧÒˋýÒñÍÀÐÛÍÍÐ̧ҴÙÐÛÍ₤ƒÍ¢ÓÙШÐÊÐÐÎÍ
ñð§ÓШҢ¯Ð¿ÐÎÐÐÐд҈˜ÓʤÐÿ¥ÐÐÐÏÐÿ¥ðƒÒ¢¯Í
ÍÛ¿ÐÛÍ
ñð§ÌÏÐð¢ÀÓ´ÌÏÐÒˆÐÐÓÓÝдÐÐÎÐÐÐ
ÐÊÐÓ˜˜ð¡Í₤ˋÐ₤ÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛÍ ÝÍÍ
ÍÛ¿Ðÿ¥ÐÍ¿°Ìÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥ÌШӤÒÎÐÐÍÍÐÛÒ̓
ÒÀÓ¤ÐÛÍ
ÍÛ¿ÍаÐÐÛÕÐÛ̧ҴÙÐÛÍ₤ƒÍ¢Ðд̧ÒÝÀÓЈ҈ÍÛÐÐÐÎÐÐÐ ÐÐÏÿ¥ð¡Ò´Í ÝÍÕð¥Ð¨ÐÐÐÎÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1Ðÿ¥Ò̓
ÒÀӤдÐÐÎÐˋÐÛÐÐЈð¤ðƒÐ¨ÐÊÐÐÎÐˋÐÛӴͤÎÍ
ñð§ÓÐ¨Í ÝÍÐÐÐШÐÊÐÐÎÍ
´ÐÒ´ÍÐÐÎÐЈÐÐ
ÐÐÐÐÿ¥Ó˜˜ð¡Í₤ˋÐ₤ÿ¥Ðð¡Ò´Ò¨Íÿ¥¿1ÐÛÍ ÝÍÍ
ÍÛ¿Ð₤ÿ¥Ò¨Íÿ¥¿1ÒˆÒ¤¨ÐÓÇÌËÓÛÌÐÐð¤ÍÛÐÏЈÐÐÐÛÐͨЃÐÐÎÐ₤ÐÐÐдÿ¥ÐÒ¨Íÿ¥¿3ШÐÐÌÙͿ͡ШÍ₤ƒÐÐÓ°Í
ËÐ̓ÐШӡÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÓÇÌËÓÛÌÐÐð¤ÍÛÐÍ ÝÍÐÐÐÐÐÛÐÐШ҈˜ÓʤÐÐÎÐÐÐÛШÿ¥ÐÍ
ËÌÒ
ШÍ₤ƒÐÐð¡ÕˋÍЈÍÎÕÐÓÑÐÐÎÐÐд҈ÐÐÐÐдÿ¥ÒÊ̯ÐÛð¡ÕˋÍЈÍÎÕÐÍÙÍ´ÐÐÐÐÛÐÐШ҈ÍÛÐЈÐÐÿ¥Í ÝÍÐÐÐдÐÐÍ
ñð§Óð¤ðƒÐð§ð¡ÐÊÒˆÍÛÐÐÎÐЈÐÐÛÐÏÐÐÐ
Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1Ðÿ¥Í¿°Ìÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËШÍÛ̧ÐÐÐÒ¨Í̘ð¤¤Í¯ÍШÐÐÐÎÿ¥Í¿°Ìÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥ÌШӤÒÎÐÐÍÍÐÛÒ̓
ÒÀӤдÐÐÎÒ¢¯Ð¿ÐÎÐÐÐÛÐ₤ÿ¥ÍýÀÍ°ÑÐÍʈӯШÍ₤ƒÐÐÎÒÀÐÈÐдÐÐÒÀӤШÐÊÐÐÎÐ ÐÐÏÐÐÿ¥ÿ¥¿1Òˆ¢Ì¡ÿ¥Ó˜˜ð¡Í₤ˋÿ¥ÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÒÀÓÛЈÐÐÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÿ¥ÒÀÓÛÿ¥ÐÐÐÛðƒÒ¢¯Ð¨ÍƒÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1Ðÿ¥ð¡Ò´Í ÝÍÕð¥ÐÏÿ¥ÍýÀÍ°ÑÐÛð¤ðƒÐ¨ÐÊÐÐÎÍ ÝÍÐÐдÐÐÎÐÿ¥Ó˜˜ð¡Í₤ˋÌ°Í£ñÐÏÒ¢¯Ð¿ÐӴͤÎШЃÐÏÍ
ñð§ÓÐÏÐÐÈÐÐÐÌÐÐÐÏÐ₤ЈÐÐ
ÐÐÐÿ¥Ó˜˜ð¡Í₤ˋÐ₤ÿ¥ð¡Ò´ÐÛдÐÐÿ¥Ðð¡Ò´Ò¨Íÿ¥¿1ÐÛÍ ÝÍÍ
ÍÛ¿Ð₤ÿ¥Ò¨Íÿ¥¿1ÒˆÒ¤¨ÐÓÇÌËÓÛÌÐÐð¤ÍÛÐÏЈÐÐÐÛÐͨЃÐÐÎÐ₤ÐÐÐдÐЈÐÐÿ¥ð¥ÒÒ´¥Ò´Ð´ÐÐÎÐÛÌÏÒ°ˆÐ¨Í¢ÐÐÍÍ°ÐÍ
´ÐÐÐÎÐЈÐÐÛÐÏÐÐÐ
ÐÎÐдÐÐÐÏÿ¥ÌÓʤð¤ÍÛÿ¥Ð₤ÿ¥ÐÍÊÕÐÛÓÌ¢ÐÐÐÐЈÐÐдÐÐÍ
ñð§Óð¤ðƒÐͨÐÐÐÛÐÏÐÐÐÛШÿ¥Ó˜˜ð¡Í₤ˋÐ₤ÿ¥Ðÿ§Ð¨ÐÐÐÎÐ₤ÿ¥Ò¨Íÿ¥¿3ШÐÐÌÙͿ͡ШÍ₤ƒÐÐÓ°Í
ËÐ̓Ðÿ¥Í
ËÌÒ
ШÍ₤ƒÐÐð¡ÕˋÍЈÍÎÕÐÓÑÐÐÎÐÐÐÐÛд҈ÐÐÐÐÐд҈ÍÛÐÿ¥ÐÍÊÕÐÛÓÌ¢ÐÐÐÐЈÐÐдÐÐÍ
ñð§Óð¤ðƒÐÛÕ´ÍÐÌ´ÒÝÀÐÐЃЃÐÏÿ¥ÐÌÓʤð¤ÍÛÿ¥Ð₤ÓÍÛд҈ÐÐÐÐÐдÐÐÎÐÐÿ¥Ó˜˜ð¡Í₤ˋÍÊÌݤÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥Ð
Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1Ð₤ÿ¥Ó˜˜ð¡Í₤ˋÌ°Í£ñШÐÐÐÎÐ₤ÿ¥ÍýÀÍ°ÑÐÛð¤ðƒð£ËÍÊШÐ₤ÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿3ШÐÐÌÙͿ͡ШÍ₤ƒÐÐÓ°Í
ËÐ̓ШÐÐÈÐÒ̓
ÒÀÓ¤ÐÛÍ
ñð§Óð¤ðƒÐ¨ÐÊÐÐÎÐ₤Í
´ÐÒ¢¯Ð¿ÐÎÐЈÐÐ
Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛÍ¿°Ìÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥ÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËð£ÐÕ°Ò¢¯Ì¡ÿ¥ð¿ÿ¥Âÿ¥ÿ¥ÿ¥ð¡ÙШÐ₤ÿ¥Í ÝÍÍ
ÍۿШÐÊÐÐÎÓÛÌÀÌ¡ÐÐÏÓ¯ÀÍЈҴҥÐÐÐÐ ÐÐÏÿ¥ÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÐˆÐÐÿ¥ÿ¥ÒÀÓÛÿ¥ÿ¥ÐãÀÍ¿°Ìÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥ÿ¥ÌШÍÍÐÐÐЃРÒ̓
Ð₤ÐÐÐдÌÐÀÌÐÐÐÐð¤ÿ¥Í
ÍÛ¿Ð₤ÒˋÝÐÐÎЃÐÐÐÿ¥ÐдҴҥÐÐÐÎÐÐÐÿ¥ÐÐШÐÐдÐÐÍ
ñð§ÓÍ
ÍÛ¿Ð₤ÌÐÐШÐÐÐÎÐЈÐÐÐãÂÍ¿°Ìÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥ÌШӤÒÎÐÐÍÍÐÛÒ̓
ÒÀÓ¤ÐÛÍ
Íۿдÿ¥ÐÐÛÌÐÛ̧ҴÙÐÛÍ₤ƒÍ¢Ð¨ÐÊÐÐÎÐдÐÐÐÍ
ñð§ÓÍ
ÍÛ¿ÐÛÒ´Ò¥Ð₤ЈÐÐ
ÐÐÈдÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ð§ÌÐÛÍ¿°Ìÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËð£ÐÕ°Ò¢¯Ì¡ÐÏÐÐð¿ÿ¥Âÿ¥ÿ¥Ð¨ÐÐÐÎÍÐÐÎÿ¥ÌÓʤð¤ÍÛÿ¥ð¡ÙÐÛÐÍÊÕÐÛÓÌ¢ÐÐÐÐЈÐÐдÐÐÒÀӤШÕÂÕÈÐÛÐÐð¤Õ
ШҴÍÐÐÎÐÐÐÐÐÐÿ¥Ì˜ð£ÑÒ´ð¤ÿ¥ÿ¥Ð¨Ò´Ò¥ÐÐÐð¤ðƒÐÏÐÐÐÛШÿ¥Ó˜˜ð¡Í₤ˋÌ°Í£ñÐÏÐÛÓ¡ÌÌ¿ÐÛðƒÒ¢¯Ð¨ÐÕ°Ò¢¯Ì¡ÐÛҴҥШÐЈÐЃЃÿ¥ð¡Ò´Ì˜ð¤¤Í¯ÍÍÛ̧̓ÿ¥Í¿ÇÐÓçÕÐÐ̓Шÿ¥Í
ñð§ÓЈÍ
ÍÛ¿ÐÏÌͤÐÐÐдÐÐÐÛÐ₤ÍÎð§Ð¨Ðð¡Í₤ÒÏÈдÐÐУÐЈÐÐ
ð¿ÿ¥Âÿ¥ÿ¥ð¡ÙÐÛÿ¥(2)ÐÛÍÌÛçШҴҥÐÐÐð¤ÍÛÿ¥ÕÌÐÛð¤ðƒð£ËÍÊÐÛð¤ðƒÿ¥Ð₤ÿ¥ð¿ÿ¥Âÿ¥ÿ¥ÐÌͤÐÐÐÎÍÐÐÎÓ°Ó¨ð¤¤Ð¨ÌÓʤÐÐÐÍ
ÍÛ¿ÐÏÐÐÿ¥ÐÍÊÕÐÛÐСÐÈÐСÐÛÓÌ¢ÐÐÐÐÎÐЈÐÒñÍÀÐÐ̯ÍÐÐдҴҥÐÐÐÎÐÐÐÐÛÐÛÿ¥Ó¿ÍÛÐÐÐÎÐÐÐÛÐ₤ÿ¥ÙÒñÍÀÐ ÐÐÏÐÐдÐÐÿ¥ÍÒñÍÀÐ₤ÿ¥ÌǃÕÈÒñÍÀÐÏÿ¥Í¿°Ìÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥ÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËð£ÐÐÏÕÌÐÐÎÐÐÿ¥ÐƒÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1Ðð¥ÒÐÐÒñÍÀÐÛ̯ÍÐÌÐÐШÐÐÐÎÐÐÐÿ¥Ó°Ó¨ð¤¤Ð´ÐÐÎÐÓͧÐÛÓ¤҈ÐÛÐÐÐÐЈÐÐ
дÐÐÐÛð£Ó˜˜ð¡Í₤ˋÐ₤ÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛÐÍ ÝÍÍ
ÍÛ¿ÐÐÛð¢ÀÓ´ÌÏÐÒˆÐÐÐÐÐÛÓÓÝдÐÐÎÿ¥Ðð¡Ò´Ò¨Íÿ¥¿1ÐÛÍ ÝÍÍ
ÍÛ¿Ð₤ÿ¥Ò¨Íÿ¥¿1ÒˆÒ¤¨ÐÓÇÌËÓÛÌÐÐð¤ÍÛÐÏÐ₤ЈÐÐÐÛÐͨЃÐÐÎÐ₤ÐÐÐÿ¥ÿ§Ð¨ÐÐÐÒ̓
ÍÕÀÐÍÊÏÐÐÍÐð¡ÐÐÐÐ̓ШÒ¨Íÿ¥¿3ÐÛÕ͘ÐÐÍ ÝÍÕð¥Ð¨ÐÐÐÍ ÝÍÐÏÐÐÐдÐÐð¡Ò´Í ÝÍÍ
ÍÛ¿Ð₤ÿ¥ÿ§ÐÏÍÊÍÐÐÒ¨Íÿ¥¿1ШдÐÎÐ(ÐÐ)ð¡ÍˋÓдЈÐÍ₤Ò§ÌÏÐÐÐдÐÐÿ¥ÐÐÐÎÒ¨Íÿ¥¿1ÐͧÒˋýÍ ÝÍÐÐÐÎÐÐÐдÐÐÒ¨Íÿ¥¿1Ðð¡Ò´Í ÝÍÕð¥Ð¨ÐÐÐÎÌÛÌÇÒͧÐÛÍ ÝÍÐÐÐð¤Ì
ÐÐÐÐÐÐЈÐÐдÐÐÌÐÐÎÐÐÐ
ÐÐÐÿ¥ÐÐÐÐÛÓÓÝÐÿ¥ÿ¥ˋÍаÿ¥ˆÐÛÍðƒÒ¢¯Ð¨ÐÊÐÐÎÍÒ¢¯ÐÐдÍÌÏÿ¥Ì˜ð£ÑÐÛÐÐЈÓÑÌ°ð¡Ð¨ÐÐÐÎÐ₤ÿ¥ÌÇШÌ
ÕЈÍÍ°ÐÐЈÐЃЃÿ¥ð¡Ò´ð¤Ì
Ð ÐÐÐÐÈÐÎÍÛÍÓÿ¥ÕÀÍÓÿ¥Í§ÂÍ¥ÓШÍÊÌÙÐÐÎÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛÐÍ ÝÍÍ
ÍÛ¿ÐÐ ÐÐÌ ¿Ì ШÌÓʤð¤ÍÛÿ¥Ð₤ÓÍÛд҈ÐÐÐÛÐ₤ÿ¥ÌÐÐШÒÀÐÕÐÐÏÐÐÐ
ÿ¥ÐÍÍ₤ˋÐÓ˜˜ð¡Í₤ˋÐÛÍÊÌÙÐÍ¥Ó´ÐÐÎÌÓʤð¤ÍÛÐÓÍÛдð¢ÀÐÐÐдÐÛӡͧÌÏÐÛÍÊÌÙШÐÊÐÐÎ
Ó˜˜ð¡Í₤ˋÐ₤ÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿5ÐÐÿ¥ÌÓʤð¤ÍÛÿ¥Íаÿ¥ÐÛð¤ÍÛÐÓÍÛдð¢ÀÐÐÐдШÐ₤ӡͧÐÛÓÓÝÐÐÐÐÐÛд҈ÐÐÐÿ¥Ì˜ÀÐÛдÐÐÍÊÝͧÐÏÐÐÐ
ЃÐÿ¥ÍÒ´ÐÛдÐÐÿ¥Íÿ¥ÿ¥Íÿ¥ÿ¥Íÿ¥Íаÿ¥ÐÓÍÛд҈ÐÐÐЈÐÍ ÇÍÿ¥Íð¤ÍÛÐð¢ÀÐÐÐдШӡͧÐÛÓÓÝÐÐÐÐÐÛд҈ÐÐÐдÐÐÏÐЈÐÐдÐ₤ÿ¥ÍƒÒ¢¯ÐÛдÐÐÐÏÐÐÐ
(1)ÐÌÓʤð¤ÍÛÿ¥ÿ¥Ì˜ð£ÑÒ´ð¤ÿ¥ÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎ
Í
ËÌÒ
ÍÛÑÌÐÛÒ´¥Ò´ÓÙÐð¥ÐÐð§ÒÈÐдÐÈÐ̘ð£ÑÒ´ð¤ÿ¥Ð¨ÌÓʤÐÐÐÐÍÍÐÛ̧ҴÙÐÛð£ÒÙñÒñÍÀÐÿ¥Í
ËÍÝ
Ò
ÐÌÛÇÐÿ¥ÕÀШÕÐÐÐð§ÐÈÐÐÐдÐÐÌÓʤð¤ÍÛÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎÿ¥Ó˜˜ð¡Í₤ˋÐ₤ÿ¥ÓÍÛÌÏШÐÊÐÐÎÐÛÍÊÌÙÐÓʤÐЈÐЃЃÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿5ÐÐÿ¥ÓÍÛÐÏÐÐдð¢ÀÐÐÐдШӡͧÐÛÓÓÝÐÐÐÐÐÛд҈ÐÐÎÐÐÿ¥Ó˜˜ð¡Í₤ˋÍÊÌݤÐÛÓ˜˜ÿ¥ÐÛÿ¥(4)ÐÊ(ÿ§ý)ÿ¥ÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÒÀÓÛÐÐÿ¥ÿ¥ÒÀÓÛÿ¥ÿ¥Ð
ÐÂÐÍÍ₤ˋШÐÐÐÎÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿5ÐÐ₤ÿ¥ÿ¥ÊãÐÛÕ°Ò¢¯Ì¡ÿ¥ð¿ÿ¥Àÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐÐÐÛÍÓÿ¥ð¿ÿ¥Àÿ¥ÿ¥ÐÛÿ¥Ð£ÿ¥ÿ¥ÐÌͤÐÐÐ
ð¡Ò´ÍÓШÍÐÐÐÐÐÐ₤ÿ¥ÌËçÐÐÎÒÀÌÓЈÐÐÛÐÏÐÐÐÐÿ¥ÿ¥ÊãÐ₤ÿ¥ÍˋÓ´Ò
ÐÛÍÛÑÌдÐÐÎÿ¥ð¡Ò´Õ°Ò¢¯Ì¡ÿ¥ð¿ÿ¥Àÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐÛð¡ÙÐÏÿ¥ÐÓËÌ₤Ð₤ÿ§Ð¨ÐÐÐÐÿ¥Ó§Í
ÕÐÏÒÎÍÐð§ð¡ÐÐÎÐЃÐÐÐÿ¥ÐÐÛÍÿ¥ÒÇÍÐÐÐÈÐÐÐÐÎÐЃÐÐÐÒˆÍШÌÇÍÐÐçÐÐÈÐð¤¤ÐÛÐдÐÿ¥ÐÐÛÍȯÒýÐÐÿ¥ÐÒËÐÐÍ
ÐÀÐÐÐдÍÊÌÙÐÐÐÛРдÌÐЃÐÐÐЈÐˋдÐÐÈÐÌ´Ò¨ÐÒ¢¯Ð¿ÐÎÐÐÐ
ÐÐÐЈÐÐÿ¥ÿ¥ÊÐÒ´ÐÈÐÎÐÐÐÍÊð¡ÙШÐÍ
ÐÀÐÐÐÌËÐÎÌÛÇÐÈÐÐдÐÐÐдÐ₤ÿ¥ÍÛÂÒΰÓÒ´¥Ì ШÓ
ÏÐÐÐÎÐÐ̓ЈÐÐдЈÐÛÐÏÐÐÐ
ÐЈÐÐÀÿ¥ÿ¥ÊÐÛÒ¤¨ð§ÓÓÒñÀÐ₤ÿ¥Í¿°Ìÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÍÍÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÍШÿ¥ÍÛð¢ð£ÒÙñÒñÍÀШÐÐÈÐÎÓ¤ÒÎÐÐÿ¥ÍÍÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÍШÌÙÎÍýÀÓÒÙñÍ¡¨ÐÓ¤҈ÐÐÎÐÐÿ¥ÐÐÛÐдÐ₤ÿ¥ÊÐÛÓÒÙñÒ´ÕýÐÛÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÐÛ̘ÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐÛÒ°ÌÐÛÿ¥ÐÛÿ¥ÿ¥ÍÒˆ¢Ì£Í ÝÍÌ¡ÐÏÐ₤ÿ¥ÒçÊÓÇШÐÐÈÐÎð£ÍÐÐÐÍÐÛÕ´ÍÐÛ̓Íÿ¥ÒÀ´ÓÇÐÍ
ËÐÐÎÿ¥ÿ¥ÌÓÛð£ËÕÿ¥Ð¨ÿ¥Ì˜ÌШÓÇÌËÓЈҰÌÐÐÐÐ₤ÐÂÐÐÐÒ°ÌÓˆÍñÐð£ÐÐÎÓÑÇÐÐÐÎÐÐÐÓýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐÛУÐÿ¥ð£ÒÙñÒ´Õýÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÎÓÒÙñÌËÒˆÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÍÌËÐÛÿ¥ÿ¥ÎÓÒÙñÌËÒˆÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥Ð¨ÐÒ´Ò¥ÐÐÐÎÐÐÐ
ð¡Ò´Ò¤¨ð§ÓÓÒñÀÐÓÐÐÌÌÐ₤ÿ¥ÍÍ¿Çÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÐÛÍ¥ÓÑÌÐÐÍÌÿ¥ÿ¥ÌËШÐÐÐÎÐÏÐÐдÒÐÐÐÐÐÿ¥Í¿°Ìÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥ÌÐÛÿ¥ÿ¥Îð£ÒÙñÒñÍÀÍÊÍÒÀ´ÿ¥ÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÿ§ÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÿ¥ÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐÛÿ¥Ð£ÿ¥ÿ¥ð¿ÿ¥Âÿ¥ÿ¥ÐÛÿ¥ÿ¥ÐÓ¤҈ÐÐдÿ¥ÓñÌÏÐÛð£ÒÙñÒñÍÀÐ₤ÿ¥ÕШÍÊÍÊÐÐÎÐЈÐÐ
ÐÐШÿ¥Í¢çÐÛÐÐÒˆ¢Ì£ÐÐдÐÐÿ¥Í¿°Ìÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥ÌÐÛÿ¥ÿ¥Îð£ÒÙñÒñÍÀÍÊÍÒÀ´ÿ¥ÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÿ§ÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÿ¥ÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐÓ¤҈ÐÐдÿ¥ÐÐÛÕÿ¥ÿ¥ÕÐÏÐÍÊÍÊдÐÐÐÎÐÐÓñÌÏÐÛð£ÒÙñÒñÍÀÐ₤ÐÐÐÿ¥ÓñÌÏð£ÒÙñÒñÍÀÿ¥ÿ¥Íÿ¥ÐпÐÎÐÛТÐÊРШХÐÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐˆÐÐÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐÓ¤҈ÐÐдÿ¥ÐÐÛÌÕÍ¡₤ШÍÊÍÐÐÎÐЈÐÐ
ÐÐÐÐÈÐÎÿ¥ÿ¥ÊÐÐÍÊð¡ÙШÒËÐÐÍ
ÐÀÐÐÐÌËÐÎÌÛÇÐÈÐÐÐдÐ₤ÐÐ̓ЈÐÐÛÐÏÐÐÐ
ÐÊÐÐдÐÐÿ¥Õ¨Õ§ÂШЈÐÈÐÍˋÓ´Ò
ÐÍ¿°ÓˋЈÓÌÇ£ÐÐÏÐÐÐдÐÕÀÐÈÐÎ̧ҴÙÐ¨Õ ÐÐÍÛÑÌÐÿ¥ÍˋÓ´Ò
ÐÛÍÊÒˆ¢Ð¨ÐÊÐÿ¥Ì§Ò´ÙÐÛð¡ÕˋÍЈÍÎÕÐÓÐÍ¢Ì
Ð₤ÍÍШÓÒÏÈÐÏÐÐÐÐÐÐÿ¥ÐÐÐÏÐÐÐÐдÐÐÈÐÎÿ¥Í ÝÕÌˋÕÂШÐÐÐÎÿ¥ÍÛÒ°ˆÓШÒð¤¤ÐÐÀÐÒ̓
ÐÍÐÐÎÐÐÐдÐÿ¥ÐÐÐÐÌÐ
Ó§Ð
ÐÛð¤ÍÛÐÏÐÐÈÐÎÓ¨Ò´¥ÐÒÎÐЈÐдÐÐÐдÐ₤ÐÏÐЈÐÐ
Í ÝÕÌˋÕÂÐÛͧ¿ÍýÐ₤ÿ¥ð¡ÙÓ¨Í
˜ÌÙÈШÍÛÂÒΰÓÐˆÍ ÝÕÐÐÐÐдÐÏÐÐÈÐÎÿ¥ÍˋÓ´Ò
ÍÛÑÌÐÛÓ¤Ò´Ðÿ¥ÍÍ°ÐÐÐдЈÐÒ´ð¤Ð´ÐÐÎÌýÒ¥Ðÿ¥ÐÐÛЃЃð¥ÐÐÐдÐÏÐ₤ЈÐÐ
̘ð£ÑÒ´ð¤ÿ¥ÐÛÐÐЈҴҥÐÐÐÐЯÿ¥Ðÿ§Ð¨ÐÐÐÎð£ÒÙñÒñÍÀШÐÐÍ
ËÌÒ
ШÍ₤ƒÐÐÌÇÒÀÐÒÀÐÐÿ¥Í
ËÌÒ
ÐÛÕÀШÕÐÐÐÐÏÐÐдÐÛͯÒÝÀÐð¡ÐÐÐÐÛÐÏÐÐÐÐдÿ¥Ó˜˜ð¡Í₤ˋÍÊÌݤÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÿ¥ÒÀÓÛð£Ëð¡ÿ¥Ð₤ÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿5ÐÐð¤ÍШÍÛ¿ÌШÓÒÏÈÐÏÐÐÐ₤ÐÐÛÐдÐÏÐÐÐ
Í¡¡Ð¨Í¢çÕ ÙШӧÛÐпÐÕÒÎЈÐдÐ₤ÿ¥Ó°Ó¨ð¤¤ÐÛð£ÒÙñÒñÍÀÐÒð¤¤ÐÐÀШÐÐÐЈÐÒ̓
ÐÍ ÐÐÎÐÐдÐÐð¤ÍÛÐÐÐÈÐÐÐˋÐÐдÐÐÐдÐÏÐÐÿ¥Ó₤ð¤¤Ð´ÌݤÐð£ÐÐÐÐÒ
ÐÐÐÿ¥ÐƒÐÿ¥Ì§Ò´ÙÐÛÍÙÓÑШÐÐÐÐÐÐÙЈÐð¤Ì
дЈÐÐÐÐÛÐÏÐÐÐÐÿ¥Ì
ÕШÍÌÌÇ£ÍÐÐÐÐдÐÍ¥ñÐÒÎÒ¨ÐÐÐÐÛÐÏÐÐÐ
ÍÒ´ÐÛдÐÐÿ¥ÌÓ¤ЈҤ¨ð§ÓÓÒñÀÐÒˆÐÐÐÐÎÐÿ¥ÍÛÂÒΰÓÒ´¥Ì ШÓ
ÏÐÐÿ¥ð£ÒÙñÒñÍÀÐÛÌÇÒÀÒÀӤШÐÐÈÐÎÓÐÐÐÐÛÐÏÐ₤ЈÐÍ ÇÍÐÏÐÐÈÐÎÐÿ¥ÒˆÓËÓÐÕýÐÐ Õ¨Õ§ÂÐÛÍ
ËÌÒ
ÐÛð¡ÙШÐ₤ÿ¥ÐÍÊð¡ÙШÐÍ
ÐÀÐÐÐÌËÐÎÌÛÇÐÈÐÐдҴÐÐдÐÐÐÿ¥ÍÛÑÌдÐÐÎÐÐÐÐÐÛЃЃÍÐÍÐÐдÐÐÐÐÛÐ ÐÐÿ¥Í ÝÕÌˋÕÂдÐÐÎÐ₤Ì
ÕЈÍÌÐÍ¢
ÒÎÐÏÐÐÐ
ÐÐÐÐÈÐÎÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿5ÐдÐÐÎÐ₤ÿ¥ÿ¥ÊÐÛÍÛÑÌШÍÌÐÿ¥ÍÓÐÓ¤҈ÐÐдÐÐÎÐÿ¥ÐÐÐ ÐÐÏÐ₤ÿ¥ÍÍЈÍÌдÐ₤ÐÐЈÐдÐÐпÐÐÏÐÐÐ
ÐÎÐÐÐÐШÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿6ð§ÌÐÛÕ°Ò¢¯Ì¡ÿ¥ð¿ÿ¥Àÿ¥ÿ¥ÐÏÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿6ÐÛͯÍШÐÐÐÎÐÿ¥ÿ¥¿6Òˆ¢Ì¡ÿ¥Õ ÿ¥ÿ¥ÒÀÓÛÐÐÿ¥Õ ÿ¥ÿ¥ÒÀÓÛÿ¥ÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÿ¥ÒÀÓÛÐÐÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÒÀÓÛÿ¥ÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÿ¥ÒÀÓÛÐÐÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÿ¥ÒÀÓÛÿ¥ÿ¥Ó¿ÍÛÐÛÍÛÑÌСÐÛÍÍËÓЈÍÌÍ
ÍۿШҢ¯Ð¿ÐÐÐÎÐÐÐÛÐ₤ÿ¥ÍÕ°Ò¢¯Ì¡ð¡ÙШÐÐÐÍÛÑÌÐ₤ÍÌШÍ₤ƒÐÿ¥ÓËÌ₤ÐÛÕÀШÐÏÐÐÐÐÐÛÍÓÐÓʤÐЈÐÐÿ¥ÐÐÐÐÛÐÐÿ¥ÐˋÐÐÐÐÛÿ¥ÐдÒÐдÿ¥ÓËÌ₤Ð₤ÐÍÊð¡ÙШÐÍ
ÐÀÐÐÐÌËÐÎÌÛÇÐÈÐÎÐÐÈÐÐдҴÐÈÐÎÐЃÐÐÐ̯ÒÒ´ð¤ÐÒÎÐÎÐÐÐÐÈÐÝÐдÌÐЃÐÐÐдÒˋÝÐÐÐдҴҥÐÐÐÎÐÐÓÛÌÐÐÐÐ ÐÐÏÿ¥ÐÐð£ËÍÊÿ¥ÍÌÌÕÿ¥ÍÌÍ₤ƒÒÝÀÒ
̯ÿ¥Í
ÝÕÐÛÍÓÙШÐÊÐÐÎÐÛÍ
̘ÓЈҴҥմÍÍÐ₤ðƒÒ¢¯Õ´ÍÐÐÐÐ ÐÐÏÿ¥ÍÐ
ÐÛÍÌÌ₤Шÿ¥ÍÌÍ₤ƒÒÝÀÒ
ÿ¥ÍÌÐÛÌËÌÍ ÇÌÿ¥Í
ñð§ÓÍ
ÍÛ¿ÐÓ¿ÍÛÐÐÒ´Ò¥Õ´ÍÍÐ₤ðƒÒ¢¯Õ´ÍÐ₤ЈÐÐ
ðƒÐЯÿ¥ð¡Ò´Õ°Ò¢¯Ì¡ð¡ÙШÐÍÊÏÍÐÛÍÛÑÌÐ₤ÐÐÐÐÐдÌÐÈÐÎÐÐÐÐð¡Í₤ˋЈÐÐÐÍÊÐÐÐÐдҴÐÿ¥Í
ñð§ÓЈð¤ðƒÐ¨ÐÊÐÐÎÒˆÐÈÐÎÐÐЃÐÐÐÐÐдÐÛÒ´Ò¥Õ´ÍÐÐÐЯÐÐÐÏÿ¥ÐÍ
ñð§ÓЈð¤ðƒÐÿ¥Ð´ÐЈÐÐÐÿ¥ð¡Ò´ð¤ÐÊÐÛӤҴШÒÎÓÇÐÐЃЃÿ¥ÍÐ
ÓЈð¤ðƒÌ₤ÐÛð¡ÙÒ¤¨Ð₤ÌÐÐШÐÐÎÐЈÐÐ
дÐÐÐÐÎÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿6ÐÛÐÐÍÌÐ₤ÿ¥ÐƒÐШÐÍÍÐð¡£Í¥çÐÐÌÓʤð¤ÍÛÿ¥Ð₤ÿ¥ÿ§Í
ËÌÒ
ÐÛÍÛÑÌÐÐÐÛÐÐЈÒˋÝÐÐÐÎÐÐÌ´ÐÌÓʤÐÐÐÐÛШÐÐЈÐÐÐдÐÐÕͤÎÐÏÐÐÐÐÛÐÏÐÐÈÐÐ
ÐЈÐÐÀÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿6Ð₤ÿ¥ÐÍÍÐÛÒ´ð¤Ð₤ÿ¥ÍÛÑÌÐÐÒÎÐÎÿ¥ÐˋÐÐÒ̓
ÐÐÐÈÐÐÛÐÏÐ₤ЈÐÐдÌÐÐÐÐÐЈÐÐдÐÿ¥ÐÐÐÐ₤Ò´ÍÐÐÐÈÐдÐÐÒÑÈÌ´ÐÛÒ´ð¤ÐÏÐÐÐÐÐˋÐÿ¥ð£ÍÐÛÐÐÛÓ˜˜ÿ¥ÍñÒ´¥ÐÛÒ´ð¤Ð´ÐÐÐÛÐ₤ÿ¥Í
ËÍÝ
Ò
ÐÛÍÛÑÌÐÓÇÌËÒ̓
ÐÛÓƒÍ ÇÐÒÎÐдÐÐÓ¿ÐÏÿ¥ÍÍÐÛÒ´ð¤Ð´Ð₤ÒÑÈÌ´ÐÕÐдÍÊÌÙÐЃÐÐÐÐÿ¥ÿ¥¿6Òˆ¢Ì¡ÿ¥Õ ÿ¥ÒÀÓÛÐÐÿ¥ÒÀÓÛÿ¥ÿ¥ÐÐÐÛÓýÓ˜˜ÿ¥ÿ¥ÍñÒ´¥ÐÛÒ´ð¤Ð´ÐÐÐÛÐ₤ÿ¥ÐÍÛÑÌÐÛÌ¿ÐÓÇÌËÒ̓
ÒÀÓ¤ÐÓÛÌÐÐдÐÐÒ´ð¤ÐÏÐ₤ÐÐЃÐÐÐÐдҢ¯Ð¿ÐÎÐÐÿ¥ÿ¥¿6Òˆ¢Ì¡ÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥Ðð¡Ò´ðƒÒ¢¯ð¡ÙÐÛÐÍÍÐÛÒ´ð¤ÐÐÓýÓ˜˜ÿ¥ÿ¥ÍñÒ´¥ÐÛÒ´ð¤ÐдÐ₤ÿ¥Ì˜ð£ÑÒ´ð¤ÿ¥ÐÏÐÐÿ¥ÐÓ˜˜ÿ¥ÍñÒ´¥ÐÛÒ´ð¤ÐдÐ₤̘ð£ÑÒ´ð¤ÿ¥ÐÛÐдÐÏÐÐÐÿ¥Ì˜ð£ÑÒ´ð¤ÿ¥Ð´ÕÐÈÐÎÿ¥Ì˜ð£ÑÒ´ð¤ÿ¥ÐÐÐЃÐÏÓÇ¿ð£Ò´ð¤ÐÏÐÐдÐÐÐдШͤÍñÐÐÎÐÐÐÛÐÏÐÐÐ
Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿6ÐÐÐÛÐÐÒÐ̿ШÐÐÈÐÎÐÐÿ¥ÐÍÍÐÛ̧ҴÙÐÛð£ÒÙñÒñÍÀÐÿ¥Í
ËÍÝ
Ò
ÐÌÛÇÐÿ¥ÕÀШÕÐÐÐð§ÐÈÐÐдÐÐÌÓʤð¤ÍÛÿ¥ÐÛÓÍÛÌÏÐÒÈð£ÐÐÐÐÐÛÍÌÐÐÐÍ¢
ÒÎÐÐÐЈÐˋдÐ₤ÿ¥ÐÐÐÐÒÐÐÎÐ₤ÐЈÐÐÈÐÐÛÐÏÐÐÈÐÎÿ¥ÌÓʤð¤ÍÛÿ¥ÐÓÍÛдð¢ÀÐÐÐдШӡͧÐÛÓÓÝÐÐÐд҈ÐÐÍ₤ƒÒÝÀдÐÐÎÐÛÍÌÐÿ¥Ì˜ Ò§ÐÐÎÐÐдÐÐУÐЈÐÐ
(2)ÐÌÓʤð¤ÍÛÿ¥ÿ¥Ì˜ð£ÑÒ´ð¤ÿ¥ÿ¥ÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎ
Í
ÒñÍÀÐÛÌÙͿ͡ШÍ₤ƒÐÐÒ´¥Ò´ÐÛÍ
ÍÛ¿Ðð¥ÐÐð§ÒÈÐдÐÈÐ̘ð£ÑÒ´ð¤ÿ¥ÿ¥Ð¨ÌÓʤÐÐÐÐÍÍÐÛÒÊ̯ÐÛÍË°ÌÏð£ÒÙñÒñÍÀÐÿ¥Í
ËÍÝ
Ò
ÐÐÐÊИШÕÈÐÐÎÒÀÐÕÿ¥Ò°ÐÐÑÐÒ¡ÐÐÐÐÊÐÐÐÏÍ¥ÐÐÐÈÐÎÐÐÈÐÐÐЈÐˋÿ¥ÍÐÛð¤ÍÛÐͨÐÌÓʤð¤ÍÛÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎÿ¥Ó˜˜ð¡Í₤ˋÐ₤ÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿5ÐÐÿ¥ÓÍÛÐÏÐÐдð¢ÀÐÐÐдШӡͧÐÛÓÓÝÐÐÐдÍÊÌÙÐÐÎÐÐÿ¥Ó˜˜ð¡Í₤ˋÍÊÌݤÐÛÓ˜˜ÿ¥ÐÛÿ¥(4)дÿ¥ÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÿ¥ÒÀÓÛÐÐÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÿ¥ÒÀÓÛÿ¥ÿ¥Ð
ÐÐÐЈÐÐÿ¥Ì˜ð£ÑÒ´ð¤ÿ¥ÿ¥ÐÍñÓÙÐÐШͧÐÐÈÐÎÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿6ÐÌÙͿ͡ШÐÐÍÌÐÛÍ
ÍۿШÐÊÐÐÎÿ¥ÌÙÍ¿Í¡ÐÐÒ´ð¤Ð¨ÐÐÍ
ñð§ÓЈӤҴÍ
ÍۿШÐÊÐÐÎÐ₤ÿ¥ð¡ÍÍÓÙÐÐÐÎÐÐЃÐÐÐдҢ¯Ð¿ÐЈÐˋÿ¥ÌÙͿ͡дÐÛÕÐÛÕÈÐÕÐÐ₤ð§ÐШӯÌÏÐÏÐÐÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÐÛÿ¥ÐˆÐÐÿ¥ÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÐÛÿ¥Ð£ÿ¥ÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÐÛÿ¥ÐˆÐÐÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐÛÿ¥Ð£ÿ¥ÿ¥ÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ§Ì¯ÒÐÐ₤ÿ¥ÐÐÐÏÐЈÐÿ¥Í ÝÕ̘մÕñдӡÌÌ¿ÿ¥¿6ÐÛÕÈÍÐÏÿ¥ð§ÐÒÙýÐÐдÐЈÐÍ
ÍÛ¿ÐÛÓ°ÐÍ
ËÐÌ¡ÿ¥ð¿ÿ¥Àÿ¥ÿ¥ÐÌÓʤÐÐÎÐÐÐ
ÐÐÛÐÐШÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿5ÐШÐÐÈÐÎÿ¥ÍƒÌËÿ¥ÍÌÐÐÐÒ
дÐÛÕÐÏÍÌÍ
ÍۿШð¤ÐÐÓ¤ÓÐÐÐÐЈͥñͥЈҴð¤ÐÛÍñÓÙУÌýÒ¥ÐÐÐÐÎÐÐÐдÐ₤ÌÐÐÐÏÐÐÿ¥ÐÐÛÐÐЈÿ¥ÒÐÐÕÈÐÕÐÐ₤ÿ¥ÍÌÐð¡ÍÍÐÏÐÐÐÐ´Ð¨Í Ðÿ¥ÍÌÐÐÍÇÐÌÍ°ÓÐÏÐÐÐÿ¥ÒˆÍñÝ̘ð§ÐÛÌÐÒƒ¥Ð¢ÐЈÐÕÐÒçñÐÐÐЈÐÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿6ÐÐÐÍÌÐÿ¥Í
˜ÌÙÈУð¡ÙӨЈÍÌÐÏÐÐÈÐдÐ₤ͯͤÒÐÐÐдÐ₤ÐÏÐЈÐÐ
ЈÐÿ¥ÌÙÍ¿Í¡ÐÛÌ
ͧÒ
Ð₤ÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿6ШÍ₤ƒÐÿ¥ÐͧÒñÐÛð¤Íð¤ÒÏÈÐ̓ÐÎÒ´ð¤Ð¨ÐÐÕÿ¥Ó°ÐÍ
ËÐÌ¡ÐÛÍ
ÍۿдͧÒñÐÛÒˆÒÙдӯЈÐ̘ͤÓð¤Õ
̯ӿШÐÊÐÐÎÿ¥Í
ñð§ÓЈð¤ÍÛÓçÕÍаͧÒñÐÛÒˆÒÙÐÌÐÐШÐÐÐдÐÛÐдÐÏÐÐÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿6Ð₤ÿ¥Ó˜˜ð¡Í₤ˋШÐÐÐÎÿ¥ÐÐШÍ₤ƒÐÐÍ₤ƒÍ¢ÐÌÐÐШÐÐÎÐЈÐÐ
(3)ÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿5ÐÐÛÍÌШÐÊÐÐÎ
Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿5ÐÐð¡ÕÈÐÛÒ´ð¤ÐÍñÓÙУÌýÒ¥ÐÐШͧÐÐÈÐÎÐÐÍÌÐ₤ÿ¥Ì˜ð£ÑÒ´ð¤ÿ¥ÍаÍÿ¥ÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎÒ¢¯Ð¿ÐÐдÐÛУÐÿ¥Ì˜ð£ÑÒ´ð¤ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐÍñÓÙУÌýÒ¥ÐÐШÕÐÐÎÐ₤ÿ¥ð¤ÍШ҈¢Ì£Ìˆð¤ÐÛÓ°Ó¨ð¤¤Ð¨Ó¯ÀÍЈÍÌÐÐÐÐ ÐÐÏÿ¥ÐÐÛ̓ÐͨÐÐÐ ÐÛð¡Í¤ÎÐÿ¥ÂШÍ₤ƒÐÐÍÌÐÐÐÎÐÐÐÿ¥Ì˜ð£ÑÒ´ð¤ÿ¥ÿ¥Ð¨ÕÐÐÎÐ₤ÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛÍ ÝÍÍ
ÍÛ¿Ðÿ¥Í
´ÐÒÈð£ÐÐдÐÐÿ¥ÐÐÛЃЃÍñÓÙУÌýÒ¥ÐÐдÐÐИÐШÐÛÐÐÛÐÏÿ¥ÍÌð¡ÍÍдÐÐÐÐÐÐÐЈÐÐÐÛÐÏÐÐÐ
ЃÐÿ¥ÌÙͿ͡ШÐÐÒˆ¢Ì£ÐÛð¡ÙÕÓçÌÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥Ðð¥ÐÐð§ÒÈÐÌÀÐ̘ð£ÑÒ´ð¤ÿ¥ÿ¥Ð¨ÐÐÐÎÐ₤ÿ¥Ò´¥Ò´ÐÛÌͰШ҈ÊÒÏÈÐÓÐÐð¡ÌÙÈÓÂ¤ÐˆÍ ÝÕÐÐÿ¥ÐƒÐÿ¥Ì˜ð£ÑÒ´ð¤ÿ¥ÿ¥Ð¨ÐÐÐÎÿ¥Ðð¤ÍÛð¡ÐÛÐ₤ÐÙÍÊÍÛÐдҴҥÐÐЈÐˋÐÛУÐÿ¥Ì˜ð£ÑÒ´ð¤ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥(1)ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥Í¿°Ìÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥ÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËð£ÐÌÝÕÌÌ¡ÍÓ
Ïÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐˆÐÐÿ¥ÿ¥ÐˆÐˋÿ¥ð£ÓʃдÐ₤Ò°ˆÓШӯЈÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿3ÐÛÍÇШÍÐÈÐÐÐÛÐÏÐÐÿ¥Í
˜Í¿°Ð´Ð₤ÐÐЈÐÍ ÝÕÐÓ¿¯ÐÒ¢ÐÐÎÐÐÐÐÛÐÏÐÐÐ
ЃÐÿ¥ÐÍÍÐÛ̧ҴÙÐÛÒÊ̯ÐÛð£ÒÙñÒñÍÀÐÿ¥Í
ËÍÝ
ÐÛÕ¨Õ§ÂÒ
ШÒ̓
ÐÓ¿¯ÐÒ¢ÐÐÎÐÐÐдÐÐÌÓʤð¤ÍÛÿ¥Ð₤ÿ¥Ì¡ÐͤÐÐÛð§ÒÈÐÏÒ´Ò¥ÐÐÐÎÐÐÐÐÛÐÏÐ₤ÐÐÐÿ¥Ì˜ð£ÑÒ´ð¤ÿ¥ÐˆÐÐÿ¥ÿ¥ÿ¥(2)ÿ¥ÿ¥ÿ¥(2)ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥(1)ÿ¥(2)ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐÏÓÑÓÑÓÍ̓ˋÓШҴҥÐÐÿ¥ÐÐÒˆð§Ðÿ¥ÍÒˆÌ₤ÌÐÛÌÓʤð¤ÍÛÐÏÐÐÐÐ´Ð¨Í Ðÿ¥ÿ§Ì¯ÒШÌýÒ¥ÐÐÐð¡ÕÈÐÛÒ´ð¤Í
´ð§ÐÐÐÐÐÕÈÒ¥ÐÏÐÐÐÐÛÐÐШÿ¥ÒˆÙÒ
ШͯÒÝÀÐÌÓʤÐÓÑÐÐÐÐÛÐÏÐÐÐ
̘ð£ÑÍÌÓʤð¤ÍÛÐÛÓÍÛÌÏÐÍÎÍÛÐÐÐÍ ÇÍÿ¥ÐÐÐШÐÊÐÐÎÐÿ¥ÓÍÛдð¢ÀÐÐÐдШӡͧÐÛÓÓÝÐÐÐд҈ÐÐÐдÐ₤ͯͤÐÏÐÐÐÐÛÐÏÐ₤ЈÐÐ
ЈÐÿ¥Í ÝÕÌˋÕÂÐ₤ÿ¥Ì˜ÌËÓШÿ¥ÐÐÛÌýÒ¥ÐÐÒ´ð¤ÐÒˆÙÒ
Шð¡ÐÐͯÒÝÀÐÌÌÀÐÿ¥ÐÐШ͢ÐÐÎÍÌÐͯ§ÐÐÿ¥ÓÍÛÌÏÐÛÓ¤҈ÐÐÐÐдÐð¡Í₤̘ ÐÏÐÐÐ
ÍÌÐð¡ÍÍÐÏÐÐÐÛШÿ¥ÐЃÐЃÿ¥ÓÍÛÐÏÐÐÈÐÐÐÕÌ°ÌÏÐÕ£ÍÇÐÐÐÐÛÐ₤ÿ¥Ò´ÇÒ´ð¡ÐÐÐ̓ЈÐдÐÐÎÐÿ¥ÍÌÐÛð¡ÍÐÓÍÛÌÏÐÍÛ¿ÌШ҈ÍÛÐÐЃÐÏÐÐÎÌÌ¡ÐÐÍ¢
ÒÎÐ₤ÿ¥Í
´ÐЈÐдÐÐпÐÐÏÐÐÐ
Ó˜˜ÿ¥ÐÍÒ´ÇÒ¨ÌÝШÐÊÐÐÎ
Ó˜˜ð¡Í₤ˋÍÊÌݤð¡ÙÐÛÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÌÒ´ÇÕ´ÍÐÌÂÐÐÎÍÐÌÑÐÐÎÿ¥ð¡Ì°ÒÀÓ¤ÐÛÌÓ¨ÐÒˆÐÐÍÍ₤ˋÐÛÍÊÌÙШÐ₤ÿ¥ÌÕ¨ÒÈÍÊÌÐÛÍÊÌÙÐЈÐÒÏÈÕÍÕÀШÐÊÐÐÎÿ¥ÒˆÊÐÈÐÌ°ð£ÊÒÏÈÕÐÐÐÕÌ°ÐÐÐÐÐ´Ð¨Í Ðÿ¥ÌÕ¨ÒÈÍÊÌÍÊðƒÐ¨ÕÍÐÿ¥Ì°ð£ÊÐÛÒÏÈÕÐÒˆÊÐÈÐÕÌ°ÐÐÐÐÐÐÛÓÓÝÐ₤ÿ¥Ì˜ÀÐÛдÐÐÐÏÐÐÐ
ÿ¥ÐÍÍ₤ˋÐÿ¥Ó°Ó¨ð¤¤Ð¨ÐÐ̘ҴÇÌÒçñÒÀÓ¤ÐÒ´ÇÐÐÛÌÒçñÐÕ̰ЈÒÀӤдÐÐÎÕÌ°ÐÏÐÐдÍÊÌÙÐÐӿШÐÊÐÐÎ
(1)ÐÍÍ₤ˋÐ₤ÿ¥ÐÌÏÒ´Çð¤¤Ð¨ÐÐ̘ҴÇÌÒçñÒÀÓ¤ÿ¥(1)ÐÛÐÂÐÛ(ÿ§¡)Íа(2)ÐÛÐÂÐÛ(ÿ§Ñ)ÿ¥Ð₤ÿ¥Ò¨ÌÏÒ´Çð¤¤ÿ¥¿1ÍаÍÿ¥¿1ÐÛÌ
Í ÝÌðƒÒÀÓ¤ÐÒͧÐÛÐÐÛÐÏÐÐÐдÐÍÌдÐÐÐÐÛÐÏÐÐдÐÐÿ¥ÍÒ´ÒˆÍÛÐÛдÐÐÿ¥ÐÐÛÌ
Í ÝÌðƒÒÀÓ¤Ð₤ÐÐÐÐð¡£ÐÐÕ´ÍШÐÐÐÎÓÍÛЈÐÐÛд҈ÐÐÐÿ¥ÐƒÐÿ¥ÍÒ´ÒˆÍÛÐÐдÐÐШÐÐЯÿ¥ÌÏÒ´Çð¤¤Ð₤ÿ¥ÿ¥ÂÐÐÐÛÐÐÒˋ°ÐÐð¤Ì
ÒÇÍÓÙͧÓÑÒÀÐпÐÒˆ¢Ì£ÐÒÀÐÐÿ¥ÿ¥ÂÐÛÒ̓
ШÕÂÐÐÒÊ̯ÐÛðƒÒ¢¯ÓÙÐÍÓÓÐˆÌ ¿Ì ÐЈÐÒͧдÌݤÐÐÊÐÐÎÿ¥Ì˜Ò´ÇÌÒçñШÍÐÐÏÐÐÿ¥Ì˜Ò´ÇÐ₤ÿ¥Ì´ˋÍˋÐÛÍÙʹШÐÊÐÐÐÐЈ҈¢Ì£ÐÐÐÐÐÐЯÓÓÝÐÛЈÐÐдÐÓËÐ̓ÐШÐÐÐÐÐÐÐÐÐÌ ÐÈÐÎÌÒçñÐÐÐÐÐÛдÐÐÐдÐÐÏÐÿ¥ÕÌ°ÌÏÐÒˆÐÐÐÐÐÐдÍÊÌÙÐÐÐ
(2)ÐÐÐÐЈÐÐÿ¥ÌÕ¨ÒÈÍÊÌÍÊðƒÐ₤ÿ¥Ò´ÇÐÐÛÌÒçñÐð¡Ì°ÒÀӤдЈÐÍ ÇÍÐÛÒÎð£ÑШÐÊÐÐÎÿ¥Ð̯ð¤Ò´ÇÒ´ÐÌÒçñÐÐÒ
ÐÌÒ´ÇÐÛÓ¤ÍÛÍÊÌݤÐÍÐÐÍ ÇÍШÐÐÐÎÿ¥Í°Ò´ÇÐÐÛÌÒçñÐÓ¡Ì̿ШÍ₤ƒÐÐÕ̰ЈÒÀӤдÐÐÐÐÛÐ₤ÿ¥Í§ÒˋýÒ´ÇҴШÐÐÐÎÌÒ´ÇÒ
ÐÛð¡£Í¥çÐÐÌ´ˋÍˋÍÐ₤̰̓ÕÂð¢ÿ¥ð£Ëð¡ÐÌ´ˋÍˋÓÙÐдÐÐÐÿ¥Ðÿ¥ð¤ÍÛÓÿ¥Ì°ÍƒÓÌ ¿Ì Ð̘ ÐÐÐÛÐÏÐÐÐÐÿ¥ÌÒ´ÇÒ
Ðÿ¥ÐÐÛÐдÐÓËÐЈÐÐÍÐ₤ÕÍ¡¡ð¤¤ÐÏÐÐЯÍÛ¿ÌШÐÐÛÐдÐÓËÐÐÐдÐÐÐÐÛШÐÐÐÎÒ´ÇÐÐÌÒçñÐÐЈÐˋÿ¥Ò´ÇÐÐÛÌÒçñÐÒÈÍÊÍÑͤÎÐÛÒÑÈÌ´ÓÛÓШÓ
ÏÐÐÐÎÒÐÐӡͧÌÏÐ̘ Ðд҈ÐÐÐÐдÐШÕÐÐÐÐÐÛдÒÏÈÐÐÐÛÐӡͧÐÏÐÐÐÐдÍÊÓʤÐÐÎÐÐдÐÐÿ¥ÐÐÛÍÌдÐÐÎÿ¥ÐÌ°ÓÓÇð¤ÐÛͧð¤Ò
ÐͧÒˋýÓÇð¤ÐÛÓçÍÝÓÒÏÈÌݤÐÒÈÍÊÌШÌÝÐÐÐÐдÐ₤ÿ¥Ì°Ìý£Í§ÍÛÑÐÛÌ ¿Í¿¿Ð¨ÐÐÐÐÕÒÎЈð¤ÌÐÏÐÐÐÐÿ¥ÒÈÍÊÐÍÐÐÌ´ˋÍˋÐ₤ÌÍÊÏÕͯÕÐÐЈÐÐЯЈÐÐÿ¥ð¡Ì°ÒÀÓ¤ÐÛÌÍÎÐÍÊÌÙÐÐШÐÐÐÈÐÎÐ₤ÿ¥ÐÐÐÐÐÒÈÍÊÍÑͤÎÐÛÍˋÓ´Ðð¡Í§Ð¨ÍÑÕÐÐÓçÌдЈÐЈÐÐÐÌ
ÕЈÕ
Ì
ÛÐÍ¢
ÒÎдÐÐÐÐдҢ¯Ð¿ÿ¥ÐƒÐÿ¥ÐÐÐ Ðÿ¥Ò´ÇÐÐÌÒçñÐÐÕШÿ¥ÌÒ´ÇÒ
ШÐÐÐÎÿ¥ÒˆÍñÝÐÛð¡£Í¥çÐÐÐдÐÐÌ´ˋÍˋÓÙÐÛð¤ÍÛÓÿ¥Ì°ÍƒÓÌ ¿Ì ШÐÊÐÿ¥Õ¨Í¤ÎÐÛÒˆ¢Ì£ÿ¥ÌÊÒ´ÐÒÎÒ¨ÐÐÐÐÐÛдÒÏÈÐÐЈÐЯÿ¥ÒÈÍÊÍÑͤÎÐÛÒˆÓÝЈÍˋÓ´ÐÒÐÐÕ£ÍÛ°ÐÐÐÓçÌдЈÐÍÎËͧÐÏЈÐÐÐÐÏÐÐÐÐдÓÓÝð£ÐдÐÐÎÐÐÿ¥ÌÕ¨ÒÈÍÊÌÓ˜˜ð¡Í¯Ì°Í£ñÌÙÍÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÍÊÌݤУ̯Õÿ¥ÿ¥Íñ£ÿ¥Íñÿ¥Õ ÿ¥ÿ¥Ò´ÇÐÐÛÌÒçñÐÕ̰ЈÒÀӤШÐÐÐÍ ÇÍÐÍÑÕÓШÒÏÈÐÐÎÐÐÐдÐ₤ÌÐÐÐÏÐÐÐ
ӃШÿ¥ð¡Ò´ÍÊÌݤÐ₤ÿ¥ÍÒ´ÇÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÐÍͯÐÛÍÈýð¡£ÿ¥ÍͯÐÛÌ¡˜ÕÐÛðƒÕ ¥Ò
ÐÏÐÐд҈Êð¢ÀÐÐÎÌÒçñÐÐÐÐÐÛÐÏÐÐдÐÐÿ¥ÓÐÛÍÈýð¡£ÿ¥ðƒÕ ¥Ò
ÐÍÛÂÒΰÓÌ¿Ì°ÐÏð¡ÓƒˋÓШÓ¤ÍÛÐÐÐÐÍ₤Ò§ÐÏÐÐð¤ÌÀШÍ₤ƒÐÐÐÐÛÐÏÐÐÐÿ¥ÐÐÐÏÐÿ¥Ðÿ§Ëÿ§Ëÿ§Ëÿ§Ëÿ§Ëÿ§Ëÿ¥ÐЃРÕÍ¡¡ð¤¤ÐÏÐÐЯÍÛ¿ÌШÓËÐÐÐдÐÐÐЈÐÐÛÐÏÿ¥ÿ§Ëÿ§Ëÿ§Ëÿ§Ëÿ§Ëÿ§ËÌÇШð¤ÍÛÐÓ¤҈ÐЈÐÐÈÐÐÐдÐÐÈÐÎÿ¥ð¡Íð¤¤ÐÛÐÐÍÒ´ÇÐÛÌÒçñÐÒÈÍÊÍÑÌÛ¢ÒÑÈÌ´ÓÛÓШÓ
ÏÐÐÐÎÒÐÐӡͧÌÏÐ̘ ÐÐÐÛдÐ₤ÐÐÐÿ§Ëÿ§Ëÿ§Ëÿ§Ëÿ§Ëÿ§ËÐЈÐˋдÍÊÌÙÐÐÎÿ¥ð¡Ì°ÒÀÓ¤ÐÛÌÓ¨ÐÍÎÍÛÐÐÎÿ¥Ò¨ÌÝÐÌÈÍÇÐÐÐ
ÐÐШÍ₤ƒÐÿ¥Ì˜ð£ÑÐ₤ÿ¥Ó°Ó¨ð¤¤Ð´ÐÐÎÐ₤ÿ¥ÍÛÂÒΰÓÓÒñÀÐЈÐÿ¥ÓÛÌðƒÒ¢¯Ð´Ò¨ÍÓ¤Ò
ÐÛðƒÒ¢¯ÐÓ¡Í₤ƒÓ¨ÐÐÎÐÐÓÑÌ°ÐÏÐ₤ÿ¥Ó°Ó¨ð¤¤Ð´ÐÐÎÐ₤ÿ¥Í¯ÐˆÐдÐÓƒÍ ÇÐÏÍ
´Ò˜Óÿ¥ÍÍËÓЈҨ¡Ð
ÐÛÕÂÐÐÐÌÐÊÐÐÛдÐÐÎÐ₤ÿ¥Ò£§ÒÎÐÏÐЈÐÍð¤¤ÕÂÒ¨ÐÏÐÛðƒÒ¢¯Í
ÍÛ¿ÿ¥ð§ÌÐÀÐÂÿ¥ÌÌ¡ÐÛÒ´Ò¥Í
ÍۿШÌËÐÿ¥ÐÐð£Ëð¡ÐÛÒˆ¢Ì£ÐÕýÐÐдÐÐÎÐÿ¥ÍÍ₤ˋÐÛÍÊÌÙдÍð¡ÐÛÓçÒ¨ÐÓÍÛдÓ¤ÍÛÐÐЈÐˋͯͤÐÏÐЈÐÓÑ̰ШÐÐÈÐÐ
ÍÒ´Ó˜˜ÿ¥ÐÛÿ¥(4)ÐÛдÐÐÿ¥ÍÙÍ´ÐÐÓˋÓÿ¥ð¤¤ÓÒ°ÌШУдÐÐˋÓÀÍÑÕШÓÇÌËÌËÐÐÐдÐÐÏÐÿ¥ÌÕÓЈÍÑÓÇÐЈÐÿ¥Òˆ¢Ì£ÐÍÛ̧ÐÐÌÙÍ¿Í¡ÐÏÐÐÿ¥ÐÍÍËÐÛÍ
ñð§Óð¤ðƒÐ¨ÐÊÐÐÎÿ¥ÒÀÓ¤Ò
ÐÐÐÛÒÀÓ¤ÐÒ´¥Ì ÓÙШÐÐÓ¿ÍÛÐÐШÐ₤Ò°ÐЈÐÐÈÐÐдÐÐÓçÌÐͤÐÐÐÐ̓ÐÐÈÐÐÛÐÏÐÐÐ
ÐÐÐÏÐÐШÐÐÐÐÐÐÿ¥Ó°Ó¨ð¤¤ÐÛÒ´ÇÐÌÒçñÐÿ¥Ðÿ§Ëÿ§Ëÿ§Ëÿ§Ëÿ§Ëÿ§ËÌ´ˋÍˋÐÛÍÙʹШÐÊÐÐÐÐЈ҈¢Ì£ÐÐÐÐÐÐЯÓÓÝÐÛЈÐÐдÐÓËÐ̓ÐÐЈÐˋд҈˜ÓʤÐÐÐÛÐ₤ÿ¥Ó°Ó¨ð¤¤Ðÿ¥ÓˆÍÎÒçñÐÐÈÐÒ̓
ÓÌÐÛð¡ÙÐÏͰ̓ÍñÎ̓ÐЈÐÐÿ¥ÓÇ ð¤¤ÐÏÓ´ÌЈÐÐÐð§Ð´ÐÓÍÛÐÓ¤҈ÐÐÐд͈ÍÐÐÎÐÐÐдШð¡ÕÀÏРШÐÐШÓÀÒÎÐÐÐÐÛШУÐЈÐÐÿ¥Ó˜ÌÙÓЈÍÊÌÙдÐÐУÐЈÐÐ
Õ¨ÓÙÒÈÍÊÌ̯ð¤Õ´Ðÿ¥ÓÛÕ´ÐÐЈÐÕ¨ÒÈÓÛÀÍ
ШÐÐÐÎÐ₤ÿ¥ð¡Ò´ÐÛÐÐЈÍÊÌÙÐÿ¥ÒÈÍÊÍÛÿ¥ÌÛШÒÈÍÊÕñÐÛÒÐУÍÌÏШÐÐÈÐÎÍÛÌШÐÐÐЯÿ¥ÓÛÀÍ
ÐÏÐÛÌÏÒ´ÇÌÒçñÐÒÓ¡ÛÌÍÑÐÐÿ¥ÒÈÍÊÍÑͤÎÐÛÒˆÓÝЈÍˋÓ´ÐÒÐÐÕ£ÍÛ°ÐÐÐÓçÌдЈÐÐÐÙЈÐÐ
ЈÐÿ¥ÍÍ₤ˋÐÏÍÐÒˆ¢Ð¿ÐÐÐÿ¥À̧ҴÙÕñÐÛÒ´¥Ò´ð¡ÙШÐ₤ÿ¥Ó¤ÐШÌÐÒƒ¥Ð¢ÓÐ ÐÐдÒˋðƒÀÐÐÐÎÐÐÐÐ̓ЈÐÐÐÛÐÐÐÐÿ¥ÐÐÐ₤ÿ¥ð¤ÍÛÐÐÛÐÐÛÐÏÐ₤ЈÐÿ¥ÍÊÌÙÕÓ´ÿ¥ÌÒÎШÕÂÐÐÕ´ÍÐÏÐÐÈÐÎÿ¥ÍÍÊÌݤð¡ÙШÿ¥ÌÂÐÐÎÿ¥À̧ҴÙÕñÐÛðƒÒ¢¯ÐͤШӡñÐ
ð¤ÍÛÒˆÍÛÐÐÐð¡Õ
ÐÒ´ÙÐÐÎÿ¥Ó°Ó¨ð¤¤Ð¨ð¡ÍˋЈÓçÒ¨ÐͯÐÌÌдÐÐЃÐÏÐЈÐдÒÐÐÐÿ¥Ó°Ó¨ð¤¤ÐÛÓ¨Í ÇдÐÐÎÐ₤ÿ¥ÿ¥À̧ҴÙÕñÐÛÒ´¥Ò´Ì
ͤÎШÍ₤ƒÐÐÕͯÍ͢дÌÐÐÐÐ̓ЈÐÐ
(3)ÐÐÐÐШÐÐÎÐÿ¥ð£Ëð¡ÐÛдÐÐÿ¥ÍÍ₤ˋÐÛÍÒ´ÍÊÌÙШÐ₤ÿ¥ÍÒ´ÌÕ¨ÒÈÍÊðƒÐ¨ÕÍÐÐÎð¡Ì°ÒÀÓ¤ÐÛÌÓ¨ÐÒˆÐÐÐÐÛÐÏÐÐÈÐÎÿ¥Ì°ð£ÊÐÛÒÏÈÕÕˋÓ´ÐÒˆÊÐÈÐÕÌ°ÐÐÐÐдÐ₤ÌÐÐÐÏÐÐÐ
ÿ¥ÐÍÍ₤ˋÐÿ¥Ó°Ó¨ð¤¤Ð¨ÿ¥ÌˆÌ§ÒÀÐÏÐÐÈÐÕ¨Õ§ÂÒ
Ò̓
ÕýÌÙÂÌ°ÐÛӨ̰ÒÑÈÌ´ÐÌÇÓ´Ðÿ¥Í
Õ´ÕÍ ÝÒ
ð¢ÒÙñÍаÍ
Õ´ÕÍ ÝÒ
ШÐÐð¡ÍˋÓÓÎÌÙÂÐÛÓƒˋÍÐÐÐдÐÿ¥ÐÐШÕÍÐÐдÐÐӿШÐÊÐÐÎ
(1)ÐÍÍ₤ˋÐ₤ÿ¥Õ¨Õ§ÂÒ
Ò̓
ÐÛÕýÌÙÂÿ¥Õ¨Õ§ÂÒ
ÐÛÕÊÒÙñÒ
ШÍ₤ƒÐÐÌ₤ÌÇÓÙШÕÂÐÐ̰̓ÿ¥ð£Ëð¡ÐÕ¨Õ§ÂÒ
Ò̓
ÕýÌÙÂÌ°ÐдÐÐÐÿ¥ÿ¥ÿ¥ÌÀÿ¥Õ
ÿ¥ÿ¥Õ
ÐÌÎÒˆ˜ÐÐÐÐÿ¥ÐḬ́̓Ð₤ÿ¥Ì˜ð£ÑÒ̓
ÒÀÓ¤ÐÍÕÀдЈÐÈÐÌÓ¿ÐÏÐ₤̧̈ÒÀÐÏÐÐÈÐÐÿ¥ÐÐÛӨ̰ÒÑÈÌ´Ð₤ÿ¥Ì˜ð£ÑÒ̓
ÒÀÓ¤ÐÛÌÓ¿ÐÏÐÿ¥ÿ§ÐͨÐÕ¨Õ§ÂÒ
ÕÊÒÙņ̃ҴÙШÐÐÐÎÍÍͯÕÐÐÐпÐÐÏÐÐÈÐдÒÏÈÐÐÐдÐÐÏÐÿ¥ÌÏÒ´Çð¤¤Ð´ÐÐÎÐ₤ÿ¥Ì§Ò´ÙÍ
ÐÏÍ
ËÌÒ
ÐÒ̓
ÐÐÎÐÐÍ₤Ò§ÌÏÐÒˆÒÙÐÐÍ ÇÍШÐ₤ÿ¥Ì͈Í
ÒˆýÕÀдÐÐÎÐÐÛð¤ÍÛÐÛÌÓÀÐ̓¿Í¤ÓШ҈¢Ì£ÐÐÓƒˋÍÐÐÐÿ¥ð¡Ò´Ò̓
ÐÛð¤ÍÛÐÓçÍÑÒ
ШÍÐÐÍ
Õ´ÒñÍÀÐ̧ҴÙÍ
ÐÏð¡ÍˋÐˆÓ¨Í ÇШÕËÐЈÐÐÐÌÍÊÏÕÐÛÕ
Ì
ÛÐÐÐддÐШÿ¥Í
Õ´ÒñÍÀÐÍÊմШð¡Ò´ð¤ÍÛÐÕÍ ÝÐÐÍ ÇÍÐÏÐÐÐШÐÐÈÐÎÍÒñÍÀШð¡ÍˋÓÐÒˆýÐЈÐÓƒˋÍÐÒý ÐÈÐÎÐÐдÐÐпÐÐÏÐÐÐÐд҈˜ÓʤÐÐÿ¥ÍÍÊÌݤ(3)ÿ¥ÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÿ¥Ð
(2)Ð̘ð£ÑÐ₤ÿ¥Õ¨Õ§ÂÒ Ò̓ ÕýÌÙÂÌ°Ð₤Í¿°Ìÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥Ìÿ¥ÌËШ̧ÒÀÐÐÿ¥Ḭ́ШÐÊÐÐÎÌÕ¨ÒÈÍÊÌÐÍÊÌÙÐÐÐдÐЈÐÐÐ´Ð¨Í Ðÿ¥Ì§ÒÀÍÐÛÒÀӤШÌÇÓ´ÐÐÎÕˋÓ´ÐÐÐдÐÐÐÐÛÐÏÐÐÈÐÎÿ¥ÌÕ¨ÒÈÍÊÌÐÛÍÊÌÙÐЈÐÒÏÈÕÍÕÀШÐÊÐÐÎÌÕ¨ÒÈÍÊÌÐÛÍÊÌÙÐÓʤÐÍ ÇÍÐÏÐÐÐÿ¥ÐƒÐÿ¥ÍƒÒ´ÐÛдÐÐÿ¥ð£ÛШ̧ÒÀÍÐÛÍÌ°ÐÌÇÓ´ÐÏÐÐдÐÐÎÐÿ¥Õ¨ÓÙÒÈÍÊÌÐÛÒˆÊÐÈÐÌ°ð£ÊÒÏÈÕÐÕ¨ÓÙÒÈÍÊÌÐÛÍÊÌݤдÐÐÎÓ¤ÍÛÐÐÐÐдÐÕˋͧÐÏЈÐÍ ÇÍÐÏÐÐÈÐÎÿ¥Ì˜ð£ÑÐ₤ÿ¥ÐÌ°ð£ÊÐÛÒÏÈÕШÕÂÐÐÕÒÎЈð¤Õ ÐͨÐÐÐÛд҈ÐÐÐÐð¤ð£ÑÐÐÏÐÐÐÐÿ¥Ì°ÍÓ̯ð¤ÍÝÍð¤ÍÛÍÛÊÓñ´Ðð¡Íð¡ÓÙ̯̯ð¤Ò´ÇÒ´Ì°Ðÿ¥ÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÿ¥ð¡ÍÍ₤ˋдÐÐÎð¤ð£ÑÐÍÓÐÐÐдÐÐÏÐÐÍ ÇÍÐÏÐÐÿ¥Ì¯Ò´ÇÌ°ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÌÀÿ¥Ð
(3)ÐÐÐÐÏÿ¥ÌÊÒ´ÐÐШÿ¥ÍÍ₤ˋÐÛÒÏÈÕÐ₤ÿ¥ÐӨ̰ÒÑÈÌ´ÐдÐÐ͈ð£ÌÎÍ¢çÐÓ´ÐÐдÐÐÎÐÿ¥ÌˆÌ§ÒÀÐṴ̂̓ÐÕˋÓ´ÐÐÐÐÛШУÐЈÐÐÿ¥ÍÓÓЈÍÕÀÐÍÙÐÐдÐ₤ÌÐÐÐÏÐÐÐÿ¥ð£ÛШÐÐÛÐÐЈ̧̈ÒÀÐṴ̂̓ÐÕˋÓ´ÐÐÌð§ÐÒ´ÝÐÐÐÍ ÇÍÐÏÐÐÈÐÎÐÿ¥ÍÍ₤ˋÐÛÐÐЈÒÏÈÕÐ₤Ò´ÝÐÐЈÐÐ
ÐЈÐÐÀÿ¥Õ¨Õ§ÂÒ
Ò̓
ÕýÌÙÂÌ°Ð₤Ðð¡ÍˋÓЈÍÌÝÐÐÐÿ¥ÍÍ₤ˋÐÿ¥Ðÿ§Ëÿ§Ëÿ§Ëÿ§Ëÿ§Ëÿ§ËÐÐÐÕÍ ÝÐÐÐ̓ÌËÙÍÀÐÐÐÛÐÐШð¡ÍˋÓЈÍÌÝÐÐÍÐЈÐÌ´ÍÛÐÐÎÐÐÐÐдҢ¯Ð¿ÐÐÐЈ̥ ÓÑдÍ
̘ÓЈÍÛÐÌ¿ÐÐÐÎÐ₤ÐÐÐÿ¥ÐÒÏÈÕÐÐÛð£ð¡ÍˋÓЈÍÐÌÝÐÐдÐÐÌÒ´ÐÓ´Ðÿ¥ÐÒÏÈÕÐÐðƒÓʤÐÐÎÍÛÐÐÎÐÐÿ¥ÍÌÏÐÛӨ̰ÒÑÈ̴ШͤÐËÐÍ
˜ÓÕÍ ÝÒ
ð¢ÒÙñÌ°ÿ¥ÌÀÿ¥ÿ¥ÌÀÿ¥ÿ¥ÌÀÐÿ¥ÒÏÈÕÿ¥ð¡ÍˋÓÍÌÝÐдЈÐÌýÌÍÎÍÐÓÎÌÙÂÐÐÎÐÐÐÛÐÏÐÐÐ
ÐÐÐÎÿ¥Õ¨Õ§ÂÒ
Ò̓
ÕýÌÙÂÌ°Ð₤ÿ¥Í
˜ÓÕÍ ÝÒ
ð¢ÒÙñÌ°ÍÌÏШÿ¥ð¡Í§ÐˆÍ
Õ´ÍÓ¤ÐЈÐÐÐÍ ÇÍШÕˋÍЈÌýÌÍÎÍÐÓÏÐÐÐдЃÐÏÓÎÌÙÂÐÐÎÐÐÐÐÛÐÏÐ₤ЈÐÐдÐð§çÐÒÌ
ÛÐÐдÿ¥Í
Õ´ÕÍ ÝÒ
ð¢ÒÙñÍаÍ
Õ´ÕÍ ÝÒ
ШÐÐð¡ÍˋÓÓÎÌÙÂÐÛÓƒˋÍÐÿ¥ð¡Ì°ÒÀÓ¤ÐÛÕÌ°ÌÏÐÌ ¿Ì ð£ÐÐÓƒˋÍдÐÏÐÐÍ ÇÍÐÐÐдÐÐÎÐÿ¥ÍƒÐ¨ÐÐÛÍ
ÍÛ¿ÐÌÀÍÊÏÐÐÎÌ¥ ÓÑÌÌÏЈӃˋÍдÒÏÈÕÐÐÐÛÐ₤ӡͧÐÏÐ₤ЈÐÐ
ÐÐÐÐÈÐÎÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÐÛÒÀÓ¤ÐÌÙÈͧЈÍ
Õ´ÕÍ ÝÒÀÓ¤ÐÏÐÐдÍÊÌÙÐÐÍÍ₤ˋÐÛÓ¨Í ÇШӨÐÈÐдÐÐÎÐÿ¥ÍÍ₤ˋÐÒˆÍÛÐÐдÐÐÿ¥ÐÍÍÒÀÓ¤Ðÿ¥ð¡ÀÍШÍ₤ƒÐÐÒ´Ó£ÓЈͨÐÐÐÒÀӤдÐÐÎÓçÓ¿ÓШÒÀÐÐÐдЃÐÏÐ₤ÒˆÐÐÐЈÐÐÐÿ¥ÍÍÊÌݤÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÒÀÓÛÿ¥ÐÛÐÏÐÐÈÐÎÿ¥ð£ÛШӰӨð¤¤ÐÛÍ¿¿Õ´ÒñÍÀÐÿ¥ÐÒñÍÀдÐÐÎÐÐЃÐÐÒÀÓ¤ÐÒÀÐÈÐÐÐÛдÐÐÎÍÊÏÐЈͨ̈ÌÐÌÝÐÐÎÐÐÐдÐÿ¥ÐÍÑÓ¤ÓЈÌÌ
ÓÒ´ÍÐÐÐÐЈÐˋÐÐд҈ÍÛÐÐдÐÐÎÐÿ¥ÐÐÐÐÍ
Õ´ÕÍ ÝÒ
ð¢ÒÙñÍаÍ
Õ´ÕÍ ÝÒ
ШÐÐð¡ÍˋÓÓÎÌÙÂÐÛÓƒˋÍШÕÍдÐÐÐÛÐ₤ÍÊÝͧÐÏÐÐÐ
(4)Ðð£Ëð¡ÐÛдÐÐÿ¥ÐÐÐШÐÐÎÐÿ¥Ó°Ó¨ð¤¤ÐÛÍ¿¿Õ´ÒñÍÀШÐÊÐÐÎÿ¥Í Õ´ÕÍ ÝÒ ð¢ÒÙñÍÐ°Í Õ´ÕÍ ÝÒ Ð¨ÐÐð¡ÍˋÓÓÎÌÙÂÐÛÓƒˋÍÐÐÐÈÐÎÒˋðƒÀÐÐÐÛÐ₤ÍÊÝͧÐÏÐÐÈÐÎÿ¥ð¡Ì°ÒÀÓ¤ÐÛÌÓ¨ÐÒˆÐÐÍÍ₤ˋÐÛÍÒ´ÍÊÌÙШÐ₤ÿ¥Ì°ð£ÊÐÛÒÏÈÕÕˋÓ´ÐÒˆÊÐÈÐÕÌ°ÐÐÐÐ
ÿ¥ÐÍÒÀÓ¤ÐÛÒˆÍÛÐÛð¤ÍÛÒˆÊ҈ШÐÊÐÐÎ
ÿ¥À̧ҴÙÕñÐÐÛÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐШÍ₤ƒÐÐÒ´ÍÐ₤ÿ¥ÍÓ¡ÌÌ¿ÐÐð§ÐÐÐÛÓýƒÓËÓÒÎÓÐÒÎÐÐдÐÐÎÐÿ¥ÓÇÐÀШÍÍ¢ÕͤÎÐÒÑ
ÐÐÐÐÛдÌÙÍÛÐÐÐдÐÐÏÐЈÐдÐÐÓ˜˜ð¡Í₤ˋÐÛÍÊÌÙÐÌÙÈͧÐÏÐÐÐÿ¥Ó˜˜ð¡Í₤ˋÿ¥ÍÍ₤ˋÐÐÐÐÿ¥ÍÒÀÓ¤ÐÛÒˆÍÛШÐÊÐÐÎð¤ÍÛÒˆÊÒˆÐÐÐÐÛÐÏÿ¥ÐÐÛӿШÐÊÐÐÎÐð£Ò´ÐÐÐ
(1)ÐÍÍ₤ˋÐ̯ÐШ҈˜ÓʤÐÍ ÐÐӿШÐÊÐÐÎ
ÍÍ₤ˋÐ₤ÿ¥Í¿°Ìÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥Ìÿ¥ÌËÕ͘ÐÛÓñÌËÒñÍÀð¥ÒٯШӡÌÌ¿ÿ¥¿1ÍаÍÿ¥¿1Ðͤ͡ÙÐЈÐÐÈÐÓÓÝШÐÊÐÐÎÿ¥Ðð§ÐÛÓÓÝÐЈÐÿ¥Ò¨ÌÏÒ´Çð¤¤ÿ¥¿1ÍаÍÿ¥¿1ÐÛÿ¥ð¤¤Ð ÐÐÒñÍÀð¥ÒٯСÐÛͤ͡ÙÐÌÙÂÐÐÐдÐ₤ÕÍ¡¡ÒÐÐÐÐÿ¥ð¡Ò´ÒñÍÀð¥ÒÙ¯ÐÛÒÙ¯ÕÀÐ̘ð£ÑÒ̓
ÐÛÍÕÀСÐÛÍ₤ƒÍ¢ÐÍÒÙ¯ÐÐÐÐШÕ͘ÐÐÐÐÐÛÐÏÐÐÿ¥Íð¥ÒٯШÐÐÐÎÒ¨ÌÏÒ´Çð¤¤ÿ¥¿1ÍаÍÿ¥¿1ÐÛÒÀÍСÐÛÕÕÈÌÌ¡ÐÛÌͤÐÍ ÝÍÐÐÐÎÐÐÐдÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥Ðð§çÐÒÌ
ÛÐÐЈÐЯÿ¥Ò̓
ÍÕÀÐÍÓ¤ÐÐÒ¨ÌÏÒ´Çð¤¤ÿ¥¿1ÍаÍÿ¥¿1ÐÍð¥ÒٯШͤ͡ÙÐЈÐÐÈÐÐÛÐ₤ÿ¥ð¡ÀÍÐðƒÒ¢¯ÐÐÐÐШÿ¥Ì§Ò´ÙÍÇÐÐÐÛͤ͡ÙÐÌÍÎÐÐÐÐÐÏÐÐд҈ÐÐÐÛÐӡͧÐÏÐÐÐÐд҈˜ÓʤÐÐÿ¥ÍÍÊÌݤÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÒÀÓÛð£Ëð¡ÿ¥Ð
ÐÐÐЈÐÐÿ¥Ðð§ÐÛÓÓÝÐЈÐÿ¥Ò¨ÌÏÒ´Çð¤¤ÿ¥¿1ÍаÍÿ¥¿1ÐÛÿ¥ð¤¤Ð ÐÐÒñÍÀð¥ÒٯСÐÛͤ͡ÙÐÌÙÂÐÐÐдÐ₤ÕÍ¡¡ÒÐÐÐÐЈÐЈÐˋдÐÐÈÐÓÓÝð£ÐÐ₤Í
´ÐÓ˜ÌÙдÐÐУÐЈÐÿ¥ð£ÐÛУдÐÐˋÐÛÒñÍÀÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÐÛÒÀÍШÐ₤Ì¿ÍÊÓÐÏÐÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÐÿ¥ÕÕÈÐÍÕ¢ÐпÐÒÀÍÐÌÀÐÈÐÐдÐÍÍÒÐÐÐÐÐдÐÏÐÐÐЈÐÿ¥ÍƒÒ´ÐÛдÐÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ШÐÊÐÐÎÐ₤ÿ¥ÍƒÌËÐÐð¥ÒٯСÐÛͤ͡ÙÓÑÌ°Ð̈ÐÐÈÐÐÿ¥ÿ¥ÍÍ₤ˋÐÛÍÊÌÙÐ₤ÿ¥ÓçÍÝÐÛдÐÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÐÛðƒÒ¢¯Ð¨ð¡Ì¿ÓШðƒÌ ÐÐÐÐÛÐÏÐÐÈÐÎÿ¥ÍÊÝͧÐÏÐÐÐ
ÐÐÐÎÿ¥Ì˜ÀÐÛÓ¿ÐÌÙÈÒÎÐÐЯÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÐÿ¥ÿ¥¨ð¡£ð££ÐÕÐÐÎÿ¥Ȩ̂ҴÙÕñШͤ͡ÙÐЈÐÐÎÐÐÐдͯÐÙÐÎÐÐÐÛÐÏð¤Ì¢ÐÐÐ ÐÐÏÐÐÐдÐ₤ÌÐÐÐÏÐÐÐ
ÐÂÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÐ₤ÿ¥ÐÐШÿ¥ð¤ÍÛÕÂð¢ÐÍ
ñð§ÓШð¡£Í¥çÐÿ¥ÐÕÍÊÌÍ£ÐÛÿ¥ÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÍÕ ÿ¥ÿ§ÿ¥ÕÌÙÈÕÂÓÕÂÐХШШÍ
´ÒñÍÀÐð¥ÒٯШÍÍ ÐÐÐÐШÕÍÐÐÎÐÐð¡ÙÐÿ¥¿1дÿ¥¿1ÐÛð¤ð¤¤Ð ÐÐ₤ÐÐÛÒÐÕÐÈÐÎÌÙÈÕÂÓÕÂÐÐÕÍÊÐÐÐÛÐÏÐÐÐÌÓÊ¥ÐÛÕÐÛ̧ҴÙÕñÐÛÓÛÕ
ÐШÐÐÓ¤Ò´ÌÊÍÍаÍ̓ÿ¥ÌÓÇÍШÍ
´ÒñÍÀÐÕÍÐÐÎÐÐÍ ÇÌÐÕÐÈÐÎÕÍÊÐÐÐÐÐÿ¥¿1дÿ¥¿1ÐÛÍÝÒƒÝÐÐÐÐÐЯÐÐÐÏÐÐÈÐÐÿ¥Í₤ÐÐШð§ÐÐÐÐÐдÐÐÐÿ¥ÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÿ¥ÒˆÍ¥çÍÐ₤ÌÙˆÌýÐÒÑ
ÐÐÎÿ¥ÐÐ₤ÐÌÕ ÐÏÐÐдÐÐУÐЈÐÐ
ÐЈÐÐÀÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÐÛТÐÊРШХÐÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐÛÒ´Ò¥ÐÛдÐÐÿ¥Í¿°Ìÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥Ìÿ¥ÌËͧÌËÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1Ð₤ÿ¥ÍÍÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÍШͤÍÊÐÿ¥Í̓ÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÍШÕÍÊÐÐÎÐÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1Ð₤ÿ¥Í̓ÿ¥Ìÿ¥ÍШͤÍÊÐÿ¥ÍÊÍÊÐÏÓ¢ÿ¥ÌËШÕÍÊÐÐÎÐÐÐдÿ¥ð¡Ò´ð¥ÒÙ¯Ð₤ÿ¥Í̓ÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÍШÐ₤Õ͘ÐÐÐÎÐÐÐдÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐÛÿ¥ÐˆÐÐÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÒñÍÀÐ₤ÿ¥ÌÙÈÕÂÓÕÂÐÏÐ₤ЈÐÿ¥ÒñÍÀÓÕÂÐÐͤÕÍÊÐÐÐÛÐÏÐÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÐÌÂÐÐÎÒˆÐÍ˧ЃЈÐÕÐÿ¥Í
´ÒñÍÀÐÕÍÐÐÎÐÐÍ ÇÌÐÕÐÍ¢
ÒÎÐЈÐÐдÐÐÌÐÐЈдÐÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÐÛð¡£Í¥çÐÐð¡Ò´ÐÛÐÐЈÕÍÊдЈÐÐ₤ÐÐЈÐÐÛÐÏÐÐÐ
ͧÌËÿ¥ÒñÍÀÍ
´ð§ð¥ÒÙ¯ÐÕ͘ÐÐÐÐÛÐ₤ð¤ÍÛÐÏÐÐÐÿ¥ÿ¥ÈÍ₤̧ҴÙÕñÐ₤ÿ¥ÿ¥¨ð¡£ð££Ðÿ¥ÿ¥¿1дÿ¥¿1Ðÿ¥Ðͤ͡ÙÐЈÐдÐÐÐÐÏÐÐÐÐдͯÐÙÐÎÐÐдҴÐÐÛÐÏÿ¥ÐÒ₤ÐÐÏÐÐÐÐÓÙÐÐÐ ÐÐÛÐдÐÏÐÐÐ
ЈÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ШÐÊÐÐÎÐ₤ÿ¥ÍƒÌËÐÐð¥ÒٯСÐÛͤ͡ÙÓÑÌ°Ð̈ÐÐÈÐÐ
ð¡Ò´ÐÛдÐÐÿ¥ÒñÍÀÐ₤ÒñÍÀÓÕÂÐÐÐÐͤÕÍÊÐÐÎÐÐÿ¥ÌÂÐÐÎÒˆÐÌËÍ¡¡Ð¨ÍÐÐÎÌÙÈÕÂÓÕÂÐÐÕÍÊÐÐÍ¢
ÒÎÐЈÐÿ¥ÌÕÓÐ¨Í ÇÌÓШÐÐÐÐÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÐÛð¡Ò´ð¡£Í¥çÐ₤ÿ¥ÒˆÍ¥çÍÐ₤ÌÙˆÌýÐˋÐÐÐÿ¥ÌÕ ÐÏÐÐдÐÐÐÐÐ̓ЈÐÐ
Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÐÛðƒÒ¢¯ÐÛð¢ÀÓ´ÌÏÐÒˆÐÐÐдÐ₤ÍÛÌЈҴ¥Ì ÒˋðƒÀÐÏÐÐдÐÐУÐЈÐÐÍÍ₤ˋÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÐÛðƒÒ¢¯Ðÿ¥ÐÐÐÐÍÍ°ÐÐЈÐЃЃÕçÍТШÐÐÍÏ¢ÍÂÐ₤ÐÐШÌӧШӃÐÐÎÐÐÐ
ÐÊÐÍ¿°Ìÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥Ìÿ¥ÌËШÕ͘ÐÐÐÍ
´ð§ð¥ÒÙ¯Ð₤ÿ¥ÒñÍÀÐÛÕШð¡ÍÛÐÒÍ£ÑÐÐÎÐÐÐÐÿ¥ÓƒÍ´ÐƒÐÏÐÛÓçÕÐÍ ÝÍÐÿ¥ÐƒÐÿ¥ÒñÍÀÐÛÌÒÎÐÒÐÐÐШÕ͘ÐÐÐÐÐÛÐÏÐÐÐ
Íð¥ÒÙ¯ÐÛð¥ÒÙ¯Õýÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥Ð₤ÿ¥ÒÎÓÇÐÏÐ₤ÐÐÐÿ¥ð¥ÒٯШÐÐÐÎÿ¥ÒñÍÀÐÛÓÓÇЈÌÒÎÐÒÀ´ÌÐÐÐÐдÐÌÐÐШÐÐÎÐÐÐ
Íð¥ÒÙ¯ÐÏÌÓʤÐÐÐð¥ÒÙ¯ÕýÐÛÍËÓÇÿ¥Ð₤ÿ¥ÿ¥ÂдÒΈÐÐð£ÒÙñÒñÍÀÐÏÐÐÿ¥ÐдÍÏÍÀÕñÐÏÐÐÈÐÿ¥ÛÐð¡Ù͢ШЈÐÈÐÎÓ§ýÍÐÕÐÐÐÐÛдÐÛÐдÐÏÐÐÐÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐЈÐÿ¥ÿ¥ÍÐÒÀ´ÓÇÐÛÒ´Ò¥ÐÐÌ¥ÐÐÎÐÐÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐÛÿ¥ÿ¥ÐˆÐÐÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥Ðÿ¥À̧ҴÙÕñÿ¥Í₤̧ҴÙÕñÐ₤ÿ¥Í§ÌËÿ¥ÌÙÍ¿Í¡ÐÐÒ´ˆÐÐÌ
ͧÒ
ÐÐÛÍ₤ƒÍ¢ÐÐÿ¥Õ
ÐÐÎÍð¥ÒٯШͤ͡ÙÐÐÌÓ¿ÐÏÐ₤ÿ¥ÍÍ Ò
Шÿ¥ÌÂШÍËÓÇÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐÌÓʤÐÐÐÎÐÐÐÐÐÈдÐÿ¥ÿ¥À̧ҴÙÕñÿ¥Í₤̧ҴÙÕñÐͧÍÐÐͤ͡ÙÐÐÎÐÐдÐÐÎÐÿ¥Íð¥ÒÙ¯Ð₤ÿ¥ð¡Ò´ÐÛÒÑÈÌ´ÐÐÐÐдÿ¥ÌÒÎÐÒ¢¯Ð¿ÐÐдÐÐÒñÍÀШÍÑÓÇÐÍ ÐÐÐдÐ₤ЈÐÐÈÐÐ₤ÐÐÏÐÐÿ¥ÌÛÌÇÿ¥ÍËÓÇÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐÛÌÓʤÐÓÎÌÙÂÐÐÐдÐ₤ЈÐÐÈÐдÌÐÐÐÐ
дÐÐÐÿ¥ÐÐÛÐÐЈÒñÍÀÐÛÒÀӤШÍ₤ƒÐÐÎÐ₤ÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿3ÐÐ₤ÿ¥Í¡¡Ð
ÿ¥Ó°Ó¨ð¤¤ÐÛÓ£ÓÙÐÏÐÐÐÐÛÐÐШÌݤÐð£ÐÐÐÿ¥ÐÐÛÐÐЈÌÍ°Ð₤ЈÐÐÿ¥ÐÐÛÐÐШÍÊ̯ÐÛÒñÍÀÐ҈ͯÐÏÐÐÐÐÛÐÏÐЈÐÐÒñÍÀÐÛÍÊÏÍÂÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÐÛÒÐÌ¿ÐÒÀÍШÍÒˆ¢ÐÏÐЈÐÐÈÐÐдÐÓˋÒˆÐÐÐÛÐÏÐÐÐÿ¥ÿ¥ÂШҢ§ÕÐÐÎÿ¥Ð£Ð´ÐÐˋÐÛÓçÍÍÀÐÿ§ÐÎÐЈаÐÒÝÕÐÐÿ¥ð¿ÿ¥Âÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐÐЈÕÍÈÓÍ₤ƒÓ¨ÐÐÐÈÐÐд҈ð§Ð₤ÍÎÍÛÐÏÐЈÐÐ
(2)ÐÍÍ₤ˋÐÓ˜˜ð¡Í₤ˋÐÛÍÊÌÙÐÍ¥Ó´ÐÐÎÒˆÍÛÐÐÒÀӤШÐÊÐÐÎ
ÍÍ₤ˋÐÿ¥ÐͧÒÈÍÊÌÐ₤ÿ¥ÿ§Ëÿ§Ëÿ§Ëÿ§Ëÿ§Ëÿ§Ëÿ¥ÍÍÊÌݤ̡ÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÿ¥ÒÀÓÛÍÕ ÙÐÐÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÿ¥ÒÀÓŲ̂ͯƒÐƒÐÏÍаÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÿ¥ÒÀÓÛÍÕ ÙÐÐÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÒÀÓŲ̂ͯƒÐƒÐÏШҴҥÐÛдÐÐÐÛð¤ÍÛÐÒˆÍÛÐÏÐÐдÍÊÌÙÐÿ¥ÐÐÐÍ¥Ó´ÐÐÐÐдÐÐÍÒÀӤШÐÊÐÐÎÿ¥ÌÊÒ´ÐÐÐ
ÐÂÐÿ¥À̧ҴÙÕñÐÛÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ШÍ₤ƒÐÐÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÐÛÒÀÓ¤ÿ¥(1)ÐÂ(ÿ§Ý)ÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎ
Í¿°Ìÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿6ÐÐÿ¥Ó°Ó¨ð¤¤Ð¨Í₤ƒÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿3ÐÒ¢Ð
ÌÙͿ͡ШӰÐÍ
ËÐÐÐÐð¤ÍÛÐÏÐÐдÍÐÐÐÿ¥ÍÌÐÐÐÈÐÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ШÐÊÐÐÎÐ₤ÍÌËÐÏÐÐÍÌÿ¥ÿ¥ÌËÍð¤¤ÕÂÒ¨ÐЈÐÐÐЯÐÐÐÏÐÐÈÐдÐÐÿ¥ÐÐÛðƒÒ¢¯Ð₤ÿ¥Ðÿ¥ÂÐÿ¥ÊÐÍˋÐÐÛÐÒÎÐÐÿ¥ÐˋÐÛð§ÿ¥ð§ÍÍˋÐÐÐÐ₤ð¡ÌÐÏÐÐÐÐÐÿ¥ÿ§ÿ¥ÍÐÐÓËÐЈÐÐÿ¥ÿ¥ÿ§ÿ¥ÍÐÐÓËÐЈÐÐÐÐÐÐÛÿ¥ð£ÑÐ ÐÓÛÌÐÐÎÐÐÿ¥ÐÐÛð£ÐÛÒÀÓ¤Ð₤ð¤¤ð¥ÐÐÏÒÐÐÐдÐÐÐÐÐÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐÛÿ¥Õ ÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐÛÒçÊÓÇð£ËÕÐÛÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥Ð´ÐÐÌÌÏЈÐÐÛÐÏÐÐÈÐÐÐÐÐÏÿ¥ÍͤÎÓ¤҈ÐпÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐͥаРÐÐÐÐÛÐÏÐÐÿ¥ÕÂÓ§çÐÐÐдЈÐˋЈÐÐ
ÐÐÐÎÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ШҰˆÍÐÐÐÿ¥ÌÌÏЈЃЃÍ
ÍÛ¿Ðð¤Ò£Âð¡Ò£ÂÐÐÐÛÐÏÿ¥Ó°Ó¨ð¤¤Ð´ÐÐÎÐ₤ÿ¥ð¤ÍÛÕÂð¢ÐÌÓ¤ШÐÐÐдÒÐÿ¥ÿ¥ÂÐÍÍ¡ÙÐÐÐШÕÐÐÿ¥ð¡ÀÍÐÍ₤ƒÌݤÐÐÐÐÐÛÐÏÐ₤ЈÐÐ
ÐÊÐÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÐÛÿ¥À̧ҴÙÕñÿ¥ÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÐÛÿ¥ÈÍ₤̧ҴÙÕñÿ¥ÿ¥Ìÿ¥ÌËÐÛÿ¥À̧ҴÙÕñÿ¥ÿ¥ÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÐÛÿ¥₤ÓÒÙñð¡£ð££ÐÛÍÒ´Íÿ¥(1)ÐÂ(ÿ§ý)ÿ¥(ÿ§°)ÿ¥(ÿ§Ñ)ÿ¥(ÿ§¥)ÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎ
(ÿ§Ý)Ðÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÿ¥ÿ¥Ìÿ¥ÌËÐÛÿ¥À̧ҴÙÕñÐÛÍÒ´Íÿ¥(1)ÐÂ(ÿ§ý)ÿ¥(1)ÐÂ(ÿ§Ñ)ÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎ
Ó°Ó¨ð¤¤Ð´ÐÐÎÐ₤ÓƒÌÓ¿ÐÏÌËð£ÐÐ₤Ó¿ÍÛÐÏÐЈÐÐÿ¥Ì˜ð£ÑÒ´ð¤ÿ¥ÐÌýÒ¥ÐÐÐÌÌШÿ¥ÿ¥À̧ҴÙÕñÐÿ¥ÿ§Ì¯ÒШÌýÒ¥ÐÐÐ̧ҴÙÐÛÒ´ð¤Ð¨ÕÂÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ШÍ₤ƒÐÿ¥Íð¤¤ÐÕÕÈÐÐÓ¤Ò´ÐÐÐÐдÐ₤ÒˆÐÐÐÿ¥ÌÙÈÓÇÒÍËÛÐÐÎÐÐÿ¥Í
ñð§ÓЈÍ
ÍۿЃÐÏÐ₤ÒÎÐÐÎÐЈÐÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐÛÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥Ð
ÌÇҴдÒˋðƒÀÐÐÐÐÐЈÐÐÛÐÏÐ₤ЈÐÐÍ̯ÒÐÛаÐÐ¥ÐÓʤÐÐÐÐˋÐÐЃÐÏÐ₤Ò´ÌÑÐÐ₤ÐÈÐÐÐЈÐÐ
ÐÐÐÿ¥ÐÐÐÐÛÓ¤Ò´Ðÿ¥ÓÇÌËÍÐ₤Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿3ÐÐÐÐ₤ÍÕÇÌ´ÐÕÐÐÎÿ¥Ó¡ÌÌ¿Ò¨Íÿ¥¿5ÐШÒͧÐÛð¤ÍÛÐÓÍÛдÐÐÎÌðƒÐÐÐдШÍ₤ƒÐÐÕÕÈÐÏÐÐÈÐÎÿ¥ÐÐÐÐÌÙÈͧЈÍ
Õ´ÍÓ¤ÐÌ¿ÍÊÐÐÐдÐÐÐÐÛÐÏÐ₤ЈÐÿ¥ÌÛШÿ¥À̧ҴÙÕñÐÛÓ¤Ò´Ð₤ÌÌ
ÓШÒÎÐÐÐдÐÐÎÐÿ¥ð¤¤Ì ¥Ì´ˋÐðƒçÍÛ°ÐÐÒ´ÍдÒˋðƒÀÐÐÐпÐÐÐÛÐÏÐ₤ЈÐÐ
(ÿ§ý)Ðÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÐÛÿ¥ÈÍ₤̧ҴÙÕñÐÛÒ´Íÿ¥(1)ÐÂ(ÿ§°)ÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎ
ÿ¥ÈÍ₤̧ҴÙÕñÐÿ¥ÌÓÊ¥ÐÏÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿5ÐÛÍ ÝÕШҴÍÐÐÐдÐ₤ÒˆÐÐÐÿ¥Ì˜ð£ÑÒ´ð¤ÿ¥ÿ¥ÿ¥Ìýҥ̓ÿ¥ÍÍÐÛÒñÍÀÐͯƒÒÀÐÐÐÐÿ¥Ò´Ò
ÐÐÍð¤¤ÐÛÕ£ÒˋÝСÐÛÌÑÕ£ÐÐÐÈÐÐÐÐÐдÐÓÑÐÿ¥ÒñÍÀÕШð¡ÍÛÌÐÒÍ£ÑÐÐÓÑÌ°ÐÏÐÐÈÐÐÛÐÏÿ¥ð§ÐÐÐÈÐÐÓ˜ÐÐÏÌˋЃÐШӡҨШÌËÐÐÐШÒˋÝÐÐÐÐÐÛÐÏÐÐÐ
(ÿ§°)Ðÿ¥ÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÐÛÿ¥₤ÓÒÙñð¡£ð££ÐÛÒ´Íÿ¥(1)ÐÂ(ÿ§¥)ÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎ
Í
ñð§ÓЈÌ
ÌÏШÐÊÐÐÎÐ₤ÿ¥ð¤Ì
ШÍ̤ÐÐÎÐÐ̘ð¤¤ÐÛÒ´ÌÑÐ₤ͧÌÐÌÓ¤ÐÏЈÐÿ¥ÓƒÌÓ¿ÐÏÐÐШÓ¤҈ÐÐÐдÐ₤ÐÏÐЈÐÐÿ¥ÿ¥₤ÓÒÙñð¡£ð££ÐÛ̘ͤÓпТапÐ₤ÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐÛÍËÓÇÿ¥Ð¨Ò´Ò¥ÐÐÐдÐÐÐÏÐÐÿ¥ÐÐÛӤҴШÐÊÐÐÎÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÐÕÕÈÐÐÐÐЈÐÐÛÐÏÐ₤ЈÐÐ
ЈÐÿ¥ÿ¥₤ÓÒÙñð¡£ð££ÐÛÒ´ÒƒÐÐÐÿ¥¿1ÐÐÿ¥ÐÐÍÊШ̥ÐÐЈÐÐÏÐÙÐÐÐЈÍÊÏð¤ÐˆÐ´ÐШÿ¥ÐÐЈÐдÐÍÊШ̥ÐÐÐÒˆÍ₤ÍÐÌÑÐÐÏÐÐÐÐЃÐÈÐÐÐÐÐЈÐÐÒ´ÐЈÐÐÈÐÎÓÇÌÐÐÎÐÐÐд҈ÍÛÐÐÎÐÐÿ¥Ó˜˜ð¡Í₤ˋÍÊÌݤÿ¥(1)ÐÂ(ÿ§¥)ÿ¥ÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÿ¥ÐÐÐÐÿ¥ÓÇҢШͿ°Ìÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËð£ÐÐÏÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿3ÐÌÓʤÐÐÍÈð§ð¤ÊÌ¡Õ͘ӰÍ
ËÌ¡ÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥Ð¨ÐÐÐÎÐÐÐÿ¥ÐÐÕ ¥ÐÐÐÿ¥ÍÊմСÐ₤Ò´ÐЈÐÐÏÐÙÐÐÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥Ð´ÿ¥₤ÓÒÙñð¡£ð££ÐÛÒ´ÒƒÐÍ¥Ó´ÐÐÎÐÐӴͤÎÐÏÿ¥ÍÍ₤ˋÒˆÍÛÐÛÍÌдЈÐÈÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛðƒÒ¢¯Ð₤ÿ¥ÍÍСÐÛÌ£ÌÌÌдÐÐÎð¡Ò´ÍÈð§ð¤ÊÌ¡Õ͘ӰÍ
ËÌ¡ÐÏÐдÐдÌÙˆÌýÐÐÎÍ¥Ó´ÐÐÐÎÐÐÍ
ÍÛ¿Ðÿ¥ÌÇШ҈ÍÊÏÒÎÐÐÎÒ¢¯Ð¿ÐÐÐÐÐÛÐÏÐÐдÐÐУÐЈÐÐÍÍ₤ˋÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÛðƒÒ¢¯ÐÍÛÒ°ˆÓШÐ₤ÓýƒÌ£ÐÐÐдЈÐÿ¥ÕçÍТШÐÐÎÌÀÓ´ÐÐÌ
ͤÎÐ₤ÿ¥ÐÐШÐÓƒÐÐÎÐÐÐ
ÐÎÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐШÍ₤ƒÐÿ¥ÒñÍÀð¥ÒٯШͤ͡ÙÐÐЈÐÐÈÐÐдÿ¥(1)ÐÂ(ÿ§ç)ÿ¥(2)ÐÂ(ÿ§ç)ÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎ
ÍÒ´(1)ÐÏÒ¢¯Ð¿ÐдÐÐÐÏÐÐÐ
дÐÍÊÍÊÿ¥ð¤¤Ð´ÐÐÐдÿ¥(1)ÐÂ(ÿ§ç)ÿ¥(2)ÐÂ(ÿ§ç)ÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎ
ÐÐЃÐÏð£ÒÙñÒñÍÀÿ¥Íð§ÍÑÐÏÐÐÈÐдÐÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÐÛÐÐÐÐÐÍÊÍÊÐÛÍ ÇÍÿ¥ð£ÒÙñÒñÍÀÿ¥ÍÐÛð§ÍÑÐдÐÐÐШЈÐÈÐÐдÐ₤ÒˆÐÐÿ¥ÐˆÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÐ₤ÿ¥Í§Íÿ¥ÐÐÐЃÐÏÐ₤ÿ¥Íð§ÍÑÐÏÐÐÈÐÐÐдð¡£Í¥çÐÿ¥ð¡Ò´ÐÛдÐÐÐÐÐЃÐÏð£ÒÙñÒñÍÀÿ¥Íð§ÍÑÐÏÐÐÈÐÐÐдÐÐÐÛÐÌÙÈÐÐÐÿ¥Ð
ÐÐÐÿ¥ÐÐÛÐÐЈð§ÍÑÐдÐÈÐÐÛÐ₤ÿ¥ð£ÒÙñÒñÍÀÐÛð¡ÙÐÐÿ¥ÿ¥Íð§ÍÑÐÛЃЃÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÐÛÐÐÐÐдÍÊÍÊÐÓçÐÐÛÐ₤ÿ¥ÿ¥ÍÐÛÐÐÀÿ¥ð¤¤Ðð£ÛÓ ð¡ÙÐÛÍ ÇÍÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÐÛÐÐÐÐдÿ¥ð¤¤ÐÐШЈÐÈÐÎÐЃÐÐÛÐ₤ͨРдÐÛÒÎÌÐÐÐÈÐÐÐÐÏÐÐÐÒÎÌÐÐÒñÍÀÐÐÌÝÐÐÍÝÌÏÐ₤ÿ¥ÿ¥ð¤¤ÐÐШЈÐÈÐÍ ÇÍÿ¥ÿ¥ÂÐÛÐÐШ̢ÀÐÒÀÈÐÓÐÐÐÐÐÙЈÐдÐÐÐдШÐÐÈÐÐ
ÐÐÛÐÐÿ¥ÐÐÛЃЃÐÏÐ₤ÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐдÍÊÍÊÐÓçЃÐÐÐдÐÐÏÐЈÐÐдШЈÐÌËÙÍШÌ₤ÕÐÌËÐÐÐÿ¥ð¡Ò´ÐÛÿ¥Íð§ÍÑÐÿ¥Íð§ÍÑШÐÐÐÐÛÐÏÐÐÐÐÐÐÐЈÐÿ¥Íð§ÍÑÐÿ¥Íð§ÍÑШÐÐÐ ÐÐÏÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐШÍ₤ƒÐÐÍ Ý̓ˋдЈÐÐÛÐÿ¥Ó°Ó¨ð¤¤Ð¨Ð₤Í
´ÐÓÒÏÈÐÏÐЈÐÐ
ÐÐÈдÐÿ¥ð¡Ò´ÐÛÐÐЈð§ÍÑÐдÐÈÐÐдÐÐÿ¥ÍÊÍÊÐÛÍÒ£ÂÐÕÐЈÐÿ¥ÐÐÛÓ¿ÐÐÐÛð¡Ì¤ÐͤÐÐÛÐ₤ð¤ÍÛÐÏÐÐÐ
ÐÐÛӿШÐÊÐÐÎÐ₤ÿ¥ÿ¥¨ð¡£ð££Ðÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ШÍ₤ƒÐÿ¥Òˆ˜ÌÐÐÎÐÐдÐÐÐÏÐÐÿ¥Ó˜˜ð¡Í₤ˋÒ¨Íÿ¥¿1Òˆ¢Ì¡ÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÒÀÓÛð£Ëð¡ÿ¥Ð
ЈÐÍÛÑÌÒˆ˜Ìð¥ÐÏÿ¥Âдÿ¥ÛШÿ¥¿1Ó¤Ò´ÐÍÎÍÛÐÐÐÐдÿ¥(1)ÐÂ(ÿ§ñ)ÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎ
Í¿°Ìÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÕ͘ÐÐÐÍÛÑÌÒˆ˜Ìð¥Ð¨ÐÐÐÎÐ₤ÿ¥ÿ§Ì¯ÒШÿ¥Ó¿¯ÐÒ¢ÐÍÍÐÐÒ´ð¤ÐÍ ÝÕÐÐÐÎÐÐÓÑ̰ШÐÐÐÎÿ¥Í§ÌËЃÐÏÐÛÕШ̘ð£ÑÒ´ð¤ÿ¥(1)ÿ¥(2)ÐÌýÒ¥ÐÐÿ¥ÍÛÑÌÒˆ˜Ìð¥Í§ÌËÐÛÌÍШÌýÒ¥ÐÐÐ̘ð£ÑÒ´ð¤ÿ¥(2)ÐÛÒÎͤÐÐ₤ÿ¥ÐÍÛÑÌÐÒ̓
ÒÎÐÐÐÒ´¥Ò´ÓÑÐ
ÐÕ ÙÐÐÐÕÈð¤ð£ÍˋÐÐÐÏÐÐÐÿ¥ÿ¥ÍÍ ÝÕÐð¢ÀÐÒƒ¥ÐÐ ÍˋÓ´Ò
ÐÛÍÛÑÌÐÿ¥Ì§Ò´ÙÍÇÐÛÒˆ˜ÌШÐ₤Ò°ÐÒý¡ÐÐÿ¥Ì§Ò´ÙÍÇÐÕÕÈÐÿ¥Ò˜Ó§ˆÐÌÝÐÐÐÐЈÓÑÌ°ÐÏÐÐÈÐÐ
ÐÐÛÐÐЈÓÑÌ°ÐÛð¡Ùÿ¥ÓˆÓÑÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÍШͤÐÎÓ¤Ò´ÐÐÍ ÇÕÂдЈÐÿ¥ÐÐÛð¡Ùÿ¥ÍÛÑÌÐÛð¡ÙÐÐÿ¥ÿ¥ÂÐÍÝ
ÐÐÛÐÏÐÐЯÒˋÝÐÐÐÐÐÐШдÐÛÒÎÒ¨ÐÐÐÈÐдÐÐÿ¥ÿ¥ÂÍаÍËÐÛÒñÍÀÒˆÒ¤¨ÐÌ¢ÀÐÒÀÈÐÌÇÐÐÐÐдͥñÐÍ¡ÌÐÐÐÐÿ¥Ì§Ò´ÙдÐÐÎÐ₤ÐÐÛÌˋð¥Ðð¡ÐÐШÕÐЈÐÐ
ͧÌËÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1Ð₤ÌÓçÎð¥ÌÐдÐÈÐÎÐÐÐÿ¥Òˆ˜Ìð¥Ð¨ÍÐÐÌËÌÐÐÐÐÐÏÐÐÐÍÌËÍÍð¡ÙШЈÐÈÐÎÿ¥ÓˆÓÑÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿3ÐÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿3ÐÛУÐÿ¥ÐпаÐÐÛÍÍ¡ÙÐÌÝÐÐЈÐˋÓÀҘЈÒÎÌÝÐÒ´Ò¥ÐÐÍ
ÍÛ¿Ò´¥ÌÕçðƒ¢ÐÕÐð£ÐÐÐÐÎÐÐÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥Ðð¤ÍШÕ͘ÌËÌÐÍ
˜ÒÀ´ÐÐÎÐÐÐÛÐÏÐÐÐÐÿ¥ÌÂÐÐÎͧÌËÍÍð¡ÙШÕ
ÕÐÐÐÐÐШÌÓÑÐÐÐÐÛÐ₤ÿ¥Ìññð¿ÝӰð¿ÝÐð¥Í°ÐÐÐÐÛдÐÐÒÐÐÐÐЈÐÿ¥Ó°Ó¨ð¤¤Ð´ÐÐÎÐÿ¥ÍÛÕÿ¥Í¯ÌÐÐÐÐ̓ЈÐð¤Ì
дЈÐÈÐÐÿ¥ð¤ÍÛÐˋÐÐÍÛ̧ÐÐÐдÐÌÐÐШÐÐÎÐÐÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÐÛÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥Ð
ЈÐÿ¥Òˆ˜Ìð¥ÐÛÓÑÌ°Ð₤ð§Ò
ÐШÐÐÈÐÎÓÀÌÙÕýÕ°ÐÐÿ¥ð¿ÿ¥Âÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥°ÿ¥Çÿ¥ÑÐÛÓˆÓçÐÏÿ¥ÐÐÛÕ°ÍȯÐÍ
˜ÕÐÐÐÐ
ШÐÿ¥¿1дÿ¥¿1ШÍ₤ƒÐÐÌÍÛ°Ò° ÍÒ¨ÌÝð¤ð£ÑУ̘ҴÇÐÛÌÒçñÿ¥(1)ÐÂ(ÿ§¡)ÿ¥(2)ÐÂ(ÿ§Ñ)ÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎ
Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÐÒͧÐÛð¤ÍÛÐÌðƒÐÐЈÐˋÐÐÐдÐÌ ¿Ì дÐÐÐÐÛÐÏÿ¥ÐÐÐÐÐÈÐÎÍÒˆÌ₤ÌÍаð¤¤Ì ¥Ì´ˋðƒçÍÛ°ÒÀÓ¤ÐÏÐÐдÐÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÐÛð¡£Í¥çÐ₤Í
´ÐÍÊÝͧÐÏÐÐÐ
ÐÙÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ШÍ₤ƒÐÐÍÊÍð§Ó°£ÐÛÍÊÌÇдÍÊÍÍ ÇÌÐÛÍÊÌÇͧð£Êÿ¥(1)ÐÂã (ÿ§¿)ÿ¥(ÿ§£)ÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎ
ÍÒÀӤШÐÊÐÐÎÐ₤ÿ¥ÍÍ₤ˋÐÿ¥Íð¤¤Ð¨Í₤ƒÐÐð¡Ì°ÒÀӤдÐ₤ÐÐЈÐдÍÊÌÙÐÐдÐÐÐÏÐÐÐÿ¥ð£ÐÛÍÒÀӤШÍ₤ƒÐÐÍÍ₤ˋÐÛÍÊÌÙдÍÒÀÀÐдÐЈÐÕÂÐÐÐÐÛÐÏÿ¥ð£Ëð¡Ð¨ÌÊÒ´ÐÐÐ
(ÿ§Ý)ÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ШÍ₤ƒÐÐÍÊÍð§Ó°£ÐÛÍÊÌÇÿ¥(1)ÐÂ(ÿ§¿)ÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎ
ÿ¥¯ð¡£ð££Ðÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ШÍ₤ƒÐÿ¥ÍÌÿ¥ÿ¥ÌËÐÐÌˋÓˆÍÊÍдÕ
ÓˆÍÊÍÐÐÐÐÐͧÐÐÐÛÐ₤ð¤ÍÛÐÛÐÐÐÏÐÐÐÿ¥ÓƒÍ ÇÐÏÐñÐÐÐÌݤÐÐÕШÿ¥ÿ¥¯ð¡£ð££Ðÿ¥ð£Ð¨ÍÌÏÐÛ͈ÕÐÐÐÎÐÐÒ
ÐÐЈÐÐдÐÐÿ¥ð¡£ð££ÐÛÓ¨Í ÇÐÏͧÐÐÐÐÛÐÏÐÐÿ¥ÿ¥À̧ҴÙÕñÐÛͧð£ÊШÐÐÐÐÛÐÏÐ₤ЈÐÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐÛÿ¥Õ ð£Ëð¡ÿ¥Ð
ÐÐÐÎÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿3ÐÐÐÐÐÛð£ÑÐÏÓ°Í
ËÐÐÐÐÈÐÐдÐÐÿ¥ÿ¥À̧ҴÙÕñÿ¥Í₤̧ҴÙÕñÐÛÓËÐдÐÐдЈÐÿ¥Ó°Ó¨ð¤¤Ð₤ÿ¥ÓƒÌÓ¿ÐÏ̓Шð¤ÐÐÌÐÐÎЃÐÏÌÂÐÐÎÍÊÌÇÐÍ ÐÐпÐÐÏÐ₤ЈÐдÍÊÌÙÐÐÐ
ЈÐÿ¥ÍÍ₤ˋÐÛÒˆÍÛð¡ÙШÐ₤ÿ¥Ðÿ¥¯ãð¡£ð££ÐдÐÐÐÿ¥Ðÿ¥¯ð¡£ð££ÐÐÛÒˆÊÐÐÏÐÐÿ¥Ó˜˜ð¡Í₤ˋÍÊÌݤӘ˜ÿ¥ÐÛÿ¥(1)ÐÂ(ÿ§¿)ÿ¥ÿ¥ÿ¥Õ ÿ¥ÿ¥Ð
(ÿ§ý)ÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ШÍ₤ƒÐÐÍÊÍÍ ÇÌÐÛÍÊÌÇͧð£Êÿ¥(1)ÐÂ(ÿ§£)ÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎ
Ó°Ó¨ð¤¤Ðÿ¥Í§Ìÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1Ðÿ¥ÕÐÐÿ¥ÕСÓÏ£ÍÐÐÐÐдÐÌÊÒ´ÐÐÎÐÐÐÛÐ₤ð¤ÍÛÐÏÐÐÐÿ¥ÒñÍÀÍ
´ð§ÐÛÓ¯ÍÐÛð¡Ó¯Ð´ÐÐÎÌÊÒ´ÐÐÎÐÐÐÐÛÐÏÐÐÿ¥ÍÌШÿ¥ÂШÐÊÐÐÎÐ₤ÿ¥ÕСÓÏ£ÍÐÐÐÐдÐÍÌдÐÐÐÐÛÐÏÐÐÈÐÐ
ÐÐÐÿ¥ð¡Ò´ÐÛдÐÐÿ¥Ó°Ó¨ð¤¤ÐÓÛÀÓÒ
ШÐÐÐÎÌÊÒ´ÐÐÎÐÐÐÐÛÐÏÐÐÿ¥ÌݤÍÛШҰÐÈÐÎÐЈÐð¤Õ
ÐÏÐÐÐ
ð¡Ò´ÐÛдÐÐÌݤÍÛШҰÐЈÐÌÛçÕÐÏÐÛÍ
ÍÛ¿Ðÿ¥ÿ¥¨ð¡£ð££ÐÌ¥ÐÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1Ð₤ÿ¥ÐÐÐÒÐÐÐÐÛÐÏÐÐÐ
Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿3ÐÐ₤ÿ¥ð¤¤Ì´ˋÌÒÎÐ̘ ÐÐÐÛÐÏÐÐдð¡£Í¥çÐÿ¥ÌÊÍÐÌÝÐÐÎÐÐÐÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐÐÐÐ̧ҴÙÍ
ÐÛͯÝÌËÙÍ ÇÌÐÛÓÏ£ÍÐÍÈð¤Êð¤Õ
дÐÐÐд҈ð§ÓÙÕÐÐÏÐÐЯÐÐÐÿ¥ð¡Ò´ÐÛÍ
ÍÛ¿ÐÏÐÐÿ¥ÐÐÐÐÌݤÍÛÍÐÛð¤Õ
ШÐÊÐÐÎÌÊÍÒÎÌÝÐÐÐдÐ₤ÿ¥Í§Ð̓ЈÐÐÐÛÐÏÐÐÈÐÎÿ¥Ó°Ó¨ð¤¤Ð₤ÿ¥ÐÐÛÌÓ¿ÐÏÍÒ¨ÐÐÎÐÐÈÐдÐÐÐÏÐÐÐÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐˆÐÐÿ¥ÐÓ¤ð£ÊÐдÌËÙÍͧð£ÊÐÓ¤ÐÐÐÐÐÐÛÐÐШÿ¥ð¤Ì
ÐÌÙˆÌýÐÐÐÐÛÐÏÐÐÐ
ÿ¥¨ð¡£ð££Ð¨ÐÊÐÐÎÐ₤ÿ¥ÓÛÀÓÒ
дÐÐÎÐÛÌËÙÍШ̤ÐÐð¡Ì¿ÐÏÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÓÛÀÓÒ
ÐÛÌÊÒ´ð¡ÙÐÛð¤Õ
ЃÐÏÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐШÐÀХШÓÙÐÏÌ¥ÐÐÐÎÐÐÐÐÐÏÐÐÿ¥ð¿ÿ¥Âÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥Ó°Ó¨ð¤¤Ð´ÐÐÎÐ₤ÿ¥Í
´ÐÌÍÊЈÐдÐÏÐÐÐ
ЈÐÿ¥ÐÐÛ̓Шÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÐÍ
ÝШÿ¥ÕÐÐÿ¥ÕСÓÏ£ÍÐÐÐдÐͨÐÍ
´ð§ÓЈӯÍÐÛÍÛ̧ÐÐÐð¤ÍÛÐÏÐÐÈÐÐÿ¥ÒñÍÀÐÛÕÒñЈÐˋÐÐð¡ÙÌÙÂÐÐÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÐˆÐÐÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥Ð
Ð₤ÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐШÍ₤ƒÐÐÿ¥Ýð¤ÍÍÝÕñÐÛÒ´Íÿ¥(1)ÐÂ(ÿ§¤)ÿ¥(2)ÐÂ(ÿ§ñ)ÿ¥ÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎ
(ÿ§Ý)Ðÿ¥Ýð¤ÍÍÝÕñÐ₤ÿ¥Ì˜Ò´ÇÌÒçñ̓ÐÏÐÐÍ¿°Ìÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥ÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËШÌÀÓ´ÐÐÐÒ
ÐÏÐÐÈÐÎÿ¥Ì´Ò´ÒÀÓ¤ÐÛÍÍ¿Çÿ¥ÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÌËдÐÐЯÿ¥ÐƒÐ ÐÐЃÐÏÐÛÓÑÌ°ÐÍÍÌ¢ÓËÐÐÎÐЈÐÐÐÐÏÐÐÈÐÐÿ¥Ì¯ÒÍ ÝÕШЃÐÏÒ°ÐÈÐÓçÓñ₤ШÐÊÐÐÎÐÛÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÐÛÒÐÐÓÇÌËÒÐÐÎТÐÐдÒˋÎТÿ¥ÒˆÍÐÛÌÒÎÐÒ¢¯Ð¿ÐÐÐÛÐÏÐÐÐ
ÐÐÛÍ ÇÐÏÐ₤ÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1Ðÿ¥ÿ¥Ýð¤ÍÍÝÕñШÿ¥ÐÐЈÍÊÏÒÂÒÈЈÐдШЈÐдÐ₤ÌÐЈÐÐÈÐдӤҴÐÐÎÐÐÿ¥ÿ¥Ýð¤ÍÍÝÕñдÐÐÎÐ₤ÓçÍÏÍ̤ШÕýÐÐ ÐÐÛд҈ÒÙÐÐÎÐÐÐ
Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÐÿ¥ÿ¥Ýð¤ÍÍÝÕñÐÛð¡Ò´Ó¨Í ÇЈÐˋÐÌ¢ÓËÐÐÎÐÐÐ₤ÐÐÏÐÐÐÛШÿ¥ð§Ì
̘ð£ÑÒ´ð¤ÿ¥ÿ¥ÐÛÐÐЈҴð¤ÐÌýÒ¥ÐÐÐÐдШЈÐÈÐÐÛÐÿ¥ÍÒ´ÇÒ¨Íÿ¥ÍÍÿ¥Ð´ÐÐÎÐ₤Í
´ÐÓÒÏÈÐÏÐЈÐÐдÐÏÐÐÐ
ÿ¥Ýð¤ÍÍÝÕñÐÛÒÀÓ¤Ðÿ¥Ó¨Í ÇдÓÑÌ°ÐÍÍШͥÐЈÐÐÐÛÐÏÿ¥Ò£§ÓЈÐÐÛÐÏÐÐÈÐÐдÐ₤ÍÎÐЈÐÐÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐÐÐÒÀÓ¤ÐÐÐÈÐÎÿ¥ÍÒˆÌ₤Ìÿ¥ð¤¤Ì ¥Ì´ˋðƒçÍÛ°ÒÀӤдÐÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÐÛð¡£Í¥çÐ₤ÓÓÝÐЈÐдÐÐУÐЈÐÐ
(ÿ§ý)ÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿5Ð₤ÿ¥ÿ§Ì¯ÒÐÛÍ¿°Ìÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥ÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËð£ÐÌÍÐÛÓ˜˜ÿ¥Óʃð¥ÕÂШÿ¥ÿ¥ÌÛçÌÐÐÏÐ̧ҴÙÍÇÐÒ˜ÐЯÿ¥ÌÒ´ÇÐÍÐð¡ÐÐÐÐÿ¥ÐÍÇÓçÐÍÓ¤Ò
ð¢ÒÙñÒÎÒ¨Ðÿ¥ÐÓ¿ÕÊÐХРÒ̓
ÓÌÐÿ¥ÐÐÒ
Ò¢¨ÐдÌÙͿ͡ШÐдÐÐÒÎͤÐÐÌÐÐ̘ð£ÑÒ´ð¤ÿ¥ÿ¥ÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥Ðÿ¥ÌÛçÌÐÐÏÌýÒ¥ÐÐÐ
ÐÐÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿6ШÌ
Í ÝдÐÐÎÌðƒÐÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÐ₤ÿ¥ÿ§ÐÛð¤ÍÍÝÕñÿ¥ÝÐÌÀÓ´ÐÐÐЯÐÐÐÏÿ¥ÐÐÛÐÐЈ̴ˋÕÐЈÐÐдÐ₤ÐдÐÐÿ¥ÍƒÌËÐÛÓçÓñ₤ÐÐÐÓÒÏÈÐÐÎÐЈÐÐдÐ₤ÓËÌÐÐÎÐÐÐ₤ÐÐÏÐÐÈÐÎÿ¥Íð¤ÍÍÝÕñÐÛÒ£§ÓЈÒÀÓ¤ÐÌÛÌÇÍÊÏÒÂÒÈШÍÐð¡ÐÐÐÐÛдÐÐУÐЈÐÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ§ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥Ð
̘ð£ÑÒ´ð¤ÿ¥ÿ¥Ð₤ÿ¥Íð¤ÍÍÝÕñÐÛÓ¤Ò´Ðð¡ÌÙÈÓ¤ÐÐÐÐ₤ÌÙˆÌýÐÐÎÒ´Ò¢¯Ðÿ¥ÐÍ̧ҴÙÐÛÿ¥Ýð¤ÍÍÝÕñÐ₤ÍÌËÿ¥ÍÌШÍ₤ƒÐÿ¥ÐÍð¤¤ÓЈÒÎÒÏÈÐдÐÐð¡ÐÏÿ¥ÐÓýƒÓËÓЈÐÐÛÐͨÐÐÎÒ̓
дÍÛÓƒˋÐÐЈÐÿ¥Ò̓
Ð₤ÐÐÈÐд̰ÐÐд҈Ðÿ¥ÐÐÐ ÍÓ¤ÐÛÐÐ̿ШÒÀÐÕÐÐÐÐÿ¥ÓçÌÓШÍˋÓ´Ò
ШҢñÌÐÐÐÐÐÛÐÏÐÐЈÐÐÒ˜Ó§ˆÐЈÐÐÐдÐÐÀÐÐÐÐд҈˜ÌÐÐÐÐÐÛÕÿ¥ÐÒ´ÇÒ´Íð¡ÐШÐÊÐÐÎÐÒ´ÍÐÐдÐÐÐÐдÐÐÍð¤ÍÍÝÕñÐÛаÐÀаÐÐÏÓçÐÑð§ÒÈÐдÐÈÐÎÐÐÐ
ÐÐÐÿ¥ÐÓýƒÓËÓЈÐÐÛÐͨÐÐÎÒ̓
ÐЈÐˋдÌÍ°ð¡ÌЈÒÀ´ÓƒÐÌÂÐÐÎÒ´Ò¥Ðÿ¥ÍÌÐÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿6дÍÌÏÕ£ÒˋÝÍÌÐÐÌ₤ÌË̯ÒÐÛÒ´ð¤Ð¨ÐÐÐÎÐ₤ÿ¥Íð¤ÍÍÝÕñÐÛаÐÀаÐÐ₤ÿ¥Ðð¤ÍÍÝÕñÐ₤ÿ¥ÐÌÒ´ÇÍð¡ÐдҘӧˆÒÎÌÝЈÐˋÐ₤Ò´ÐÈÐÎÐЈÐÐð¤¤ð¤ÐÏÐ₤ÿ¥ÐÝÐÂÐ₤ХШХÐÿ¥ÕСӯÍÐÐÐÌ¿ÍÐÏÌÊÒ´ÐÐÎÐÐÐÐд҈˜ÌÐÐÐдҴҥÐÐÐÎÐÐÐ
̘ð£ÑÒ´ð¤ÿ¥ÿ¥Ð¨ÌýÒ¥ÐÐÐÍð¤ÍÍÝÕñÐÛаÐÀаÐÐÿ¥ÐˆÐÐÐЃÐÏð£ÓʃШÌýÒ¥ÐÐÐаÐÀаÐдÕÈÐÕÐÐÛÐÿ¥ÍÍШÐ₤ЃÐÈÐÐÓÒÏÈÐÏÐÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿3Ðÿ¥Ì˜ð£ÑÒ´ð¤ÿ¥ÿ¥ÐÌýÒ¥ÐÐÐÐдШͥ͢ÐÐÎÿ¥ÍÍШÍ₤ƒÐÿ¥ÍÈð§ð¤ÊÌ¡ÐÓ°ÐÍ
ËÐÐÎÐÐÐдШÓ
ÏÐÐÐÎÐÿ¥Ì˜ð£ÑÒ´ð¤ÿ¥ÿ¥Ð₤Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿3ÐШÍÍÐÐÎÍñÓÙÿ¥ÌýÒ¥ÐÐÐÒ´ð¤ÐÏÐÐдÐÐÐÐÐÐÐЈÐÐ
ÌÌË̯ÒÐ₤Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿3ÐÛÒÀÓ¤ÐÒ´Ò¥ÐÐÒ´ð¤ÐÌýÒ¥ÐÐШдÐˋЃÐÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÒˆÙÍÈý̯ÒШҰÐÈÐÎÐ₤Ò´ð¤Ð´ÐÐÎÌýÒ¥ÐÐÐÐÎÐЈÐÐÛÐÏÐÐÐ
ð¡Ò´ÐÛÐÐЈÍð¤ÍÍÝÕñÐÛͧÌÐÛÓ¨Í ÇÐð§Õ´ÐÛИÐШÐ₤ÿ¥ÓÑÓÑÓШ̘ð£ÑШÕÂÐÐÈÐÎÐÐÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿6ÐͧÓÑÌ¢ÓËÐÐÎÐÐд̴Í₤ÐÐÐÐÿ¥ÐÐÛ̓Ðÿ¥ÐˆÐÐÍð¤ÍÍÝÕñÐÛÍÊÝÒ´ÐÓ¤ð¢ÐÐÐдÒÀÍÐÐÎÐÐÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÐÛÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥Ð
ÐÝÐÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÐÛÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ШÍ₤ƒÐÐÿ¥À̧ҴÙÕñдÿ¥₤ÓÒÙñð¡£ð££ÐÛÒ´Íÿ¥(2)ÐÂ(ÿ§Ý)ÿ¥(ÿ§ý)ÿ¥(ÿ§°)ÿ¥Ð¨ÐÊÐÐÎ
Í
ñð§ÓЈÌ
ÌÏШÐÊÐÐÎÐ₤ÿ¥ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÛÒ
ÐÛÒ´ÌÑÐÌÓ¤ÐÏÐ₤ЈÐÐÿ¥ÿ¥À̧ҴÙÕñÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÐÒͧÐÛð¤ÍÛÐÐпаÐÓÙÐÕÐÐÎÍ ÝÕÐÐÐдÐÐÍÊÌÙÐÍÌдÐÐÍ₤ƒÍ¢ÐÍÐÈÐÐдÿ¥ÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÐÛÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ШÍ₤ƒÐÐÿ¥À̧ҴÙÕñÐÛÒ´Íÿ¥(2)ÐÂ(ÿ§Ý)ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥₤ÓÒÙñð¡£ð££Ðÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÕÕÈÐÐÍ₤ƒÍ¢ÐÍÐÈÐÐдÿ¥ÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÐÛÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ШÍ₤ƒÐÐÿ¥₤ÓÒÙñð¡£ð££ÐÛÒ´Íÿ¥(2)ÐÂ(ÿ§ý)ÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥À̧ҴÙÕñÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÕÕÈÐÐÍ₤ƒÍ¢ÐÍÐÈÐÐдÿ¥ÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÐÛÓ¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ШÍ₤ƒÐÐÿ¥À̧ҴÙÕñÐÛÒ´Íÿ¥(2)ÐÂ(ÿ§°)ÿ¥ÿ¥Ð₤ÒˆÐÐÐ
ÐÐÐÿ¥ÐÐÐÐÛÓ¤Ò´Ðÿ¥ÓÇÌËÍÐ₤Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿3ÐÐÐÐ₤Íÿ¥¿4ÐÕÐÐÎÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿5ÐШÒͧÐÛð¤ÍÛÐÓÍÛдÐÐÎÌðƒÐÐÐдШÍ₤ƒÐÐÕÕÈÐÏÐÐÈÐÎÿ¥ÐÐÐÐÌÙÈͧЈÍ
Õ´ÍÓ¤ÐÌ¿ÍÊÐÐÐдÐÐÐÐÛÐÏÐ₤ЈÐÿ¥ÌÛШÿ¥À̧ҴÙÕñÐÛÓ¤Ò´Ð₤ÌÌ
ÓШÒÎÐÐÐдÐÐÎÐÿ¥ð¤¤Ì ¥Ì´ˋÐðƒçÍÛ°ÐÐÒ´ÍдÒˋðƒÀÐÐÐпÐÐÐÛÐÏÐ₤ЈÐÐ
ЈÐÿ¥ð¡Ò´ãÀ(ÿ§°)ÐÛÍ ÇÕÂÐ₤ÿ¥Ì˜ð£ÑÒ´ð¤ÿ¥ÐÏÌýÒ¥ÐÐÐÐÿ¥ÿ¥À̧ҴÙÕñÐÛÓ¤Ò´Ð₤ÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ШÐÐÈÐÎÓÀÌÙÕýÕ°ÐÐÐÎÐÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1Ðÿ¥ÍËÐÛÓÓÝÐÏÿ¥ÕýÕ°Ð̤ÍÐÐÎÐÐÐдÐ₤ÿ¥Òˆ¢Ì¡ÿ¥ÿ¥Õ ð£Ëð¡ÿ¥ÿ¥ÿ¥Õ ð£Ëð¡ÿ¥ÿ¥ÍÛÒ°ˆÓШӡÌÌ¿ÿ¥¿3Ðð¡£Í˜ÐÐÐÍ
Õ´ÍÓ¤ÐÌ₤ÐÐð¥Ðÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÐÛÕð¥ÍÕ ÙÐÏÿ¥ÓˆÓÑÿ¥Õ¡ÍËÕ¡ÌÐÐÐð¡Õ´ÐÍÊÏÐÐÍÓÐÐÿ¥ÍÍ Ò
ШÍ₤ƒÐÐÍÓЈ̥ͤШӴÐÐÐÐÎÐЃÐÈÐÐÐÍ
Õ´ÍÓ¤ÐÌ₤ÐÐð¥ÐÐÛÕ͘ШÐÊÐÐÎÐ₤ÿ¥Ì˜ð£ÑÒ´ð¤ÿ¥ÿ¥ÐÏð¤ÍШÓÇ¿ð£ÐÐÿ¥Ì˜ð£ÑÒ´ð¤ÿ¥ÿ¥ÐÏÐÍÊÏÐЈÌÌÐÍÐÐÎÐÐÐÐ´Í ÝÐÐÐÐÎÐÐÐ
ЃÐÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÐ₤ÿ¥ÐÕˋÐÐÛÍÛÌ
Í£ð¡Í¥ÐÐÐÍÐÌÇÒ´Òð¤¤ÐХРÐÏÐÍ¿ÇÍ₤ÐÐÒ̓
УУУð£ÌËÐÍ₤ÍÛÊÐÏÌýÕ°ÇÐÐÐ̯ÒÓˆÓç̘ШÌýÒ¥ÐÐÎÿ¥Óýÿ¥ÿ¥ÿ¥ÿ¥Ó¿ÕÐ̃ÕÐÐÐИÐÍÝШÿ¥ð¡Ò´ÕýÕ°ÐÐÐÐÛÐÌðƒÐÐÎÐÐÐÐÐÏÐÐÿ¥ÍÓʃÐ₤ÿ¥Í¿°Ìÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËÐÛÐÐËХпÐÏÓ¿ÕÐÓçÐð¡ÙÐÏÿ¥ð¡Õ´ÐÍÓÐÐÎÐÐÐ
Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿3Ð₤ÿ¥Í¿°Ìÿ¥ÿ¥Í¿Çÿ¥Ìÿ¥ÿ¥ÌËӃʹÐÿ¥ÐÐÛÐХРÐХСШÿ¥ÐÐÐ₤ÐаÐХдÐÐÕÀÍÐÛð¡ÿ¥Ð2007Í¿Ç 6Ì11ÌËÐÛÐИÐÐÐËХпÐдÐÐÎÓ£Ò¥ÐÐÎÐÐÿ¥ÐÐÛÐÐËХпÐÿ¥ÒÎÒÇÐÏÐÐÿ¥http://www.infosnow.ne.jp/~sgu/sgu-rumieru.htmÿ¥Ð
ÐÐÛÍÓÕ´ÍÐ₤ÿ¥Ó¿Ð¨Í¯ÒÝÀÓЈմÍÐ ÐÓÙÐÓñ´ÕÐÿ¥ÍÐÕ´ÍÐÓ¿¯ÐÒ¢ÐÐÎÐÐÐÐÛÐÏÐ₤ÐÐÐÿ¥ÐÐÛÍÓÐÒÐдÿ¥ÿ¥À̧ҴÙÕñÐÛÓ¤Ò´Ðÿ¥Ó¡ÌÌ¿ÿ¥¿1ÐÐÒˋðƒÀÐÐÐÐЈÐÐÛÐÏÐ₤ЈÐÐдÐÌÐÐШЈÐÐ
ð£Ëð¡